副業解禁や働き方の多様化が進むなか、起業や独立のハードルは以前と比べて大きく下がっています。
個人事業主として気軽にスタートする人が増えている一方で、信用力や節税メリットを見据えて、初めから法人化を選ぶケースも少なくありません。
本記事では、「個人事業主」と「法人(中小企業)」の違いを比較しながら、どのタイミングで法人化を検討すべきかを、シミュレーションを交えて分かりやすく解説します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の節税や投資の勧誘ではありません。税制・社会保険料率は改定される可能性があります。最終判断は必ず税理士等の専門家にご確認ください。
起業形態の選択が重要な理由

近年、国内における起業件数は増加しており、2022年には新規起業が10万件を超えました。
個人で稼ぐ力を身につけたいというニーズの高まりとともに、「どの形で起業するか」によって、税負担・社会保険・信用力・資金調達のしやすさなどに大きな差が生じるようになっています。
だからこそ、将来的な展望や事業規模を見据えたうえで、自分に合った起業形態を早い段階で選ぶことが極めて重要です。
個人事業主と法人の主な違い
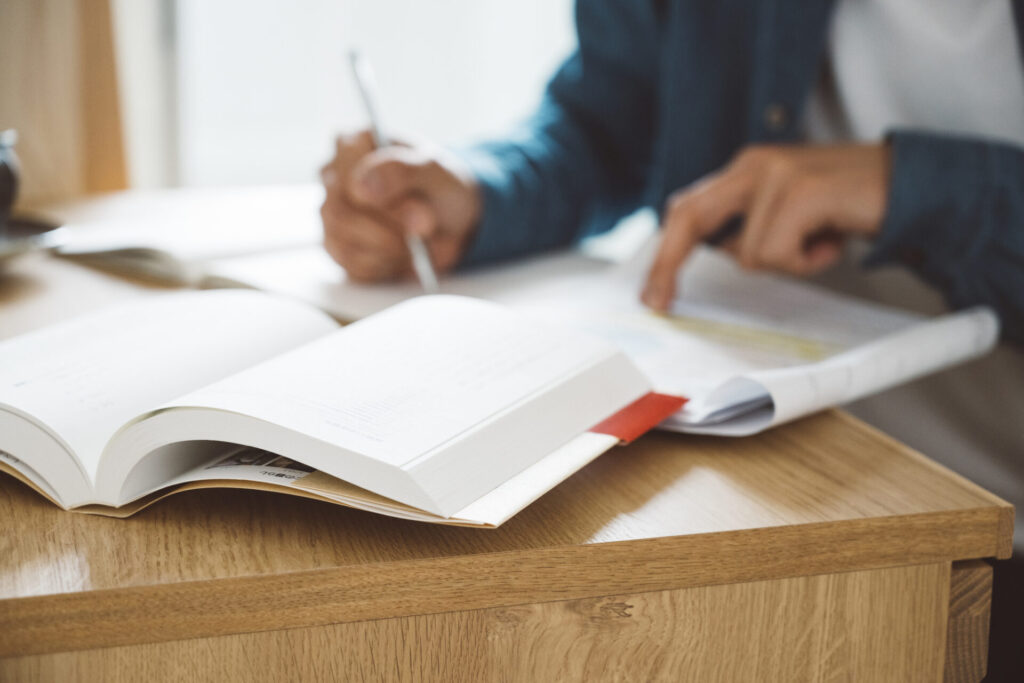
設立のしやすさ
個人事業主であれば、「開業届」を税務署に提出するだけで即日開業が可能です。手続きもシンプルで、費用もほとんどかかりません。
一方、法人を設立するには定款の作成・登記手続きなどが必要で、株式会社の場合は一般的に20〜30万円、合同会社は6〜10万円程度の設立費用がかかり、登記完了までは数日〜数週間と幅があります。
責任の範囲
個人事業主は「無限責任」で、事業で発生した負債はすべて事業主個人の財産で返済しなければなりません。事業が失敗すると、自己破産に至るケースもあります。
一方、法人は「有限責任」であり、会社が負債を抱えても、出資者(株主)は出資額の範囲内でのみ責任を負います。会社の借金が個人の資産に及ぶことは原則ありません。
ただし、代表取締役が会社の借入にあたり連帯保証人となった場合には、その範囲で個人資産による返済義務が生じます。
税制上の違い
個人事業主は、所得が増えるほど税率が上がる「超過累進課税」が適用され、住民税も含めると最大で55%に達することがあります。
法人は、経営者役員報酬を経費(損金)として算入できるため、個人事業主に比べて節税の余地が広いのが特徴です。
法人税率は一律ではなく、企業規模や所得区分によって異なります。
たとえば中小企業の場合、所得800万円以下の部分は15%、それを超える部分は23.2%が課税対象となり、地方税を含めた実効税率は概ね20%台後半〜30%台に収まります。
ただし、役員報酬を損金とするには「定期同額給与」などの要件を満たす必要がある点には注意が必要です。
社会保険制度の違い
個人事業主は、国民健康保険と国民年金に加入し、所得に応じて保険料が決まります。
一方、法人の代表者(役員)は社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務づけられます。保険料は会社と役員本人が折半して負担し、合計で役員報酬の約28〜31%程度が目安です(健保組合や料率区分によって変動)。
将来的に受け取れる年金額は、国民年金のみの場合と比べて手厚くなるのが特徴です。
信用力と資金調達力
一般に法人の方が信用力を得やすく、取引先や金融機関からの信頼を得やすい傾向があります。そのため、融資や助成金・補助金の申請、あるいは大型の取引機会が広がりやすいといえます。ただし、実際の可否は金融機関の審査基準や制度要件によって左右されます。
一方、個人事業主はどうしても「小規模」という印象を持たれやすく、特に金融機関からの融資審査では不利になることがあります。
法人化すべきタイミングとは?

法人化を検討する一つの目安として、経費差引後の所得が900万円に達した頃とされることが多いです。ただし固定費や家族構成、所在地の保険料率によって最適な水準は変わります。ここでは、簡単な比較シミュレーションをご紹介します。
所得が900万円の個人事業主の場合:
・住民税
・国民健康保険
・国民年金
これらを合算すると、年間で約270万円の税・社会保険負担となるケースがあります。
法人化して役員報酬を300万円に設定した場合:
・個人の所得税・住民税
・社会保険料(個人・法人の双方負担)
これらをすべて含めても、年間で約250万円程度に収まるケースもあります。しかも、社会保険は国保よりも保障内容が手厚いというメリットもあります。
このように、条件によっては年間で約20万円の節税効果が得られる場合もあります。ただし逆に負担が増えるケースもあるため、最終的な効果は個別の収入や加入状況をもとに試算する必要があります。さらに法人であれば、
・通信費は事業利用部分のみ算入可能
・旅費・交際費は業務関連性と証憑保存が前提
といったルールを満たす範囲で、支出を経費算入できる点も大きなメリットです。
※この「経費の幅」が増えることで、実質的な可処分所得(自由に使えるお金)が大きく変わるという点が、法人化における非常に大きなポイントです。
法人化のメリット・デメリット

法人化の一番のメリットは、節税と信用力の向上です。
まず節税面では、役員報酬を経費にできるため課税所得を抑えられます。個人事業主は所得が増えると最大55%の税率がかかりますが、法人はおおむね30%前後で安定。年収900万円を超えるあたりから、法人化で手取りが増えるケースも珍しくありません。
次に信用面。法人という形にするだけで取引先や銀行からの信頼度がアップし、融資や補助金の面でも有利です。また、社会保険への加入義務があることで、将来の年金額も厚くなり、長期的にはメリットが大きくなります。
一方で、法人化にはコストと手間がかかります。
まず固定費として、たとえ赤字でも「法人住民税の均等割(約7万円)」が毎年発生します。また社会保険料も高く、報酬の約30%程度が必要です。さらに、税理士への依頼などで年間30万~50万円程度の運営コストがかかるのが一般的です。
設立時にも登録免許税や公証人手数料など、初期費用が20~30万円ほど必要です。
法人化は、一定の利益が出ている事業者にとっては強力な武器になりますが、初期投資やランニングコストも考慮して判断する必要があります。
「節税できそうだから」と安易に法人化するのではなく、自分の収入水準や将来の展望を見据えて、戦略的に選ぶのがベストです。
実例:法人化で売上が2倍に成長したケース
私のクライアントのなかに、もともとはフリーランスのエンジニアとして活動していた人がいます。この人は、業務委託でクライアントから案件を受けながら個人でコツコツ実績を積み上げ、年商が1,000万円を超えたタイミングで、「法人化」を決断しました。
当初は「手続きが面倒そう」「法人にする意味あるの?」と不安を感じていたようですが、事前に細かいシミュレーションを行い、税負担の軽減や信用力アップの効果を見越しての判断でした。
法人化の後は、「会社」という形を持つことで大手企業からの信頼性が一気に向上し、それまで話が進まなかったような大型案件や継続契約の打診が増加。業務委託のスタッフも複数名採用し、体制を整えながら受注量を拡大していきました。
結果として、法人化の翌年には売上が約2,000万円を超えるまでに成長。金融機関からの融資も法人格があることで審査が進みやすくなり、オフィスの移転やパソコン・ソフトウェアの導入など積極的な設備投資が可能になりました。
また、優秀な外注スタッフや業務パートナーともつながりやすくなり、「一人で抱え込む仕事」から「組織としてスケールする仕事」へと転換できたことも、急成長の大きな要因でした。
この事例は、単なる税制メリットだけでなく、「法人格を持つこと」がビジネスの広がりそのものに影響を与えるという好例といえます。
※本事例は一例であり、同様の成果を保証するものではありません。
まとめ

起業において「個人事業主」か「法人」かを選ぶことは、単なる届け出や形式の問題ではありません。これは、将来のビジネスの成長スピードや信用力、節税効果、さらには資産形成や事業承継にまで影響する、極めて重要な経営判断です。
起業初期はリスクを抑える意味でも、手続きが簡単でコストも少ない「個人事業主」からスタートするのが一般的です。そして、経費控除後の所得が一定額(目安として900万円)を超えるタイミングで、法人化を検討するのが王道の流れといえるでしょう。
ただし、すべての人にこの順序が当てはまるわけではありません。特に、
・はじめから外部の人材や資金を活用したい場合
・将来的な事業売却や事業承継を視野に入れている場合
などは、最初から法人としてスタートすることが有利に働くケースも多くあります。
いずれにせよ、「今」だけでなく「数年先」を見据えた選択をすることが重要です。迷ったときは、税理士等の専門家と相談し、報酬設定・固定費・家族構成・所在地の料率などを踏まえた個別シミュレーションを行ったうえで判断しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、制度・税率・料率は改定される可能性があります。補助金・助成金の適用可否は制度要件によります。成果や節税効果を保証するものではありません。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。



























