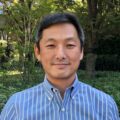将来に備えて資産を増やす方法として、少額から始められる「積立投資」が注目されています。毎月決まった金額をコツコツ続けることで、無理なく資産を育てていけるのが特徴です。
とはいえ、「毎月いくら投資すればいいの?」と悩む方も多いもの。この記事では、無理のない金額から始める方法と、目標額から逆算する考え方を紹介します。
継続できる投資は「生活の余剰資金」からのスタートがカギ

投資は「継続」が何よりも重要。そのためには、無理のない額から始めることが大切です。「投資=ある程度大きな金額が必要」だと思われがちですが、実際には月100円程度からでもこつこつ投資信託で積立投資がスタートできます。
投資信託は運用会社が代わりに運用してくれるので、手軽に利用できる金融商品です。例えばNISAを活用すれば、少額でも手軽に、そして非課税で投資を始めることが可能です。
投資に回すお金は、家計に沿った現実的な金額設定が重要です。
そこでまず取り組みたいのが、足元の生活費を把握すること。無料の家計簿アプリを使って、ざっくりとでも3ヵ月分の支出を記録してみましょう。
とくに固定費は見直しの余地があることが多く、光熱費や携帯代、動画配信サービスなどのサブスクリプション契約をリストアップすることで、不要な出費を見える化&カットできます。
こうして浮いたお金をもとに、小さな額から積立設定を行い、投資を習慣化していきましょう。
大切なのは「途中でやめない」ことです。将来大きな金額の資産形成を目指す場合でも、焦らず現実的な金額設定を意識し、継続を第一に意識しましょう。
大きなお金や特別な知識がなくても、投資は始められます。NISA口座を開設して、100円でよいので投資信託の積立設定をしてみましょう。
その後、家計にどれだけの余剰資金があるか、そして自分には将来どのくらいの資金が必要かを段階的に考えていけるといいですね。
目標から逆算する方法で「必要な投資額」が見えてくる

投資を考えるうえで大切なのは、「いつまでに、いくら必要か」というゴールを決めることです。
例えば「老後に月2万円程度、年金を補う資金がほしい」「10年後に50万円を旅行資金として準備したい」「65歳以降、リフォーム費用として10年おきに100万円がかかる」といったように、目的や金額をざっくりでもよいので想定してみましょう。ゴールが見えることで、そのための道筋も具体的になります。
また、運用を継続しながら運用資産を取り崩していくことで「資産寿命」を延ばすことができ、貯金だけに頼るよりも長く資金を保てる可能性があります。何歳から取り崩しを始めて、どれくらいの期間続けるか、利回りの目標を設定すれば、その時点までに用意しておきたい金額がわかります。
運用しながらの取り崩しをシミュレーションできるサイトもあるので、活用してみてください。私たちの年金を運用しているGPIFによると、平均的な利回りの目安は、外国株式が7.2%、国内株式が5.6%、外国債券が2.6%、国内債券が0.7%とされています(※)。
![[図表]取り崩しシミュレーション](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/3a763853876c953970086214c9cd4550-1024x657.png)
毎月2万円・取り崩し期間25年・想定利回り(年率)4.0%で計算
参照元:みんかぶ 資産運用シミュレーション
目標金額を算出したら、次に考えたいのが「毎月いくら積み立てれば目標金額に到達するか」です。金融庁の「つみたて投資シミュレーター」に想定利回りや運用年数を入力すれば、毎月の積立額を簡単にシミュレーションできます。
シミュレーションの結果として出た金額が、家計を逼迫する額になっていないかは確認が必要です。目標を持つことは大事ですが、現実的に継続できるかどうかを見直しながら、調整していきましょう。
※ 「貯める・増やす」 ~ 資産形成 (体験)資産形成シミュレーターを使ってみよう!(3)
「自分に合った投資額」の考え方とは?

投資額に正解はありません。大切なのは、自分の年齢や収入、生活状況に合わせて設定することです。
投資に回すお金と、生活費や緊急時の備えとしての資金は明確に分けて考えます。例えば、生活防衛資金として、最低でも生活費の3~6ヵ月分を確保しておくと安心です。そのうえで、「今後10年間使う予定のないお金」を投資に回しましょう。
ただ、生活防衛資金が足りていないからといって、投資をあきらめる必要はありません。投資資金、生活防衛資金、近い将来に使う資金は、並行して準備していけばよいのです。
また、積立額はいつでも変更できます。収入が減った場合や急な支出があった場合には、積立額を減らす、あるいは一時的に停止することが可能です。
すでに預貯金が十分にある方であれば、それまで貯金に回していた分を、投資に振り分けるのも一つの方法です。ただし、シミュレーションでは資産が右肩上がりに増えるように見えても、実際には相場は上下しています。
値動きに不安を感じるような大きな金額ではなく、「少し下がっても気にならない程度」の金額でコツコツ続けることが大切です。値動きに不安がある方は、価格変動が大きい株式100%の投資信託ではなく、4資産均等バランス型など、値動きがマイルドな商品を選ぶのもよいでしょう。
![[図表]MSCI ACWI(※)の推移](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/4ed408edcfd8ea5596b80803f75727fc-1024x504.jpg)
参照元:MSCI ACWI 公式サイト
※ 世界の株式市場の時価総額約85%をカバーする、世界中を対象とした代表的な株式指数
資産運用を続けていると、必ず相場が下がる局面に直面します。そのときに怖くなってやめてしまいたくなるのは自然なことですが、そこで投資をストップしてしまうと、長期的なリターンを得るチャンスを逃してしまいます。
重要なのは、自分が冷静でいられる金額で始めること。
相場の上がり下がりに一喜一憂せず、コツコツと積み上げていきましょう。
投資をするなら非課税制度で

投資を始めるなら、NISAやiDeCoといった非課税制度の活用がおすすめです。
利益が出ても、通常の口座では約20%の税金がかかってしまいますが、これらの非課税制度を使えば税金がかからないので、その分効率よくお金を増やすことができます。
NISAでは長期投資を行っていただきたいですが、資産の引き出しにとくに制限はないため、万が一資金が必要になった場合は金融商品を売却して資金を引き出すことができます。
一方でiDeCoは原則60歳まで引き出せません。ただ、運用時の利益が非課税になるだけでなく掛金が所得控除になり、受取り時にかかる税金を抑える控除があるなど、税制上のメリットがあります。
もう一つ、会社員の方なら知っておきたい資産形成の制度が企業型DC(企業型確定拠出年金)です。会社が掛金を拠出してくれるだけでなく、自分で掛金を上乗せできるマッチング拠出制度を導入している会社もあります。
これらの制度はいずれも税制面でメリットのある制度なので、それぞれ特徴をおさえて、効果的に活用しましょう。
おわりに
投資は、特別な知識やまとまったお金がなくても始められます。
無理のない範囲でコツコツ続けていくことが大切です。
投資信託なら月100円から始められます。まずは家計を見直して、できそうな額で積立投資をしてみましょう。
「いつまでに、いくら必要か」をざっくり考えてみると、自然と目標が見えてきます。続けるうちに、自分に合ったやり方も見えてくるはずです。
税制の優遇がある制度を活用すれば、より効率よくお金を増やすこともできます。
もし資産形成の方法に迷ったときは、中立な立場から相談に乗ってくれるJ-FLEC(金融経済教育推進機構)の無料相談を利用するのも一つの方法です。
思っているより投資は気軽に始められます。将来の安心のために、できることから少しずつ始めてみませんか?
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。