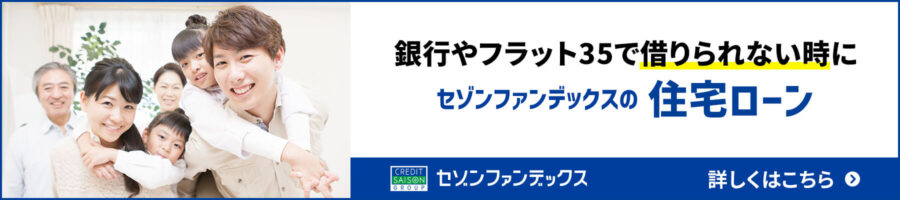変動金利で住宅ローンを組む場合、金利上昇を心配する方も多いでしょう。そこで多くの金融機関では、変動金利が上昇した場合に「5年ルール」と「125%ルール」を適用し、急激な返済額の増加を抑える仕組みを設けています。
本記事では、変動金利の5年ルールと125%ルールの内容、そしてそれらのメリットとデメリットについて詳しく解説します。これらを理解することで、変動金利における返済額上昇の抑制方法や、金利上昇リスクへの対処法を把握することができます。
- 住宅ローンの5年ルールとは変動金利は金利が上昇しても5年間は返済額が据え置かれる措置
- 125%ルールとは5年間返済額が据え置かれた後の増額分がそれまでの返済額の125%までという決まり
- 5年ルールと125%ルールを採用しているのはすべての金融機関ではなく、採用していない金融機関もある
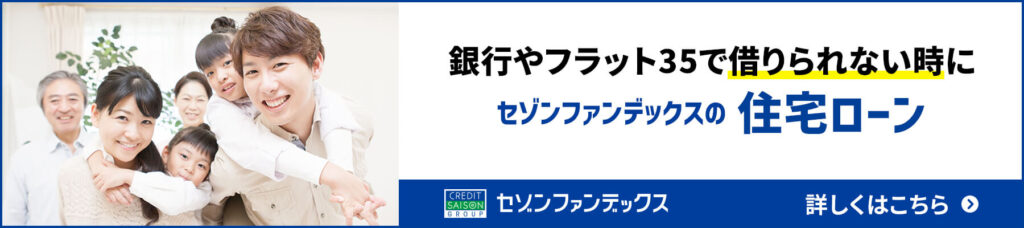
住宅ローン変動金利の5年ルールとは?

住宅ローンを検討する際、金利タイプの選択肢として「変動金利」と「固定金利」の2種類があります。変動金利は定期的に金利が見直されるタイプで、固定金利は一定期間金利が変わらないタイプです。
変動金利を選択した場合、金利情勢によっては金利が上がり、返済額が増加するリスクがあります。しかし、多くの金融機関では「5年ルール」を設けています。5年ルールとは5年間は金利が上昇しても毎月の返済額を据え置く措置です。
なお、5年ルールは変動金利特有のルールであり、固定金利を選択した場合は対象外となります。
5年経過後は125%ルールが適用される
変動金利が上昇してから5年経つと返済額が上がりますが、6年目以降は、「125%ルール」が適用されます。125%ルールとはたとえ金利が大幅に上昇しても、毎月の返済額は従来の125%が上限となるルールです。それまでの返済額が100,000円だった場合、6年目以降の返済額は125,000円を超えないことになり、家計負担の急激な増加を回避できます。
ただし、125%ルールが発動するほどの金利上昇は稀です。
変動金利の元金均等返済には5年ルールがない
変動金利の住宅ローンの5年ルールは、「元利均等返済」のみに適用されるという点に注意が必要です。
元利均等返済とは返済当初から毎月返済額が一定になる返済方法です。返済額は一定ですが、返済初期は利息の割合が多く、返済が進むにつれて元金の割合が多くなります。
一方、元金均等返済は、毎月の元金の返済額が一定になる返済方法です。返済額は元金の返済分と利息分の合計となるため、返済当初は返済額が高くなりますが、返済が進むにつれて元金の割合が多くなり、利息の割合が減っていくため、総返済額を抑えられます。
しかし、5年ルールは適用されないため、金利が変動すると毎月の返済額も変動します。
5年ルール適用のシミュレーション
変動金利の5年ルールは金利が上昇しても返済額が変わりませんが、増えた利息分の支払いは必要である点に注意が必要です。つまり、返済額は据え置かれますが、利息が増えた分、返済額に占める元金の割合が減るのです。
変動金利の住宅ローンの返済中に金利が上昇した場合の、元金と金利の割合をシミュレーションしてみます。
前提条件は、以下のとおりです。
- 借入金額:3,000万円
- 金利:当初年0.5%(元利均等返済)
- 返済期間:30年
- 当初の返済額:元利合計で約9万円
- ボーナス返済なし
- 1年後に1%、2年後、3年後に0.5%ずつ金利が上昇
なお、簡易的なシミュレーションであるため、結果は目安であると考えてください。
| 金利(年率) | 元金分 | 利息分 | |
|---|---|---|---|
| 当初 | 0.5% | 77,500円 | 12,500円 |
| 1年後 | 1.5% | 53,000円 | 37,000円 |
| 2年後 | 2.0% | 43,000円 | 47,000円 |
| 3年後 | 2.5% | 34,000円 | 56,000円 |
上記のシミュレーション結果から、金利上昇時の返済の仕組みがわかります。
- 金利が上昇すると、毎月の返済額のうち利息分が増加します。
- 5年ルールにより、毎月の返済総額は変わりませんが、その内訳が変化します。
- 利息分が増えた分だけ、元金の返済に回せる金額が減少します。
- 結果として、元金の減少ペースが遅くなり、長期的には支払う利息の総額が増加します。
例えば、当初は元金返済に77,500円充てられていましたが、金利が2.5%に上昇すると34,000円にまで減少します。これは、ローン残高の減少速度が遅くなることを意味し、結果的に総支払額の増加につながるのです。
住宅ローン変動金利の5年ルール2つのメリット

住宅ローンの変動金利が上昇した場合に5年ルールが発動されるメリットには、以下の2つがあります。
返済額が一気に上がるリスクを減らせる
変動金利の住宅ローンで5年ルールが適用されると、返済額が急激に上昇するリスクを抑えられます。仮に金利が上昇しても、5年間は返済額が変わらないためです。
子育て中などで家計の出費が大きくなる時期に住宅ローンを借りる場合、5年ルールは家計を安定させるうえで大きなメリットとなります。ただし、5年経過後は返済額に反映されるため、金利上昇の影響を完全に回避できるわけではありません。あくまでも、金利上昇リスクを先延ばしする仕組みである点を理解しておきましょう。
家計への負担を軽くできる
変動金利の5年ルールが適用されると、金利上昇時の家計への負担を軽減できます。長期にわたる住宅ローンの返済中には、ライフスタイルの変化により生活費や教育費といった支出が増加する場合もあり、家計が圧迫されがちです。
例えば、住宅ローンを組んだ後に子どもが生まれて教育費が必要になったり、親の介護により支出がかさんだりする場合があります。そのような状況下で金利上昇により返済額が増加すると、家計が苦しくなるおそれがあります。
5年ルールが適用されていれば金利上昇があっても5年間は返済額が据え置かれるため、その影響を緩和できるのです。
住宅ローン変動金利の5年ルール2つのデメリット

住宅ローンの変動金利で5年ルールを適用すると金利上昇時のリスクを緩和できますが、一方で以下のようなデメリットもあります。
未払い利息が生じる恐れがある
5年ルールのデメリットのひとつが、未払い利息が発生する可能性です。未払い利息とは、ローンの返済額が金利の支払いに満たない場合に発生する利息です。極端な金利上昇局面では月々の返済額のほとんどが利息の支払いに充てられ、元金の返済が進まなくなります。さらに金利が上昇し、月々の返済額が利息の支払いにも満たない状況になると、未払いの利息が発生してしまうのです。
この未払い利息は、ローンの残高に上乗せされるため、借主は利息の支払いばかりが増え、なかなかローンの残高が減らない状況に陥ってしまいます。5年ルールが適用されていても、未払い利息の発生によりローンの返済が思うように進まなくなるおそれがあるのです。
契約終盤に支払額が一気に上がる可能性がある
5年ルールと125%ルールによって、金利上昇による返済額急増リスクはある程度抑制できます。しかし、契約終盤に支払額が一気に上がるリスクも理解しておく必要があります。5年ルールと125%ルールは月々の返済額を抑えるためのものであり、金利上昇に伴い増加した総返済額自体は変わりません。
元利均等返済では毎月の返済額は元本と利息の合計が一定になるように設定されています。金利が上昇すると、月々の返済額のうち利息の占める割合が増え、元本の返済に回る額が減ってしまいます。
5年ルールや125%ルールが適用されている間は月々の返済額の増加が抑えられますが、その分、元本の返済が進まず、ローン残高が減りにくくなります。これが長期間続くとローンの契約終盤で大きな額の元本が残ってしまい、そこに金利上昇で膨らんだ未払い利息が加わり、支払額が一気に増加する可能性があるのです。
住宅ローンの5年ルールがない銀行がある?

一部の金融機関では、5年ルールと125%ルールを適用していません。代表的な金融機関にSBI新生銀行、ソニー銀行、PayPay銀行などのネット銀行があります。例えば、SBI新生銀行の変動金利は年0.410%(2025年3月現在)とネット銀行の中でも最低水準となっています。これらの銀行では金利変動をダイレクトに返済額に反映させる代わりに、金利を低く抑えている点が特徴です。
5年ルールや125%ルールがない銀行のメリットは、金利上昇局面でも未払い利息が発生しにくい点です。金利上昇と同時に返済額も増えるため、支払い利息の残高が積み重なるリスクが軽減されます。一方、デメリットとして、金利上昇の影響を直接受けるため返済額の急増にさらされるリスクがあります。
住宅ローンの5年ルール適用に備えた対策とは

これまでの内容を踏まえ、住宅ローンの金利が上昇して5年ルールが適用されるケースに備えた対策を解説します。
繰り上げ返済を視野に入れる
住宅ローンの変動金利が上昇して5年ルールの適用を受ける場合、元金の支払いの遅れを防ぐために繰り上げ返済は選択肢のひとつとなります。
繰り上げ返済には返済期間を変えずに毎月の返済額を減らす「返済額軽減型」と、毎月の返済額は変えずに完済までの期間を短縮する「期間短縮型」の2種類があります。繰り上げ返済によって元金返済を早め、総返済額や利息負担の軽減が可能です。
ただし、返済途中に金利が上昇してから一部繰り上げ返済をする場合には注意が必要です。繰り上げ返済後のローン残高や返済期間、その時点の金利水準によって毎月の返済額が再計算されるため、返済額が増える可能性があります。
家計に無理のない借入額に抑える
住宅ローンを検討する際は、家計に無理のない範囲で借入額を抑えることが重要です。金利が上昇して5年ルールが適用されても、金利上昇に伴う返済額の増加は回避できません。そのため、変動金利を選ぶなら返済額の増額を見越して、無理のない借入額でローンを組む必要があるのです。
無理のない借入額とは将来的な収入や支出を考慮したうえで、返済負担が家計を圧迫しない金額です。借入の際に返済シミュレーションを行い、将来的な金利上昇を想定した返済額を把握しましょう。
固定金利や5年ルールがない商品をあえて選ぶ
変動金利の住宅ローンでは金利上昇リスクに備えるために、あえて固定金利や5年ルールがない商品を選ぶという考え方もあります。
固定金利の場合、金利上昇の影響を受けずに返済額を一定に保てるメリットがあります。ただし、金利下降局面では変動金利よりも不利になる点に注意が必要です。
また、5年ルールがない住宅ローンを選ぶと金利上昇と同時に返済額が増えますが、未払い利息発生のリスクを回避できます。
金融機関で住宅ローンを借りられない場合は「セゾンファンデックス」

住宅ローンは勤続年数の短い方や、契約・派遣社員だと契約できない場合があります。また、老後資金にするためにご自身がお子様に自宅を売る親族間売買の場合、金融機関から借入を断られることも考えられます。このようなケースは、ぜひ「セゾンファンデックス 住宅ローン」をご検討ください。
セゾンファンデックス 住宅ローンは、銀行などで借入が難しいケースでも柔軟な対応が可能です。勤続年数が短い方や契約社員の方、自営業の方などもお申し込みいただけます。
融資金額は100万円から5億円まで幅広く、融資利率は変動金利3.75%からご用意しております。銀行での住宅ローン審査に通らなかった方も、諦める前にセゾンファンデックスに相談してみてはいかがでしょうか。
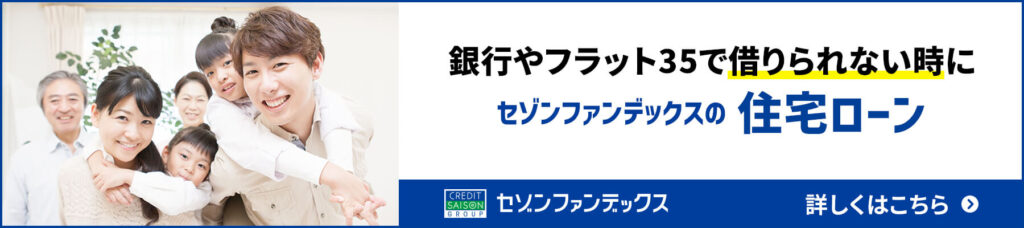
おわりに
住宅ローンの変動金利で金利上昇リスクに備えるには、5年ルールと125%ルールの十分な理解が必要です。これらのルールは金利上昇時の返済額の急増を抑えるメリットがある一方で、未払い利息の発生や契約終盤の支払額増加といったデメリットもあります。
金融機関によっては、5年ルールと125%ルールが適用されない変動金利の住宅ローンもあります。そのため、変動金利を選ぶ場合、5%ルールの有無も考慮するようにしましょう。住宅ローンは長期にわたる契約であるため、将来を見据えた慎重な選択が大切です。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。