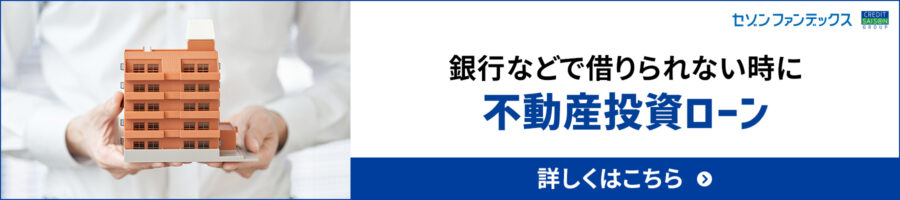定年後に必要な資金は数千万円といわれており、老後の生活費を用意する方法として退職金の運用を考えている方は多いのではないでしょうか。
運用方法はさまざまありますが、この記事でおすすめするのは不動産投資です。不動産投資は家賃収入を得られるため、年金とは別の収入源を作ることができます。一方で、不動産投資には空室リスクや家賃変動リスクなどのデメリットもあるので、投資を行う際には慎重な検討が必要です。
この記事では、退職金の運用が必要な理由や4つの運用方法、不動産投資のメリットとデメリットを解説します。記事の最後では、定年を迎えた方でも利用できる可能性がある不動産投資ローンも紹介するので、退職金の運用を考えている方は参考にしてください。
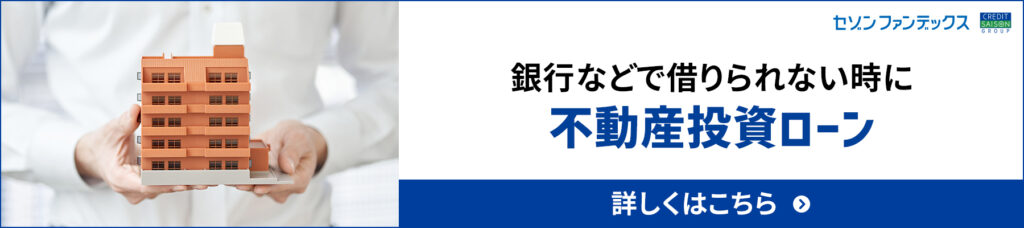
退職金の運用が必要な3つの理由
退職金の運用が必要な理由は以下の3つです。
- 60代の平均余命は20年近くある
- 退職金の平均額はおよそ2,000万円
- 会社員の年金受給額は月額14.4万円
順番に確認していきましょう。
60代の平均余命は20年近くある
厚生労働省の「令和5年簡易生命表の概況|主な年齢の平均余命」によると、令和5年(2023年)時点での60歳と65歳の平均余命は下記のとおりです。
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 60歳 | 23.68年 | 28.91年 |
| 65歳 | 19.52年 | 24.38年 |
つまり、2023年時点で60歳の男性は83.68歳、65歳の男性は84.52歳まで生きるとされています。一方で、60歳の女性は88.91歳、65歳の女性は89.38歳まで生きる計算です。この調査結果からわかるように、多くの方が退職後、20年以上の生活費を年金と退職金で賄わなければいけません。
退職金の平均額はおよそ2,000万円
厚生労働省(中央労働委員会)の「令和5年退職金、年金及び定年制事情調査 P7」によると、満勤勤続した大学卒の退職金の平均額はおよそ2,139万円、また高卒者は2,020万円でした。
※満勤勤続とは、学校を卒業した後に期間をあけず、同一の企業で定年まで勤務することです。
退職金を2,000万円とした場合、毎月8万円ずつ生活費に充てると、約20年でなくなる計算です。
会社員の年金受給額は月額14.4万円
厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金のみを受給している方の平均月額は5.6万円です。また、厚生年金と国民年金を受給している方の平均月額は14.4万円です。
また、生命保険文化センターの「生活保障に関する調査」/2022(令和4)年度」によると、老後の最低日常生活費は月額で23.2万円とされています。ゆとりある生活を送るためには、平均で37.9万円が必要です。
つまり、20年間で必要な生活資金は下記のとおりです。
- 最低日常生活費:5,568万円(23.2万円 × 12ヵ月 × 20年)
- ゆとりある生活費:9,096万円(37.9万円 × 12ヵ月 × 20年)
また、20年間で受給できる年金の総額は3,456万円(14.4万円 × 12ヵ月 × 20年)です。さらに、退職金2,000万円を加えると、老後資金の合計は5,456万円となります。
老後資金の合計と20年間で必要な生活資金の差額は以下のとおりです。
- 最低日常生活費:112万円(生活費5,568万円 -老後資金5,456万円)
- ゆとりある生活費:3,640万円(生活費9,096万円 -老後資金5,456万円)
よって、20年間で「年金 + 退職金」とは別に、約100万円〜3,000万円以上の資金を用意しなければいけません。上記の差額は老後が20年と想定して算出しているため、このシミュレーションよりも長生きする場合は、さらに多くの資金を用意する必要があります。
退職金を運用する方法4選
退職金は老後生活を送るための重要な資金です。多くの方が、年金では足りない生活費を補う目的で退職金を活用します。
この使い方の問題点は「老後期間が何歳まで続くのかがわからない」ので、想定よりも長生きした場合、生活費が足りなくなってしまうことです。
この問題を解決するためには、退職金を運用するのが有効です。運用がうまくいけば資産寿命が延びるので、前述した長生きリスクに備えられます。本項では、以下4つの運用方法を解説します。
- 不動産投資
- 株式投資
- 投資信託
- 定期預金
運用方法によって、メリットやデメリット、リスクの大きさが異なります。それぞれの特徴を把握して、ご自身に最適な運用方法を見つけましょう。
不動産投資
不動産投資とは、投資用物件を購入して家賃収入や売却益を得る方法です。一度入居者が決まると、定期的に家賃収入を得られます。そのため、年金だけでは足りない老後資金を補う手段として非常に有効です。
また、家賃は株価や配当金と比べると変動が少なく、「来月から突然家賃収入が半分になる」といったリスクが低いことも魅力です。
さらに、物件の管理を管理会社に委託すれば、入居者との連絡やトラブル対応を任せられるので、ご自身の手間を大幅に減らせます。ただし、空室リスクや突発的なトラブルに伴う修繕費などのリスクも存在するため、投資エリアや物件選びは慎重に行わなければいけません。
不動産投資は適切なリスク管理と対策を行えば、毎月安定した家賃収入を期待できるのが魅力です。年金では足りない生活費を補う手段として長期的な収益源を期待している方には、不動産投資がおすすめです。
株式投資
株式投資とは、直接企業の株式を購入して配当金または売買益を得ることを目的に行う投資方法です。特に近年は、老後の生活資金を作る方法として、配当金を得ることを目的にした株式投資が人気を集めています。
比較的業績のブレが少ない会社や業界の株を購入して保有することにより、長期で安定した配当金を得られるためです。また、一度株式を購入すると、年1回または2回定期的に配当金が口座に振り込まれるため、運用の手間がほとんどかかりません。
ただし、株式投資には元本割れのリスクがあります。特に短期で株価の動きを予想するのは専門家でも非常に難しいです。そのため、投資する銘柄や会社の業績、相場状況によっては、受け取れる配当金以上に株価が下落してしまうおそれがあります。
また、会社の業績悪化や業界全体が低迷すると、減配(配当金が減らされること)や無配(配当金がなくなること)になる可能性があります。
投資信託
投資信託とは、投資家から集めた資金を運用の専門家が株式や債券などに投資し運用する金融商品です。運用は専門家であるファンドマネージャーが行うため、投資にあまり詳しくない方でも始められます。
また、ひとつの投資信託を購入すると複数の銘柄に分散投資できるため、前述の株式投資よりも値下がりリスクを抑えられます。
近年はNISAやiDeCoといった非課税制度も充実してきており、税金面でも非常にお得です。ただし、投資信託は元本保証がないため、運用成績によっては元本割れのリスクがあります。
また、NISAやiDeCoで購入できる銘柄は、毎月分配型の投資信託が購入できません。NISAの成長投資枠では隔月分配型(2ヵ月に1度分配金が支払われる投資信託)など、分配金を受け取れる投資信託に投資することも可能ですが、分配金を支払う投資信託は基本的にコストが高く、長期的には高額な手数料を支払わなければなりません。加えて、運用成績が悪いと、元本を取り崩して分配金を支払うため、基準価額(投資信託の価格)が下がるリスクがあります。
そのため、非課税制度を利用して分配金を受け取れる投資信託を購入することは、おすすめできません。また、投資信託は売却して現金化しなければ、老後の生活資金としては使えないこともデメリットです。
これらの理由から、投資信託は定期的な収入源としてはあまり向いていません。投資信託をメインに老後の生活費を準備する場合は、売却計画を立てる必要があるため、投資や運用に詳しくない方では取り扱いが少々面倒に感じることもあるでしょう。
定期預金
定期預金は、あらかじめ預け入れ期間を指定して金融機関にお金を預ける金融商品です。預け入れ期間は金融機関によって異なり、1ヵ月〜10年が一般的です。
預け入れ期間中は原則お金を引き出すことはできないので、使い道が決まっていないお金を保管しておく、または特定の用途のために資金を確保しておくのに適しています。
定期預金は「1,000万円 + 利息」まで元本保証されているのがメリットです。しかし、定期預金は安定性が高い分、運用してもほとんど増えないデメリットがあります。
定期預金の一般的な金利は0.125〜0.4%程度で、預入期間に比例して高くなる傾向があります。ただし、比較的高い金利が適用される場合でも大きなリターンは期待できません。例えば、退職金の1,000万円を年利0.4%で運用しても、1年後の利息はわずか4万円程度と、毎月の生活費や余裕資金としては物足りないでしょう。
また定期預金は、基本的に満期を迎えるまで引き出しができないため、病気やケガによる治療費などの突発的な資金需要には対応しにくい点もデメリットです。
定期預金は退職金を守る運用としては優秀ですが、増やす運用にはあまりおすすめできません。
不動産投資の2つのメリット

退職金の運用方法としておすすめできるのは不動産投資です。不動産投資は定期的に家賃収入を得られるだけでなく、短期的な元本割れのリスクが少ないことが魅力です。また、管理会社に物件の管理を委託すると、ご自身の手間を大幅に減らせるメリットもあります。
本項では、不動産投資のメリットをさらに深掘りします。
- 年金以外の収入源を作れる
- 金融機関から融資を受けて投資ができる
これらのメリットに魅力を感じる方は、退職金での不動産投資を検討しましょう。
年金以外の収入源を作れる
不動産投資は、年金以外の収入源を作る方法として有効です。理由として、投資用物件を購入し、入居者が決まると定期的に家賃が振り込まれる点が挙げられます。入居者や物件によっては、5年以上住み続けてくれるケースもあり、家賃収入は年金以外の安定した収入源として期待できます。
例えば、大学や大企業の工場などがあるエリアは、入居者が長期で入居する傾向にあるので、安定して家賃収入を得ることが可能です。
上記はあくまで一例ですが、不動産投資は購入するエリアや物件を厳選すれば、年金以外の強固な収入源を作れる非常に有効な方法と言えます。
金融機関から融資を受けて投資ができる
不動産投資の特有のメリットは、金融機関から融資を受けて投資ができることです。
基本的に株式や債券、FXなどの投資に対して金融機関は融資をしてくれません。一方で、不動産投資は不動産賃貸業として扱われるため、金融機関から融資を受けて物件の購入ができます。
融資を受けて物件を購入するメリットは、手元資金(退職金)がなくならないことです。手元資金があれば、退職金を運用以外に使うことが可能です。例えば、病気やケガの治療費、旅行をはじめとした趣味のお金に充てることができます。
また、退職金で別の投資用物件を購入することも可能です。例えば、退職金だけではひとつの物件しか購入できない場合でも、融資を利用すれば複数の物件を同時に取得し、家賃収入を増やすこともできます。
さらに複数の物件を所有することで、一部屋が空室になったとしても焦らずに済みます。他の物件が埋まっていれば、家賃収入全体が大きく減少することはないためです。
つまり、融資を受けることで不測の事態に備えたり、投資効率を上げたりすることができます。
不動産投資のデメリットと対策
不動産投資にはメリットも多い一方で、以下2つのデメリットもあります。
- 空室リスクと家賃変動リスクがある
- 融資を受けられないこともある
対策も併せて紹介するので、不動産投資で失敗したくない方は参考にしてください。
空室リスクと家賃変動リスクがある
不動産投資には、空室リスクと家賃変動リスクがつきものです。家賃収入は入居者がいて初めて発生するため、住人が退去すれば家賃収入はゼロになります。
特にマンションの1室といった小規模な賃貸経営を行っている場合は、住人が退去した場合の影響は非常に大きいです。例えば、家賃8万円のマンション1室のみ運営している場合、1ヵ月空室になると8万円分の収入すべてが失われます。空室が2ヵ月、3ヵ月と続くと、損失額が大きくなることに加え、ローン返済や管理費の支払いが難しくなる可能性が高いです。
また、家賃は一定に保てるわけではありません。周辺に新築のアパートやマンションが建設されたり、所有物件の内装や設備が古くなると、家賃を下げないと入居者の確保が難しくなります。
このような空室リスクと家賃変動リスクは、需要の高いエリアや物件を選ぶことで軽減しましょう。例えば、都市部の駅近や学校または会社周辺の好立地のエリアは、入居者が集まりやすく空室を防ぎやすいです。
さらに、人気エリアの物件を選ぶことで、家賃の値下げを行わなくても入居者を確保しやすくなります。
融資を受けられないこともある
金融機関から融資を受けるためには、審査に通過しなければならず、場合によっては借り入れできないこともあります。特に定年後は収入が減るため、返済能力が低いと判断されやすく、審査が厳しくなる傾向にあります。
融資を受けられないと、全額自己資金で物件を購入しなければなりません。購入する物件によっては、退職金を全額使わなければならず、想定外のリスクに対応できなくなるおそれがあります。
融資を受けやすくするための対策としては、頭金を多く入れて借り入れ額を減らす方法があります。不動産投資に対する融資では、物件価格の1〜2割の頭金を求められるのが一般的です。例えば、2,000万円の融資を受ける場合は200〜400万円の頭金が必要です。
上記の例では400万円を超える頭金を用意できれば、借り入れ額が少なくなり、金融機関の貸し倒れリスクが小さくなるので、審査に通過する可能性を高められます。
また、事業計画書の作成も有効です。事業計画書には以下の内容を盛り込みましょう。
- 購入予定のエリアで投資する理由
- 入居者の集め方
- 想定家賃の推移や返済計画
- 失敗のリカバリー方法
例えば、「駅近のエリアで単身者向けの物件を購入し、周辺の家賃相場に合わせて収益を見込む」といった具体的な計画があれば、金融機関も融資の可否を判断しやすくなります。
さらに、空室時の対策も明記しておくと、事業計画書のクオリティが上がり、金融機関に不動産投資の本気度を示すことが可能です。
事業計画書をしっかりと準備し、説得力のある投資計画を示すことで、融資を受けられる可能性は高まります。
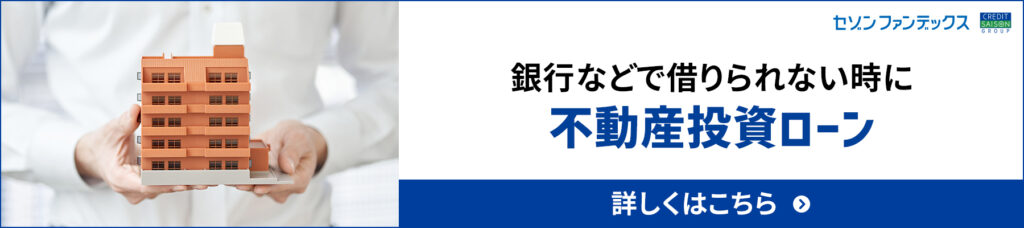
投資効果を高くするには不動産投資ローンの利用を
投資効率を高めるためには、不動産投資ローンの活用が非常に有効です。
しかし、不動産投資ローンの活用はリスクが高いと感じる方もいるでしょう。ただし、全額自己資金で投資用物件を購入すると、先述した想定外のリスクに対応できないおそれがあります。
また、妥協して自己資金で購入できる安価な物件に投資するよりも、不動産投資ローンを活用して収益性の高い物件を購入した方が、空室リスクや家賃変動リスクの軽減が期待できます。
収入や借り入れ枠が原因で銀行の融資条件に当てはまらないので、希望額を借りられない、そもそも融資を受けられないと悩む方もいらっしゃるでしょう。
そのような方は「共同担保」を活用しましょう。共同担保とは、ご自宅やすでに保有している不動産物件を担保にすることで、借り入れ可能額を増やす仕組みです。例えば、すでにローン返済が終わっているご自宅を担保にすれば、追加での借り入れがしやすくなります。
セゾンファンデックスの不動産投資ローンは「共同担保」が認められているのが魅力です。退職金だけでは希望の物件を購入できない方でも、共同担保を活用すれば、理想とする物件への投資が行えます。
加えて、セゾンファンデックスの不動産投資ローンは、中古物件や狭小物件、借地権付き建物など一般的な金融機関では融資が難しい物件にも対応しているのがメリットです。そのため、他の金融機関で融資を断られてしまった方でも、活用できる可能性があります。
気になる方は下記のリンクからお問い合わせください。
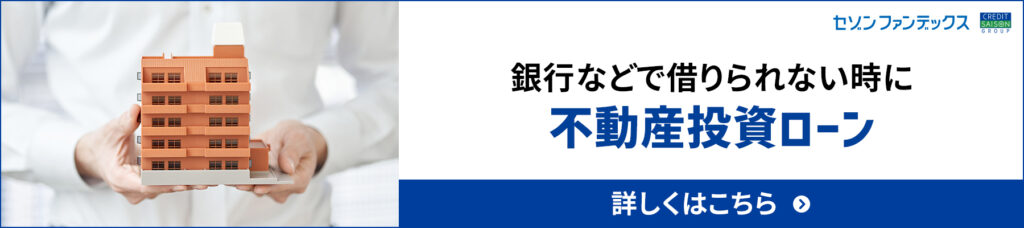
おわりに
厚生労働省の調査によると、現在60代の方の平均余命は20年以上もあります。そのため、生活資金が枯渇しないように退職金を賢く運用する必要があります。この記事で特におすすめしている資産運用方法は、不動産投資です。
不動産投資は家賃収入を得ることで、長期的な収益が期待でき、資産として子どもや孫へ引き継ぐことも可能です。一方で、空室リスクや融資の審査が厳しいというデメリットもあるため、不動産投資を始める前には慎重な検討が欠かせません。特に定年後は収入が下がるため、返済能力が低いと判断されやすく、審査に通りにくい点には注意が必要です。
しかし、セゾンファンデックスの不動産投資ローンであれば、他の金融機関に融資を断られてしまった方でも利用できる可能性があります。
また、断られやすい中古物件や狭小物件、借地権付き物件にも柔軟に対応しており、共同担保の活用で借り入れ可能額を増やせる点も大きな魅力です。
退職金を活用した不動産投資に興味のある方は、下記のリンクからご相談ください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。