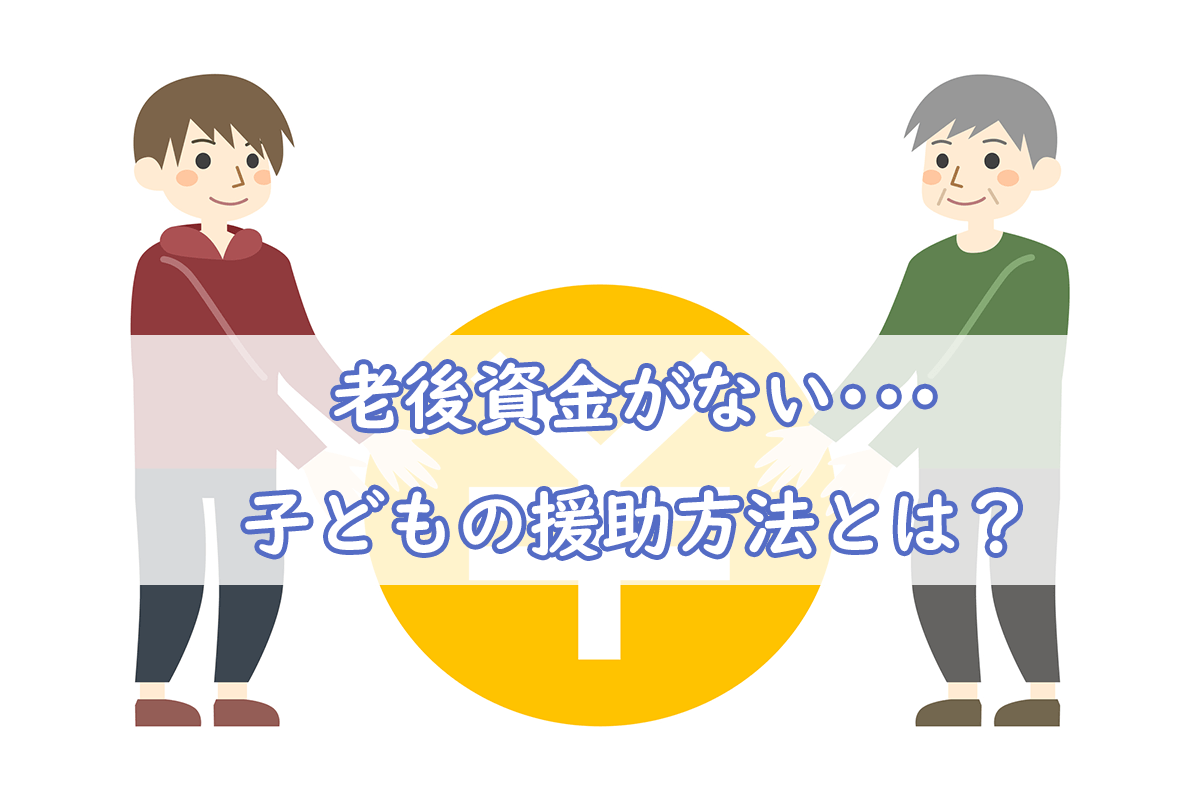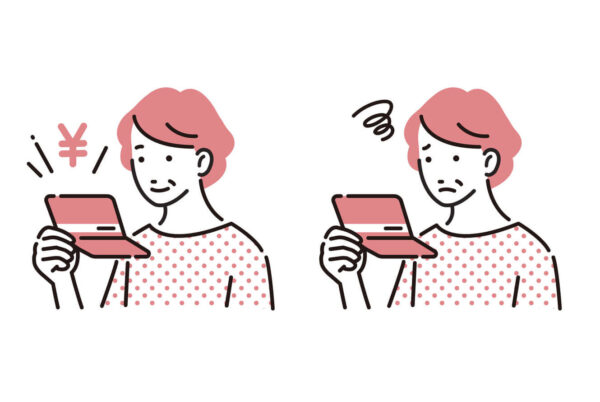親の老後の蓄えが十分でないとわかったら、多くの方は不安や戸惑いを覚えるでしょう。「自分にできることはあるのか」「親の生活は大丈夫なのか」など、さまざまな思いが頭をよぎるかもしれません。
実際、超高齢化社会と呼ばれる日本では、親世代の経済的余裕が無いことに悩む方が増えています。この問題は、子ども世代の将来設計に大きな影響を与えかねません。
そこでこの記事では、親の老後の資金不足に直面している方に向けて、以下の内容を解説します。
- 確認すべき5つのチェックポイント
- 子どもにできる5つの対策
- 3つの公的制度
- 介護費用の目安
- おすすめの資産活用方法
本記事を読むことで、親の老後生活を経済的に支援するための具体策がわかり、この窮地を乗り越える道筋が見えてくるはずです。持ち家がある場合に利用できるおすすめの方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。


親の老後にお金がないことがわかったら!確認すべき5つのチェックポイント

親の経済状況が厳しいとわかった場合、まずは現状を把握することから始めましょう。以下の5つのポイントを順番にチェックしていきましょう。
- 年金その他の収入金額保有資産の種類と金額
- 毎月の支出の内訳と金額
- 親の健康状態今後の大きな出費と予定額お金の話はデリケートな話題ですが、支援するには欠かせない確認事項です。親の気持ちに配慮しながら、協力をお願いしましょう。
年金その他の収入金額をチェック
まずは、親の定期的な収入がどのくらいあるのか確認します。年金の支給額は「ねんきんネット」や「年金定期便」、すでに年金が支給されているのであれば「年金振込通知書」などで確認できます。企業年金や個人年金に加入している場合には、公的年金に加えて支給されます。漏れなく確認しましょう。
パートなどの副収入は、給与明細や通帳などを親の同意を得たうえで見せてもらいましょう。
その他、以下の収入もあわせて確認し、総収入額を算出します。
- 不動産収入
- 株式配当金
保有資産額をチェック
次に、資産状況についても確認しておきましょう。一般的な家庭の資産の例を挙げるので、参考にしてみてください。
- 金融資産(預貯金、保険商品、株式、債券、投資信託など)
- 不動産(自宅、賃貸用不動産、投資用不動産など)
- 貴金属や宝飾品
- その他(車、家具、骨董品など)
定期預金や保険は、満期日と解約返戻金もあわせて確認しましょう。その他の、換金可能な資産は概算額を出し、総資産を把握します。
また、ローンやクレジットカードの返済残高など、マイナスの資産も忘れずにチェックしましょう。
毎月の支出額をチェック
家計の収支を把握するには、日々の暮らしにかかる費用の確認も不可欠です。家賃や光熱費、食費、医療費などを確認し、毎月の支出を固定費と変動費に分けて算出します。そのうえで、収支を分析しましょう。また、無駄な支出がないかどうかもチェックします。
ただし、親を責めるのは逆効果です。この時点ではあくまで現状の把握と、削減可能な項目の洗い出しにとどめましょう。
親の健康状態をチェック
将来の生活費を見積もるには、親の健康状態も把握しておく必要があります。高齢者は、生活費に占める医療費の割合が高いからです。持病の有無や通院状況、服薬状況などを聞いて、今後予想される医療費を試算しましょう。
また、状況によっては将来の介護の可能性も考慮し、介護費用についても考えておくと安心です。
とくに、親が遠方に住んでいる場合、健康状態は丁寧にチェックしましょう。万一、認知症が疑われる場合は、今後お金の管理が難しくなります。早めに医療機関を受診して、方針を検討しましょう。
大きな出費予定をチェック
近い将来、まとまったお金が必要になるか、あわせて確認しておきましょう。主な出費には次のようなものがあります。
- 住宅の修繕費やバリアフリー対策費用
- 車や家電製品の買い替え
- 冠婚葬祭費用
今後、想定される大きな出費にはどんなものがあるでしょうか。戸建てでもマンションでも築年数が経過すれば老朽化に伴い修繕費がかかります。車や家電製品も購入から10年が経過すれば買い替えを検討すべきでしょう。ライフプランに合わせて必要な費用を準備する必要があります。
「老後のお金ない」と親に言われた子どもができる5つの対策

親から「老後のお金ない」と打ち明けられた場合、子どもにできる対策は以下の5つです。
- 家計の見直しを提案する
- 経済的に援助する
- 親を扶養に入れる
- 同居を検討する
- 公的支援制度を調べる
それぞれの対策について、具体的に説明していきます。
家計の見直しを提案する
まずは親に収支状況を説明することから始めましょう。
退職後も現役時代と同じような生活を送っていると、収入が減る分だけ家計が圧迫されるのは当然です。そこで、収入と支出の状況を親子で一緒に確認し、見直しが必要な点を洗い出しましょう。
とくに固定費は毎月の支出に大きく影響するため、優先的に見直します。例えば、携帯電話料金のプラン変更や保険料の見直しをすると、月々の支出を楽に抑えられます。
その他にも、光熱費の節約や、食費の見直し、趣味にかける費用の調整など、親ができそうなところから支出を抑える提案をしてみましょう。
経済的に援助する
子ども世帯が経済的に余裕がある場合は、親世帯へ金銭面での支援を検討してみましょう。ただし、援助をする際はご自身の経済状況を考慮しつつ、無理のない範囲で支援することが大切です。
医療費や介護費用など今後発生する可能性がある支出についても、計画的に準備していくと安心できます。
親を扶養に入れる
親を扶養に入れることで、条件を満たせば「税法上」と「社会保険上」の2種類の控除が受けられます。
【税法上の扶養控除】
子ども世帯の所得税や住民税が軽減されます。例えば、親が70歳以上で同居し、年収158万円以下の場合、年間58万円の所得控除を受けられます。
【社会保険上の扶養控除】
親が75歳未満の場合、子どもの扶養に入ることで親は健康保険料の負担を減らせる可能性があります。
これら2種類の優遇措置により、経済的負担が軽減される可能性があります。ただし、扶養控除を受けるには収入など細かい条件があるため、あらかじめ詳細を確認しましょう。また、医療費や介護関連の費用が増加する可能性もあるため、総合的な判断が求められます。
同居を検討する
経済的な負担を減らす選択肢のひとつとして、親との同居があります。共同生活をすることで、家賃や光熱費などの固定費を抑えられるでしょう。また、親の体調の変化にすぐ気づけるメリットもあります。
ただし、お互いの生活リズムやプライバシーを尊重する必要があるため、事前によく話し合うことが大切です。
公的支援制度を調べる
いざという時のために、利用できる公的支援制度について調べておくことをおすすめします。制度をうまく活用することで、親の生活を支えられる可能性があります。
多くの高齢者は、制度の存在自体を知らなかったり、インターネットでの手続きに不安を感じたりすることが多いものです。そのようなときは、子どもがサポートすることで親の経済的な負担を軽減できます。
親の老後を支援する3つの公的制度
親の老後資金が不足している場合、公的制度を利用することで経済的な負担を軽減できる可能性があります。ここでは、親の老後のお金の問題に役立つ3つの公的制度をご紹介します。
- 高額医療・高額介護合算制度
- 生活保護制度
- 生活福祉資金貸付制度
それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度は、医療費や介護費用の負担を軽減するための制度です。この制度は、同じ世帯内で1年間に支払った医療費と介護費の合計額が、一定の限度額を超えた場合、その超えた金額が払い戻される仕組みです。
適用対象は、健康保険と介護保険の両方を利用している世帯で、医療費と介護費が重なる場合に限られます。世帯所得に応じて自己負担限度額が設定されており、所得が低い世帯ほど限度額は低くなります。
この制度を利用するには申請が必要なので、詳しい手続きについてはお住まいの市区町村窓口に問い合わせましょう。
生活保護制度
生活保護制度は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を送れるよう、保障するために設けられました。この制度は一定の困窮状態にある方が利用でき、不動産や預貯金などの資産がないことが適用の条件です。
年金だけでは生活費をまかなえない方も対象となりますが、親族などから支援が可能な場合はその支援が優先されます。これらの要件を満たし、世帯収入が国で定める最低生活費を下回る場合、生活保護が適用される仕組みです。
適用後は、日常生活費を支給する「生活扶助」をはじめ、「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」といった支援が必要に応じて受けられます。ただし、毎月の収支報告が義務付けられている点には留意しましょう。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは、地域の社会福祉協議会が主体となって行っている制度で、一定の条件に当てはまる方に対して、低利子でお金を貸してくれる仕組みです。
貸付の対象となる世帯は、「障害者世帯」や「低所得世帯」「高齢者世帯」です。
福祉資金には、生活に必要な費用も含まれており、資金使途に応じて最高580万円まで借りられます。返済期間も最長20年と長く設定されており、連帯保証人がいれば無利息となるのが大きな特徴です。
保証人がいない場合には利息が発生しますが、金利は年1.5%とかなり低い水準に抑えられています。高齢者世帯は65歳以上の世帯を指しますので、該当するなら申請を検討してみましょう。
お金がないでは避けて通れない!老後の親の介護費用の目安額

親の介護にかかる費用は、予想以上に高額になる可能性があります。子ども世代は、将来どのくらいの介護費用が発生するのか、目安金額を把握しておきましょう。
生命保険文化センターの「2021(令和3)年度生命保険に関する全国実態調査」より、介護費用の目安金額を紹介します。
- 一時的な費用:約74万円(住宅リフォームや介護用ベッド購入など)
- 月額平均費用:自宅介護は約4.8万円、施設に入所している場合は約12.2万円
このうち、公的介護保険の自己負担割合は、所得に応じて1割~3割です。同調査によると、平均介護期間は約5年間となっており、かなりの長期戦が予想されます。
では、介護状態によって費用はどのように変化するか、以下の表で確認してみましょう。介護度は、右にいくほど重くなります。
単位:万円
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一時的費用 | 101 | 37 | 39 | 61 | 98 | 48 | 107 |
| 月額費用 | 4.1 | 7.2 | 5.3 | 6.6 | 9.2 | 9.7 | 10.6 |
〈参考〉生命保険文化センター「2021(令和3)年度生命保険に関する全国実態調査」
介護費用を介護度別に見ると、一時的な費用(住宅リフォームや介護用ベッド購入など)と毎月かかる費用の、どちらも概ね介護度が上がるほど費用も高くなっています。
お金がない親の老後におすすめの資産活用方法
親の家が持ち家であれば、それは大きな資産として活用できます。その方法のひとつとしておすすめなのが「リースバック」です。リースバックとは、自宅を売却して現金化したあとも、毎月の家賃を支払うことでそのまま住み続けられる仕組みです。
リースバックには4つのメリットがあります。
- まとまった資金が手に入る
- 住み慣れた家に住み続けられる
- 引っ越しの費用が不要
- 固定資産税の負担がなくなる
長年住み慣れた自宅を離れたくない親にとって、リースバックは有力な選択肢となるでしょう。
リースバックを検討するなら、セゾンファンデックスが提供する「セゾンのリースバック」がおすすめです。セゾンファンデックスはプライム市場に上場しているクレディセゾンの100%子会社のため、安心して任せられます。また、セゾンのリースバックなら、将来買い戻せるのも大きな魅力です。


セゾンのリースバックの説明動画です。(音声が出ます。音量調整にご注意ください。)
おわりに
老後の資金不足問題は、少子高齢化や日本の人口減少問題とともに見過ごすことができない重要課題です。貯蓄があったとしても、この超高齢化社会では十分とは限りません。親は子どもに負担をかけたくないあまり、限界まで我慢しがちです。そのため、気付いた時には取り返しのつかない状況に陥っている可能性もあります。親の資金不足が気になる方は、早めに問題を共有してできる対策から取り組んでいきましょう。
とくに、親がリタイアした際には、老後の資金は大丈夫か、自分たちにできることはないかなどを話し合い、可能な範囲で援助することを伝えておくことが大切です。
その対策のひとつとして、親の自宅が持ち家ならばリースバックという選択肢があることを伝え、意向を確認しておくことをおすすめします。そのためにも、まずはご自身がリースバックの特徴を理解し、メリットやデメリットをしっかりと把握しておきましょう。
リースバックに興味をお持ちの方は、ぜひセゾンのリースバック公式WEBサイトをチェックしてみてください。老後資金確保以外にもさまざまな活用法があるので、あなたの生活に役立つヒントが見つかるかもしれません。


※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。
あなたにおすすめのコラム