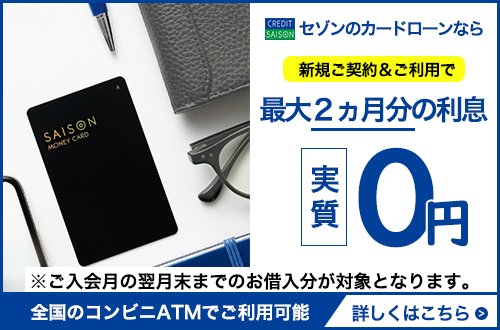生命保険文化センターが公表しているデータによると、入院時の自己負担額(手術費用を含む)の平均は約21万円です。傷病の種類や入院期間によって高額な医療費が発生するため、支払いについて考えておかなければいけません。手術費用の備え方や自己負担を抑える制度などを解説します。


入院・手術費用はどのくらい?一覧で紹介

入院・手術の際にはさまざまな費用が発生します。主な入院費用は傷病ごとに異なりますし、理由によって入院の平均日数も変わってきます。
傷病の治療にかかる費用だけではなく、医療費以外に支払うべきものもあるため注意しましょう。ここでは入院・手術にかかる費用について、1日あたりの入院費用の平均や傷病別に発生する費用、妊娠・出産や子どもの入院時にかかる費用などを解説します。
1日あたりの入院費用の平均
公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、1日あたりの入院費用の平均は2万700円という結果でした。全体の4分の1を占めているのが1〜1.5万円(23.3%)で、次に多いのが2~3万円(16.0%)です。
| 直近の入院時の1日あたりの自己負担費用 | 割合 |
|---|---|
| 5,000円未満 | 13.8% |
| 0.5〜0.7万円未満 | 8.8% |
| 0.7〜1万円未満 | 11.5% |
| 1〜1.5万円未満 | 23.3% |
| 1.5〜2万円未満 | 7.9% |
| 2〜3万円未満 | 16.0% |
| 3〜4万円未満 | 5.5% |
| 4万円以上 | 13.2% |
参照元:公益財団法人生命保険文化センター「2022(令和4)年度生活保障に関する調査」
また、同調査によると、入院した際にかかる全体的な自己負担額の平均は19万8,000円です。この数字には後述する差額ベッド代や食事代なども含まれます。
| 直近の入院時の自己負担費用 | 割合 |
|---|---|
| 5万円未満 | 9.4% |
| 5〜10万円未満 | 26.5% |
| 10〜20万円未満 | 33.7% |
| 20〜30万円未満 | 11.5% |
| 30〜50万円未満 | 10.1% |
| 50〜100万円未満 | 5.8% |
| 100万円以上 | 3.0% |
参照元:公益財団法人生命保険文化センター「2022(令和4)年度生活保障に関する調査」
主な病気の入院費用の平均と入院平均日数
病気を患って入院する際は、どんな傷病かによって入院費用や入院日数が異なります。公益社団法人全日本病院協会と厚生労働省の調査を元に、主な病気の入院費用と入院日数の平均をまとめました。
| 傷病の種類 | 入院費用の平均 ()内は1日あたりの金額 |
|---|---|
| 脳梗塞 | 180万5,592円(6万8,577円円) |
| 急性心筋梗塞 | 200万7,744円(17万5,113円) |
| 糖尿病 | 76万1,967円(4万9,402円) |
| 気管支がん及び肺がん (気管支及び肺の悪性新生物) | 93万3,507円(12万770円) |
| 胃がん(胃の悪性新生物) | 104万5,951円(8万7,797円) |
| 乳がん(乳房の悪性新生物) | 74万3,373円(10万6,514円) |
| 肺炎 | 92万1,133円1(5万2,910円) |
| 胃潰瘍 | 77万3,696円(6万1,624円) |
| 喘息 | 46万9,599円(4万8,129円) |
参照元:公益社団法人全日本病院協会「「医療費」重症度別20230年度1月〜3月分」
いずれも高額な費用がかかることがわかります。特に急性心筋梗塞は1日あたり約17万円の費用が発生するため、入院時の負担は大きいでしょう。
| 傷病の種類 | 入院日数の平均 35〜64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 |
|---|---|---|---|
| 脳血管疾患 | 51.8日 | 83.6日 | 93.2日 |
| 心疾患(高血圧性のものを除く) | 12.6日 | 27.6日 | 33.7日 |
| 糖尿病 | 15.6日 | 40.7日 | 51.1日 |
| 気管支がん及び肺がん(気管・気管支及び肺の悪性新生物) | 16.1日 | 22.3日 | 26.6日 |
| 胃がん(胃の悪性新生物) | 19.4日 | 22.9日 | 26.4日 |
| 乳がん(乳房の悪性新生物) | 8.6日 | 23.8日 | 38.5日 |
| 肺炎 | 21.9日 | 41.0日 | 43.1日 |
| 消化器系の疾患 | 9.1日 | 16.4日 | 19.6日 |
| 喘息 | 12.2日 | 30.8日 | 37.6日 |
入院日数の平均に関しては、傷病の種類のほかに年代においてもばらつきが見られます。
妊娠・出産の入院時に発生する費用
傷病以外の入院理由として、妊娠や出産が挙げられます。いずれも病気ではないため、正常分娩の場合は公的医療保険が適用されません。公益社団法人国民健康保険中央会の調査によると、妊娠・出産時に負担が発生する費用の内訳は以下のとおりです。
| 項目 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 入院日数 | 6日 | 6日 |
| 入院料 | 11万2,726円 | 10万2,000円 |
| 室料差額(差額ベッド代) | 1万6,580円 | 0円 |
| 分娩料 | 25万4,180円 | 25万円 |
| 新生児管理保育料 | 5万621円 | 5万1,500円 |
| 検査・薬剤料 | 1万3,124円 | 1万円 |
| 処置・手当料 | 1万4,563円 | 5,560円 |
| 産科医療補償制度 | 1万5,881円 | 1万6,000円 |
| その他 | 2万8,085円 | 1万8,440円 |
| 妊婦合計負担額(自己負担額) | 50万5,759円 | 49万3,400円 |
参照元:公益社団法人国民健康保険中央会「正常分娩分の平均的な出産費用について(平成28年度)」
これらの費用をサポートする公的医療保険制度として、出産育児一時金や出産費貸付制度などがあります。出産育児一時金は子ども1人あたり一律50万円が給付されます。出産費貸付制度は、出産育児一時金が給付されるまでの期間に見込額の8割までを無利子で貸し付けてもらえる制度です。
ただし、これらの制度だけでは妊娠・出産にかかる費用をすべてカバーするのは難しく、切迫早産や帝王切開などがあれば費用負担がより大きくなるケースもあります。公的な制度を賢く利用しつつ、不足する分は民間の医療保険でのカバーを検討しましょう。
参照元:厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」
全国健康保険協会「出産費貸付制度」
子どもの入院時に発生する費用
日本では、子どもが医療を受ける際の費用負担が抑えられる仕組みが整っています。例えば、小学校に通う前の乳幼児の場合、治療にかかる費用の自己負担は2割です。 なお、子どもの年齢や助成される金額、助成を受けるための方法などの要件に違いがあるものの、各自治体では子どもの医療費を助成する制度が設けられています。ただし、入院に際して発生する医療費以外の費用には目を向けなければいけません。
入院するとなれば、交通費や雑費が発生するほか、子どもが複数人いる家庭では留守番時にベビーシッターを利用することもあるでしょう。子どもの入院中に付き添うのであれば、仕事を休むことによる収入の減少は避けられません。 子どもの医療費をサポートする制度は充実していますが、医療費のほかにもさまざまな費用がかかることを覚えておきましょう。
参照元:厚生労働省「子どもの医療の費用負担の状況」
入院時にかかる医療費以外の費用
入院する際は、治療費以外の以下の費用がかかります。
- 交通費
- 差額ベッド代
- 食事代
- 生活費
- 交通費 など
交通費は入院する本人ではなく、家族が付き添いや面会のために病院を訪れる際に発生します。
差額ベッド代とは、個室や少人数の病室を希望する際にかかる追加料金です。
食事代は入院中の病院食に対して支払うもので、自己負担額は全国一律1食あたり460円です。なお、住民税非課税世帯は条件に応じて100円、210円と負担が軽くなります。
生活費として、病室で見るテレビの視聴料や、着替えのためのクリーニング代などが挙げられます。これらは公的医療保険の対象に含まれないため、かかった費用はすべて自己負担です。
参照元:厚生労働省「入院時の食費について」
入院・手術費用の自己負担割合

入院・手術の際には、公的医療保険制度を適用することで自己負担額を抑えられます。どのくらいの金額を負担するかは、それぞれの年齢や所得によって決められています。
そもそも、日本には国民皆保険制度があり、以下3つのいずれかの保険に加入する必要があります。
- 被用者保険
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療制度
被用者保険の対象者は、会社で働く方やその家族です。国民健康保険は75歳に満たない自営業者とその家族、後期高齢者医療制度は75歳以上の方を対象としています。保険の加入者は健康保険証を所有でき、医療を受ける際に提示することで自己負担額が軽減されます。
公的医療保険制度を適用してもすべての医療費がカバーされるわけではなく、区分ごとに定められた割合の分の費用を負担しなければいけません。
| 年齢の区分 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 6歳未満(就学前の子ども) | 2割 |
| 小学校入学後〜69歳 | 3割 |
| 70〜74歳 | 2割 |
| 75歳以上 | 1割 |
ただし、70歳以上の方でも課税所得が145万円以上ある方は現役並み所得者とされ、自己負担割合は1割や2割ではなく3割負担となります。 なお、以下のような保険診療に当てはまらない項目は、給付を受けられません。
- 自由診療
- 先進医療
- 入院中の食事代
- 差額ベッド代
- 入院中の日用品代
- 家族の付き添い時に発生する交通費や宿泊費など
公的医療保険制度は、適用できる範囲が決まっている点に注意しましょう。
参照元:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
入院・手術費用に利用できる8つの制度

入院・手術を受ける際は高額な費用の支払いが発生するため、費用負担を軽減するためにさまざまな制度が設けられています。ここでは、以下の8つの制度についてわかりやすく解説します。
- 高額療養費制度(限度額を超えた医療費の還付・限度額適用認定証・多数該当)
- 高額医療費貸付制度
- 付加給付制度
- 医療費控除
- 傷病手当金
- 一部負担金減免制度
- 無料低額診療事業
- 生活保護
「入院・手術にかかる費用を抑えたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.高額療養費制度|限度額を超えた医療費の還付
高額療養費制度とは、医療を受けた際の自己負担額が一定のボーダーラインを超えた際に、超えた分の金額が還付される仕組みです。ご自身が負担した1ヵ月あたりの費用の合計が対象で、国民健康保険・社会保険の加入者であれば適用されます。 高額療養費の申請を行うタイミングは退院後です。申請から給付までにはタイムラグがあり、およそ3ヵ月程度はかかるため注意しましょう。
適用を受ける方の所得や年齢によって、ボーダーラインとなる限度額の計算方法が異なります。年齢の区分は69歳以下と70歳以上の2パターンで、所得は細かく分類されています。
【対象:69歳以下|自己負担限度額の計算方法】
| 適用区分 | 世帯ごとの自己負担限度額/月 |
|---|---|
| 区分ア|年収約1,160万円~ | 25万2,600円+(総医療費-84万2,000円)×1% |
| 区分イ|年収約770万~約1,160万円 | 16万7,400円+(総医療費-55万8,000円)×1% |
| 区分ウ|年収約370万~約770万円 | 8万100円+(総医療費-26万7,000円)×1% |
| 区分エ|~年収約370万 | 5万7,600円 |
| 区分オ|住民税非課税者 | 3万5,400円 |
出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
【対象:70歳以上|自己負担限度額の計算方法(平成30年8月以降の診療分)】
| 適用区分 | 世帯ごとの自己負担限度額/月 | 外来(個人ごと) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者(年収約370万円以上) | 69歳以下の区分ア〜ウと同じ | 69歳以下の区分ア〜ウと同じ |
| 一般(年収156万~約370万円) | 5万7,600円 | 1万8,000円(年14万4,000円 ) |
| Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 2万4,600円 |
| Ⅰ 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) | 8,000円 | 1万5,000円 |
出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
例えば、70歳以上で年収約370~約770万円(自己負担割合:3割)の方が医療費100万円のうち3割負担の30万円を支払う場合、30万円から自己負担の上限額を差し引いた金額が還付されます。
- 自己負担の上限額:8万100円+(100万円-26万7,000円)×1% = 8万7,430円
- 高額療養費として支給される金額:30万円-8万7,430円 = 21万2,570円
還付される金額の目安は、 21万2,570円です。
限度額適用認定証|窓口での医療費負担の軽減
限度額適用認定証は、窓口での医療費の支払いが軽減される制度です。高額療養費制度を適用して超過分の医療費を受け取るまでは、申請からおよそ3ヵ月を要します。医療を受ける際は窓口での一時的な支払いが発生するため、家計に大きな負担がかかるでしょう。
入院や手術費用の支払いが高額になると前もってわかっていれば、限度額適用認定証の申請をしておくのが賢明です。申請書類を提出すると、限度額適用認定証が発行されます。医療費の会計をする際に保険証と一緒に窓口に提出すれば、窓口での支払いは自己負担限度額までに抑えられます。
併せて知っておきたいのが、高額療養費受領委任払い制度です。制度を利用すると、高額療養費として還付される予定の金額が公的医療保険から病院に支払われます。窓口で支払わなければいけない金額は自己負担限度額までとなるため、家計にかかる負担を軽減できます。
加入している公的医療保険によって、高額療養費受領委任払い制度を利用できるかが異なるため、前もって調べておきましょう。
多数該当|同一世帯で使える医療費負担の軽減
多数該当は、同一世帯の医療費の負担軽減を目的とした制度です。過去12ヵ月のうちに同一世帯で高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目からは多数回と見なされ、自己負担すべき費用の上限額が3回目までよりも下がります。
【対象:69歳以下|多数回該当の場合の自己負担限度額】
| 適用区分 | 多数回該当の場合の自己負担限度額 |
|---|---|
| 区分ア|年収約1,160万円~ | 14万100円 |
| 区分イ|年収約770万~約1,160万円 | 9万3,000円 |
| 区分ウ|年収約370万~約770万円 | 4万4,400円 |
| 区分エ|~年収約370万 | 4万4,400円 |
| 区分オ|住民税非課税者 | 2万4,600円 |
出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
【対象:70歳以上|自己負担限度額の計算方法(平成30年8月以降の診療分)】
| 適用区分 | 多数回該当の場合の自己負担限度額 |
|---|---|
| 年収約1,160万円~ | 14万100円 |
| 年収約770万~約1,160万円 | 9万3,000円 |
| 年収約370万~約770万円 | 4万4,400円 |
| ~年収約370万円 | 4万4,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 多数該当の適用なし |
出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
多数該当の適用を受けられるのは、同一被保険者での治療に限ります。そのため、退職に際して被保険者から被扶養者になった場合は多数該当の月数にカウントされません。なお、加入する医療保険も同一である必要があります。
高額医療費貸付制度|無利子での医療費の貸付
高額医療費貸付制度とは、医療費を無利子で借りられる制度です。高額療養費を受け取るまでの間に、還付される見込金額の8〜9割に相当する金額を貸し付けてもらえます。なお、貸付可能額は公的医療保険ごとに異なります。
制度を利用すれば、高額療養費の支給を待つ間の自己負担額を抑えられるため、家計へのダメージを軽減できるしょう。申請にあたっては、以下の書類を揃える必要があります。
- 高額医療費貸付金借用書
- 被保険者証(または受給資格者票)
- 診療報酬明細書 など
高額医療費貸付制度の利用を検討している方は、必要書類に漏れがないように注意しましょう。
参照元:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
付加給付制度|健康保険組合独自の保障
医療を受ける際には、健康保険組合が独自に行う付加給付制度を利用できます。制度の内容は健康保険組合によって異なるため、前もって調べておくと安心でしょう。
例えば、1ヵ月あたり2万5,000円以上の医療費がかかった際に払い戻しを受けられるケースもあります。制度の呼び方も組合ごとに違いがあり「一部負担金払戻金」「療養費付加金」など、名称はさまざまです。
医療費控除|所得税・住民税の軽減
医療を受けた際にかかった費用には控除が適用され、所得税と住民税の軽減効果が期待できます。これを医療費控除といい、1年間で10万円以上の医療費(扶養家族の医療費も含む)の支払いがあった場合に利用できます。
国民健康保険・社会保険のいずれの加入者も対象ですが、控除の適用を受けるためには確定申告をしなければなりません。申請は確定申告の期間前でも行えるほか、5年前の分までさかのぼって申請することも可能です。
治療や薬にかかった費用だけではなく、主に公共交通機関を利用した病院までの交通費、介護関連のサービスの利用料なども控除対象に含まれます。なお、健康保険が適用されない妊娠・出産の際の費用も対象です。
参照元:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
傷病手当金|給与の3分の2程度を支給
傷病手当金は、会社員や公務員などが病気やケガで働けないときに、生活の保障として給与の3分の2程度が支給される制度です。以下の4つの条件に該当する方が対象です。
- 業務外で病気やケガを負って仕事に就けない
- 労務不能(仕事に就けない状態)と判断される
- 4日以上仕事に就けない(連続する3日間を含む)
- 休業中に給与の支払いがない
1日あたりの金額は、以下の計算式を用いて算出されます。
1日あたりの金額=支給開始日(一番最初に給付が支給される日)以前の継続した12ヵ月間の各月の標準月額を平均した額÷30日×2/3
なお、支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たないケースだと、以下のどちらか低い額を使用して計算します。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 標準報酬月額の平均額
出勤していない日に対して傷病手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額を受け取れることになっています。
参照元:全国健康保険協会「傷病手当金」
一部負担金減免制度|医療費負担の減免
一部負担金減免制度とは、その名のとおり医療費負担の減免を受けられる仕組みです。災害や失業などによって生活の維持が一時的に困難になり、収入が一定基準を下回った場合において、医療費の自己負担額が一定期間減免されます。
どのくらい生活に困っているかを基準として、減免の区分が以下の3つに分かれます。
- 免除
- 減額(自己負担額の20%〜80%の減額)
- 徴収猶予(一定期間の支払いが猶予され、猶予期間経過後に支払いが発生)
減免される期間は申請月から3ヵ月です。ただし、継続して減免が必要であると認められれば、さらに3ヵ月間延長できます。
参照元:厚生労働省「第一 一部負担金の徴収猶予及び減免」
無料低額診療事業|医療費が無料または減額
無料低額診療事業は診療が無料または低額で実施される制度です。病気やケガなどによって生計の維持が難しい方や、経済面の理由から必要な医療を受けられない方などが対象となります。低所得者以外に、要介護者やDV被害者、ホームレスなども対象に含まれます。
制度を利用するためには、源泉徴収票や給与明細票などの提出が必要です。医療費の支払いが難しく、世帯収入が診療にかかる費用の減免基準に達していることを示すためです。
生活の状況が改善するための一時的な措置であり、制度を受けられる期間には一定の基準が定められています。例えば、無料診療を受けられる期間は原則として1ヵ月、最大でも3ヵ月までです。なお、病院以外で発生した診療費は対象外のため、院外処方箋による調剤薬局での支払いなどはカバーされません。
参照元:厚生労働省「無料低額診療事業について」
生活保護|入院・手術の際の医療扶助
生活保護は、医療にかかる費用はもとより、生活を維持すること自体が難しい方向けのセーフティーネットです。健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、さまざまな金銭的サポートが用意されています。
例えば、入院や手術にかかった費用は医療扶助の対象です。病院に対する医療費の支払いは生活保護費から直接行われるため、生活保護の対象者には負担が発生しません。 生活保護では金銭的なサポートを受けられますが、以下のような制約もあります。
- 車や贅沢品を所有できない
- ローンを組めない
- ケースワーカーによる定期的な訪問
生活保護の利用を検討している方は、お住まいの自治体の福祉事務所へ相談してみましょう。
参照元:東京都福祉局「生活保護制度とはどのような制度ですか。」
入院・手術費用と併せて考えたい収入減のリスク

入院・手術の際は、医療費による支出の増加に加えて、収入減のリスクも考えておかなければいけません。病気やケガを負って入院や手術をすることになると、それまでのように働くことは難しくなります。本来であれば働いて収入を得られていたのに、事情によって得る機会を失った収入を「逸失収入」といいます。
特に逸失収入に気をつけなければいけないのは、自営業者の場合です。会社員であれば有給休暇や傷病手当金を利用できるため、収入減のリスクに備えられます。 しかし、自営業者の場合は休業時の収入を保障するセーフティーネットが乏しく、入院する期間分の収入が丸ごと減ってしまう可能性があります。
入院・手術時にはいくらくらいの逸失収入が発生し得るのか、公益財団法人生命保険文化センターの調査を元に表にまとめました。
【直近の入院時の逸失収入】
| 直近の入院時の逸失収入 | 割合 |
|---|---|
| 5万円未満 | 14.2% |
| 5〜10万円未満 | 25.5% |
| 10〜20万円未満 | 24.8% |
| 20〜30万円未満 | 7.1 % |
| 30〜50万円未満 | 13.5% |
| 50〜100万円未満 | 5.7% |
| 100万円以上 | 9.2% |
参照元:公益財団法人生命保険文化センター「2022(令和4)年度「生活保障に関する調査」」
調査によると、入院時に発生した逸失収入の平均は32万円です。
【直近の入院時の自己負担費用と逸失収入の総額】
| 直近の入院時の逸失収入 | 割合 |
|---|---|
| 5万円未満 | 7.6% |
| 5〜10万円未満 | 23.3% |
| 10〜20万円未満 | 32.0% |
| 20〜30万円未満 | 13.7% |
| 30〜50万円未満 | 10.8% |
| 50〜100万円未満 | 7.5% |
| 100万円以上 | 5.1% |
参照元:公益財団法人生命保険文化センター「2022(令和4元)年度「生活保障に関する調査」」
入院に際してかかった自己負担額に逸失収入を合計した金額の平均は30万4,000円です。また、入院日数から1日あたりの合計金額を算出すると、平均2万8,400円という結果でした。
入院・手術の備えを考える際は、医療費だけではなく逸失収入もカバーできるかどうかがポイントとなるでしょう。
入院・手術費用と収入減に備える方法

入院・手術の際は、医療費による支出増加と逸失収入による収入の減少が考えられます。どちらも家計に大きなダメージを与え得るため、前もって備えておく必要があるでしょう。これらのリスクに備える方法として、主に2つの選択肢が挙げられます。
- 民間の医療保険
- 就業不能保険
民間の医療保険とは保険会社が提供する保険商品のことで、加入者自らが保険会社や商品を選択します。医療保険の基本構造は入院と手術に対する保障です。病気やケガによって入院・通院・手術をした際には、主契約として入院給付金や手術給付金が給付されます。
また、主契約に特約を付加することで保障を充実させられるのが特徴です。主契約の内容や給付される金額、特約などは保険会社によって異なります。 就業不能保険も民間の保険会社が提供する商品の一種で、主な目的は病気やケガによって働けない期間の生活費の保障です。商品ごとに定められた要件を満たす方であれば、入院でも在宅療養でも給付金を受け取れます。
入院・手術費用が払えないときに起こること

入院・手術が必要な病気やケガを負った際は大きな費用負担が発生します。場合によっては支払うのが難しいこともあるでしょう。これらの費用の支払いが滞った場合は、以下のような事態に発展する可能性があります。
- 書面や電話などで支払いの督促がくる
- 入院時に指定した保証人に連絡が入る
- 財産が差し押さえられる
- 病院との関係が悪化する
入院・手術費用を支払わずにいると、書面や電話などで病院から督促の連絡が届きます。担当者が自宅を訪問し、口頭で支払いを求めるケースもゼロでありません。督促を無視して支払いの遅延状態を続ければ、病院への提出書類に記載した保証人に連絡が入ります。
それでも支払わない姿勢を続けていると、最終的には病院側の弁護士とのやりとりに発展しかねません。病院側が民事訴訟を起こすケースもあり、最悪の場合は財産を差し押さえられる可能性があります。
支払いを請求される以外に、病院との関係が悪化するかもしれない点にも注意が必要です。支払うべき費用を滞納して病院との関係にヒビが入れば、入院中でも退院や転院を求められることがあります。また、病気の再発によって医療を受けたい際にも利用しにくくなるでしょう。
入院・手術費用が払えないときの3つの対処法
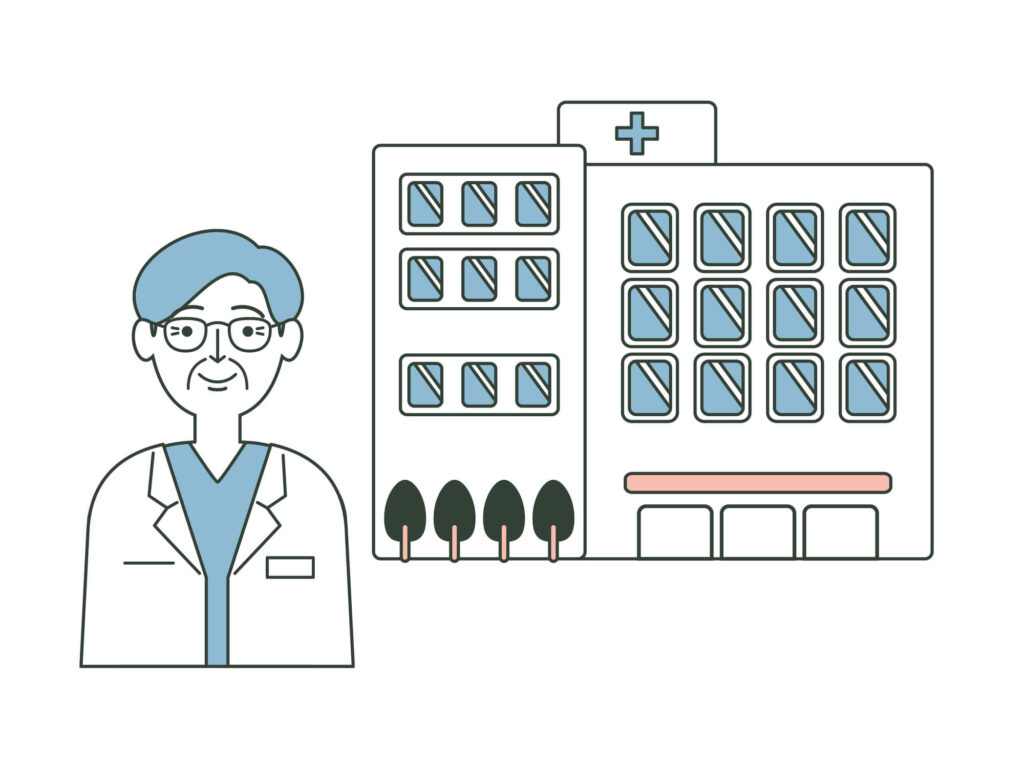
病院への支払いが滞ると、支払いの督促が来たり財産が差し押さえられたりなどのトラブルに発展する可能性があります。経済的な理由からどうしても支払いが難しい場合は、以下3つの対処法を検討しましょう。
- 病院に分割払いを相談する
- 加入している保険の給付金を利用する
- クレジットカードやカードローンを利用する
適切な対処を心がけることで、督促や財産の差し押さえをされる心配は少なくなります。ここでは、入院・手術費用が払えないときに知っておきたい対処法について解説します。
病院に分割払いを相談する
第一に考えたい選択肢が、病院への相談です。病院によっては分割払いに対応していたり、支払いの先延ばしを受け付けていたりします。給与明細や預金通帳のように分割払いの金額やサイクルなどを検討できる書類を準備し、支払いが難しい旨を相談してみましょう。
ケースワーカーやソーシャルワーカーが常駐している病院であれば、支払いが難しいときの対処法や公的医療保険制度の仕組みなどを相談できることもあります。
加入している保険の給付金を利用する
入院・手術費用の支払いが難しい場合は、加入している保険の給付金を利用するのもひとつの手です。医療保険やがん保険などでは退院後に給付金を受け取れるケースが多いですが、商品によっては給付金の一部を先に支払ってもらえることがあります。 賢く利用すれば給付金を入院・手術費用に充てられるため、自己負担額を抑えられるでしょう。
クレジットカードやカードローンを利用する
入院・手術費用が払えない場合の対処法として、クレジットカードやカードローンを利用する方法もあります。これらを利用すれば、現金の用意ができなくても医療費の支払いが可能です。クレジットカードの機能によっては分割払いに設定できます。 ただし、あくまで建て替えに過ぎず、引き落としまでにお金を用意できなければ信用情報が傷つくこともあるため注意しましょう。
入院・手術にかかる費用の支払いが難しいときは、セゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD(マネーカードゴールド)」の利用がおすすめです。MONEY CARD GOLDはクレディセゾンが提供するカードローンで、資金の使用使途が自由なので、医療費用や冠婚葬祭費用などさまざまな用途に使えます。
全国のコンビニ・ATMで利用できるほか、振込キャッシングを使えばパソコン・スマートフォンでの申し込みから最短数十秒で指定の口座に振り込みが可能です。月々の返済は4,000円からとなっており、利用者の都合に合わせて早期返済も受け付けています。突然の入院・手術費用による家計の負担増にお困りなら、MONEY CARD GOLDの利用を検討してみてください。


MONEY CARD GOLDについて詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
入院・手術費用に関するよくある質問

こちらでは、入院・手術費用に関するよくある2つの質問に回答します。
- 入院・手術の費用はいつ支払う?
- 高額医療費の申請はどこですればいい?
順番に見ていきましょう。入院・手術の費用について疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。
入院・手術の費用はいつ支払う?
入院・手術の費用は、退院時に支払うのが一般的です。
ただし、追加の検査や処置が最後に行われるなどで退院時に精算できない場合は、正確な請求額の算出に時間がかかるケースがあります。
加えて、病院の内部処理や請求システムの都合で、退院時に正確な請求額を確定できないケースも考えられます。この場合、病院側から後日に郵送やオンラインで請求書が送られ、そのタイミングで支払いが求められる可能性がある点を覚えておきましょう。
高額医療費の申請はどこですればいい?
高額医療費の申請は、住んでいる自治体の保険年金業務担当で申請する必要があります。なお、申請時には以下の提出が求められます。
- 高額療養費支給申請書
- 保険証
- マイナンバーカード
- 病院の領収書
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 特定疾病療養受療証(あれば)
- 世帯主名義の金融機関口座通帳
提出が必要な書類が多いので、漏れのないように注意しましょう。
おわりに

病気やケガを負って入院・手術を受ける際は、平均して約21万円の自己負担が発生します。1日あたりの入院費用の平均は2万3,300円ですが、傷病によってかかる費用は大きく異なるため注意しましょう。
併せて、入院・手術によって働けない場合に発生する逸失収入についても考えておかなければいけません。高額な医療費の負担軽減を目的とした公的保障を利用しながら、民間の保険で万一に備えることが大切です。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。