親の介護には多くの費用がかかり、経済的な負担が大きくなることがあります。そのため、親や兄弟姉妹から介護費用をもらうことを検討する人も多いですが、お金を受け取る際には適切な手続きやルールを理解することが重要です。また、介護に関する支援制度を活用することで、自己負担を抑えることも可能です。
本記事では、親の介護でお金をもらうべき理由や、費用の捻出方法、注意点について詳しく解説します。さらに、介護関連の支援制度やサービスについても紹介し、経済的な負担を軽減する方法を提案します。親の介護をするにあたり、金銭面の不安を少しでも減らしたい方は、ぜひ参考にしてください。
- 親の介護にかかる費用は月額8.3万円が平均で、一人で抱え込む必要はなく、正当な理由があればお金をもらうことは自然な選択である
- 介護費用の捻出方法は、親から直接受け取る、兄弟姉妹と分担する、補助金制度を活用するという3つの選択肢がある
- 親の介護費用を受け取る際は、勝手な使用を避け、税務上の確認をし、将来の相続トラブル対策をすることが重要である
- 介護休業給付金や介護慰労金など、7つの公的支援制度や民間サービスを組み合わせることで、介護の経済的負担を軽減できる
親の介護でお金をもらうべき2つの理由

親の介護にお金をもらうことに罪悪感を覚える方も少なくないでしょう。しかし、介護には予想以上の費用と時間がかかるため、一人で抱え込むのは現実的ではありません。
以下では、親の介護でお金をもらうべき理由を解説します。
介護にかかる費用は高額であるため
2021年の調査によると、介護にかかる費用は月々平均8.3万円にも及びます。これには、介護サービスの自己負担分に加え、住宅改造や介護用ベッドの購入など一時的な費用も含まれており、その合計額は平均74万円となっています。
また、施設に入所した場合は月額12.2万円、在宅介護でも月額4.8万円かかることがわかっています。要介護度が上がるにつれて費用も増加する傾向にあり、要介護5の場合は月額10.6万円程度必要になります。
参照元:公益財団法人生命保険文化センター|生命保険に関する全国実態調査、公益財団法人生命保険文化センター|リスクに備えるための生活設計
親により良い介護を提供するため
介護期間は平均で5年1カ月という長期にわたります。この期間、介護費用の負担を一人で背負い続けることは、経済的な負担だけでなく、大きな精神的プレッシャーとなります。
特に一人っ子の場合は、介護の実務から費用まですべてを一人で担わなければならず、その重圧は計り知れません。親により良い介護を提供するためにも、介護にかかる費用を支援してもらうことは自然な選択といえるでしょう。むしろ、支援を受けることで精神的な余裕が生まれ、より質の高い介護を提供できる可能性が高まります。
親の介護費用どこから捻出する?3つのケースを紹介

介護費用の捻出方法には、親から直接受け取る方法、兄弟姉妹と分担する方法、公的制度を活用する方法があります。
以降では、それぞれの特徴と注意点について解説します。
【ケース1】親からお金をもらう
親の介護費用は、基本的に親本人や夫婦の貯蓄から支払うことが望ましいといえます。ただし、親の介護でお金を受け取る際には、事前に親や兄弟姉妹と十分な話し合いが必要となります。
具体的な話し合いの項目としては、介護にかかる労力や時間の見積もり、親の経済状況の確認、介護の役割分担などが挙げられます。特に介護の負担については、24時間体制での見守りが必要になることや、夜中の介助で睡眠が取れないこともあるなど、具体的な状況を共有することが重要です。
なお、親の介護をしたことによって親からお金を受け取っても、扶養義務者間の生活費として扱われるため、通常は贈与税の課税対象とはなりません。ただし、受け取る金額が年間110万円を超えるような場合は、贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。
【ケース2】兄弟姉妹からお金をもらう
住んでいる場所や仕事の都合で、直接的な介護に参加できない兄弟姉妹から、介護費用としてお金を受け取るケースもあります。このような場合、介護の実務を担当する人への感謝の気持ちとして、定期的な支援や必要に応じた費用負担という形で協力を得られることがあります。
兄弟姉妹も扶養義務者に該当するため、介護を理由にお金を受け取っても生活費の贈与として扱われ、贈与税の心配はありません。
【ケース3】介護関連の補助金制度を活用する
国や自治体では、介護にかかる経済的負担を軽減するためのさまざまな補助金制度を設けています。高額介護サービス費や介護慰労金など、条件を満たせば利用できる制度が多数存在します。
これらの制度を適切に活用することで、介護費用の負担を大きく軽減できる可能性があります。
親の介護でお金をもらうときに注意するべきポイント

親の介護でお金を受け取る際には、いくつかの重要な注意点があります。
違法性や税務上の問題、将来の相続トラブルを避けるために、以下の3つのポイントをしっかりと押さえておきましょう。
親の貯金は勝手に使ってはいけない
介護の対価として親の預貯金を自己判断で引き出すことは、たとえ介護をしている立場であっても違法行為となります。特に親が認知症になり判断能力を失っている場合、親の同意があったとしても法的に認められない可能性があります。
両親のお金を適切に管理するためには、預かり金として現金や通帳を預かる方法や、子供名義の口座を開設して両親の預金を管理する名義預金の方法を活用することが望ましいでしょう。また、すでに認知症と診断されている場合は、成年後見制度を利用した管理方法も検討する必要があります。
介護費用が年間110万円を超える場合は税理士に相談する
通常、介護を理由に受け取ったお金は扶養義務者間の贈与として扱われるため、相続税の対象とはなりません。しかし、年間の受取額が110万円を超えるような場合には、贈与税が発生する可能性があります。
このような場合には、税理士や税務署に相談し、贈与税の対象となるかどうかを確認することが賢明です。専門家のアドバイスを受けることで、適切な税務処理を行うことができます。
将来の相続トラブルを避けるためにもしっかり対策する
介護のためにお金を受け取っていた事実が、相続時に発覚することで家族間のトラブルに発展するケースがあります。このようなトラブルを防ぐために、親との取り決めは必ず書面に残しておくことが重要です。
また、介護に直接参加していない兄弟姉妹に対しても、親からお金を受け取っている事実を事前に伝えておく必要があります。透明性を確保することで、「親の財産を勝手に使っていた」などの誤解を防ぎ、円滑な相続につながります。
介護関連の支援制度やサービス7選
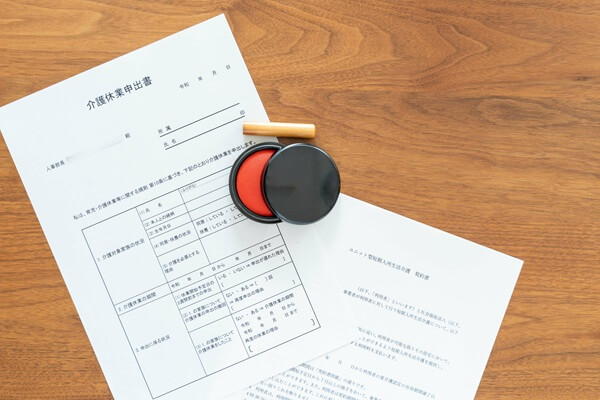
介護にはさまざまな公的支援制度が用意されています。
ここでは、介護にかかる費用負担を軽減できる7つの制度やサービスについて詳しく解説していきます。
介護休業給付金
要介護状態の家族の介護のために仕事を休む必要がある場合、介護休業給付金を受け取ることができます。この制度では、休業前の賃金の約67%が支給されます。給付金の上限期間は最長93日間で、条件を満たせば最大3回まで利用可能となっています。
申請手続きは、勤務先の会社で介護休業の申請を行い、その後ハローワークへ必要書類を提出します。審査完了後、約1週間で給付金が振り込まれる仕組みとなっています。
介護休暇制度
介護休暇制度は、要介護状態の家族の介護や通院の付き添いなどに利用できる休暇制度です。対象家族が1人の場合は年間5日まで、2人以上の場合は年間10日までの取得が可能です。特徴として、突発的な介護ニーズにも対応できるよう、口頭での申し出も認められています。
参照元:厚生労働省|介護休暇とは
介護慰労金(介護手当)
介護慰労金は、要介護4~5の高齢者を在宅で1年以上介護している家族に対して、自治体から支給される制度です。支給額は自治体によって異なりますが、年間10~12万円程度となっています。ただし、介護保険サービスを利用していない場合に限られる場合が多いため、申請前に居住地の自治体で確認が必要です。
高額介護サービス費
1ヶ月間の介護サービスの自己負担額が所得に応じた上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。例えば、一般的な所得世帯では月額44,400円が上限となっており、これを超えた分が後から支給されます。
高額医療・高額介護合算療養費制度
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している場合、1年間の自己負担額の合計が基準額を超えると、超過分が還付される制度です。世帯の所得区分によって負担上限額が設定されており、超過分について払い戻しを受けることができます。
介護保険の負担限度額認定制度
所得や資産状況に応じて、介護施設の食費や居住費の負担を軽減できる制度です。この制度を利用することで、施設入所時の経済的負担を大幅に抑えることが可能となります。認定を受けるためには、自治体窓口での申請手続きが必要です。
民間の介護保険外サービス
公的な介護保険制度では補いきれない部分を補完するため、民間の介護保険サービスの活用も検討に値します。特に、十分な貯蓄がない方や、より充実したサービスを望む方にとって、有効な選択肢となるでしょう。民間の保険は現金給付が基本となるため、柔軟な資金活用が可能です。
おわりに
親の介護にはまとまった費用が必要となりますが、一人で抱え込む必要はありません。介護にはさまざまな公的支援制度があり、親や兄弟姉妹からの支援を受けることも自然な選択です。介護費用について家族で話し合い、必要な制度を活用することで、経済的な負担を分担・軽減しながら、質の高い介護を提供することができます。また、別居での介護や仕事との両立に不安がある場合は、民間の介護サポートサービスを利用することで、安心して親の介護に向き合うことができるでしょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。
































