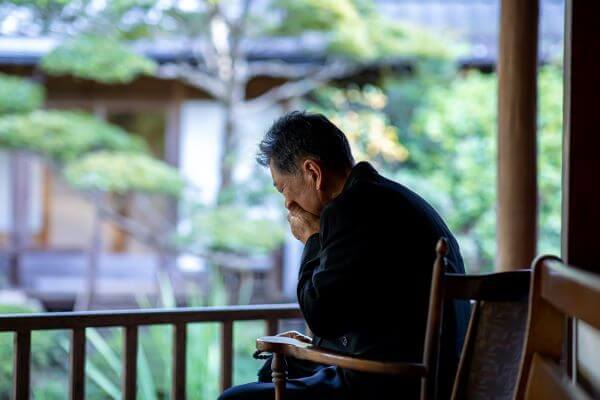高齢者の孤独死は、現代社会において誰にとっても身近な問題となりつつあります。ご自身や大切なご家族が、誰にも看取られずに亡くなってしまうかもしれないという不安を抱えている方もいるでしょう。
この記事では、孤独死がなぜ起きてしまうのか、その背景にある原因を深掘りします。さらに、孤独死の現状や遺された家族への影響、そして具体的な予防策まで、順を追って詳しく解説します。孤独死を防ぎ、安心して老後を迎えるためのヒントを見つけていただければ幸いです。
- 孤独死とは「看取る人がいない状態での死」であり、高齢者の一人暮らしが増加している日本では社会問題となっている
- 孤独死が増える主な原因は「ひとり暮らし」「経済的困窮」「近所付き合いの希薄化」の3つである
- 孤独死した場合、遺族への影響は発見時の遺体の状態によるトラウマなどの精神的負担と、特殊清掃費用などの金銭的負担がある
- 孤独死を防ぐ対策として「家族との連絡」「自治体サービスの利用」「社会活動への参加」「見守りサービスの活用」などの方法がある。
高齢者孤独死の概要と日本の現状

高齢者の孤独死は、現代日本が抱える課題のひとつとして認識されています。この問題について理解を深めるために、まず孤独死の定義や国内の現状、主な死因、そして混同されやすい孤立死との違いについて解説します。
孤独死の定義
孤独死には明確な定義が存在しません。一般的には、誰にも看取られることなくひとりで亡くなり、その後発見されるケースを指します。
内閣府の白書では「看取る人が誰もいない状態の中での死」として扱われており、特に「社会的に孤立し、十分なケアを受けられない状態の中での死」が問題視されています。
また、死亡から発見までの期間も重要な要素とされていますが、具体的な期間の定義はありません。社会とある程度接点があり、介護・保健・医療サービスを利用していた人が偶然ひとりで亡くなったケースは、一般的に孤独死には含まれないとされています。
孤独死と孤立死の違い
孤独死と孤立死には明確な位置づけや意味の違いはありませんが、一般的には以下のように使い分けられています。
孤独死:家族との交流や地域でのつながりがあっても、老衰や突然の病気などにより自宅で誰にも気づかれずに亡くなる場合
孤立死:親族とも疎遠で地域でのつながりもなく、社会から日常的に孤立している人が自宅で亡くなり、そのまま誰にも気づかれない場合
「孤立」は物理的に社会との関係が少ない独りぼっちのニュアンスがあり、「孤独」は家族や周りの人との交流があっても本人が感じる孤独感を示すニュアンスがあります。
厚生労働省は「孤立死」という言葉を使用していますが、2024年4月に施行された孤独・孤立対策推進法では、孤独と孤立を同列に扱っています。
日本における高齢者の孤独死の現状
日本では65歳以上のひとり暮らしの高齢者が急増しています。令和6年版高齢社会白書によると、令和2年(2020年)時点で男性約231万人、女性約441万人がひとり暮らしをしており、65歳以上人口に占める割合は男性15.0%、女性22.1%に達しています。また、2024年12月に発表された日本少額短期保険協会の調査によると、孤独死する人の平均年齢は62.8歳で、平均寿命より男性で18.1歳、女性で25.3歳も若く亡くなっていることがわかっています。
また、同調査によれば孤独死全体の約半数は65歳までの現役世代であり、必ずしも高齢者特有の問題ではありません。さらに、男女比を見ると孤独死の8割以上が男性であり、男性の方が孤独死のリスクが高いことがわかります。
参考:
高齢者の孤独死の死因
日本少額短期保険協会の調査によると、孤独死の死因として最も多いのは、病死で全体の62.0%を占めています。次いで多いのが自殺で9.2%、事故死が0.9%となっており、残りの27.9%は死因不明です。死因不明の多くは、実際には病気による死亡と考えられていますが、データ上で判別できないため不明として計上されています。
自殺の割合を男女別に見ると、特に20代女性の自殺率が全体の36.1%と突出して高くなっています。
また、亡くなってから発見されるまでの平均日数は18日です。実際には37.8%が3日以内に発見される一方で、18.8%が30日以上経過してから発見されています。発見が遅れることで遺体の腐敗が進行し、より悲惨な状況になることが懸念されています。
孤独死が増える3つの原因

高齢者の孤独死が年々増加している背景には、社会構造の変化や経済状況、人間関係の希薄化などさまざまな要因が関わっています。
ここでは、孤独死が増える主な原因を3つのポイントから解説します。
ひとり暮らしをしている
日本では未婚率が上昇しており、ひとり暮らしの高齢者が増え続けています。令和2年の国勢調査によると、65歳以上の高齢者の未婚率は、2010年には男性11.8%、女性12.2%だったものが、2020年には男性33.5%、女性23.9%と大きく上昇しています。特に男性の未婚率の上昇が著しく、これに伴いひとり暮らしの高齢者も増加傾向にあります。
また、結婚していても配偶者との死別や離婚により、ひとり暮らしを余儀なくされるケースも少なくありません。特に問題となるのは、それまで食事や掃除などの家事を配偶者に頼っていた場合です。配偶者を失うと食生活の乱れ、栄養状態の悪化、住まいの衛生状態が保てなくなるなど、健康リスクが高まります。
経済的に余裕がない
孤独死の増加には経済的な困窮も大きく関わっています。東洋大学の研究によると、高齢単身世帯の貧困率は23.1%に達しており、単身高齢者の約4人に1人が経済的に困難な状況にあることがわかっています。経済的余裕がないと、老人ホームへの入居や定期的な通院といった適切なケアを受けることが困難になります。
健康面でも影響が出やすく、病気やケガをしても治療費が払えないために病院に行かず、症状が悪化してしまうケースもあるでしょう。また、エアコンの使用を控え、熱中症や寒さによる体調不良を招くこともあります。さらに、栄養バランスの良い食事にお金をかけられないため、体力の低下から病気にかかるリスクも高まります。このように経済的困窮が健康状態に悪影響を及ぼし、孤独死につながる可能性が高まるのです。
参考:東洋大学|高齢単身者の貧困率の計測とその社会経済的要因の分析
近所付き合いがない
近所づきあいの減少も孤独死を増加させる重要な要因です。内閣府の「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」によると、「お茶や食事を一緒にする」といった近隣住民との交流は、2010年の29.3%から2020年には14.2%に、「病気のときに助け合う」は9.3%から5.0%へと大幅に減少しています。
地域コミュニティとのつながりが希薄になると、体調不良や緊急事態が発生しても助けを求められない状況に陥りやすくなります。自治会への加入率も年々低下しており、たとえば東京都町田市では2005年の60%から2024年には44%まで減少しています。
このような人付き合いの減少は特に男性に顕著で、独居高齢者のうち「困ったときに頼れる人がいない」と答えた男性は約20%で、女性の8.5%の2倍以上になっています。孤立が進むと引きこもり状態になりやすく、精神的ストレスも増加して心身の健康を損なう原因にもなります。
【チェックリスト】孤独死する高齢者の特徴

以下は、孤独死の可能性が高くなる方の特徴です。
- ひとりで暮らしをしている
- 配偶者や子どもがいない
- 家族と連絡を取り合わない
- 近所付き合いをしない
- 働いていない
- 持病がある
- 不健康な生活を送っている
- 男性
- 趣味がない
- 家事が苦手
配偶者との死別や離婚でひとり暮らしになったタイミングは、精神的に不安定になりやすく体調を崩す危険性が高まります。悲しみやストレス、孤独感が精神状態に悪影響を与え、うつ病などの発症につながることもあります。
また、部屋にものがあふれて片付けられなくなった状態は要注意です。このような状況は、セルフネグレクトやうつ病、認知症など精神的ダメージを深く負っている兆候かもしれません。これらの異変に気づいたら、必要に応じて早急に対応することが大切です。
高齢者が孤独死した場合に遺族へ与える影響

孤独死は亡くなった本人だけでなく、遺された家族や親族にも大きな影響を与えます。精神的なショックや予期せぬ金銭的負担など、遺族は複数の面で負担を負うことになります。
ここでは、孤独死が遺族に及ぼす影響について解説します。
精神的な負担|発見時の姿がトラウマに
孤独死の場合、亡くなってから発見されるまでに数日間、時には数週間経過してしまうことも珍しくありません。日本少額短期保険協会の調査によると、孤独死の発見までの平均日数は18日にも及びます。発見が遅れると、遺体の腐敗や変色が進み、第一発見者となった家族はその悲惨な状況に直面することになります。
このような光景を目にすることはトラウマとなり、長期にわたって心の傷として残る可能性があります。また、多くの遺族は「もっと頻繁に連絡を取っていれば」「あのとき訪問していれば」といった後悔の念に苛まれ、自責の気持ちを抱え続けることになるでしょう。
金銭的な負担|清掃費や退去費など
孤独死が起きた場合、発見までの時間が長くなるほど、遺族は予期せぬ高額な費用負担を強いられます。遺体の腐敗が進むと「特殊清掃」と呼ばれる専門業者への依頼が必要となり、床や壁の清掃、脱臭・消臭、害虫駆除などで数十万円の費用が発生します。状況によっては100万円以上になることも珍しくありません。賃貸住宅の場合は「事故物件」という扱いになり、家主から原状回復費用の補償を求められることもあるでしょう。
また、特殊清掃が必要となった現場の遺品は買取対象外となり、別途遺品整理専門業者への依頼費用として10万円から30万円程度が追加で必要になります。こうした突然の出費は遺族にとって大きな負担となります。
高齢者の孤独死を防ぐ方法5選

孤独死を防ぐためには、社会的孤立を防ぎ、定期的な見守り体制を構築することが重要です。高齢者自身の取り組みだけでなく、家族や地域社会、行政、民間サービスなど多方面からのサポートを組み合わせることで、孤独死のリスクを大きく減らすことができます。
以下では、実践しやすい孤独死対策を5つご紹介します。
家族・親族と頻繁に連絡を取る
孤独死の大きな原因のひとつが人とのつながりの希薄化です。家族や親族と定期的に連絡を取り、元気に暮らしているか確認することが極めて重要です。遠方に住んでいて直接会うことが難しい場合でも、電話やメール、LINEなどのSNSを活用して連絡を取り合うことで、孤独感を和らげることができます。
毎週決まった曜日に電話をするなど、連絡を習慣化することで、もし連絡が取れなかった場合にすぐに異変に気づくことができます。また、普段から連絡を取り合っていると、話し方や声のトーンなどの微妙な変化から体調不良などにも気づきやすくなります。高齢者の状況を正確に把握することで、早期に適切な対応をとることが可能になります。
自治体のサービスを利用する
近年、多くの自治体では高齢者の孤独死や孤立死を防ぐためのさまざまな見守りサービスを実施しています。たとえば、東京都立川市では郵便受けに新聞や郵便物が溜まっている、雨戸やカーテンが数日間閉まったままもしくは開いたままになっている、部屋の明かりが点灯したままになっているなどの異変があった場合に、市のホットラインに相談できる体制を整えています。
また、「会話がかみ合わない」「季節にそぐわない服を着ている」など認知症が疑われる言動についても、相談できる自治体もあります。市区町村や地域包括支援センターには福祉の専門員が配置されているため、気になることがあれば積極的に相談してみましょう。自治体によっては、職員による定期訪問や電話確認、緊急通報装置の貸し出しなどのサービスも提供しています。
ボランティア活動やサークルに参加する
孤独死を防ぐために効果的な方法のひとつが、地域社会との接点を持つことです。ボランティア活動や趣味のサークルに参加することで、定期的に人と交流する機会が生まれ、孤立を防ぐことができます。前述の内閣府の調査によると、なんらかの高齢者グループ活動に参加したことがある人は61%に上り、参加者の半数近くが「新しい友人を得ることができた」「生活に充実感が出てきた」と回答しています。
社会とつながりを持つことは、認知症予防にも効果的とされており、高齢者の心身の健康維持にも役立ちます。特にボランティア活動は地域社会への貢献を通じて達成感ややりがいを感じられるため、生きがいづくりにもつながります。趣味を通じて同じ興味を持つ仲間と出会うことで、孤独感が解消され、困ったときに助け合える関係を構築できるでしょう。
民間の見守りサービスを活用する
家族が遠方に住んでいる場合や、仕事などで頻繁に訪問できない場合は、民間企業が提供する見守りサービスの活用も効果的です。近年では、さまざまな見守りサービスが登場しており、ニーズに合わせて選択することができます。たとえば、郵便局員や宅配便の配達員が定期的に訪問して安否確認を行うサービスや、水道メーターや電気の使用量をモニターして異変があれば連絡するサービスなどがあります。
また、高齢者の自宅にセンサーやカメラを設置して、日常生活の動きを検知したり、施錠センサーや非常ボタンを設置して万が一の際に自宅に駆けつけてもらうサービスもあります。これらのサービスは有料のものが多いですが、家族の負担を軽減しながら高齢者の安全を確保できるという大きなメリットがあります。状況や予算に応じて適切なサービスを選択することで、効果的な見守り体制を構築することができるでしょう。
老人ホームや高齢者向け住宅を利用する
孤独死を防ぐための最も確実な方法のひとつが、老人ホームなどの介護施設への入居です。施設では専門知識を持ったスタッフが24時間体制で見守りを行っているため、体調の急変などにも迅速に対応することができます。特に持病を抱えている方や、日常生活に不安を感じている方にとっては、大きな安心につながるでしょう。
施設では食事や入浴などの生活支援サービスが受けられるだけでなく、レクリエーションや季節のイベントなども豊富に用意されており、他の入居者との交流を通じて充実した日々を送ることができます。老人ホームには「特別養護老人ホーム」や「有料老人ホーム」、「サービス付き高齢者向け住宅」など、さまざまな種類があり、介護度や経済状況に応じて選択することができます。ただし、費用面での負担が大きいことや、人気の施設は入居待ちになる場合もあるため、早めに情報収集や準備を始めることが大切です。
おわりに
高齢者の孤独死は、ひとり暮らしの増加や人間関係の希薄化、経済的困窮など複合的な原因によって引き起こされています。孤独死を防ぐには、家族や親族との定期的な連絡、地域とのつながり、自治体や民間のサービス活用など、複数の対策を組み合わせることが重要です。孤独死は本人だけでなく遺族にも大きな精神的・経済的負担をもたらすため、早期からの対策が必要です。将来に備えて今からできることからはじめましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。