老後の生活に向けて、どれくらい資金が必要になるか不安を感じていませんか?特に独身の方は、頼れるパートナーがいない分、生活費や医療費などすべてを自分で賄う必要があります。
この記事では、独身の方が老後に必要となる資金の目安や、今からできる備えについて詳しく解説します。老後を安心して暮らすために必要な情報や具体的な対策方法を知り、自分らしい将来設計を始めましょう。
- 独身者の老後の生活費は平均で月14.5万円程度かかるのに対し、収入は平均で約12.7万円と不足気味である
- 20年の老後生活では約432万円、30年では約648万円の貯蓄が最低限必要となる
- 老後資金の確保には固定費見直し、年金繰下げ受給、投資信託(iDeCo・つみたてNISA)、保険加入などの方法がある
老後に必要な資金│独身の場合

独身で老後を迎えた場合、どのくらいの資金が必要になるのでしょうか。まずは生活にかかる費用や年金などの収入を確認し、現実的な資金計画を立てましょう。
配偶者やご家族がいない場合、すべての費用を自分ひとりで賄う必要がある点を念頭に置くことが大切です。
老後の生活にかかる費用
基本的な生活を維持するために必要な生活費には、以下のような項目があります。
- 食費
- 居住費
- 水道光熱費
- 衣服、家具購入費
- 通信費
- 保険、医療費
これらの基本的な生活費に加えて、友人との外食や旅行などの娯楽費用もプラスすると、独身高齢者の生活費は平均して月に約14.5万円必要とされています。特に医療費は年齢とともに増加する傾向にあるため、余裕をもった資金計画が重要です。
参考: 総務省統計局│家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)
老後の収入源
老後の主な収入源は社会保障給付、つまり年金です。しかし、社会保障給付の平均額は月に12.7万円程度です。また、自営業者などが受給する国民年金の月の支給額は約6.9万円(令和7年)で平均額を下回ります。前述の生活費と社会保障給付の平均額の差額1.8万円を毎月貯蓄から補う場合、老後生活が20年続くと仮定すれば約432万円、30年続くと648万円の貯蓄が最低限必要になります。
また、旅行や趣味など充実した老後生活を送りたい場合は、さらに多くの貯蓄が必要です。急な出費や医療費の増加にも備えるためには、基本的な生活費を賄う以上の資金を準備しておくことが望ましいでしょう。
参考:総務省統計局│家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)
独身者の平均貯蓄額
金融広報中央委員会の調査によると、独身高齢者の金融資産保有額の平均は60代で1,860万円、70代で1,786万円となっています。
中央値で見ると60代では460万円、70代では800万円と大きく下がります。この差は、多くの資産を持つ一部の人が平均値を引き上げていることを示しています。実態としては1,000万円以下の貯蓄で老後生活を送る独身者が多い現状です。
参考:金融広報中央委員会|家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和3年)
いつから老後資金を貯めるのがいい?

老後資金の準備は早く始めるほど有利です。若いうちから少額ずつ積み立てることで、負担を軽減できるからです。20代や30代から始めれば、月々の積立額はわずかで済みますが、50代になってから同じ目標金額に向けて貯金を始めると、毎月の負担が何倍にもなってしまいます。長い期間をかけてコツコツと積み立てることで、無理なく資産形成ができるでしょう。
効果的に老後資金を確保するためには、具体的な目標設定が重要です。「65歳までに1,000万円貯める」など、明確な金額と期限を決めましょう。この目標から逆算して、毎月必要な貯蓄額を計算できます。たとえば35歳から65歳までの30年間で1,000万円を貯めるなら、月々約2万8千円の積立が必要になります。自分のライフプランに合わせた目標を立て、計画的に貯蓄を進めることが大切です。
目標達成に向けては、定期的な見直しも欠かせません。収入の増加や支出の変化に応じて貯蓄計画を調整し、着実に老後資金を積み立てていきましょう。独身者は配偶者からの支援が期待できないため、早めの準備が特に重要となります。
今からできる老後資金の確保方法
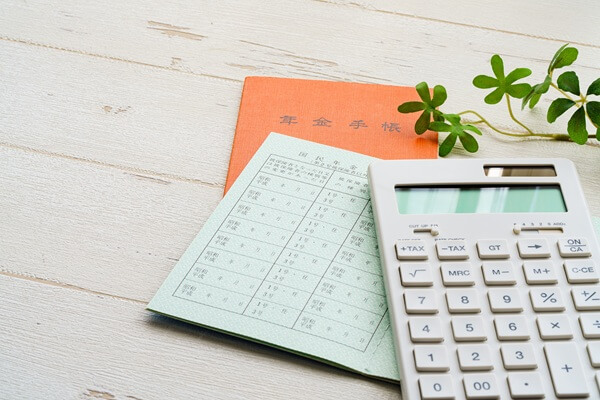
独身者の老後に備えた資金計画は、早めに始めることが大切です。将来を安心して過ごすために、今からできる資金確保の方法をいくつかご紹介します。支出を見直す基本的な対策から年金の活用法、資産運用の手法まで、さまざまな角度から老後資金を増やすコツを解説しますので、参考にしてください。
固定費を見直す
毎月の生活費、特に固定費を見直せば、大きな節約効果が期待できます。家賃、水道光熱費、通信費、自動車関連費、サブスクリプションサービスなど、日常的に支払っているものを精査し、不要なものはカットしましょう。
そして、節約できた金額は老後資金として貯めていくことがポイントです。専用の口座を作り、毎月一定額を自動的に積み立てる仕組みを利用すると効果的です。さらに、勤務先で財形年金貯蓄を利用できる場合は、給与や賞与から天引きで老後資金を貯められます。この制度の利点は、貯蓄から得られる利息に税金がかからないという点にあります。堅実に老後資金を積み立てていく手段として検討してみてはいかがでしょうか。
年金受給額を確認する
年金は老後の主な収入源となるため、今のうちから自分の受給見込み額を把握しておくことが重要です。将来もらえる年金額を知ることで、足りない分をどれだけ貯蓄すべきかを計算できるからです。
具体的な確認方法としては、日本年金機構から1年に1回送られてくる「ねんきん定期便」があります。これによって、これまでの加入実績や将来の受給見込み額を確認できます。
より詳しく知りたい場合は、「ねんきんネット」というオンラインサービスを活用するとよいでしょう。このサービスでは、今後の働き方や受取開始年齢などの条件を設定することで、さまざまなパターンの受給見込み額をシミュレーションすることが可能です。現状を把握し、必要な対策を講じるための第一歩となります。
年金を繰下げ受給する
年金は原則65歳から受け取り始めることができますが、受給開始時期を遅らせる「繰下げ受給」という選択肢も存在します。この制度を利用すると、遅らせた月数に応じて年金額が増加し、最大で84.0%も増額されるメリットがあります。
たとえば、66歳から受給を始めると年金額が8.4%増、70歳から始めると42.0%増となります。長生きすればするほど、生涯で受け取る総額が増えるため、健康状態に自信がある方にとっては有利な選択肢となります。特に65歳を過ぎてもまだ仕事を続けている方は、その間の収入があるため、年金の受け取りを繰り下げることで将来的な収入増加を図れます。
一方で、繰下げ受給には注意すべき点もあります。年金額が増えることで、所得税や住民税といった税金、そして国民健康保険料や介護保険料などの社会保険料の負担が増加する可能性があります。また、年金受給を遅らせる期間は、貯蓄を取り崩して生活費を賄う必要が生じます。これにより、老後資金が想定よりも早く尽きてしまうリスクも考慮しなければなりません。
ご自身の資産状況や健康状態、将来のライフプランを総合的に考慮し、メリットとデメリットを慎重に比較検討した上で、繰下げ受給について判断することが大切です。
参照元:日本年金機構|年金の繰下げ受給
投資信託を始める
投資信託は、毎月一定金額を積み立てて運用のプロフェッショナルに投資を任せる金融商品です。株式や債券など複数の資産に分散投資できるため、リスクを抑えながら資産形成が可能です。運用成績に応じて分配金を受け取ることができます。
老後資金づくりにおすすめの投資信託としては、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」と「新NISA」が挙げられます。iDeCoは掛金の全額が所得控除の対象となるため、所得税や住民税に対する節税効果が期待できます。原則として60歳まで引き出せないことから、老後資金に特化した制度といえるでしょう。
一方、新NISAは、生涯にわたる投資非課税保有限度額が1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)に拡充され、非課税で投資できる期間も無期限となりました。つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能で、年間最大360万円まで投資できます。いつでも資金を引き出せる柔軟性があり、病気になった時など急な出費にも対応可能です。
参照元:iDeCo公式サイト 金融庁|NISA特設ウェブサイト
保険に加入する
老後資金を確保するもう一つの方法として、保険商品への加入があります。代表的なものには個人年金保険や終身保険があり、将来に向けた資産形成の役割を果たします。これらの保険は一定の年齢になると年金形式で受け取ることができ、その期間は10年、15年、または一生涯など多岐にわたります。
保険商品の特徴として、払込期間が終了した後に解約すると、払った保険料よりも多い解約返戻金が受け取れる可能性がある点が挙げられます。老後資金が不足した際には、必要に応じて保険を解約して資金を確保するという選択肢も考えられるでしょう。
ただし、払込期間の途中で解約すると、支払った保険料よりも少ない返戻金しか受け取れないケースがあるため、加入する際はこの点に注意が必要です。自分のライフプランに合った保険を選びましょう。
おわりに
独身者の老後資金は、早めの準備が何よりも重要です。生活費と年金収入の差を埋めるためには、生活費の見直しから始め、年金受給額の確認や繰下げ受給の検討、投資信託や保険の活用など複数の方法を組み合わせることが効果的です。ひとりで悩まず専門家のアドバイスも取り入れながら、計画的に準備を進めていきましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。




























