資金調達ができたからといって安心するのは危険です。実際には、資金ショートの多くは調達後に起こっています。
その原因の多くは、「資金繰り」の見通しの甘さです。
本記事では、資金調達を検討する事業者があらかじめ理解しておくべき資金繰りの基本と、現場での実践的な対策を、具体的な事例を交えて解説します。
資金調達と資金繰りは別物?
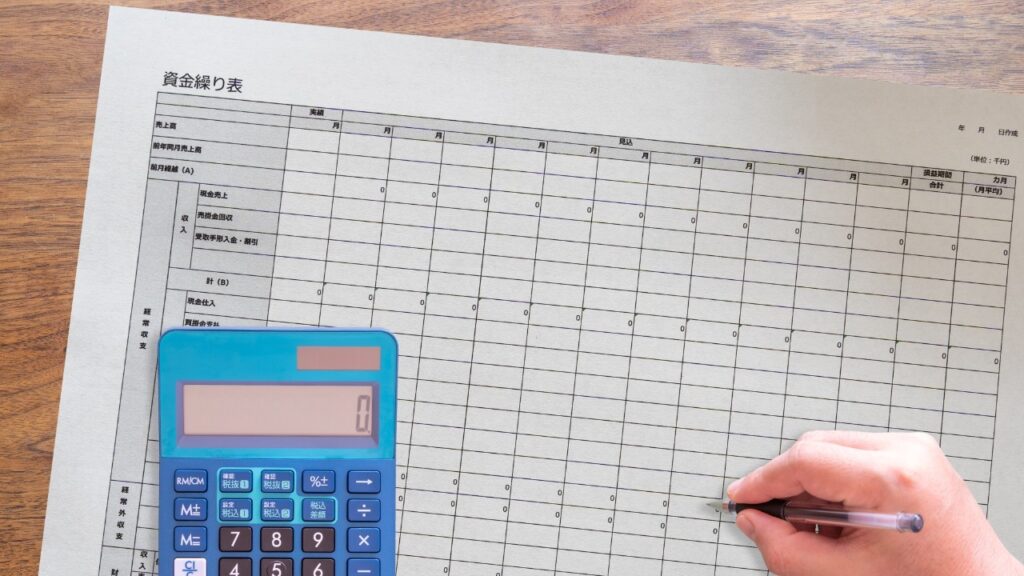
資金調達とは、外部からまとまった資金を「集める」行為。一方、資金繰りとは、その資金を「いつ・いくら使い、どのように回すか」を管理することを指します。
資金調達に成功したからといって、資金繰りまでうまくいくとは限りません。むしろ、資金ショートの多くは、資金の流れに対する見通しの甘さに起因します。
資金調達は「点」の対応、資金繰りは「線」での管理です。調達した資金がどのタイミングで出ていき、どの時点で現金が入ってくるか――入出金のズレを把握し、資金残高が切れないように設計する必要があります。
なお、資金繰りは経理担当者だけでなく、経営者自身が毎月“数字”を確認し、意思決定に生かす習慣をつけることが、企業の安定経営に直結します。
資金繰りリスクとは?~ショートの原因

資金ショートとは、現金が不足して支払不能になる状態です。「黒字倒産」という言葉があるように、売上が順調で利益が出ていても資金繰りが悪ければ倒産につながります。
これは、特に成長期の企業で見られます。売上が急増すると、それに伴って仕入・人件費・外注費などの支出も増加しますが、入金は後からしか来ないためです。
よくある原因
・得意先の倒産や不払いによる入金遅延
・季節性コストの集中(賞与、税金、年末仕入など)
・設備投資などでキャッシュアウトが先行
【事例1】映像制作P社:納品遅延による資金繰り悪化
大型案件を受注し、スタッフを増員して対応したものの、契約では納品・検収が4ヵ月後、入金もさらに先という条件でした。ところが、先方の都合で納品がさらに3ヵ月延び、資金繰りが急速に悪化しました。
資金調達時に見落としがちな落とし穴
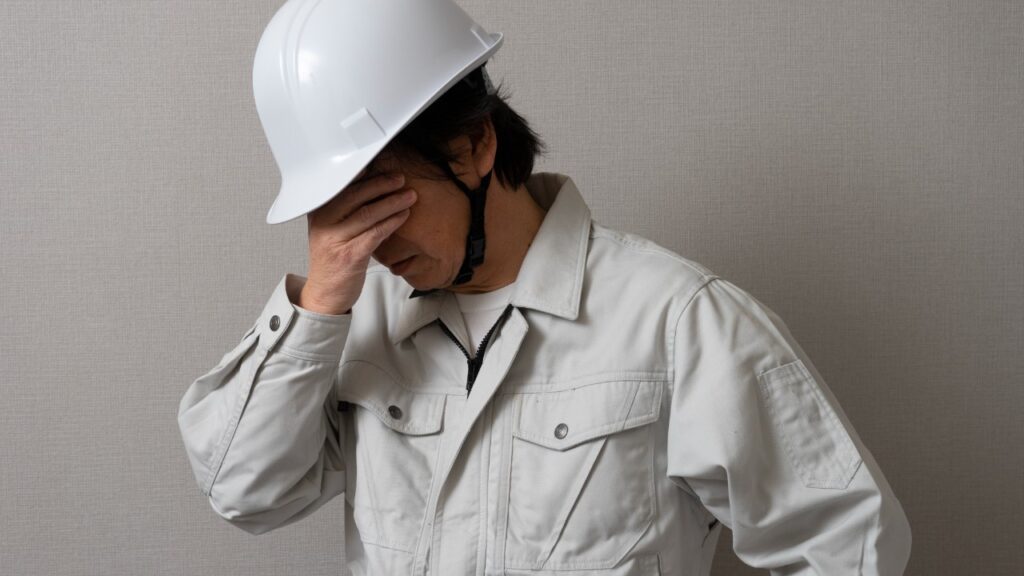
資金繰りが悪化する原因の多くは、資金調達の「前段階」=計画時点の見落としにあります。借入や出資を受ける際には、事業計画や資金用途の説明に注力しがちですが、実際に資金が“入ってきた後”の出入りを十分に見通せていないケースが見られます。
見落としがちな項目
・突発的な修繕費や人員採用コスト
・売上が計画通りに立つという前提の過信
実際には計画との差異が出ることが普通なので、月次でズレを早期発見し、支出や調達計画を柔軟に見直すことも大切です。
【事例2】製造業H社:人件費は見ていたが…
工場の設備導入のために借入を実行。人件費の増加は織り込んでいたものの、社会保険料と固定資産税を見落としており、資金が不足して対応に追われた。
調達前にすべき資金繰り準備

資金繰り表の作成(6~12ヵ月分)
最低でも月単位で、キャッシュインとキャッシュアウトの計画を立てましょう。資金繰り表は、たとえば、以下のように分類して作成します。
・投資収支:設備の購入・売却などの入出金
・財務収支:借入金の入金・返済・出資・配当など、資金の外部調達・返済に関する入出金
資金の動きが整理され、問題のある月を早期に察知できます。
不安な場合や初めて資金繰り表を作る場合は、顧問税理士や会計士、金融機関の専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
支払サイト・回収サイトの調整
・支払条件の延長交渉は可能か
【事例3】訪問看護V社:資金繰り表が判断材料に
拠点拡大を検討する中で資金繰り表を作成。運転資金が3ヵ月後に不足する見込みがわかり、消耗品の支払サイトを交渉したうえで、段階的な採用を進める計画に変更した。
資金繰りリスクを見越した資金調達戦略
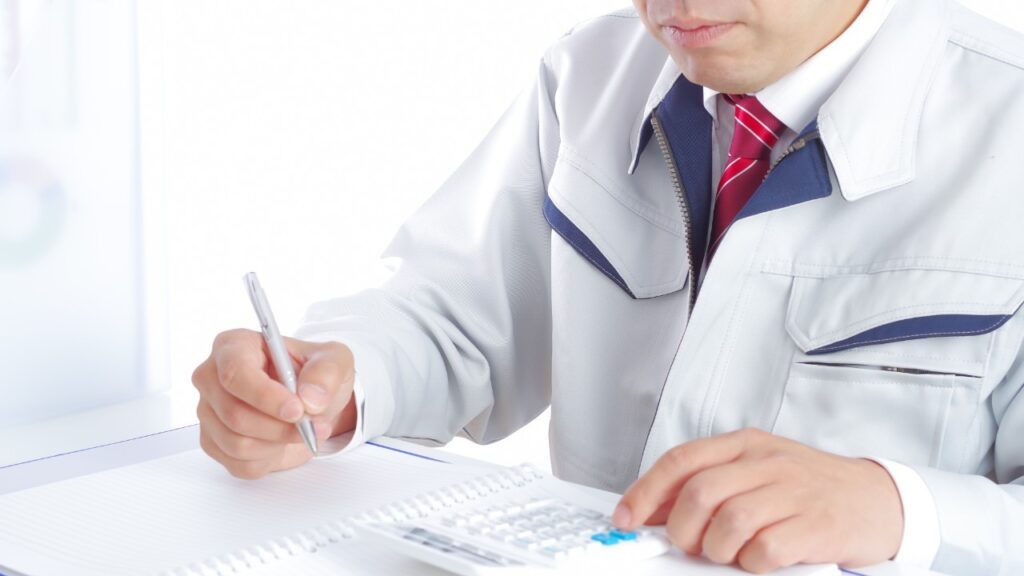
資金繰りリスクは、戦略的に備えることで大きく軽減できます。調達が成功しても、返済負担や支出タイミングを誤れば、すぐに資金は枯渇します。
① 余裕資金の確保
「必要な分だけ借りる」が理想ですが、実務では不測の支出に備えた余裕資金が現実的です。ただし、金融機関や投資家に納得される明確な理由づけが必要です。
【例】
・設備修繕・採用・キャンセルリスクに備える説明を付記
・資金繰り表に余裕資金として明示
※「なんとなく多めに借りる」では信頼されません。合理性が重要です。
② 複数の資金調達手段を検討しておく
調達手段の「選択肢の数」は、資金繰りの柔軟性に直結します。一つの手段に依存しない体制が、突発事態への備えとなります。
【例】
・ノンバンク(リース・ファクタリング)との取引
・前受金・支払サイト見直しなどの取引先との交渉
③ 調達後の資金モニタリング体制を整える
資金があるうちにこそ、“見える化”しての管理が重要です。
【例】
・想定との差異を分析し、見直しや次の対策を検討
・金融機関への報告を通じて信頼を蓄積
まとめ:資金繰りの視点が、事業の持続可能性を決める

資金調達が終わると安心しがちですが、調達直後から資金ショートに陥るケースも多くあります。資金が「ある」ことと「回る」ことは別物です。
現金は残高ではなく「流れ」で管理するもの。支出のタイミングのズレや、予定どおりにいかない売上計画で、資金はすぐに枯渇してしまいます。
資金繰りに成功している企業は、調達前から冷静に「お金の流れ」を設計しています。
・いつ現金として入ってくるか
・その前に必要な支出は何か
こうした視点で資金の過不足を予測・管理することが、経営を持続させる鍵になります。また、資金繰りの計画や表の内容は、税理士・会計士・銀行担当者など第三者のチェックを受けることで、より確実で安心感のある経営判断につながります。
銀行や投資家も、資金繰りへの配慮がある計画には信頼を寄せます。リスクを洗い出し、それに備える姿勢こそが「計画的な資金調達」なのです。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、最新情報はホームページ等でご確認ください。


























