相続した不動産は、相続税の納税資金を賄うため、できるだけ早く現金化したいと考える人が少なくありません。
しかし、その「早く売りたい」という気持ちが不動産会社に伝わると、足元を見られて売却価格が不当に低くなる恐れも。このような事態を避けるためには、生前からの入念な事前準備がなによりも大切です。
本記事では、相続不動産を売却する際の方法とそのポイント、注意点について不動産投資と不動産専門の税理士・MK Real Estate 税理士事務所の川口誠氏が解説します。
相続不動産をできる限り高く売却するための不動産会社選び

相続不動産を売却する際、不動産会社をどのように選べばよいかということをよく聞かれます。
まず重要なのは、査定の際の注意点です。売却の際は「早く売りたい」「いくらで売りたい」といった希望や売却理由を、最初から詳細に伝えすぎないことも大切です。こうした情報が伝わると、希望より安く査定されてしまうリスクがあります。
不動産会社を選ぶ際は、以下の3タイプに分けて考えていきます。
- 全国規模で事業を展開している大手不動産会社
- 地元の中小規模の不動産会社
- 収益不動産を扱う不動産会社
最初から1つの不動産会社を選ぶ必要はありません。できる限り高い金額で売却するために大切なことは、複数の不動産会社に話を持ち掛けることです。1から3にまたがってもいいですし、1、2、3のそれぞれに属する複数の不動産会社でもいいでしょう。
その際、1から3の不動産会社には、得意、不得意の分野があるということも考慮してください。
敷地が広かったり、物件の規模が大きかったりする場合、買える人はそう多くいません。そのような場合には、1の大手の不動産会社のほうが、扱う情報量が圧倒的に多いため、買主を見つけるうえで有利になります。
一方で、地元の顧客の情報について詳しいのは、2の地元の不動産会社です。また、賃貸不動産については、3の収益不動産を扱う不動産会社のほうが、投資面からの適正な金額を判断することができます。
相続不動産売却時にかかる税金「譲渡所得税」の基本
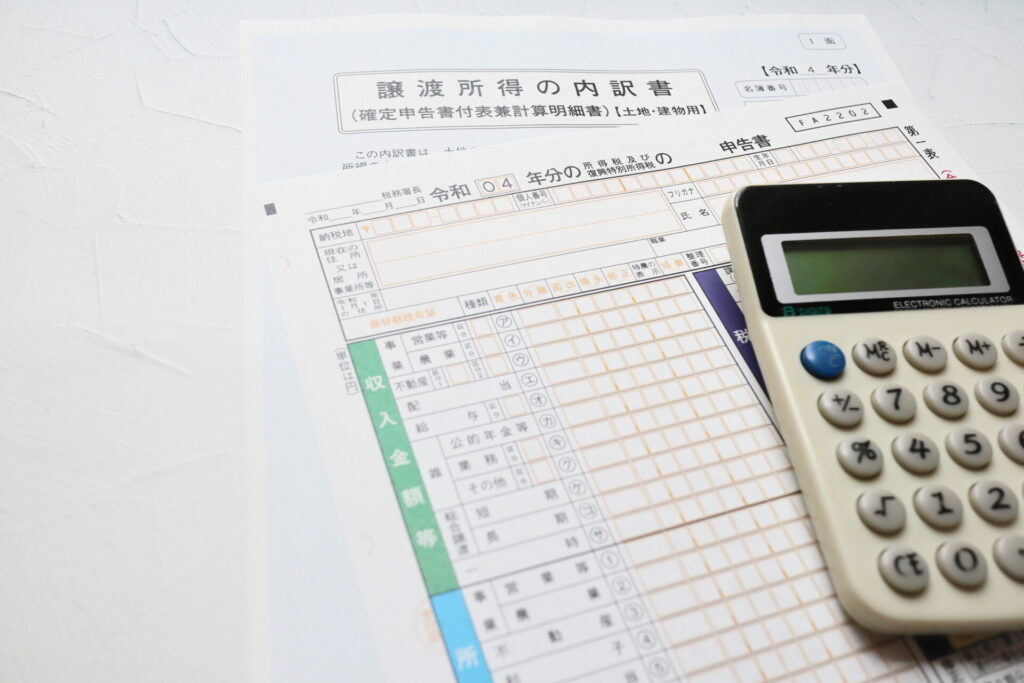
不動産を売却すると、その利益に対して「譲渡所得税」が課税されます。この税金は、売却した年の翌年の2月16日から3月15日までに、譲渡所得の申告を行う必要があります。個人の確定申告と同時期です。
不動産の譲渡所得は分離課税と呼ばれ、給与所得などの所得とは別に課税されます。特に重要なのは、不動産の所有期間によって税率が大きく異なる点です。
譲渡所得税率は、売却した年の1月1日において5年以下の所有だと39%(うち、住民税の税率9%)です。一方、5年を超えて所有していると20%(うち、住民税の税率5%)に軽減されます。
たとえば、2020年6月5日に取得した不動産を2025年12月31日に売却するとします。取得日から売却日までは5年を超えていますが、売却した年の1月1日は2025年1月1日となり、取得日から5年を超えていません。つまり、軽減税率は適用されないことになります。
このように、税率判定では「売却日が5年超だから大丈夫」と誤解しやすいため、「1月1日時点での所有期間判定」を必ず確認することが重要です。慌てて売却してしまい、高い税率が課せられることのないよう、注意してください。
不動産の譲渡所得は、売却収入から取得費と譲渡費用を引いて計算します。取得費と譲渡費用には、以下の費用が挙げられます。
![[図表1]譲渡所得にかかる費用(筆者作成)](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/2efb4fab8d6a4bb2cd6648fa33c50866.jpg)
事業所得など他の所得で経費になっているものは取得費になりません。また、建物の取得費は減価償却を行ったあとの金額になります。
不動産を相続した場合には、亡くなった方の取得費を引き継ぐことになりますが、不明なことも多いです。その場合、基本的には売却収入の5%をかけて計算した金額が取得費になります。これを概算取得費と呼びます。
不動産価格が高騰しているときに購入した不動産に概算取得費(売却代金の5%)を使うと、納税者にとって大きな不利益になります。取得費の資料がない場合、税額が大幅に増えるため、売買契約書などは必ず保管しておきましょう。
市街地価格指数に基づき取得費を計算することもありますが、この方法は納税者が購入時の資料から取得費を立証することが求められます。税務調査で否認されるリスクもありますので、税理士に相談してから使うようにしてください。
相続不動産特有の税金軽減特例

不動産を譲渡する際に、相続が関係してくる特例としては以下の2つ。両者は選択適用とされています。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
この特例は、相続人が相続税と譲渡所得税という二重の税負担を負うことを緩和するために創設されました。
相続により取得した不動産を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、譲渡した不動産に係る相続税を取得費として加算することができます。
相続開始日は、基本的には亡くなった日となり、相続税の申告期限は亡くなった日から10ヵ月です。
この特例を適用する要件としては、亡くなった日から3年10ヵ月のあいだに不動産を譲渡すること。また、相続により不動産を取得した人が譲渡し、その人に相続税が課税されていることが必要になります。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
近年、空き家の数が増加しているというニュースを耳にしたことがあるという人も多いでしょう。その抑制の一環として平成28年の税制改正により創設された特例です。いわゆる「空き家特例」と呼ばれています。
相続により取得した不動産のうち、一定の要件を満たすものを譲渡した場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することが可能です。この特例の対象となる不動産は、被相続人(亡くなった方)が居住していた建物と土地になります。
ただし、相続人がその家に住んでしまった場合や、売却までの期限を過ぎた場合、その他の要件を満たさない場合などは、空き家特例や取得費加算の特例は適用できません。
この特例の適用を受けるには、以下のとおり多くの要件が設けられています。適用の可否については、必ず事前に税理士などの専門家にご確認ください。
![[図表2]空き家特例の要件(筆者作成)](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/802ec3e062ad1584fade022fd423dafd-1024x725.jpg)
契約から引き渡しまで、相続不動産売却の手順と注意点

実際に相続不動産を売却する際の手順は、通常の不動産売却との違いはありません。以下の4つのステップで進んでいきます。
- 不動産会社に売却依頼
- 売却活動と購入者との価格交渉
- 売買契約締結
- 決済と不動産の引渡し
不動産会社に売却依頼をする際に、専門サイトに不動産を登録すると、複数社まとめて査定依頼することができます。
不動産会社は契約をしたいために、最初は高い金額を提示してくることが多いです。契約後に売却価格を徐々に下げて、結果、当初の金額より相当低い金額で売却せざるを得なくなる話も聞きます。
そうならないためにも、提示された金額が相場として、近隣や過去の取引事例と比較して適正な金額であるかどうかを見極めることが大切です。
冒頭の不動産会社選びで触れたように、複数の不動産会社に話を持ち掛けることによって、なんとなく相場観がわかってくると思います。
また、価格の妥当性を見極めるだけでなく、その不動産会社が買主となる顧客をどれだけ抱えているかも非常に重要です。
たとえば、特定のエリアに特化している会社であれば、その地域の物件を探している顧客リストを豊富に持っている可能性がありますし、ファミリー層向け物件に強みを持つ会社であれば、子育て世代の買主が多いかもしれません。
1社のみと契約する専任媒介契約では、他の不動産会社と契約することができません。そのため、より多くの不動産会社と契約できる一般媒介契約で、高く売れる可能性を探るほうが有利な場合もあります。
税理士からの助言…不動産相続後の不動産の売却で、知らないと危険なこと

特に注意すべきは相続税の特例の期限です。取得費の特例は亡くなってから3年10ヵ月、空き家特例は亡くなってから3年後の年末までに、不動産を売却する必要があります。
そして、空き家特例の適用を受けるには、建物の取壊しや耐震基準を満たすことが要件となり、追加コストが生じます。
相続不動産は誰が相続するのかを生前から家族と話し合い、遺言書により円満に相続をすることが大切です。
相続対策が十分に行われていなければ、相続不動産を売却するまでに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に基づき相続の登記を済ませる必要がでてきます。
遺産分割協議では相続人全員の合意が必要ですので、合意がなければ、相続不動産を売却することができません。
また、不動産を共有名義で相続した場合にも、共有者の一人が「住み続けたい」と言い出したり、売却の条件が合わなかったりと、相続不動産を売却することができないでいる事例もたびたび見受けられます。
将来的なトラブルを避けるためにも、共有名義で不動産を相続するのは、できる限り避けたほうがよいでしょう。
多くの人にとって相続不動産の売却は、一生のうち何度も経験することではありません。不明点や不安がある場合は、税理士や不動産会社、弁護士等の専門家に早めに相談することで、思わぬ損失やトラブルを防げます。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、最新情報はホームページ等でご確認ください。























