不動産相続は、家族の数だけ異なる形があります。親の亡きあと、仲の良かった兄弟で揉めるなんて想像ができない、という人もいるでしょう。
しかし、特に不動産が絡む相続では、多くの家族で揉めやすい傾向にあります。実際の相続事例とその解決策、今後の相続に活かせるアドバイスを不動産と相続に精通する山村暢彦弁護士が紹介します。
実家の相続が兄弟姉妹の仲を壊す…よくある“想定外”の現実

「家制度・家父長制度」により、かつて「家」は長男が継ぐものとされてきました。
しかし現在の相続制度では、すべての相続人に平等に権利が認められます。法律上の相続分は平等でも、家族のなかには「実家は長男が継ぐもの」と信じて疑わない人もいまだ多く、この価値観のギャップがトラブルの火種になります。
ここからは実際にあった事例をご紹介します。
母の遺志に戸惑う弟妹、法定相続に異議を唱える長男
地方在住の40代長男・Aさんは、実家に母と奥さんとの三人暮らし。そして、都心部に離れて暮らす妹と弟がいました。
母が亡くなったあと、遺言書がないことが判明。そこで、母名義の不動産である実家をどう分けるかという問題が起きました。
Aさんは「自分や妻が介護してきたのだから、実家は当然自分が引き継ぐべき」と主張。実家に住み続ける意思も強く、他の兄弟姉妹には代償金を支払うつもりもありませんでした。
これに対し、妹と弟は「法定相続分に基づいて不動産も公平に分けるべき」「現金で代償金を払えないのなら売却すべき」と反発。兄弟姉妹間の話し合いは平行線をたどり、ついに遺産分割調停へ。
さらに、調停でもなかなか折り合わず、不動産鑑定による遺産分割審判目前までいきました。
不動産鑑定費用が高額であり、その支出をすると、兄弟姉妹双方が損をするという点と、それまでにも2年前後と長期的な紛争になっていたこともあり不動産鑑定・審判直前でやっと折り合い、なんとか終結したという事案へと発展しました。
なぜこうなる?背景にある3つの“相続トラブルの芽”

このような相続トラブルは、実は「珍しくない事例」です。その背景には、以下のような要因が複雑に絡み合っています。
価値観の衝突:「家を継ぐ」という旧来の感覚
戦前の家父長制度において「家」は長男が継ぐものでしたが、現代の法律ではすべての子に法定相続分があります。Aさんのように「自分が継ぐべき」という考えを持つ方は少なくありませんが、それを他の相続人が理解できるとは限りません。
介護や同居の「寄与分」が認められにくい現実
Aさんは母親の介護を一人で担ってきました。しかし、現行の民法における「寄与分」の認定は極めて限定的で、家庭内の無償介護は金銭的評価を受けにくいのが現実です。
裁判でも“特別の寄与”と認定されるには、職業的な介護人を雇うのと同等レベルの労力が求められることが多く、ハードルは非常に高くなっています。
結果として、「こんなに尽くしたのに」という思いが、他の兄弟姉妹に対する不信感や怒りに変わっていくのです。
不動産の評価の不透明性と分けにくさ
実家という不動産は、評価が難しいだけでなく「現物分割」ができません。結果として「売るか」「誰かが取得し、他の相続人に代償金を払うか」の選択を迫られます。
調停や審判になると不動産鑑定費用や弁護士費用が重くのしかかり、解決までに1年以上かかることも珍しくありません。感情面で「売りたくない」「お金は払えない」などの主張がぶつかり、話し合いはこじれやすくなります。
弁護士が実践した“劇的解決”のプロセス

Aさんの件では、審判直前に和解で終結しましたが、少なくともAさんの当初の意向どおりに裁判所で解決することは難しく、法定相続分に従って、実家を売却せざるを得ない一歩手前までいきました。
Aさんの実家を売却したくないという気持ちを汲み取り、金融機関、不動産会社等と協議を重ね、最終的に“ある方法”で和解の道が開けました。それが、賃貸併用住宅を兼ねた物件の再建築と、それによる代償金の借り入れでした。
Aさんは当時60歳。定年間近ということもあり、シンプルに代償金を金融機関から借り入れるというスキームだと、金融機関が貸し渋りました。
実家の土地は広く立地もよかったのですが、昔ながらの家屋が雑然と建てられており、あまり効率的に土地が利用できている状態ではありませんでした。
そのため、現状の老朽化した戸建て住宅の状態であれば、融資は難しいが、新たに賃貸併用住宅などに効率的に土地を利用すれば融資可能性がある、と考え、案を練っていきました。
最終的には、代償金+建築費の返済も考慮すると、土地を分筆して売却するよりも、土地全体に賃貸併用住宅を建てて、融資の返済と賃料による収入のバランスを取るのが一番よいだろうと、このスキームで代償金を含めた資金を借入れ、解決することができました。
この方法は、都市部や立地が良いケースに限られる場合も多いですが、親世代の家を新たな収益物件として活用することで、相続人全体にメリットがある選択肢となることもあります。
裁判所の解決自体は、どうしても法定相続という帰結を変えることはできなかったので、不動産の活用を見直すことで、「売却しなければならない」という前提を覆しました。
「実家を売却したくない」というAさんの意向をなんとか守りきることができた解決方法だと思います。
相続トラブルを防ぐには
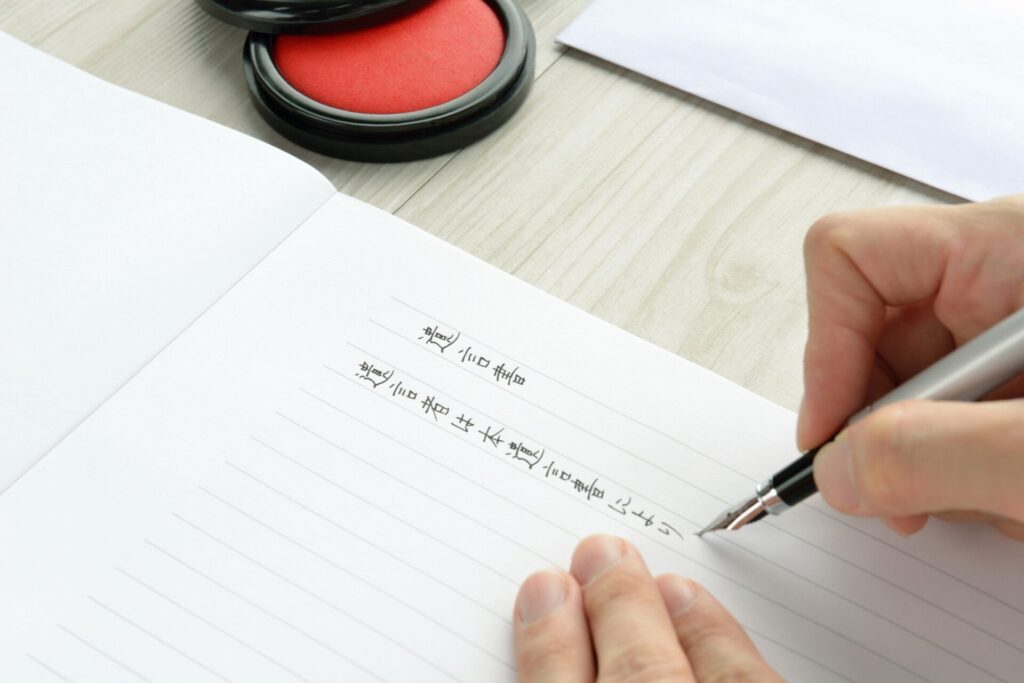
このようなトラブルを未然に防ぐために、できる限り早い段階で次のような対策を検討しておくことが重要です。
遺言書の作成
「親の気持ち」が明確に書かれた遺言書があれば、多くの争いは未然に防げることが多いと思います。形式不備のないよう、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を推奨します。
財産の構成を見直す
不動産ばかりを遺すのではなく、預貯金など流動性のある資産を残すことも大切です。これにより、代償分割がスムーズになります。
家族での定期的な対話
「うちの家族に限って揉めるはずがない」と思っていても、相続は価値観・感情・事情が絡みます。
親が元気なうちに、どのように財産を分けたいのかを話し合う機会を設けることが肝要です。相続発生後では話し合いが感情的になりやすいため、事前の意向確認が欠かせません。
「心情」と「法」の狭間で
弁護士として多くの相続案件に関わってきましたが、「法律だけで解決できる問題ではない」と感じる場面が多々あります。兄弟姉妹それぞれに事情があり、親との関わり方、経済状況、価値観も異なります。相続は、その“積年の家族関係”が一気に表面化する場面です。
だからこそ、「法的な整理」と「心情的なケア」の両方が必要になります。そして、どちらにも正解はありません。
ですが、専門家として、少なくとも法のルールのもとに「いま、なにができるか」「どこに落とし所があるか」を提示することは可能です。家族だけで抱え込まず、第三者の意見を取り入れることで、解決への糸口が見つかることも多いです。
おわりに…後悔しない相続のために、いまできることを

相続問題は、誰にとっても避けて通れません。特に実家のような不動産は「モノ」であると同時に、「想い出」でもあるため、話し合いが難航しやすいものです。
しかし、きちんとした準備と冷静な第三者のアドバイスがあれば、感情的な対立を抑え、円満な解決に導くことも十分に可能です。
「うちには関係ない」と思わずに、早めにご家族で話し合ってみるほうがよいと思います。
そして、もしも判断に迷ったら、どうぞ、税理士・弁護士等の士業、不動産会社、金融機関等の私たちのような専門家にご相談ください。あなたのご家族にとって最良の道を、一緒に探していきましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、最新情報はホームページ等でご確認ください。

























