相続が発生し、不動産を引き継いだ際に行う名義変更手続き、いわゆる不動産の相続登記が2024年4月より義務化されました。この変更によってどのような影響がおよぶのでしょうか?
本記事では法律改正の具体的な内容とともに、自身で登記手続きを進める場合と、専門家に依頼する場合のメリット・デメリット、必要な書類や費用について、司法書士の近藤崇氏がわかりやすく解説します。
2024年4月、相続登記が義務化…放置するとどうなる?
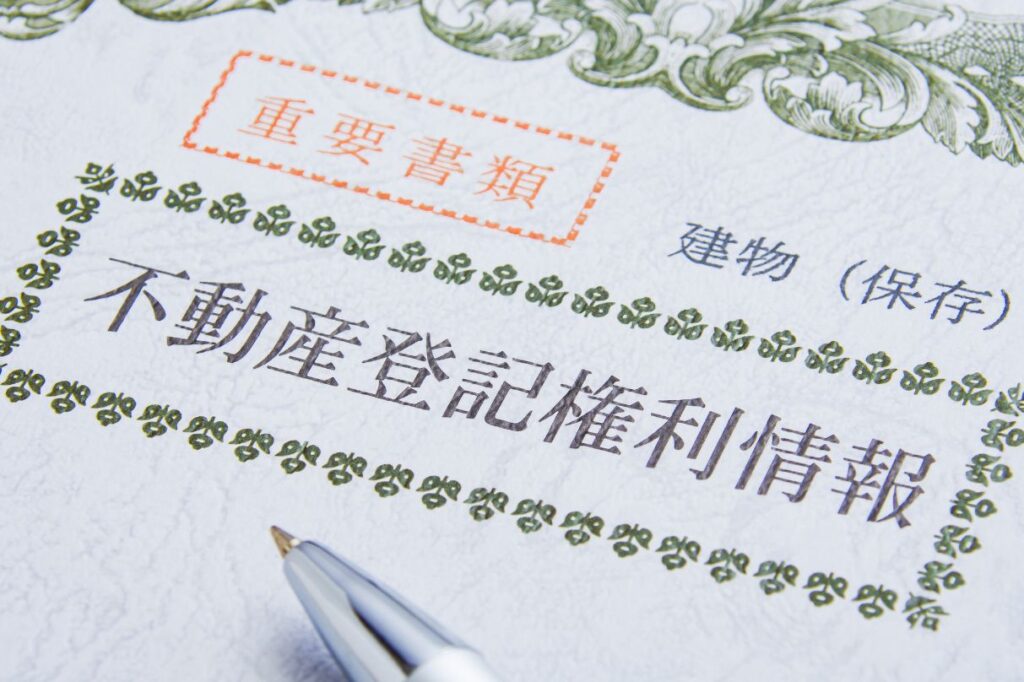
相続登記が義務化された背景には、長年不動産の名義変更が行われず、故人の名義のままになっている土地が増え続けているという社会問題があります。全国的に所有者不明の土地面積の合計は、全国で九州本島より広い規模に達しているともいわれています※。
今回の法律改正により、 相続(遺贈も含む)によって不動産を取得した相続人や受遺者は、「その所有権の取得を知った日から3年以内」に相続登録を行うことが義務化されました。
また遺産分割が成立した場合には、遺産分割協議の成立した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
※参照元:所有者不明土地問題研究会 最終報告
今回の相続登記義務化のポイントは下記の3点です。
- 対象者:相続によって不動産を取得したすべての人(遺贈を含む)
- 期 限:相続が発生したことを知った日から3年以内
- 罰 則:正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性
相続登記を怠ると、過料(かりょう)という行政上の金銭的な制裁が科される場合があります。刑事罰ではありませんが、法律上の義務違反として見逃せないポイントです。
現時点(制度導入から3年未満)では実際に過料が科された事例は報道されていませんが、今後ペナルティを回避するためにも「早めの対応」が何より大切です。
相続登記は自分でできる?専門家に頼むべき?

自分で相続登記を行う場合、司法書士の報酬がかからないためコスト面のメリットがあります。
一方で、必要な書類の収集や手続きもすべて自分で進める必要があり、想像以上の手間や、誤記載・不備のリスクが伴います。具体的には、戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書の準備、さらに申請書作成や法務局への申請が必要となります。
自分で手続きする場合
メリット
- 費用を抑えられる
- 手続きを学ぶことで知識が身につく
デメリット
- 書類の準備や手続きが複雑
- 誤記載や不備があると、役所や法務局へ再提出が必要
- 平日昼間にしか窓口が開いておらず、社会人には不便
司法書士に依頼する場合
メリット
- 手続きのミスを防げる
- 書類の収集や作成を代行してもらえる
- 複雑な相続案件にも対応可能
- 相続に精通した司法書士なら、節税や二次相続対策のアドバイスも受けられる
デメリット
- 報酬が発生する
司法書士に依頼する場合、費用相場は地域や案件内容によって差がありますが、「親から子」への単純な相続であれば数万円から十万円前後が目安です。
なお筆者の事務所の場合、戸籍謄本等も司法書士側で極力取得するため、ご用意いただく書類は相続人の印鑑証明書程度で済みます。
相続登記の必要書類と準備のポイント

相続登記に必要な主な書類には、故人(被相続人)の戸籍謄本、相続人の住民票、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが含まれます。これらの書類は、正確にそろえる必要があります。
主な書類の目的や入手先は下記のとおりです。

戸籍謄本は役所で取得、遺産分割協議書は相続人全員の署名・押印が必要です。
準備には予想以上に時間がかかることがあるため、余裕を持ったスケジュールを意識しましょう。
もし登記の申請書や添付書類に不備がある場合、法務局から「補正」の連絡が入り、再提出や修正が必要になります。
自分で手続きを行う場合、一度の提出では完了しないので、この補正のたびに時間を取られます。また、法務局は平日昼間しか開庁していないため、仕事をしている人にとっては不便かもしれません。
そもそも法務局は裁判所と同じ「審査機関」であるため、書類作成について親切に回答をすることができない立場です。裁判所が勝訴できるような訴状の書き方を教えてくれるわけがないのと同じです。
相続登記には登録免許税(印紙代)が必要です。税率は不動産登記のなかでは比較的安く、相続不動産の評価額の0.4%となっています。
司法書士に依頼する場合、この登録免許税は報酬とともに司法書士に支払い、司法書士が登記申請時に代理で納税することが一般的です。さらに、戸籍謄本の取得費用、登記簿謄本の取得費用なども必要となります。
自分で相続登記する場合の「落とし穴」とは?

自分で相続登記を行う場合のデメリットは、手間や時間の負担だけでなく、相続税において不利な分割での登記をしてしまうリスクがあることです。
特に多いのが、二次相続(次に起こり得る相続への対策)を検討せずに法定相続分で登記してしまうケースです。また、登記自体が遅れることで、相続税の申告期限内に受けられたはずの相続税上の恩恵を逃してしまうケースも見受けられました。
相続した不動産を売却予定している場合、空き家控除などの特例を受けられないような登記内容となってしまうリスクも見逃せません。登記に不備があることで、売却時の決済日に間に合わないといったトラブルも起こるでしょう。
特に注意が必要なのは、法定相続分で登記したあとに、遺産分割協議をやり直すケースです。
登記簿上では「遺産分割」を理由とした不動産所有権移転登記は可能ですが、これは新たな財産の移転とみなされ、「贈与税」や「譲渡所得税」が課税される可能性があります。相続税の納税申告期限が過ぎたあとの移転は特に要注意です。
「とりあえず登記しておく」のではなく、将来の相続や売却も見据えた適切な登記を行うため、事前に専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
相続登記義務化は「不動産を次世代に確実に引き継ぐ」ための大切なステップ

2024年4月から相続登記が義務化され、これまで放置されがちだった不動産の名義変更手続きが必須となりました。
新たなペナルティが設けられた背景には、相続登記を怠ることで不動産の売却や管理、さらには二次相続においてさまざまなトラブルが発生していた現実があります。
相続登記は単なる「役所への届け出」ではなく、大切な資産を次の世代に確実に引き継ぐための重要な行為です。自分で手続きを進めれば、費用を抑えられるものの、手間と正確さが求められ、考慮すべきリスクがあったとしても誰からも指摘を受けられません。
一方、司法書士に依頼すればスムーズで安心感がある反面、一定の費用はかかります。どちらの方法を選ぶかは、ご家族の状況や相続財産の内容によって判断が分かれるでしょう。
相続登記は単なる手続きではなく、不動産という財産を守るための重要な作業です。義務化された今、先送りせずに早めの対応をお勧めします。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、最新情報はホームページ等でご確認ください。
























