老後の生活設計では「資産を守る」ことに目が向きがちですが、本来お金は生活を支え、人生を豊かにするために活用するものです。
貯めた資産をどのように使うかは、老後の満足度を大きく左右します。計画的に使えば、資産の減少は恐れるべきものではなく、人生の豊かさを高める手段となるでしょう。
本記事では、不安を抑えながら資産を活用し、心豊かな老後を実現するための考え方と具体的な方法を紹介します。
お金は使うためにある!

老後生活に備えてお金を貯めることは大切ですが、そもそも資産は生活を豊かにするために築くものです。今こそできる経験や満足度にお金を使うことで、人生はより充実します。
資産が減ると心理的に不安に思うこともあるかもしれませんが、使うことで資産が減っていくのは当然のこと。
使わないようにと必要以上に生活を切り詰めるより、資産が枯渇しないよう適切に使っていけるよう、コントロールすることが重要になります。
世界的ベストセラー『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』(ダイヤモンド社)で語られた「お金を残すのではなく、使いきることで満足度を高める」という考え方も広まっています。
ただし、支出の多さと生活の満足度は必ずしも比例するわけではありません。あくまで自分にとって「豊か」だと感じられる使い方を見極めることが肝心です。
お金を預貯金などに寝かせている高齢者は多く、その一部を使うことは、経済の循環、次世代への還元にもつながります。
また、地方在住者が遺産を残して亡くなった場合、都心に住む遺族に資産が移ることになるため、今のうちに居住地でお金を使うことは地方活性化にも寄与します。
資産が減っていく不安をなくす取り崩し計画

生活の満足度は①健康、②仕事・やりがい、③人間関係、④資産水準の4項目からなります。
そのうち①〜③は支出によって向上できますが、④資産水準についてはお金を使うほど不安が高まるため、満足度が低下します。
資産の減少による不安を軽減するには、行動経済学でいう「参照点」の概念が有効です。評価の基準をどこに置くかで、資産の増減に対する感じ方が変わるという考え方です。
例えば、現在の株価が1,000円だと仮定します。1カ月前が1,200円の場合は現時点で値下がりしていると感じますが、1年前が800円である場合は比較して上昇したと考えられるでしょう。
この考え方を応用し、老後の資産計画でも65歳で4,000万円、70歳で3,800万円、75歳で3,600万円と、年齢ごとの目標残高(参照点)を設けておきます。
68歳時点で3,900万円あれば、65歳時点の4,000万円から100万円減っていることにはなりますが、70歳時点での目標金額3,800万円を参照点とすれば、比較して「まだ余裕がある」と心理的な負担を軽減できます。
![[図表]目標設定のイメージ](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/e32c57ea45a2797ba1f26c1ea34dd13c.png)
年齢ごとの目標金額は、老後の生活をイメージしながら、高齢のタイミングから逆算していくのがポイントです。
90歳時点でどのくらいあれば安心か、80歳時点ならどのくらいか、と考えていきます。そうすれば、何歳までにいくら用意しておけばいいか、そのために今何ができるかといった課題も見えてきます。
「いつまで取り崩すか」と期限を設定することは、「いつまで生きるか」を考えることにもなりますが、寿命は予想できません。
そのため、100歳まで生きても大丈夫なように、なるべく資産を長持ちさせることが重要です。保守的に計画すれば、「お金がなくなる」という不安感を払拭できます。
理論上、定額ではなく定率で取り崩したほうが設定した年齢ごとの残高目標に着地しやすくなります。
市場の値動きによって受け取れる金額は変わりますが、例えば年に1回、定率で取り崩すと決めて、その時点で得られた金額で1年をどう使っていくかを考えるのもひとつの方法です。
人生を豊かにする老後のお金の使い道

資産形成をするうえでは、「生活費」と「趣味・娯楽」を分けて用意するイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、退職後は趣味や楽しみのための時間も生活の一部となります。旅行などのイベントにかかる費用も、実際にいつどのくらいの金額がかかるかは見通しにくいものです。
明確に分けて備えるよりも、資産全体で見て柔軟に対応していくのがよいでしょう。
好きな場所で働きながら趣味を深めるなど、生活と娯楽が融合したライフスタイルになる可能性があります。「どのような生活を送りたいか」「何が人生の潤いになるか」をイメージしておくと、お金の使い道が自然と見えてきます。
具体的な使い道の例としては、旅行や小規模ビジネス、子や孫への支援、自己投資、友人との交流などが挙げられます。
![[図表]お金の使い道の例](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/beb0a71fef2f1354f7514cdd4d6896da.png)
シニア層へのインタビューを続けていると、老後の生活といっても誰もが同じではなく、多様な生活とお金の使い方があることがわかります。
定年退職を迎えてからも、仕事を続ける方は少なくありません。むしろ、自分の好きな仕事を選べたり、やりたくない仕事を断れたりと、柔軟性が上がることもあります。
資産がある方は、別荘地との二拠点生活をしていたり、サービス付き高齢者向け住宅への転居を検討していたりと、ライフスタイルの変化に伴って、住まいのあり方も変わっているようです。
保有する株式を売却してソーラーパネルを設置して売電を行っている方や、シニアになってから実家の米農家を継いで家族や地域の方と充実した生活を送っている方もいます。
何にどのくらい使っている?シニアの実体験
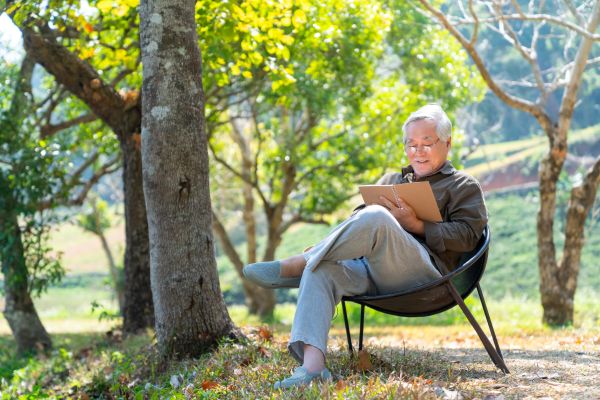
野尻氏は60代へのアンケート調査や個別のインタビューを実施し、シニアの生の声を吸い上げています。その中から、豊かにお金を使っている例をご紹介します。
実体験① 子どもへの住宅援助:贈与300万円+貸与500万円
66歳のNさんは、外資系研究所のセキュリティの仕事で月10回の夜勤勤務をこなしています。
野球観戦と将棋が趣味で、それ以外にとくにやりたいことがあるわけではないため、70歳くらいまでは働く意向です。
勤労収入に加え、転居前に住んでいたマンションの賃貸収入、企業年金で生活費はカバーできています。
現在の資産の使い道はお子さんへの住宅購入費の援助。300万円を贈与し、500万円は10年のローンとして契約書を取り交わして貸与しました。
実体験② 海外旅行:年間200万円程度
60歳で単身世帯のGさんは、58歳で退職して現在は年金と配当収入で暮らしています。
海外旅行で、世界中のHard Rock Cafeを回ってTシャツを買い集めるのが趣味です。
1回当たりの旅費は高くないものの、年10回ほどと回数が多いため、年間にすると200〜250万円の支出になっています。
身軽にひとり旅ができる生活が楽しく、そのための費用も惜しみたくないとのこと。「資産は死ぬまでに使い切りたい」と充実した生活を送っています。
実体験③ 中古戸建購入:頭金1,100万円
地方に住む59歳のKさんは、息子と二人、父子家庭で過ごしてきました。
2,000万円の退職金のうち1,100万円を頭金に、2,400万円の中古の戸建てを購入。残りの1,300万円は息子さんが住宅ローンを組んで、月35,000円を負担しています。
旅行などの多額な出費や没頭するほどの趣味はないようですが、日々の買い物や食事の準備、ごろごろと自由な時間を過ごすことに幸せを感じている様子です。
おわりに
老後資産は、守るべき「貯蓄」としてだけではなく、人生の満足を支える「使う資源」として向き合うことも大切です。お金を使うことは、自分の生活の満足度を上げるだけでなく、経済循環や地方活性化にもつながります。
年齢別の目標額や取り崩し計画を設けるなどの工夫をすると、不安と支出額をコントロールしながら、自分にとって意味ある体験に資金を使えるようになります。
「どう暮らしていきたいか」「何にお金を使いたいか」自分の老後をポジティブにイメージしながら、支出の面からも計画を練っていきましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。























