海外に住んでいる相続人が、日本の不動産を相続することになった場合、なにから手をつければよいのでしょうか。現地の法律や税制、複雑な手続きなど、国内での相続とは異なる課題が多く生じます。
具体的な注意点や、相続発生から完了までのタイムラインについて、海外居住者が知っておくべき不動産相続のポイントを税理士の奥村眞吾氏が解説します。
海外在住者が日本の不動産を相続する際の「3つの壁」

筆者の米国事務所があり、日系人が一番多く住む街である、ロサンゼルス。そこには約15万人の日本語を話すことができる日本人が住んでいます。留学生や海外転勤者、移住者などさまざまです。
もちろん日本語が得意でない2世、3世もいますが、日系一世の彼らは、昔の移民のように日本では生活に困り新天地を求めてアメリカや南米に渡った人たちではなく、新しいビジネスを求めて渡米した人や、留学をしてそのままアメリカに住んだ人、そして家庭をアメリカに築いた人などが多いです。
そしてそのほとんどがグリーンカードホルダー(永住権)か米国市民権を取得しています。従って、親や兄弟、親戚が日本にいるという状況の人たちが大半です。
人生100年時代、親が90歳以上ということも珍しくなくなり、相続する子の側も海外での生活基盤が固まっている年代です。日本の民法では、在米の子も日本に居住している子も等しく相続権があります。
しかし、実際に相続が始まると、国内での手続きとは異なる、大きく3つの壁が立ちはだかります。
- 物理的な距離の壁:手続きのために頻繁に帰国するのは、時間的にも費用的にも大きな負担となります。
- 感情的な壁:同じ親を持つ兄弟姉妹であっても、海外で遠く離れて暮らしているため、親交がないこともあります。海外在住で距離があるゆえに、国内の兄弟姉妹との間で「介護負担」や「遺産分割」をめぐるすれ違いが生じやすいのも現実です。
- 制度的な壁:日本に住民票や印鑑証明がない場合、手続きが非常に複雑になります。
将来日本に住む予定がない場合、海外から日本の不動産を管理・納税していくのは大きな負担です。さらに近年は、相続人全員が海外在住というケースも増加傾向にあります。
この場合、日本の相続登記や納税手続きがさらに複雑化します。こうした特有の事情を理解したうえで、手続きを進めなければなりません。
不動産の相続手続きの進め方
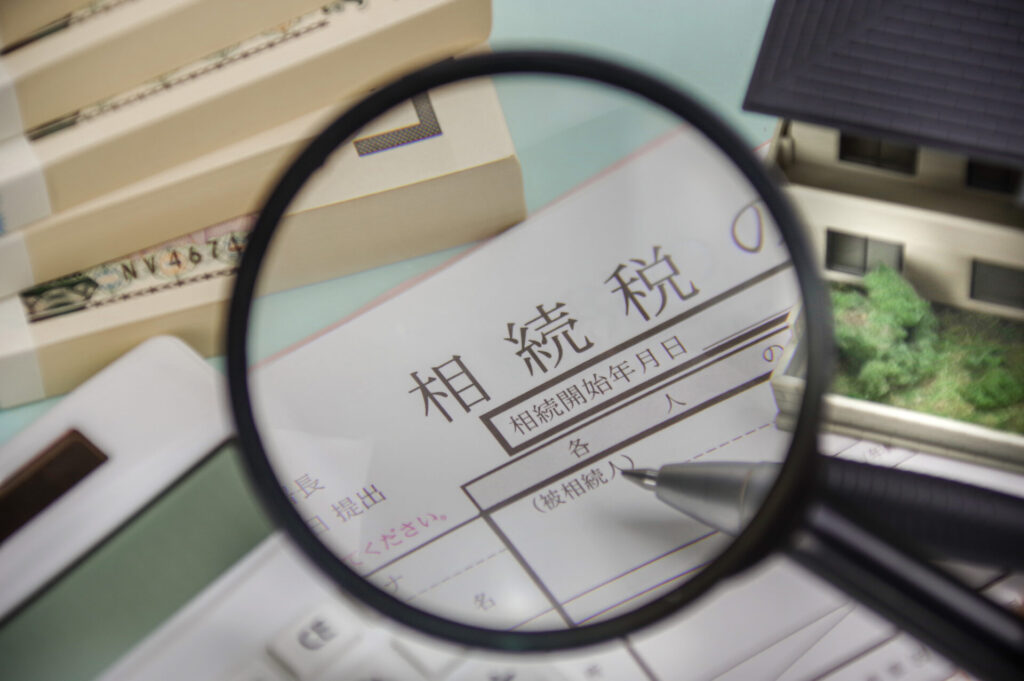
では、相続人に海外居住者が含まれる不動産相続は、どのように進めていくのでしょうか。3つのステップに分けて説明していきます。
〈STEP 1〉相続登記の手続き:必要書類と注意点
不動産の相続登記は、相続取得を知った日から3年以内の申請が義務化されています。期限を過ぎると過料の対象となるため、早めの着手が必要です。
相続人が日本国籍で日本在住であれば、一般には遺産分割協議書に実印を押し、戸籍謄本や印鑑証明書を添付して司法書士に依頼します。
海外に住んでいても日本に住民票がある場合、あるいは日本に住民票が移せる場合は、日本居住者と同様に不動産の相続登記が可能です。
しかし、日本に住民票や印鑑証明書がない海外居住者の場合は、手続きが異なります。
〇日本国籍を持つ海外居住者の場合
居住地の日本大使館や領事館といった在外公館で、「在留証明書」(住民票の代わり)と「サイン証明書」(印鑑証明書の代わり)を発行してもらう必要があります。
〇日本国籍を放棄している場合
在外公館で証明書を発行できません。この場合、現地の公証・認証(宣誓供述書等)を経て、アポスティーユや領事認証を付した上で日本側で受理される形式に整えます。
いずれにせよ、海外から手続きを進めるには、以下の書類等を日本にいる代理人(他の相続人や専門家)に送り、手続きを委任するのが一般的です。
実務面を考慮すると、日本国籍を有している場合は、住民票や印鑑証明書を取得できる道を環境を整えておくと、登記などの手続きが円滑に進みやすくなります。
★海外居住者の不動産相続に関しての必要書類
- 在外公館での在留証明書および署名証明書(サイン証明書)
- 遺産分割協議書への押印あるいはサイン(サイン証明書添付)
- 相続する不動産の登記簿謄本並びに固定資産税評価証明書
- 死後10ヵ月以内の相続税の申告書および相続税の納付
帰国が不可能な場合は、納税管理人を立てて委任をしますが、納税管理人は親族のほか、税理士事務所に依頼することも可能です。ア、イ(在留証明書・署名証明書)以外の手続きを海外居住者が帰国せずに行うことはできません。
代理人や納税管理人を置くか、他の共同相続人(兄弟姉妹等)に委任する方法があります。その場合、国外で取得しなければならない書類やア、イの証明書を日本に送付し、手続きを委任することになります。
〈STEP 2〉相続税の申告:あなたは「制限」or「無制限」納税義務者?
日本の相続税は、相続人の国籍や居住地によって、課税される財産の範囲が変わります。
〇無制限納税義務者
課税対象:被相続人(亡くなった親など)が遺した、日本国内および海外のすべての財産
主な該当者:
- 日本国内に居住している人(国籍問わず)
- 海外に居住している日本国籍の人で、相続発生前10年以内のいずれかの時点で日本に住所があった人(一時的な海外赴任者など)
〇制限納税義務者
課税対象:被相続人が遺した、日本国内の財産のみ
主な該当者:
- 海外に居住している外国籍の人
- 海外に居住している日本国籍の人で、相続発生前10年間、継続して日本に住所がなかった人(海外永住者など)
上記の区分を分けるのが、「日本の居住者かどうか」という点です。これは、単に住民票の有無や年間の滞在日数(183日ルールなど)だけで決まるわけではありません。
税法上の「居住者」か「非居住者」かは、住民票の有無や滞在日数ではなく、「生活の本拠(家族・職業・資産の所在など)」を基準に総合的に判断されます。
判断基準の例としては、
- 家族(配偶者や子)がどこに住んでいるか
- 仕事の主たる勤務地はどこか
- 預貯金や不動産など、主な資産はどこにあるか
などが挙げられます。もう少し具体的かつ詳しくみていきましょう。
相続発生日に国外に居住していて、日本国籍を持たない人は、被相続人が所有していた日本国内財産のみが課税対象になり、被相続人の海外資産には日本の相続税は課税されません。
さらに、日本国籍があっても相続発生日以前10年以内に海外居住者であり続ける人も同様に、被相続人の所有する日本国内財産にのみ相続税がかかります。
それ以外の日本人、たとえば海外に居住して8年の人や、一時的に海外に住んでいる人などは、「無制限納税義務者」としてすべて日本国内居住者と同様に扱われ、被相続人が残した全世界の財産が日本の相続税の課税対象です。
ただし、日本のように住民票制度のある国はほとんどなく、日本の住民票には国外へ出国した旨のみが記載されています。つまり実務上は、日本を出国して海外のどこに住んでいたかという判断は、在留証明書の記載でしか証明できなくなります。
海外に居住していたかどうかの判定は、海外に住み続け、日本に帰国していなければ海外居住者となりますが、ときどき帰国している人や、頻繁に出入りしている人の居住地については問題が発生することがあります。
たとえば、留学や短期の海外出張で一時的に海外にいる場合は「居住者」とみなされます。一方、海外で就労ビザを取得し、家族とともに長期間暮らしている場合は「非居住者」と判断されるのが一般的です。日本人のMLBプレーヤーなどをみるとわかりやすいでしょう。
《要注意!「国外転出時課税(出国税)」の特例》
1億円以上の有価証券等を持つ人が日本から出国する場合、その有価証券を売却したとみなして課税される「国外転出時課税(出国税)」という制度があります。
なお、国外転出時課税(出国税)で納税猶予を受けている場合は、一定期間は「居住者」とみなされ、無制限納税義務者として扱われる可能性があります。適用可否は個別判定のため、専門家への確認が望まれます。
〈STEP3〉申告と納税:10ヵ月の期限と「納税管理人」の役割
相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です。この期間内に遺産分割協議書や必要書類を整えておく必要があります。
共同相続人が日本にいて、遺産相続や申告を主導してくれるのであれば、大きな負担にはならないでしょう。しかし、以下の書類等は誰が相続するにしても必要です。
〇相続税申告書
国税庁所定の用紙に日本語で記入し、提出する必要があります。海外居住者が自ら行うのは困難なため、税理士や共同相続人、納税管理人に委任するのが一般的です。
〇相続税の納付
相続税の納付は、金融機関窓口のほか、ダイレクト納付やインターネットバンキングなども選択できます。海外在住者は納税管理人を選任し、納付方法を事前に決めておくことが重要です。
※クレジットカードでの納付も可能ですが、別途決済手数料が発生します。また、海外発行のカードや利用状況によっては決済がブロックされる可能性もあるため、事前に利用可否を確認しておくとより安心です。
こうした手続きを円滑に進めるため、海外居住者は「納税管理人」を選任し、税務署へ届け出る必要があります。納税管理人は、申告・納税手続きを本人に代わって行う代理人であり、親族のほか、税理士に依頼することも可能です。
おわりに…時間との闘いになる海外居住者の不動産相続

海外居住者が日本の不動産を相続する手続きは、時間的制約があるなかで、国内での相続とは比較にならないほど複雑で、負担が大きいのが現実です。
いざというときに慌てないためにも、最も重要なのは「早期の準備」と「信頼できる日本国内の代理人(納税管理人)を事前に決めておくこと」です。
ご自身の状況でどのような手続きや書類が必要になるのか、そして誰に代理人を依頼するのか。親子が元気なうちに、税理士や司法書士など専門家を交えて必要書類や代理体制を整理しておくことが大切です。準備が早いほど、期限超過や手戻りを防げます。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。























