重度の認知症などで本人の判断能力が不十分になった場合、資産の管理や保護を目的として代理人を選任する制度を成年後見制度といいます。本記事では、成年後見制度の概要や後見人になれる人について、実際の利用の流れやデメリットについても紹介します。
(本記事は2024年2月1日時点の情報です。)
- 成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類がある
- 法定後見は家庭裁判所に申し立てが必要であり、任意後見は公正証書での契約が必要である
- たとえ家族が後見人になったとしても、本人の財産を勝手に動かすことはできない
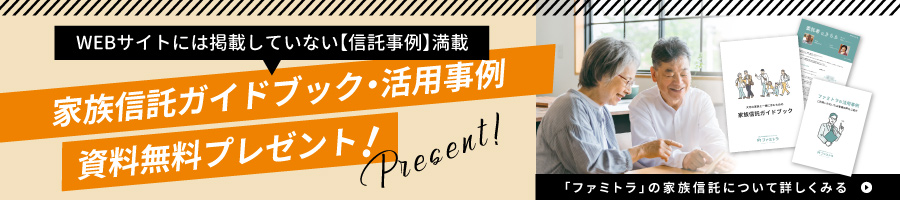
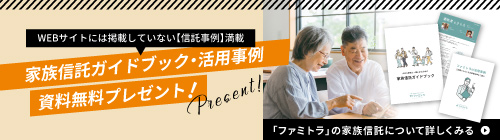
成年後見制度とは

認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人が生活をする上で不利益を被らないよう、「成年後見人」が本人の代わりに適切な財産管理や契約行為の支援を行う制度を成年後見制度といいます。
認知症などが理由で判断能力が低下すると、本人の意思確認ができないため金融機関から取引不可と判断されてしまいます。本人の資産などを適切に守るためにも、代理人である成年後見制度を活用しましょう。
成年後見制度の利用がおすすめのケース
成年後見制度の利用を積極的に検討したいケースとして、次の2つがあります。
- 金融機関の手続きや不動産の契約ができない場合
- 財産管理が不安な場合
金融機関の手続きや不動産などの契約ができない場合
金融機関にある本人名義の口座から金銭を引き出すことや、本人以外が本人名義の不動産売却などの手続きをすることはできません。本人以外が金融機関の手続きや不動産の契約を代行する場合は、成年後見人を立てる必要があります。
財産管理が不安な場合
本人の意思能力に不安があり詐欺被害に遭わないか心配な場合や、家族が本人のお金を使い込んでいないかなどが心配な場合にも成年後見制度は有効です。
成年後見制度は2種類

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」という2種類の制度があります。どちらを利用するかは、成年被後見人(成年後見人による支援が必要な人)の判断力があるかどうかを基準にして選ぶことになります。ここからは、法定後見制度と任意後見制度にわけて、それぞれ解説していきます。
法定後見制度とは
法定後見制度とは、成年被後見人(本人)の判断力が不十分と判断される場合に利用される制度です。まずは家庭裁判所へ申し立てることで、制度の利用ができるようになります。支援を受ける本人の判断能力の程度ごとに「後見」「保佐」「補助」と細かく3つに分類されます。
後見
後見とは、最も状態が重い状態で、常に本人の判断能力が欠けている場合に対象となります。重度の認知症患者や重度の精神疾患の患者などがこれに該当します。本人が被後見人とされた場合、後見制度で指定される人のことを成年後見人といいます。
保佐
補佐とは、本人の判断能力が著しく不十分な場合に対象となります。本人が保佐である場合、サポートをする人のことを保佐人と呼びます。
補助
補助とは、本人の判断能力が不十分な場合でこれら3つのなかで最も状態が軽い場合に対象となります。この場合、サポートする人のことを補助人と呼びます。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、成年被後見人の判断力がまだ十分にある場合に採用される制度です。今後判断能力が低下する恐れのある将来に不安を抱える人が、健康なうちに自ら後見人をあらかじめ指名し、契約を結んでおくものです。
本人の意思能力がはっきりしているうちに契約を結ぶため、任意後見制度では本人が指定した人を後見人とすることができます。
成年後見人とは?

成年後見人とは、判断能力が不十分な成年被後見人に代わって手続き等を支援する人のことです。成年後見人について、解説していきます。
成年後見人の役割
成年後見人は、生活・医療・介護・福祉などの観点から成年被後見人(本人)を保護・支援する役割があります。
ただし、成年後見人であっても本人の居住用不動産を処分する場合には家庭裁判所の許可が必要です。そのため、勝手に売却等はできない決まりになっています。さらに成年後見人に利益があるような法的行為が生じる場合には、成年後見人以外に特別代理人や成年後見監督人を選出する必要があります。具体的には、本人と後見人がいずれも相続人となり、遺産分割協議を行う場合などがあります。
成年後見人になれる人は?
成年後見人になるには特別な資格や条件は必要なく、誰でもなれます。多くの場合は親族が選ばれますが、弁護士や司法士、社会福祉士などの専門家が選任されることもあります。家族ではない第三者が選ばれるケースとしては、家族関係に問題がある場合などがあります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は成年後見人になれません。
- 未成年
- 過去に後見人を含む法定代理人を解任されたことがある人
- 破産者
- 被後見人に訴訟を起こしている人やその配偶者および直系血族
- 行方不明の人
- その他被後見人とトラブルのある人
成年後見制度において、後見人を一人ではなく複数人とする共同後見を活用する場合もあります。
成年後見制度を利用する流れ

成年後見制度を利用する際の流れについて解説します。法定後見と任意後見で手続きが異なりますので、それぞれについてまとめて紹介していきます。
法定後見制度を利用する流れ
法定後見制度を利用する場合の流れは次の通りです。
- 家庭裁判所へ申し立ての準備をする
- 家庭裁判所で審理が行われる
- 裁判官により審判が下される
- 後見の登記が行われ、この後成年後見人の仕事が開始される
申立ての準備には次の書類が必要です。
- 申立書一式(家庭裁判所で入手するかホームページからダウンロード)
- 医師の診断書
- 後見人候補者や親族の同意書
任意後見制度を利用する流れ
任意後見制度では、契約時と利用時にそれぞれ手続きが必要です。まずは任意後見受任者を選び、契約内容を取り決めます。契約後、時間が経過し本人の意思能力が低下し実施に任意後見制度を利用する場面になると「任意後見監督人」を選び、その後任意後見人となった人の職務が開始される流れになります。
- 任意後見の契約をする(必ず公正証書で行う)
- 家庭裁判所に任意後見監督人の選任を依頼する
なお、任意後見監督人の選任申立手続は、本人やその配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者が行います。
成年後見制度を利用するときに必要な費用

成年後見制度を利用する際には、法定後見人と任意後見人のどちらを立てる場合でも費用がかかります。具体的には、手続き費用と後見人への報酬の2つの費用が発生します。それぞれについて以下に解説していきます。
- 申し立ての際にかかる費用
- 後見人などへの報酬の相場
申し立ての際にかかる費用
成年後見制度の申し立てに必要な費用と内訳には、次のものがあります。
【法定後見制度】
- 申立手数料 800円(収入印紙)
- 登記手数料 2,600円(収入印紙)
法定後見開始の審判の申立てに必要な費用について
| 補助 | 保佐 | 後見 | |
| 申立手数料(収入印紙) | 800円※1 | 800円※2 | 800円 |
| 登記手数料(収入印紙) | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 |
| その他 | 連絡用の郵便切手※3、鑑定料※4 | ||
※1 補助開始の審判をするには、補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなり ませんが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。
※2 保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立 てをするには、申立てごとに別途、収入印紙800円が必要になります。
※3 申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。
※4 後見と保佐では、必要なときには、ご本人の不安の程度を医学的に十分確認するために、医師に よる鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なります が、ほとんどの場合、10万円以下となっています。
引用元:厚生労働省 成年後見はやわかり 法定後見制度とは(手続の流れ、費用)
【任意後見制度】
| 任意後見契約公正証書の作成に必要な費用について | |
| 作成の基本手数料 | 11,000円 |
| 登記嘱託手数料 | 1,400円 |
| 登記所に納付する印紙代 | 2,600円 |
| その他 | ご本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など |
- 任意後見制度契約にかかる公正証書作成の基本手数料 11,000円
- 登記嘱託手数料 1,400円
- 登記所に納付する印紙代 2,600円
- その他本人などに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など実費が必要
引用元:厚生労働省 成年後見はやわかり 任意後見制度とは(手続の流れ、費用)
後見人などへの報酬の相場
後見人などへの報酬の相場費用は、通常の後見等の事務を行った場合で毎月の報酬として1~
2万円程度と決定されることが多いようです。
任意後見制度の場合は、任意後見監督人への報酬も別途発生します。また、任意後見人は任意後見契約で定められた金額を受け取れ、管理財産額により報酬額は異なります。
成年後見制度を利用する際のデメリット
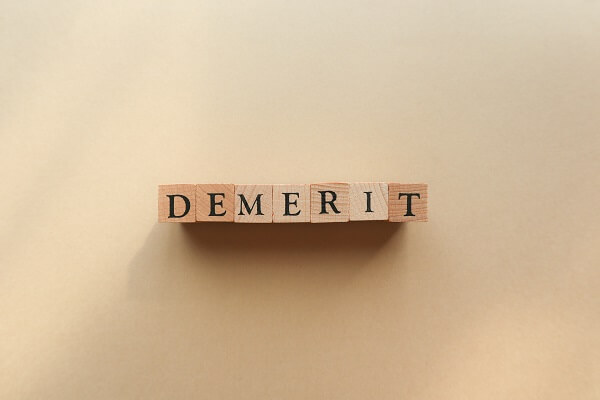
ここまで解説してきた成年後見制度は、ひどいといわれることも多いようです。どのようなことを原因としてひどいといわれるのか、成年後見制度のデメリットについて解説していきます。
- 家族でも本人の財産を管理できない
- 職務の負担が大きい
- 後見制度を途中でやめることは難しい
家族でも本人の財産を管理できない
後見を受けている本人(被後見人)のための財産保護が目的ですので、財産を親族のために活用することはできません。そのため後見人ではない家族が、いくら本人のためであっても資産運用で資産を増やすこともできません。このように、家族であっても何も手出しできないという状態から、後見制度はひどいといわれているようです。
職務の負担が大きい
家族が後見人になった場合、書類の準備や裁判所への報告など負担が大きいことも、ひどいといわれる理由のひとつです。まず、後見人は本人の資産をすべて把握し家庭裁判所へ提出する必要があります。さらに年に1回は裁判所へ定期報告をしなければならず、大きな負担になることが想像できます。
後見制度を途中でやめることは難しい
万が一、被後見人である本人の判断能力が回復した場合以外では、基本的に途中で後見人をやめることはできません。被後見人の財産管理や保護が目的であるため、いつでも簡単に辞任されるようでは適切な支援ができないと考えられるからです。
親の認知症リスクに備えよう!ファミトラの家族信託

前項で説明したように、成年後見人制度には2種類が「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。これらはいずれも本人の意思能力が喪失した後に効力が発生するのに対し、家族信託は契約締結と同時に効力が発生する点が異なります。
家族信託とは、本人の判断能力があるうちに家族へ資産を託すことです。本人の意思をより尊重でき、本人が納得のいく財産管理を指定することができます。
家族信託に興味がある場合は、1度家族信託のプロフェッショナルが揃う「ファミトラ」に無料相談してみてはいかがでしょうか。
ファミトラの家族信託は、家族信託組成のプロセスをITで効率化することで、手続きにかかる時間やコストの大幅削減に成功しました。まず、無料相談ができるのも嬉しいポイントです!
家族信託組成サービスも充実しており、相談から契約までしっかりサポートしてくれます。
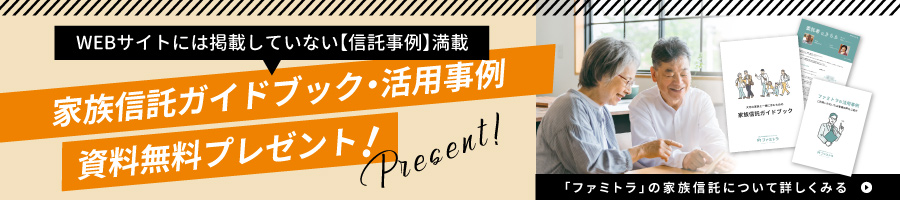
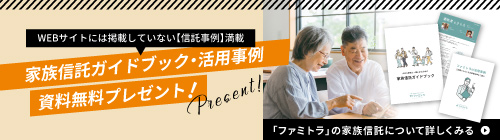
おわりに
成年後見制度は、本人の判断能力が不十分であるとされた場合に、代理で財産管理や保護をするために後見人を専任する制度です。後見制度には法定後見と任意後見があり、後見人には家族をはじめ誰でもなれます。本人が認知症などになってから検討するのでは、スムーズに財産管理や保護ができない場合もあるため、将来的にどうしたいかについてはなるべく本人の意思がはっきりしているうちに行いましょう。































