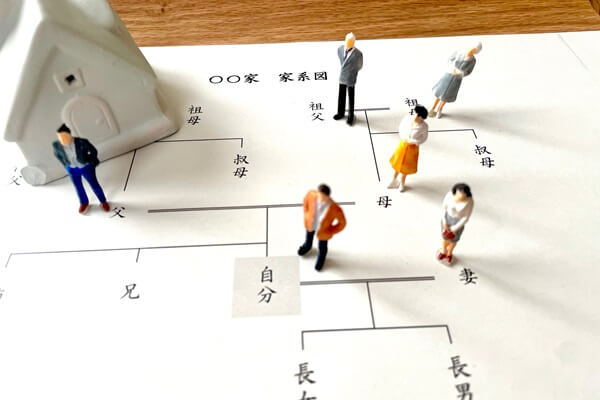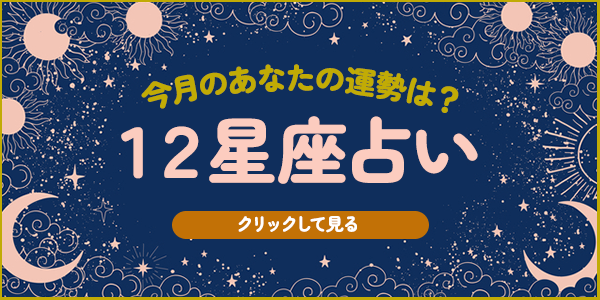「弔慰金って何?」「香典や死亡退職金となにが違うの?」「相続税の対象になるの?」といった弔慰金に関する疑問は意外と多いようです。原則的には「弔いと慰め」を意味するため非課税ですが、相当額を超える金額や複数から支給される場合には例外もあります。
このコラムでは、弔慰金についての基本情報とともに、例外として相続税の対象となる場合について、計算や申告方法、注意点や疑問点について解説していきましょう。
この記事を読んでわかること
- 弔慰金は、亡くなられた方を弔い、遺族を慰める気持ちを表すために渡すお金であり、社会通念上相当とされる金額であれば、原則として非課税であり相続税の対象とはならない
- 「社会通念上相当」の額を超えた部分については、例外的に死亡退職金とみなされ、相続税の対象となる
- 課税対象となる場合の基準ライン、相続財産とする金額の計算や申告の方法、また複数の企業から弔慰金を受け取った場合や注意点
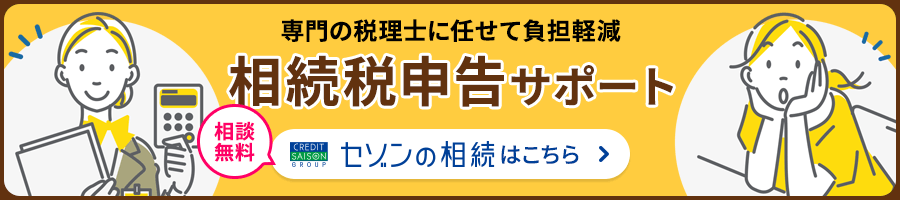

弔慰金に関する基本情報

会社員の方が亡くなると、勤め先から「弔慰金」が支給される場合があります。家族の死亡にともない受け取るお金は、香典や死亡退職金などさまざまです。家族を失った悲しみのなか、弔問客への応対や、自治体や関係機関への届出など、混乱しがちな日々ですが、まずは基本的なことを確認しておきましょう。
そもそも弔慰金とは
「弔慰金(ちょういきん)」は、亡くなった方を弔い、遺族を慰める気持ちを表すために渡すお金です。企業における弔慰金は、福利厚生として制度を導入している場合、従業員が亡くなった際に、遺族に対して支給するもの。
支給金額については、企業ごとの規定によりさまざまですが、社会通念上相当とされる金額であり、数万円から数十万円が相場のようです。
規定においては、職位により、また、業務外や業務中、通勤途上のアクシデント、出張先での被災など死亡事由に応じて支給額が定められているケースが一般的となります。
香典とは何が違う?
「香典」は、亡くなられた方に供えるお金です。昔は、香(線香)やお花を持参して供えましたが、時代とともに、現金を供えるように変化し、また、葬儀という突然の出費に対し「助け合う」という意味に変わりつつあります。
一般的に、受取人は、香典が喪主であることに対し、弔慰金は亡くなられた方の遺族である点が相違点です。また、香典は通夜もしくは葬儀会場の受付で手渡しますが、弔慰金は、多くの場合、葬儀が終わり、遺族の生活が落ち着いたタイミングで振り込まれます。
死亡退職金とは何が違う?
「死亡退職金」は、亡くなられた方が受け取るはずだった退職金のことです。もともと退職金には、企業として、これまで働いたことに対する感謝と労い、そして今後の生活に支障がないようにとの意味もあるため、弔慰金とは目的が異なります。
ただし、最近では、退職金規定のない企業も多く、必ずしも支給されるわけではありません。
弔慰金は相続税の課税対象?

弔慰金を受け取ったものの、収入として課税されるのかどうかが気になるところです。相続という人生においてもそう度々遭遇することのない手続きで、大きな金額が動くことから「相続税」について不安に思うことが多くあることでしょう。
弔慰金については、原則と例外がありますので、事例とともに解説していきます。
基本的に弔慰金は非課税
被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。ただし、弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は、相続税の対象です。
「所得税」や「贈与税」についても、弔慰金が「社会通念上相当と認められる」範囲、つまり、常識的に考えてあまりにも高額な金額などでなければ、非課税扱いになることとされています。
参照:国税庁「No.4120 弔慰金を受け取った時の取扱い」
課税対象になる場合の基準ライン
例外として、弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、社会通念上相当と認められる額を超えて受け取った場合を考えてみましょう。
受け取った金額は、非課税枠(限度額)を基準として課税か非課税が判断されます。また、限度額は、「業務上」での死亡か、「業務外」での死亡かで基準ラインが異なるのです。
業務上での死亡
被相続人が、業務上の死亡であった場合の非課税限度額は、給与月額×36ヵ月で計算します。
給与月額35万円であった場合、弔慰金500万円が課税か非課税かの判断は、算出式から
35万円(給与月額)×36ヵ月=1,260万円となり、
非課税限度額1,260万円に収まっているので相続税はかかりません。
業務外での死亡
被相続人が、業務外の死亡であった場合の非課税限度額は、給与月額×6ヵ月で計算します。
給与月額が35万円であった場合、弔慰金500万円が課税か非課税かの判断は、算出式から
35万円(給与月額)×6ヵ月=210万円となり、
非課税限度額210万円に対して290万円が超過しているため、290万円は「みなし相続財産」として相続税の対象です。
ただし、死亡退職金にも非課税枠があります。非課税枠は、死亡保険金とは別枠で「500万円×法定相続人の数」です。ひとりでも相続人がいれば、マイナス210万円となり相続税はかかりません。
弔慰金と死亡退職金の両方を受け取った場合
弔慰金と死亡退職金の両方を受け取った場合には、少し複雑になります。
給与月額35万円、法定相続人2人であった方が業務上で死亡、
弔慰金1,500万円、死亡退職金2,000万円の両方を受け取った場合で考えてみましょう。
- まず、弔慰金の非課税限度額を計算します。
35万円×36ヵ月=1,260万円まで非課税 - 非課税限度額の超過部分は、
1,500万円-1,260万円=240万円 - 死亡退職金の非課税枠は、
500万円×2人(法定相続人の数)=1,000万円 - 死亡退職金の相続税対象額は、
2,000万円-1,000万円=1,000万円 - 相続税対象額の合計は、
240万円+1,000万円=1,240万円
弔慰金の限度額計算に用いる普通給与の額
上記の算式での給与月額とは、支給される給与のうち何が含まれるのか疑問に思う方も多いでしょう。
国税庁ホームページによれば、業務上の場合には、死亡当時の「普通給与」の3年分に相当、業務外の場合には、死亡当時の「普通給与」の半年分に相当すると記載されており、また、「普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。」と明記されています。
つまり、「基本給」だけではなく、諸手当も含めた支給額が普通給与なのです。ただし、給与とは別に賞与が支給される場合、賞与の額は普通給与には含まれません。
参照:国税庁「No.4120 弔慰金を受け取った時の取扱い」
弔慰金が相続税の課税対象となる場合の申告方法

では、弔慰金で受け取った額が非課税枠を超え、相続税の対象となる場合には、どのように申告すれば良いのでしょうか。具体的には、相続税申告書第10表「退職手当金などの明細書」に必要事項を記載します。
相続税申告書「退職手当金などの明細書」に記入
相続税申告書第10表「退職手当金などの明細書」は、上下の2部構成になっており、上部には「1.相続や遺贈によって取得した者とみなされる退職手当金など」、下部には「2.課税される金額の計算」を記載します。
上部「1.相続や遺贈によって取得した者とみなされる退職手当金など」の項目を見ると、ここでの受取金額は、弔慰金については、非課税限度額を超えた部分の金額のみ記入します。
- 勤務先会社等の所在地
- 勤務先会社等の名称
- 受取年月日
- 退職手当金などの名称(「弔慰金」「死亡退職金」など)
- 受取金額
- 受取人の氏名
一方で、死亡退職金については、実際に受け取った金額をそのまま記入します。
下部「2.課税される金額の計算」では、
「法定相続人の数」は、相続人が1名であれば、右A欄は「5」百万円、2名であれば、「10」百万円と記入します。下部では、受取人別の課税金額を記入するため、弔慰金と死亡退職金の受取人が同じであれば合算。課税金額は、限度額を超えた「弔慰金」と死亡退職金の非課税枠を差し引いた「死亡退職金」の金額です。
前述の事例であれば、①受け取った退職手当金などの金額2,240万円、②非課税金額1,000万円、③課税金額1,240万円となります。
参考:国税庁 相続税申告書第10表「退職手当金などの明細書(平成21年4月分以降用)」
相続税の申告期間は?
「相続税の申告」は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納付しなければなりません。
被相続人のすべての財産を、誰がどのように引き継ぐのか、相続税額をどう支払うのかについて記載し、遺言書もしくは遺産分割協議書など必要書類とともに被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。遺産分割協議による分割の場合には、すべての相続人が署名する必要がありますので、時間的余裕をもって準備をしたいものです。
誤りのないよう書類を作成するためには、費用はかかりますが、相続専門の税理士への依頼をおすすめします。
弔慰金は受け取り先の違いで計算方法が変わる

弔慰金は、亡くなられた方の勤務先から支給されることが一般的ですが、最近では、複数の勤務先に所属される方も増えてきており、複数の弔慰金が支給のほか、さまざまなパターンも想定されます。また、被災による死亡の場合、公的な弔慰金を受け取るケースもありますので、あわせて確認しておきましょう。
複数の会社から弔慰金を受け取った場合
亡くなられた方が、X社とY社の2つの勤務先に所属しており、それぞれ弔慰金を受け取った場合には、それぞれの勤務先ごとに普通給与の額をもとに非課税限度額の計算を行います。
それぞれの会社ごとに限度額を超えた金額は、死亡退職金として、相続税の課税対象です。
以前勤務していた会社から弔慰金を受け取った場合
X社を退職後、Y社へ再就職。再就職先での在職中に死亡した場合に、Y社だけでなく、以前勤めていたX社からも弔慰金を受け取った場合には、勤務先でないX社からの弔慰金は、退職金として認められず、相続人(受取人)の一時所得扱いとなります。
一方で、勤務先であるY社からの弔慰金が非課税限度額を超えた部分について、みなし相続財産として相続税の対象です。
国や地方自治体などから弔慰金を受け取った場合
弔慰金には、自然災害によって亡くなった場合などでは、国や地方自治体から遺族に対して災害弔慰金などが支払われることがあります。
代表的なものとして、以下が挙げられます。
- 災害弔慰金
- 国会議員が死去した場合の弔慰金
- 戦没者遺族への弔慰金・特別弔慰金
- 国籍離脱者となった戦没者遺族への弔慰金
- 国外犯罪被害弔慰金
こうした公的な弔慰金は、原則として、金額に関わらず非課税扱いです。
弔慰金に関する注意点や疑問点

弔慰金は、原則として、弔意を表す金銭であるため、相続財産に該当せず非課税ですが、例外的に課税されるケースについてお伝えしてきました。さらに、弔慰金に関する注意点や疑問点について、確認しておきましょう。
弔慰金や死亡退職金を利用した事業承継・相続対策には注意
実際のところ、社会通念上相当とされる「弔慰金」を受け取るケースが大半です。ただし、退職金規定のない企業も増えていることから、弔慰金の名目で、死亡退職金の意味合いが強いお金を受け取るケースも見られます。こうした場合の税務の取扱いには注意が必要です。
会社員の場合には、勤め先企業の規定にもよりますが、会社経営者や役員が弔慰金や死亡退職金の金額の設定を決められるケースもあり、非課税枠を活用した事業承継や相続税対策として規定に盛り込むケースもみられます。
いずれにしても、高額な弔慰金を受け取る場合や、死亡退職金と両方が支給される場合には、相続税の申告の時点で否定されることもあり得ますので、対策をしたつもりが、遺族に迷惑をかけることにもなりかねません。検討にあたっては、相続に詳しい税理士に相談、確認することをおすすめします。
「セゾンの相続 相続税申告サポート」では、経験豊富な提携専門家のご紹介も可能です。不安な方は一度相談してみてはいかがでしょうか。
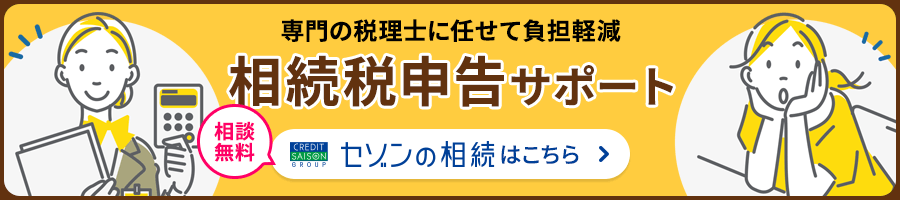

弔慰金はいつ支給される?
弔慰金は、お勤め先企業の配慮もあり、葬儀が終わり、少し落ち着いたころに支給されることが一般的です。
弔慰金は誰のもの?
基本的には、香典と同じく喪主が受け取ります。ただし、死亡退職金の意味合いが含まれると、相続財産として扱われるため、相続人の共有財産となり、遺産分割の対象になり得るのです。
弔慰金の受け取りに申請は必要?
基本的には申請は不要です。ただし、公的な弔慰金の場合には申請が必要となります。
また、企業によっては、受取人の氏名、振込先を確認する必要があるため、書類の返送が必要な場合もありますので、確認が必要です。
おわりに
弔慰金は、亡くなられた方を弔い、遺族を慰める気持ちを表すために渡すお金です。社会通念上相当とされる金額であれば、非課税であるため、相続税を気にする必要はありません。ただし、「社会通念上相当」という抽象的な表現であるため、悩まれる方も多いようです。
また、退職金規定のない企業も増え、さらに、最近の働き方の変化により「弔慰金」の意味合いも変化しつつあります。相続税の対象となり得るかどうかの基準、さらに業務上か常務外かについても参考にしつつ、相続手続きを進めていきたいものです。
いずれにしても、思い込みや短絡的な判断をせず、迷った時には、税理士などの専門家への相談をおすすめします。