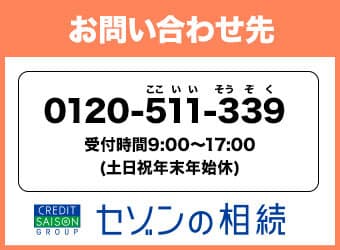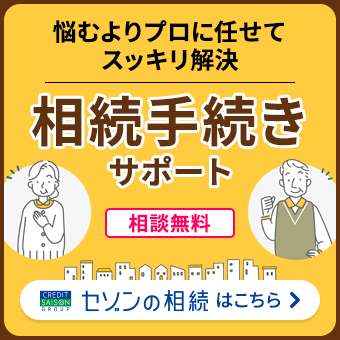相続登記の手続きを進める中で、亡くなった方の登記簿上の住所が実際に住んでいた住所と違うことに初めて気づく方は少なくありません。この場合、亡くなった方が所有者と同一人物であることを証明しないと相続手続きは進められません。この記事では、相続登記で住所がつながらない場合の対応策について解説します。
- 相続登記で住所がつながらない場合、住民票の除票や戸籍の附票で過去の住所が証明できる。
- 2014年以前の住民票の除票や戸籍の附票は保存されていないことがある。
- 相続人全員の署名・実印による上申書で、被相続人と所有者の同一性が認められることがある。
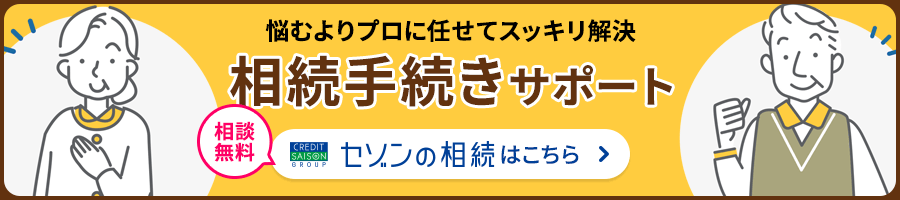

相続登記で「住所がつながらない」とはどういうこと?

相続登記の手続きを進めていて、住所がつながらないケースがあります。住所がつながらないとは、被相続人(亡くなった方)が実際に住んでいた住所(通常は住民票の住所)と登記簿上の住所が違う状況のことを指します。
相続登記では、被相続人の住民票の住所・氏名と登記簿に記載された住所・氏名が一致すれば、同一人物として手続きを進められます。しかし、住所が違う場合は、同一人物であることを証明しなければなりません。
戸籍謄本には本名、氏名、生年月日しか記載されていないので、住所の変更を証する書面として、住民票除票や戸籍の附票などを提出して、登記簿上の人物と被相続人の同一性を証明します。
ただし、相続人への名義変更登記で、被相続人の登記簿上の住所が、死亡時の住所と異なっていても、わざわざ被相続人の住所変更登記を行う必要はありません。
相続登記の重要性と義務化

相続登記は、2024年4月1日から申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされています。また、遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由がなく、この義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象になりますから、手続きを後回しにしないよう手続きを進めてください。
相続登記で住所をつなげるための方法

被相続人が実際に住んでいた住所と登記簿上の住所が異なっていた場合、どうやって登記上の人物が被相続人と同一人物であることを証明すればいいのかを説明します。
基本的な証明方法から、各種書類が取得できない場合の最終手段まで、段階を追って紹介していきましょう。
基本的な確認書類
相続登記で住所をつなげるためには、住民票の除票や戸籍の附票によって登記簿上の住所に住んでいたことを証明するのが基本的な方法です。
住民票の除票
死亡により住民登録が削除された住民票が「住民票の除票」です。死亡時の住所を証明する書類になりますから、まずは、住民票の除票を確認します。ここには、被相続人の住所、氏名が記載されています。登記簿上の住所と一致すれば、スムーズに相続登記の手続きが行えます。
また、住民票の除票には前住所も記載されているので、これが登記簿上の住所と一致した場合でも相続登記の手続きが行えます。
戸籍の附票
戸籍の附票とは、本籍地の置かれている市町村に備えられている住所の情報です。住所地の変遷がすべて記載されているので、住民票の除票でつなげられなかった過去の住所が、つなげられる可能性があります。前の住所よりもさらに前の住所を証明する書類として有効に活用できます。
補足的な証明方法
住民票の除票で同一性が証明できなかったり、戸籍の附票が取得できなかったりした場合は、次の書類によって同一性を証明することができます。
不在住証明書・不在籍証明書
戸籍の附票が取得できない場合に、同一性を証明するものが「不在住証明書・不在籍証明書」です。
被相続人が、かつて登記簿上の住所に住んでいたこと、そして現在、その住所・本籍にその人物が実在しないことを市町村が証明してくれるものです。2023年12月18日付法務省民二第1620号の通達により、住所がつながらない場合に、この書類を提出することによって、相続登記ができるものとして認められました。
固定資産税の納税証明書・評価証明書
固定資産税の納税証明書・評価証明書を提出することで、相続登記を進めることができます。
固定資産税納税証明書または評価証明書には、相続登記を申請する不動産の所在、地番、家族番号等の登記簿に記載されている不動産の表示(所在、地番、家族番号等)のほか、納税義務者の住所及び氏名が記載されています。
こちらも上記の第1620号の通達通達によって、本人確認ができる書類として認められました。
登記済証(登記識別情報通知)
不在住証明書・不在籍証明書、固定資産税の納税証明書・評価証明書でも同一人物であることが証明できない場合の方法として、登記済証(登記識別情報通知)を提出する方法も有効です。
登記済証とは、不動産について所有権移転登記をしたときに法務局から発行される書類です。一般的には権利証と呼ばれています。登記時に所有者本人に対して交付され、いかなる理由があっても再発行がされないので、本人であることを証明できます。
なお、2017年3月23日法務省民二第174号の通達により、所有権に関する被相続⼈名義の登記済証の提供があれば、不在籍証明書及び不在住証明書は不要であるとされています。
最終手段
同一人物であることを証明する書類等がどうしても取得できないケースでは、最終手段として上申書を提出する方法があります。
相続人全員の上申書
住民票等で住所がつながらず登記済証も紛失してしまっている場合には相続人全員の上申書を提出するという方法を用います。
「登記簿上の所有者が自分の被相続人に相違ない」ことを相続人全員が法務局に対して申告するもので、本書類に相続人全員の署名と実印を押して添付します。
相続登記に関する注意点

相続登記で、被相続人の住所がつながらない場合、住民票の除票や戸籍の附票によって、登記上の所有者と同一人であることを証明します。また、証明する書類が何もない場合は、相続人全員による上申書を提出することになります。
これらの提出書類の注意点を紹介していきましょう。
住民票の除票・戸籍の附票のデータが消去されていることもある
現在、住民票の除票や戸籍の附票の保存期間は150年ですが、2019年6月20日の住民基本台帳法改正以前は5年とされていました。
そのため2014年の時点で亡くなってから5年以上経過している場合は、データを取得できない可能性があります。
相続人全員の上申書の書き方
住民票等で住所がつながらず登記済証も紛失してしまっている場合には不在籍証明書、不在住証明書、固定資産税の課税明細書、登記済証(登記識別情報通知)を提出することで、相続登記を進めることができます。
これらの書類もすべて入手できない場合は、相続人全員の上申書を提出するという方法を用います。上申書は、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
上申書はひな形を参考に作成してください。
【上申書 ひな形】
上 申 書
被相続人 見本例壱
(令和 6年9月15日死亡)
最後の本籍 東京都渋谷区宇田川町○○−○○
最後の住所 東京都中野区中野4丁目○○−○○
登記簿上の住所 千葉県千葉市中央区千葉港○○−○○
今般、被相続人名義の下記不動産について相続を原因とする所有権移転登記を申請しますが、同人の登記簿上の住所から最後の住所への変遷を証する書面が保存期間経過により廃棄されたため添付することができません。
しかしながら、登記簿上の所有権登記名義人見本例壱は、被相続人である見本例壱本人に間違いありません。
また、今後いかなる紛争も生じないことを確約し、決して御庁にはご迷惑をおかけいたしません。
つきましては、本件登記申請を受理して頂きたく、ここに上申いたします。
不動産の表示
所 在 千葉県千葉市中央区千葉港
地 番 ○○番地○○
地 目 宅地
地 積 250㎡
相続人
住所 東京都田谷区世田谷4丁目○○−○○
氏名 見本例次 (実印)
住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目○−○
氏名 雛形様子 (実印)
相続登記で住所がつながらないときはセゾンの「相続手続きサポート」へ

相続登記の手続きを進めていて、被相続人が実際に住んでいた住所と登記簿上の住所が違うことに初めて気づくことがあります。その場合、登記されている名義人と亡くなった方が同一人物であることを証明しないと、相続登記の手続きは進みません。
住所がつながらないときは司法書士などへの専門家への相談が解決への近道です。セゾンの相続では、相続登記を得意とする司法書士と提携しているため、信頼できる専門家から適切な解決に導いてくれます。無料相談から開始できますのでお気軽にご利用ください。相続全般にわたるサポートも展開していますので、遺産分割や相続手続きに関する悩みや疑問もご相談ください。
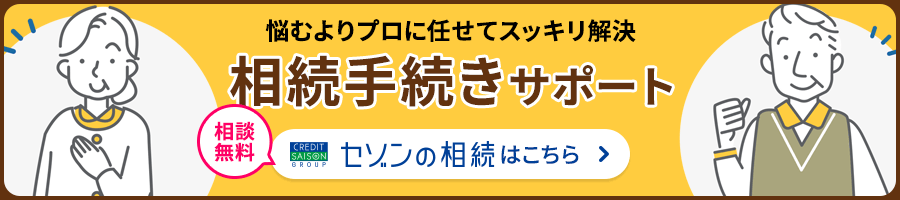

おわりに
相続登記の手続きで、住所がつながらないとは、被相続人が実際に住んでいた住所と登記簿上の住所が違う状況のことをいいます。この住所が一致しないと相続登記は行えません。
相続登記で住所をつなげるには、基本的に住民票の除票や戸籍の附票によって登記簿上の住所に住んでいたことを証明します。しかし、2014年以前のものは、保存期間が5年だったため、管轄の市区町村に保存されていないことがあります。
その場合、不在住証明書・不在籍証明書や固定資産税の納税証明書、登記済証を提出することで証明が認められます。これらの書類が何もない場合は、相続人全員による上申書を提出します。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。