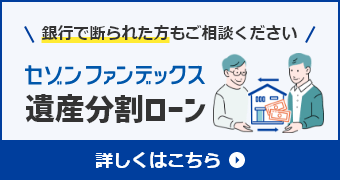実家などの不動産を共有名義で相続することはよくあるケースです。共有名義での相続は、遺産として不動産を取得できたり相続税を抑えられたりする点がメリットです。一方で、後々トラブルの原因となることも珍しくありません
そのため、できれば共有名義での相続を避けるか、早期解消を目指すのが望ましいでしょう。この記事では、共有名義での相続がなぜトラブルの原因となるのか、その理由と解決方法を解説します。
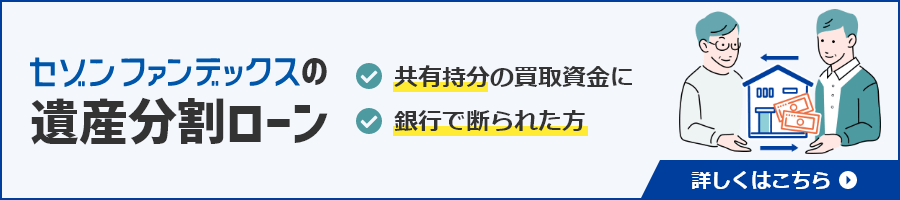
不動産を共有名義で相続する主な理由

実家をはじめとする不動産が共有名義での相続となる理由は、主に次の2つです。
- 相続財産が不動産しかなかったり、不動産が大半を占めていたりするから
- 遺産分割協議を早く終わらせたいから
不動産は現金とは異なり、金額をきれいに均等に分けられません。売却して現金化して分けるとしても、時間がかかります。そのため、相続人同士で形式上均等に財産を分けようとして、共有名義とするのです。
また、遺産分割協議に手間をかけたくないという理由もあるでしょう。相続人同士が離れて住んでいる、スケジュールを合わせられないといった状況下では、相続完了までに多くの時間を費やしてしまいます。そこで、不動産を共有名義にしてしまえば、各相続人が引き継ぐ財産は形式上きれいに分かれるため、大きな揉め事には発展しにくいのです。協議を早期に終わらせるために、仕方なく共有名義で不動産を所有することにしているケースもあります。
不動産を共有名義で相続するメリット・デメリットとは

共有名義での不動産相続には、メリットだけでなくデメリットも存在します。どのようなメリット・デメリットがあるのかをおさえて、相続の名義を今後どうしていくか決めましょう。
共有名義で相続するメリット
共有名義で不動産を相続するメリットは、以下の2点です。
- 遺産を法定相続分に従って分けられる
- 相続税の節税につながる
不動産を半分ずつ、あるいは4分の1ずつといった形で所有すれば、法定相続分どおりに遺産を分けられるため、各相続人が遺産額について大きく不満を持ちにくくなります。結果として、余計な揉め事もなくなるでしょう。
また、共有名義で相続すれば、単独で不動産を相続するよりも、ひとりあたりの相続税を抑えられます。相続税は相続税評価額に基づいて算出され、土地の相続税評価額では「路線価×奥行価格補正率×面積」の計算式を使う形式が多いです。面積が半分なら評価額も半分になるため、個々人の相続税負担が軽減されます。
建物の相続税評価額も固定資産税評価額が基準となるため、持分に応じて分割されます。ひとりあたりの相続税評価額が下がるため、相続税が抑えられるのです。
ただし、あくまでひとりあたりの負担が減るだけであり、相続税の総額が下がるわけではありません。また、不動産のうち何割を共有するかに応じて評価額は分かれるうえ、相続税は累進課税であることからも、節税効果は限定的といえるでしょう。
共有名義で相続するデメリット
共有名義で不動産を相続するデメリットは、以下の2点です。
- 不動産の売却がしにくくなる
- 固定資産税の負担で揉める可能性がある
不動産を売却する際は、共有者全員の同意が必要です。共有者のうち誰かが「まだ住み続けたい」「他の方には売りたくない」と反対すれば売却できず、売り時を逃してしまったり、維持費ばかりかかったりしてしまうでしょう。
また、固定資産税の負担割合でも揉める可能性があります。固定資産税納税通知書は「代表者 外◯名」などのように代表者宛に送られてくることが多いため、代表者に負担が偏りやすいのです。加えて、共有名義物件の固定資産税は誰がどのように支払うか法律で厳密に決まっておらず、負担を押しつけ合うような展開になりかねません。
トラブルを避けるためには、共有者同士で事前に支払方法を取り決めておくことが大切です。隔年で交互に支払ったり、一方は納税、もう一方は管理費を支払うようにしたりと、共有者同士が納得して納税できるルールをつくっておきましょう。
共有名義での相続はやめたほうがよいのか

共有名義での相続にはさまざまなリスクがあるため、できれば避けるほうが無難でしょう。
主な理由は、売却や増改築など将来的に思うような行動をとりづらくなるからです。前述のとおり、共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。誰かが売却に反対した場合、維持管理費を支払いつづけるはめになるかもしれません。
もうひとつの理由は、再度不動産を相続する際に遺族が迷惑する可能性があるためです。共有者のひとりが亡くなって新たな相続が発生すると、共有人数が増えてしまい管理がさらに複雑になるケースがあります。こうした状態が続くと、誰がどのように不動産を管理しているかが不明瞭になり、遺族間で揉めやすくなってしまいます。
特に「遺産分割協議を早く終わらせたいから」といった理由で安易に共有名義にすると、将来大きく後悔するかもしれません。今後のことを見据えて、共有名義を解消すべきかどうか判断することが望ましいでしょう。
共有名義がトラブルになるケース

共有名義で不動産を相続すると、法律関係の複雑化や共有者同士での話し合いがうまくいかず、いろいろなトラブルが想定されます。法律関係のト争いは司法書士など専門家の助力によって解決しやすい部分もありますが、感情的な対立は長期化することも少なくありません。
どのケースでも、結果的に相続完了までの期間が延びる可能性もあります。想定されるトラブルを事前に把握しておき、未然に防げるようにしましょう。共有者同士で意見がまとまらない
共有者のうち誰か1人でも「売却したい」「家を取り壊して駐車場にしたい」と考えても、ほかの共有者が反対すれば実行できません。売却や取り壊しといった行為は民法上、「共有物に変更を加える行為」にあたり、共有者全員の同意が必要だからです。つまり、共有者のうちの誰か1人や、一部の方たちだけでは、勝手に実家を売却したり取り壊せないのです。
なお、自分の持分のみを売却するのであれば、全員の同意がなくても売却手続きは可能です。ただし「一部分を自分で持ち、一部分を所有者から借りる」といった複雑な所有形態となるため、需要は高くありません。仮に見つかったとしても通常よりも安い価格になるケースが多いでしょう。
維持管理の負担が特定の共有者に偏る
共有名義の不動産は、場所や所得、家族構成などの事情により、維持管理の手間を負担できる人に偏る傾向があります。建物であれば定期的な換気や、経年劣化する内外装・設備等の修繕、土地であれば草刈りは努力義務となっています。維持管理を適切に続けなければ、どんどん劣化していきます。
しかし、共有者にもさまざまな事情があるでしょう。「お金がない」「住んでいる場所から遠い」「仕事が忙しい」などの理由があれば、共同での不動産の維持管理は疎かになります。
結果的に管理負担が大きい共有者とそうでない人との間で不満が高まり、深刻なトラブルに発展する可能性があるのです。
不動産を放置してしまう
「売却できなかった」「維持管理が面倒に感じてきた」といった理由で、不動産自体を放置してしまうおそれもあります。草が伸び放題で近隣に迷惑がかかったり、建物の老朽化が進むと取り壊す際の費用が大きくなるため再利用も難しくなるでしょう。さらに相続人が管理しないまま亡くなれば、その土地・建物が“所有者不明”となり取り扱いがさらに複雑化します。
相続のたびに権利関係が複雑になる
共有不動産は、相続を繰り返すたびに共有者の数が増えたり、当初の共有者ではない方が権利を得たりして、管理や協議が難しくなることが考えられます。例えば元は兄弟3人共有で相続したとします。当初は問題なく共有状態を維持できるでしょう。しかし、兄弟のうちAが亡くなりAの子(兄弟からみた甥や姪)2人が相続した場合、共有者は1人増え権利関係が複雑になります。これまで兄弟3人であれば円滑にできていた話し合いや維持管理も、年齢や考え方、経済力が異なる甥姪が入るとこれまで発生しなかった摩擦が生じやすくなります。
あまり面識のない人と不動産を共有する可能性がある
共有名義で相続した方が亡くなった場合、その遺族が財産を引き継ぎます。結果として、面識の薄い親族と不動産を共有しなければならなくなるケースもあります。面識のない方と不動産を共有すれば、不動産の取り扱い方や維持管理の仕方で意見が合わず、揉める可能性が考えられるでしょう。
また、共有者が自己破産や債務整理の対象となった場合、持分が債権者や管財人に移り、まったく関係のない第三者と共有することになる場合もあります。そのような状況だと、不動産の売却や増改築を考えていたとしても、債権者や管財人から反対されて思うように進まないかもしれません。
共有名義を解消する解決策

共有名義で相続した実家の共有状態を解消するには、以下の4つの方法があります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有物分割請求
遺産分割協議は一度正式に完了した場合でも、相続人全員の同意があれば再度やり直せます。共有名義で相続すると協議で決定したあとでも、あらためて話し合いができるため、共有状態での所有を解消できる可能性があるのです。
共有名義の解消方法をおさえて、不動産相続をスムーズに完了しましょう。
現物分割
現物分割とは、特定の相続人ごとに財産を分ける遺産分割の方法です。例えば「実家の建物と土地は兄が取得し、預貯金は弟が引き継ぐ」といった形で分割します。シンプルで手続きが少なく、共有名義となった不動産の共有状態を解消しやすい点が特徴です。相続実務においても多く用いられています。
一方、不動産以外に財産がなかったり、相続財産の価格に大きな差がある場合は、適しません。
例えば、実家しか相続財産がなく、実家のほかは僅かな現金や車などしかないというようなケースでは、なかなか相続人全員の納得を得られないため、他の方法で解決する必要があります。
代償分割
代償分割は、相続人のうち1人が実家を現物取得して、ほかの相続人に対して持分相当額の金銭を支払う方法です。すでにその実家に住んでいて、これからも暮らし続けたい相続人がいる場合よく用いられます。ただし、代償金や維持管理費用を負担する相続人には相応の経済力が求められるでしょう。ローンの利用や、相続人同士でお金の貸し借りを行うケースもあります。
換価分割
換価分割は、不動産を含む遺産をすべて売却してお金に換え、そのお金を相続人で分配する方法です。不動産を手放せるため、後々の維持管理の手間を考えずに済みます。現金化しやすい点で、相続人同士で公平に財産を分けやすいこともメリットです。
ただし、不動産が売却できなければいつまでも解決できないリスクがあります。売却を待つ間は固定資産税や維持管理費がかかるため、可能な限り早期売却できるよう、不動産会社に積極的に相談するとよいでしょう。
共有物分割請求
共有物分割請求とは、共有者全員で合意できない場合に、共有者の一方または一部が裁判所に申し立てて、法的手続きで共有物を分割する方法です。判決には法的拘束力があるため、最終的に共有状態は解消されますが、手続きに時間がかかり費用も高額(50~150万円程度)になるのが難点です。できるだけ話し合いで解決を図り、それでも合意できないときの最終手段といえるでしょう。
相続人が住んでいる不動産なら代償分割がおすすめ

共有名義で相続する際、相続人のうち1人が実家に既に住んでおり、これからも住み続ける場合には、代償分割が最もスムーズな方法になりやすいです。居住者はそのままマイホームを確保できますし、ほかの相続人は自由度の高い現金で遺産を受け取れます。
代償分割を実行するときは、ほかの相続人に支払う代償金が用意できるか気になる方もいるでしょう。代償分割で支払う金銭は、住宅ローンを利用して確保できます。そのため、手持ちの現金に不安があっても代償分割ができる可能性があります。
代償分割において住宅ローンが利用できる理由は、代償分割がマイホームを取得するための住宅の売買と実質的に同じとみなされるからです。「一度遺産分割にて相続人全員で不動産を共有名義で相続し、その後他の相続人から不動産の持分を買い取る」という行為は、自分が住宅を購入することと変わらないため、住宅ローンが使えます。
ただし、代償分割は親族間の売買となるため、不動産会社から物件を購入したときに比べてローンの審査が厳しくなる傾向にあります。審査落ちしてしまうと代償金の支払手段がなくなってしまい、代償分割できなくなる可能性があります。共有名義で相続した実家の代償分割を行う際、代償金の準備が難しい場合は、親族間売買に対応したローンの利用を検討するとよいでしょう。親族間売買のローンを取り扱う金融機関はいくつか存在するため、それぞれの条件やサービス内容を比較し、自分に最適な商品を選ぶことが重要です。
一例としてセゾンファンデックスの「遺産分割ローン」であれば、親族間売買に対応しているだけでなく、相続で取得する築年数の古い物件にも柔軟に対応している点が特徴です。また、銀行やフラット35でのローン審査が否決された場合でも申し込みが可能なため、代償金の確保に悩む方にとって有力な選択肢となるでしょう。
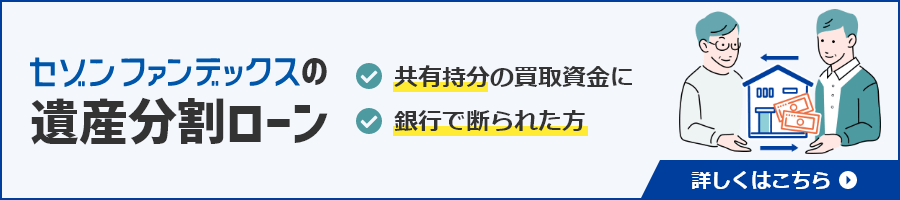
おわりに
共有名義で実家を相続すると、相続人同士の意見対立や法律関係の複雑化など、さまざまなトラブルが生じやすくなります。こうしたトラブルは長期化すれば親族同士の関係が悪化するリスクも高まります。
そのため、共有名義の不動産を相続した場合は、早めに共有状態の解消を検討することをおすすめします。必要に応じて弁護士・税理士に相談し、専門家の助言を仰ぎながら進めるとよいでしょう。もし実家を手放さずに共有を解消したいなら、代償分割がおすすめです。
親族間売買に対応した住宅ローンを活用すれば、実家を手放さずに共有を解消できる可能性が高まります。たとえば、セゾンファンデックスの「遺産分割ローン」は、親族間売買に対応しているため、代償分割を進める際の選択肢となるでしょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。