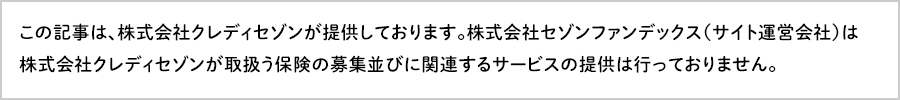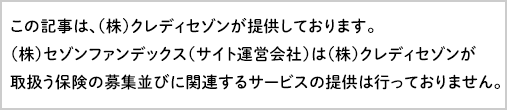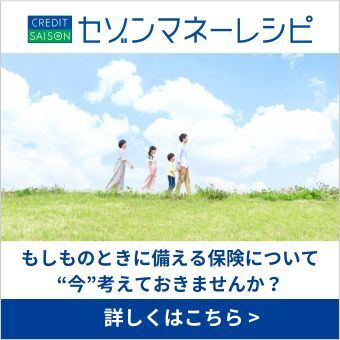厚生労働省が実施した令和4年の統計調査では、平均入院日数は27.3日で、30日を下回っています。また、過去のデータから、徐々に平均入院日数が短くなっている実態もわかりました。一方で、公益財団法人生命保険文化センターの調査によると入院1日あたりの自己負担額は平均2.7万円で2万円を超えています。多くの方にとって入院時の金銭的な負担は大きな問題ともいえるでしょう。
このコラムでは年代別・病気別の平均入院日数や入院時の自己負担額、入院による金銭面でのリスクについて解説します。

入院日数の平均は30日を下回る

入院日数の平均は、厚生労働省が実施した統計調査「令和4年(2022)年医療施設(動態)調査・病院報告」によると、2022年の平均入院日数は27.3日でした。これは、前年と比較して0.2日短い結果となっています。
【年代別】入院日数の平均
年代によって入院日数が大きく異なる点も理解しておきましょう。厚生労働省が実施した「令和2年(2020年)患者調査の概況」の結果によると、各年代の平均入院日数は以下のとおりです。
| 年代 | 平均入院日数 |
|---|---|
| 0〜14歳 | 8.9日 |
| 15〜34歳 | 12.2日 |
| 35〜64歳 | 24.4日 |
| 65歳以上 | 40.3日 |
| 70歳以上 | 41.7日 |
| 75歳以上 | 45日 |
15〜34歳の平均入院日数と75歳以上の平均入院日数で1ヵ月以上も差があることがわかります。また、このデータから年代が上がるにつれて入院日数の平均は長くなる傾向があることも確認できます。
【病気別】入院日数の平均
平均入院日数は病気の種類によっても大きく異なります。厚生労働省が実施した「令和2年(2020年)患者調査の概況」では、病気別の平均入院日数は、以下のとおりです。
| 病気の種類 | 平均入院日数 |
|---|---|
| 結核 | 59.5日 |
| ウイルス性肝炎 | 13.8日 |
| がん(全体) | 19.6日 |
| 糖尿病 | 30.6日 |
| 統合失調症 | 570.6日 |
| アルツハイマー病 | 273日 |
| 高血圧性疾患 | 47.6日 |
| 心疾患 | 24.6日 |
| 脳血管疾患 | 77.4日 |
| 肺炎 | 38日 |
| 肝疾患 | 23.4日 |
| 慢性腎臓病 | 53.4日 |
| 骨折 | 38.5日 |
上記のデータから、統合失調症やアルツハイマー病などの精神系および神経系の病気は、入院が100日以上と長引く傾向があります。
【病床別】入院日数の平均
厚生労働省が実施した「令和2年(2020年)患者調査の概況」によると、最も入院日数の長い病床は307.8日の介護療養病床で、最も短い病床は10.5日の感染症病床でした。各病床ごとの平均入院日数については以下の表をご覧ください。
| 病床の種類 | 平均入院日数 |
|---|---|
| 前病床 | 27.3日 |
| 精神病症 | 276.7日 |
| 感染症病床 | 10.5日 |
| 結核病床 | 44.5日 |
| 療養病床 | 126.5日 |
| 一般病床 | 16.2日 |
| 介護療養病床 | 307.8日 |
病床ごとの入院日数については、精神病症、療養病床、介護療養病床の3つと、それ以外の病床との入院日数の差は大きい傾向にあります。入院する病床によっても入院期間が大きく変わるため注意しましょう。
平均入院日数は徐々に短くなっている

厚生労働省の資料「令和2年(2020)患者調査(確定数)の概況」によると、1990年から2017年まで入院日数が縮小し続けていたものの、2020年は増加に転じたことがわかります。この資料をもとに作成した表は以下のとおりです。
| 年代 | 平均入院日数 |
|---|---|
| 1987年 | 44日 |
| 1990年 | 44.9日 |
| 1993年 | 41.9日 |
| 1996年 | 40.8日 |
| 1999年 | 39.3日 |
| 2002年 | 37.9日 |
| 2005年 | 37.5日 |
| 2008年 | 35.6日 |
| 2011年 | 32.8日 |
| 2014年 | 31.9日 |
| 2017年 | 29.3日 |
| 2020年 | 32.3日 |
参照元:厚生労働省 令和2年(2020)患者調査(確定数)の概況
1987年から2022年までの33年間で、平均入院日数が11.7日も短くなりました。入院日数が短くなっている背景にはさまざまな要因が考えられます。
2020年に平均入院日数が増加した理由
厚生労働省の資料「令和2年(2020年)患者調査の概況」によると、1987年以降、短縮化が続いた平均入院日数が、2020年に増加に転じました。その理由には、新型コロナウイルスの流行が大きく影響しています。
2020年は新型コロナウイルスが全国的に蔓延した年です。感染者の増加に伴いq、短期入院で治療できる軽度な患者が受診を控えたり、手術予定だった患者の手術日を延期したり、多くの病院が通常と異なる対応を求められました。例えば、新型コロナウイルスが蔓延している時期は、全国的に不要不急の外出を控えるように呼びかけられ、普段であれば気軽に病院を受診していた場面でも、できるだけ自宅で療養する方が増えました。
また新型コロナウイルスにより重篤な状態になる方も増加したため、医療機関の治療がそちらに集中した結果、比較的緊急性の低い手術が後回しにされることもありました。これによって、普段であれば短期で退院できていたはずの方が長期間入院する事例も発生したのです。
このような新型コロナウイルスによる社会全体の変化が、2020年に一時的に平均入院日数を増加させた要因のひとつだとされています。
2017年まで平均入院日数が短くなっている2つの理由
新型コロナウイルスの影響を受ける直前の2017年まで、入院日数は徐々に短くなっています。入院日数が短くなっている背景には、以下の2つの理由が大きく影響していると考えられています。
- 医療技術の進歩によって長期入院を必要としないから
- 政府が入院期間を短期化する政策を進めているから
徐々に平均入院日数が短くなっている2つの理由について、詳しく解説します。
参照元:入院は大幅減少、外来は微減-2020年の「患者調査」にあらわれたコロナ禍の影響
医療技術の進歩によって長期入院を必要としないから
平均入院日数が短くなっている理由のひとつとして、医療技術の進歩が挙げられます。年々新しい医療技術が確立され、患者の身体に大きな負担を掛けない手術も増えてきています。
内視鏡手術がその一例です。内視鏡手術とは、身体に小さな穴を開けて手術をする方法です。小さな傷跡で手術できるため、回復までの時間が早く、長期間の入院を必要としなくなりました。患者の身体に大きな負担をかけずに手術できることから、平均的な入院日数が短くなっているのです。
政府が入院期間を短期化する政策を進めているから
年々、平均入院日数が短くなっているもうひとつの理由として、政府が入院期間の短縮を目的とした「医療費適正化計画」を進めていることが挙げられます。
少子高齢化が進む中、医療給付費の増大が問題となっています。また、高齢者が増加することで入院患者数が増え続け、病床が不足する事態も想定されます。
このような事態を未然に防ぐため、政府は平均入院日数の短縮を目的とする政策を推進しています。具体的な取り組みとして、医療機能の分化・連携、在宅療養の推進、療養病床の転換支援の取組みなどを行っています。
こうした国の施策によって、各医療機関ができるだけ早期に患者を退院させる動きが強まっているのです。
入院1日あたり自己負担額の平均は20,700円

2022年に公益財団法人生命保険文化センターが行った調査「生活保障に関する調査」によると、入院1日あたりの自己負担額は平均で20,700円です。入院1日あたりの自己負担額と構成割合は以下のとおりです。
| 入院1日あたりの自己負担額 | 構成割合 |
|---|---|
| 5,000円未満 | 13.8% |
| 5,000円〜7,000円未満 | 8.8% |
| 7,000円〜1万円未満 | 11.5% |
| 1万円〜15,000円未満 | 23.2% |
| 15,000円〜2万円未満 | 7.9% |
| 2万円〜3万円未満 | 16% |
| 3万円〜4万円未満 | 5.5% |
| 4万円未満 | 13.2% |
これは過去5年以内に入院をし、入院費用などを支払った方を対象に調査したもので、調査対象者には高額療養費制度を利用した方も含まれています。日本には公的医療保険制度があるとはいえ、入院1日あたりの自己負担額の平均が2万円を超えるとなると家計負担も大きくなるでしょう。
長期入院による2つのリスク

入院期間が長引くことで、以下の2つのリスクが発生します。
- 自己負担額が大きくなる
- 収入が減る恐れがある
生命保険文化センターの調査「生活保障に関する調査」では、入院期間が長引くほど、自己負担額も大きくなることが明らかになっています。さらに、入院中は仕事ができないため、働けない期間が長くなるほど収入も低減するでしょう。
入院期間が長引くことで生じる2つのリスクについて、以下で詳しく解説します。
自己負担額が大きくなる
長期入院をすると自己負担額が大きくなる可能性が高いです。実際、生命保険文化センターの調査内容を見ると、入院期間が長期化するにつれて入院時の自己負担額も大きくなっています。
| 入院期間 | 入院時の自己負担額の平均 |
|---|---|
| 5日未満 | 8.7万円 |
| 5〜7日 | 15.2万円 |
| 8〜14日 | 16.4万円 |
| 15〜30日 | 28.4万円 |
| 31〜60日 | 30.9万円 |
| 61日以上 | 75.9万円 |
参照元:生活保障に関する調査 <図表 II-12> 直近の入院時の自己負担費用〔直近の入院時の入院日数別〕
入院期間が7日以下の方の過半数は入院時の自己負担額が20万円未満で済んでいるのに対し、入院期間が31日以上となると過半数の方が20万円以上を負担しています。
このように入院時の自己負担額は、入院期間に連動して大きくなる傾向があります。そのため、長期入院の際は経済的負担が大きくなることも覚悟しておきましょう。
収入が減る恐れがある
長期入院によるもうひとつのリスクは、収入が減る恐れがある点です。入院中は仕事ができないため、入院日数が長引くほど収入も減ってしまいます。生命保険文化センターの調査「生活保障に関する調査」によると、年代別に入院によって収入が低減した方の割合は以下のとおりです。
| 年代 | 減収となった方の割合 |
|---|---|
| 20代 | 9.1% |
| 30代 | 15.8% |
| 40代 | 26.3% |
| 50代 | 22.3% |
| 60代 | 17.6% |
| 70代 | 13.8% |
参照元:2022(令和4)年度 生活保障に関する調査 P69 <図表 II-16> 直近の入院時の逸失収入の有無〔年齢別〕
入院によって収入が低減した方は、特に働き盛りの40〜50代の方に多い傾向です。勤務先で加入している健康保険から傷病手当金が支給される場合もありますが、支給額は給料(標準報酬日額)の3分の2のみのため、入院による収入の低減は避けられません。
本来得られるはずだった収入のうち、入院によって失われた収入分を逸失収入といいます。2022年の生命保険文化センターの調査「生活保障に関する調査 P61」によると、入院時の逸失収入は平均30.2万円で、入院1日あたりの逸失収入は平均21,000円です。
ただし、これは入院によって低減した収入のみを示したもので、実際は逸失収入に加えて入院費用などの自己負担額も発生します。入院時の自己負担額と逸失収入の総額については以下のとおりです。
| 入院期間 | 入院時の自己負担額と逸失収入の総額 |
|---|---|
| 5日未満 | 9.6万円 |
| 5〜7日 | 18.9万円 |
| 8〜14日 | 26.3万円 |
| 15〜30日 | 38.6万円 |
| 31〜60日 | 44.8万円 |
| 61日以上 | 96.5万円 |
参照元:2022(令和4)年度 生活保障に関する調査 P71 <図表 II-20> 直近の入院時の自己負担費用と逸失収入の総額〔直近の入院時の入院日数別〕
入院期間が長引くにつれて家計負担も大きくなる傾向があります。特に61日以上の入院になる場合は、100万円近くの費用が必要になる場合もあるため注意しましょう。長期入院によるリスクに備えたい方は、医療保険への加入をおすすめします。
保険が打ち切られる可能性がある
多くの医療保険では、あらかじめ支給限度日数が決まっています。想定外に入院が長期化すると、保険金の支給が止まる可能性があるため注意しましょう。
入院中は、治療費や家族の生活費など、さまざまな費用が必要です。さらに、働くこともできないため、収入も途絶えてしまいます。そんな生活を支えるのが医療保険です。
仮に、生活を支えている医療保険までも受け取れなくなってしまったら、日常生活が困窮してしまうでしょう。そうした状況を避けるためには、支給日数も踏まえた上で保険を選ぶことが大切です。
例えば、生活習慣病による入院の場合は長期化しやすいため、支給限度日数が無制限になる保険もおすすめです。他にも、想定外の長期入院でも支給日数を延長してくれる長期入院特約が付いている保険を活用する方法や、就業不能保険と併用する方法などがあります。
医療保険を選ぶ際には、想定外に入院が長期化するリスクも考えて保険を選ぶとよいでしょう。
保険選びには「セゾンマネーレシピ」がおすすめです。さまざまな保険商品が取り揃えられています。保険料は抑えつつも手厚い補償を受けたい方は、「セゾンマネーレシピ」を利用しましょう。

そもそも自分にはどのような保険が必要かというところから相談したいときは、セゾンのオンラインFPショップ「セゾンのマネナビ」で相談してください。
何度相談しても無料で利用でき、オンラインで相談ができます。
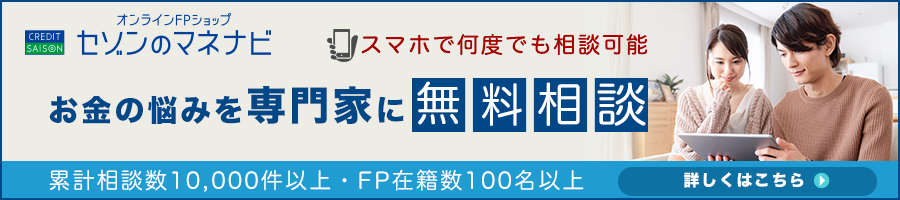
入院日数は予測できないからこそ事前に備えておく

現在の平均入院日数は、30日未満です。過去のデータを振り返ると、徐々に平均入院日数は短くなっているため、今後も入院日数が短くなる可能性があります。一方で、入院1日あたりの自己負担額の平均は約20,700円というデータもあります。決して安くはない金額なので、家計への影響は大きいでしょう。特に、入院期間が長期に及ぶ場合は、さらに費用が増大する可能性があるため、想定以上に入院が長引くことも想定して備えておくことが大切です。
入院による家計負担を少しでも軽減したい方は、医療保険への加入を検討しましょう。医療保険に加入することで、高額な入院費や逸失収入が発生する事態に備えられます。
病気が見つかったあとでは保険に加入できないケースも多いため、早めに医療保険に加入して万一に備えましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。