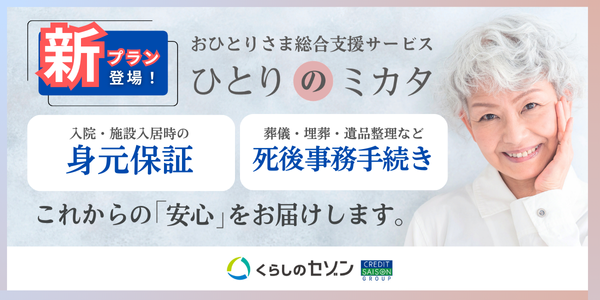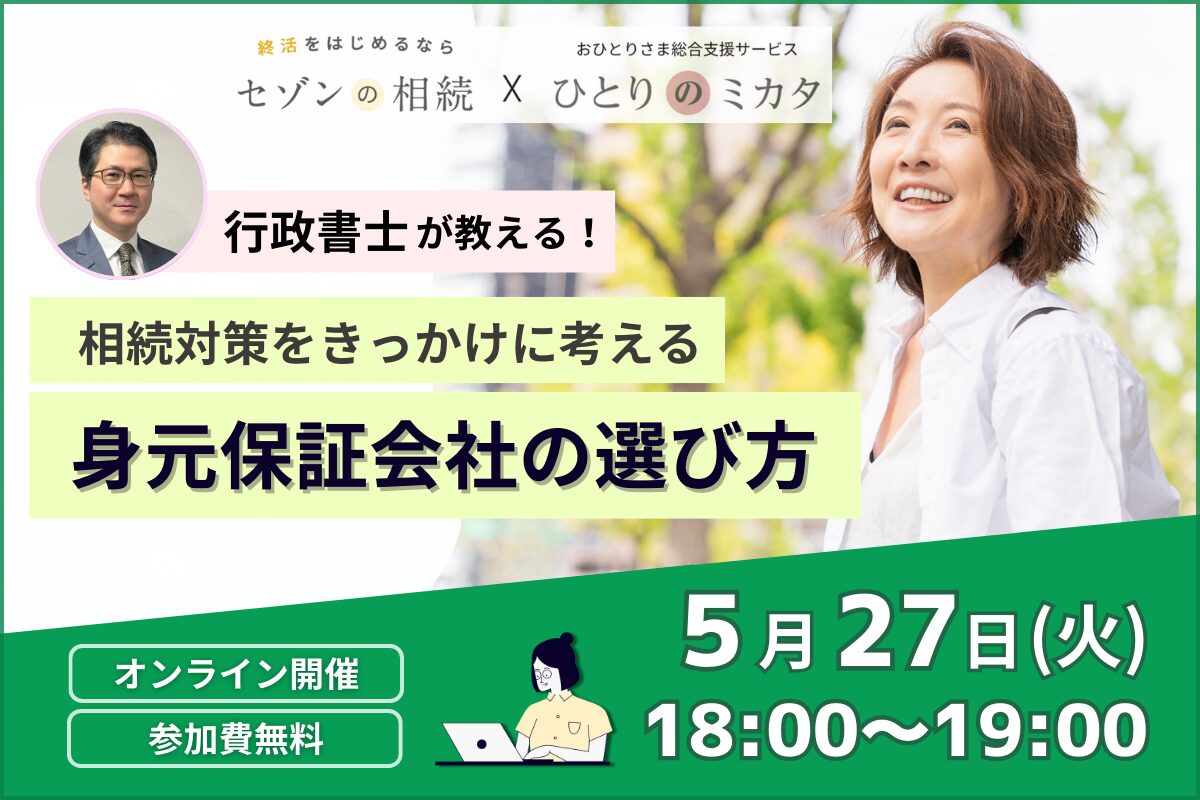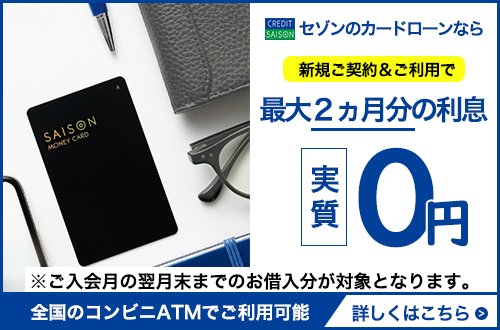老後は孫と遊んだり国内外に旅行をしたりと、ワクワクするような毎日を思い描いている方が多いのではないでしょうか。しかし、老後の楽しみには何かとお金がかかるもの。十分な蓄えがないと、思い描く生活を実現できない可能性があります。
定年後の充実した暮らしを実現するには、貯蓄額など老後資産の確認が欠かせません。そこで本記事では、以下の内容を統計データに基づいて分かりやすく解説します。
- 65歳前後の平均的な貯蓄額と収支状況
- 老後の貯蓄不足で直面する課題
- 将来資金不足に陥るリスク要因
- 必要な貯蓄額を確保するための具体策
- 効果的な資産運用の方法
この記事を読むことでご自身の資産状況を見直すきっかけとなり、資産形成のヒントが見つかるはずです。ゆとりあるセカンドライフを送るため、ぜひ参考にしてください。


65歳平均貯蓄額を夫婦・単身別に解説
老後2,000万円問題が話題になるなか、実際に老後に向けて貯蓄できている方はどれくらいいるのでしょうか。夫婦世帯と単身世帯に分けて確認してみましょう。
夫婦世帯の平均貯蓄額と中央値
金融広報中央委員会が出した「家計の金融行動に関する世論調査(2023年)」によると、60代の2人以上世帯における貯蓄額(金融資産保有額)は、平均値が2,026万円、中央値が700万円となっています。
この平均値と中央値の差は、貯蓄額に大きな格差があることを示しています。平均値は一部の高所得者の影響を大きく受けてしまうため、必ずしも一般的な世帯の実態を反映していません。
そのため、中央値の方がより実態に近い指標だといえるでしょう。中央値の700万円は、60代の2人以上世帯を金融資産の額で順番に並べた際の真ん中の値を示しています。
つまり、60代の2人以上世帯の半数は700万円以上の貯蓄があり、残りの半数は700万円未満となります。ただし、老後30年を想定した場合、中央値の700万円では大幅に不足する可能性が高い点にはご注意ください。
参照:家計の金融行動に関する世論調査〔二人以上世帯〕令和5年調査結果
単身世帯の平均貯蓄額と中央値
60代の単身世帯の貯蓄額は、夫婦世帯と比べてかなり少ない傾向にあります。
同調査によると、60代の単身世帯における貯蓄額(金融資産保有額)は、平均値が1,468万円であるのに対し、中央値はわずか210万円です。
平均値と中央値の大きな差は、一部の高所得者が平均値を引き上げている実態を表しています。金融資産を多く持つ単身世帯と、そうでない世帯の二極化が進んでいるといえるでしょう。
中央値の210万円という数字は、単身世帯の半数がこの金額以下の貯蓄しかない事実を示しています。夫婦世帯の中央値700万円と比べると、かなり厳しい水準といえるでしょう。ひとり暮らしの方は、老後に向けてできるだけ早めの資産形成を心がける必要があります。
参照:家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯]令和5年調査結果
65歳平均貯蓄額と同時に確認しておきたい収入の目安金額
老後の生活設計を立てる際は、貯蓄額と合わせて主な収入源もチェックしておきましょう。ここでは、年金と退職金について解説します。
年金
老後の定期的な収入源として、中心となるのが公的年金制度です。公的年金の受給額は、加入期間や保険料の納付状況によって変わります。
日本年金機構が発表した最新の情報によると、2024年4月分からの老齢基礎年金(満額)は1人あたり月額6万8,000円です。また、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)は、月額約23万円となっています。
これらの金額を前提に、必要な貯蓄額を考えましょう。
退職金
会社員にとって、退職金は老後生活の大切な資金源です。退職金の金額も、勤務先の企業規模や学歴、勤続年数などによって大きく異なります。
退職金の一般的な目安金額は次のとおりです。
| 大企業 | 大学卒男性 | 約2,140万円 |
| 高校卒男性 | 約2,020万円 | |
| 中小企業 | 大学卒 | 約1,092万円 |
| 高校卒 | 約994万円 |
なお、これらの金額は、定年まで同じ会社に勤め続けた場合の満額の数値です。転職や早期退職などにより、受け取れる金額も変わります。
65歳平均貯蓄額では足りない!高齢者世帯の支出額

65歳以上の高齢者世帯の平均支出額は、単身無職世帯で月額約14.5万円、夫婦のみの無職世帯は月額約25万円です。年間に換算すると、単身世帯で約174万円、夫婦世帯では約300万円にものぼります。
では、具体的にどのような項目にお金が使われているのでしょうか。2023年の家計調査報告(家計収支編)によると、主な項目の支出額は以下のとおりです。
【65歳以上無職世帯のひと月あたり平均支出額(単位:円)】
| 項目 | 単身世帯 | 夫婦世帯 |
|---|---|---|
| 食費 | 40,103 | 72,930 |
| 住居費 | 12,564 | 16,827 |
| 水道光熱費 | 14,436 | 22,422 |
| 日用品費 | 5,923 | 10,477 |
| 衣料品費 | 3,241 | 5,159 |
| 医療費 | 7,981 | 16,879 |
| 交通通信費 | 15,086 | 30,729 |
| 教育費 | 0 | 5 |
| 教養娯楽費 | 15,277 | 24,690 |
| その他 | 30,821 | 50,839 |
| 支出合計 | 145,430 | 250,959 |
このように、65歳以上の無職世帯では食費が最も大きく、単身世帯で月額約4万円、夫婦世帯で約7.3万円を占めています。次いで、交通通信費や教養娯楽費、水道光熱費といった基本的な生活費が大きな割合を占めています(その他の支出を除く)。
これらの支出は年金だけでまかなうのが難しい場合も多く、老後の生活設計を考える際は、月々の支出を見据えた計画を立てる必要があるでしょう。
65歳平均収支を夫婦・単身別に解説
高齢者の実際の生活では毎月の収支がどうなっているのか、夫婦世帯と単身世帯に分けて詳しく見ていきましょう。
夫婦無職世帯の収支
65歳以上の無職の夫婦世帯における家計収支について、平均的な数字は以下のとおりです。
- 月間収入:213,042円
- 月間支出:250,959円
- 収支差額:▲37,917円(赤字)
上記の赤字を補うには、毎月貯蓄を約3万8,000円分取り崩す必要があります。この状況が続くと、1年間で約45.5万円もの赤字になります。さらに、65歳から95歳までの30年間で考えると、約1,365万円もの貯蓄が必要となるのです。
老後の生活を維持するには、1,400万円程度の貯蓄が必要だといえるでしょう。
単身無職世帯の収支
65歳以上の単身無職世帯の平均収支は以下のとおりです。
- 月間収入:114,663円
- 月間支出:145,430円
- 収支差額:▲30,767円(赤字)
赤字額を年間に換算すると約37万円となり、65歳から95歳までの30年間では約1,110万円の赤字になります。したがって単身世帯の方は、最低でも1,200万円以上の貯蓄を準備しておく必要があるでしょう。
単身世帯では、光熱費や住居費などの固定費を1人で負担しなければならず、家計のやりくりが難しい状況にあります。そのため、現役時代からの計画的な資産形成はもちろん、支出の見直しや年金以外の収入確保など、将来に向けた綿密な生活設計が必要となります。
高齢者の6割「生活が苦しい」
2023年の国民生活基礎調査によると、高齢者世帯の約6割が「生活が苦しい」または「やや苦しい」と回答しています。その一方で、「生活にゆとりがある」と答えた世帯はわずか4.3%にとどまりました。この結果から、多くの高齢者が老後の生活に不安を感じている現状が浮き彫りとなっています。
背景には、物価上昇による生活費の増加や、医療費・介護費用の負担増加などがあると考えられます。また、年金支給額の伸び悩みも、生活の苦しさを感じる要因のひとつとなっているようです。
このような状況を踏まえると、老後に向けた計画的な資産形成の重要性が改めて分かります。
65歳平均貯蓄額の不足で直面する4つの課題
老後に貯蓄がないと、日常生活のさまざまな場面で困った状況に陥ります。ここでは、以下の4つのシーンについて解説します。
- 冠婚葬祭の費用が捻出できない
- 子どもや孫への援助や贈り物ができない
- 住居の修繕や改築ができない
- 娯楽のためのお金がない
具体的にどのように困るのか、詳しく見ていきましょう。
冠婚葬祭の費用が捻出できない
突然の出費に頭を悩ませることになるのが、冠婚葬祭の費用です。
子どもの結婚式では、親として相応の費用負担を求められるかもしれません。100万円以上の費用が突然必要になる場合もあります。また、親族の葬儀での香典代、孫の七五三や入学式、成人式などの大切な節目でのお祝い金など貯蓄が心もとないと、満足のいく対応ができないかもしれません。
早い段階で資産形成をしておかないと、将来身近な方々に望む形で寄り添えず、悲しい思いをすることになるでしょう。
子どもや孫への援助や贈り物ができない
経済的なゆとりがないと、家族との関係にも影響が出てきます。子どもや孫に欲しいものを買ってあげたくても、お金がなくてできないのは親としてつらいものです。
子どもが住宅を購入するときも、援助したくてもできない可能性もあるでしょう。
子ども家族から外食や旅行に誘われても断わることが多くなれば、交流が減っていくかもしれません。子どもや孫と良い関係を築くためにも、老後に向けて貯蓄しておきましょう。
住居の修繕や改築ができない
年月が経つにつれて必要になってくるのが、住まいの修繕や改築です。屋根の雨漏りや外壁の劣化、水回りの故障など、放ってはおけない問題が次々と発生します。
しかし、貯蓄が不足していると必要な修繕もできず、住環境が悪化の一途をたどってしまいます。結果として、家の資産価値も大きく下がってしまうでしょう。
住んでいる家に不満があるとその先の生活が楽しくなくなってしまいます。老後の生活を楽しめるようにリフォーム代は残しておきたいものです。
娯楽のためのお金がない
生きがいを持って充実した老後を過ごすためには、趣味や娯楽も大切です。しかし、お金がないと旅行に行ったり習い事を始めたりする余裕がなくなってしまいます。
毎日の生活が節約一色になり、楽しみを見いだせない単調な日々を送ることになりかねません。健康な身体があっても、やりたいことができないのは残念なことです。
このような事態を避けるためにも、現役時代から計画的に貯蓄をして、充実した老後生活を送れるよう備えておきましょう。
将来65歳平均貯蓄額では不足する?!3つのリスク要因
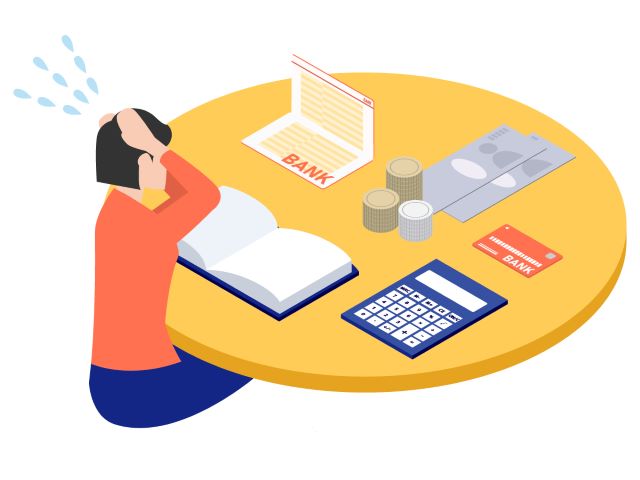
これからの時代、65歳時点で平均的な貯蓄額を持っていても、将来老後資金が不足するリスクを想定しておかなければなりません。考えられる主な要因は以下の3つです。
- インフレによる預貯金や年金の目減り
- 医療費や介護費の負担増
- 増税の可能性
これらについて、具体的な数字を交えながら解説します。
インフレによる預貯金や年金の目減り
物価の上昇は、日々の生活費を押し上げるだけでなく、預貯金の価値も大きく目減りさせます。
例えば、年間2%のインフレが続くと、1,000万円の預貯金は10年後に約820万円相当(1,000万円×(1/1.02)^10年=約820万円)の価値となってしまいます。つまり、同じ金額を持っていても、10年で約180万円分も実質的な資産価値が減ってしまうのです。
年金については物価スライド制が採用されていますが、実際の物価上昇に追いつかないことが少なくありません。現在の預貯金金利は0.125%程度と極めて低い水準にとどまっており、インフレ率が2%を超えると、預貯金をしているだけでは資産が徐々に目減りしていってしまいます。
医療費や介護費の負担増
高齢期の医療費や介護費用は、年々上昇する傾向にあります。
医療制度の改正により、75歳以上の方で一定以上の所得がある場合(※1)、医療費の窓口負担が1割から2割に引き上げられました。
さらに介護が必要になった場合、要介護度に応じて1割から3割の自己負担が発生し、月額数千円~30万円程度の支出増となる可能性があります。
【事例1】介護付き有料老人ホームに入所した場合の自己負担金:入居一時金30万円、月額利用料20万円
【事例2】脳梗塞の後遺症がある方を自宅介護する場合の自己負担金:月10万円
また、先進医療を受けた場合は、保険適用外の医療費負担が予期せず発生するリスクがあります。
【事例】前立腺がんで重粒子線治療を受けた場合の保険外治療費:約295万円
(※)一定所得以上:課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額(事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いたあとの金額)」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合は合計320万円以上
増税の可能性
将来的な社会保障費の増大に対応するため、今後さまざまな形での増税が検討されるでしょう。具体的には、今後消費税率のさらなる引き上げや所得税の実質増税が懸念されます。
また、固定資産税や相続税の見直しにより、不動産保有コストや相続時の税負担が増加するリスクも考えられます。特に、不動産を複数所有している方や相続予定の資産が多い方は、今のうちから心づもりしておくと安心かもしれません。
さらに、社会保障関連では健康保険料の引き上げなど、国民の負担が増加する可能性も否定できない状況です。
これらの増税リスクに備えるためにも、将来を見据えた資産づくりをお勧めします。
65歳平均貯蓄額達成のための5つのポイント

老後の資金計画を立てるうえで、重要なポイントは以下の5つです。
- 退職金の受け取り方
- 退職金の資産配分方法
- 年金受給開始時期の選択
- 継続雇用vs転職vs退職の選択
- 配偶者の就労状況との調整
これらを組み合わせることで、ゆとりある老後生活を送れるでしょう。順に解説します。
退職金の受け取り方
退職金やiDeCo(個人型確定拠出年金)は、受け取り方法により税金の負担が大きく異なります。
まず、退職金の受け取り方法を確認しておきましょう。具体的には以下の3種類があります。
- 年金として受け取る
- 一時金として受け取る
- 年金と一時金を組み合わせる(併給)
退職金の受け取り方法は会社のルールにより制限される場合があるため、退職前に就業規則や退職金規程を確認しておきましょう。
退職金を賢く受け取るポイントは「退職所得控除」という非課税枠を最大限に活用することです。一時金方式で受け取る場合、「退職所得控除」を適用することで、課税負担を大幅に軽減できる場合があります。
なお、退職金と同時に受け取ることが多いiDeCoも、退職金と同様の扱いとなります。ただし、退職金が多い方は、iDeCoの受け取り時期をずらすと節税対策になる場合があります。
「退職所得控除」を活用した受け取り方の具体例として、金融広報中央委員会によるシミュレーション結果を見てみましょう。退職金2,000万円(30年勤務)、iDeCoの受給額500万円(40歳から60歳まで積み立て)の場合、受取方法3パターンのそれぞれの課税合計額は以下のとおりです。
| 受け取り方法 | 課税合計額 |
|---|---|
| iDeCoと退職金を両方60歳で受け取る | 107万2,500円 |
| 退職金を60歳、iDeCoを65歳で受け取る | 72万5,000円 |
| iDeCoを60歳、退職金を65歳で受け取る (65歳退職の場合) | 40万2,500円 |
※各種人的控除や復興特別所得税を考慮しない
このシミュレーションから、退職金とiDeCoは同時に受け取るよりも、受け取り時期を5年以上ずらすことで節税効果が高くなることがわかります。これは、受け取りの間隔を5年以上あけると、退職所得控除を再度利用できるためです。
ただし、退職金とiDeCoの受け取り順序によって税金の計算方法が異なるため、課税金額が違ってくる点には注意しましょう。
最適な受取方法は個々の状況により異なります。退職時期やiDeCoの積立額、年金額、生活設計などを総合的に考慮する必要があるため、具体的な判断は専門家への相談をお勧めします。
退職金の資産配分方法
退職金を受け取ったら、「生活費分」と「ゆとり分」に分けて管理しましょう。
生活費分は、年金支給までの期間の必要額を計算して確保します。具体的には、毎月の生活費に月数をかけた金額を基準とし、予備費として3ヵ月分を上乗せした額を目安にしてください。この生活費分は安全性の高い金融商品で運用します。
一方、生活費分を差し引いた残りの資金はゆとり分として確保し、資産を増やすチャンスと考えて積極的に運用しましょう。
主な金融商品のメリット・デメリットは次のとおりです。
| メリット | デメリット | ||
|---|---|---|---|
| 生活費分 | 普通預金 | いつでも引き出せる 元本保証 | 金利がほぼゼロ インフレに弱い |
| 定期預金 | 普通預金より金利が高い 元本保証 | 中途解約すると金利が下がる インフレに弱い | |
| ゆとり分 | 投資信託 | 少額から分散投資できる 専門家が運用 | 手数料がかかる 元本割れのリスクあり |
| 個別株式 | 値上がり益と配当が期待できる 自分で銘柄を選べる | 企業の業績や相場の影響を受けやすい ハイリスク |
投資する際はひとつの商品に集中せず、複数の金融商品に分散投資を心がけることで、リスクの軽減効果を期待できます。
年金受給開始時期の選択
老齢年金は受給開始時期を遅らせるほど、受給額が大きくなります。例えば、65歳から75歳まで受給を繰り下げると、支給額が最大84%増える仕組みです。これは支給開始を1ヵ月延ばすごとに0.7%ずつ増額されるためです。
ただし、繰り下げ受給を選択する際は、次の3点を検討する必要があります。
- 繰り下げ期間の約10年間、生活費をどう工面するか
- 平均寿命を考慮した場合の総受給額
- 健康状態や医療費の見込み
まず、75歳まで繰り下げた場合で考えてみましょう。84%増額された年金を受給できる一方で、65歳から74歳までの約10年間は年金収入がありません。この期間の生活費を補う方法としては、退職金の運用や、パートタイム勤務による収入確保、iDeCoなど他の年金制度の活用が考えられます。
また、厚生労働省が公表した「令和5年簡易生命表の概況」によると、平均寿命は男性で81歳、女性で87歳です。このデータを基に想定余命年数を平均寿命から逆算すると、75歳から受給を始めた場合の受給期間は男性で約6年、女性で約12年です。
これらを踏まえ、退職金や貯蓄を計画的に活用しながら、ご自身の状況に合わせて最適な受給開始時期を選びましょう。
継続雇用vs転職vs退職の選択
定年後の働き方は、老後の経済基盤を左右する重要な選択です。仕事ができるうちはしっかり稼ぐのが原則ですが、継続雇用か転職かの選択肢があります。また、いずれ引退を考えるときも来るでしょう。
継続雇用と転職、退職を選ぶための参考として、それぞれのメリット・デメリットを確認してみてください。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 継続雇用(再雇用) | 慣れた環境で働き続けられる、経験やスキルを活かせる、安定した収入が得られる、健康保険や厚生年金の継続加入が可能 | 給与が下がることが多い、役職が下がることへの心理的負担、モチベーションの維持が難しい場合も |
| 転職 | 新しい環境での挑戦が可能、経験を活かしつつ新たなスキル習得、条件の良い職場を選べる可能性、気分転換になる、人脈の拡大 | 就職活動の負担、新しい環境への適応、収入が不安定になる可能性、新しい人間関係構築の必要性 |
| 退職(完全引退) | 趣味や家族との時間に充てられる、ストレスから解放される、健康管理に時間を使える | 収入が年金中心になる、生活リズムの維持が難しい、社会との接点が減少、喪失感、健康保険料の負担増 |
ここで把握しておきたいのが「在職老齢年金」の仕組みです。給与収入と年金受給額の合計額が月額50万円を超えると、在職老齢年金制度により年金額が調整されます。超過分の2分の1が年金から減額されるため、定年後の収入を考える際は、この年金調整の仕組みを理解した上で計画を立てることをおすすめします。
いずれの選択肢も、ご自身の健康状態、経済状況、生活設計に合わせて判断することが大切です。特に、在職老齢年金制度による収入調整を踏まえた上で、理想的な働き方を検討しましょう。
配偶者の就労状況との調整
老後の経済的な安定のためには、夫婦で家計の収支バランスを調整することが欠かせません。配偶者の就労状況に応じて、最適な組み合わせを検討しましょう。
【夫が正社員の場合】
60歳以降も継続して働きながら、年金の繰り下げ受給を選択して将来の年金額を増やす選択肢があります。ただしこの場合、在職中は在職老齢年金が一部または全額停止される可能性があります。このため、基準額である50万円を確認しつつ、生活設計に反映させるよう意識しましょう。
【妻がパートタイム勤務の場合】
年収を103万円以下に抑えることで配偶者控除を活用できます。いわゆる「103万円の壁」で、配偶者を扶養に入れることで所得税が軽減されます。
一方、社会保険料の負担を避けるため従来は「130万円の壁」が意識されてきましたが、2023年10月から年収106万円以上、勤務時間週20時間以上などの条件で適用されることになりました。しばらくは企業側も準備段階の可能性が高いため、勤め先に社会保険の年収の壁に関する対応はどのようになっているのか、確認しておくと良いでしょう。
なお、本情報は2024年11月時点のものです。今後、制度変更の可能性があるため、最新の情報をご確認ください。
【配偶者が専業主婦(夫)の場合】
国民年金の保険料納付状況を必ず確認しましょう。例えば、国民年金保険料の未納期間がある場合は、60歳以降でも65歳まで任意加入(追加で保険料を支払う制度)することで、将来の年金受給額を増やせます。未納期間がある場合は、早めに年金事務所で確認しましょう。
このように、配偶者の就労形態に合わせて適切な戦略を選択することで、より安定した老後の経済基盤を築けます。定期的に制度の変更をチェックし、必要に応じて計画を見直しましょう。
65歳平均貯蓄額を増やす3つの資産運用術
人生100年時代に突入していくなか、老後の資産を増やすためには、長期的な視点での資産運用が欠かせません。ここでは、以下3つの運用方法について解説します。
- iDeCo(確定拠出年金)
- NISA
- 不動産投資(任意組合出資)
安定した老後生活に向けて、ぜひ参考にしてください。
iDeCo(確定拠出年金)
iDeCoとは、自分で掛金を運用して資産を増やす年金制度です。65歳になるまで掛金を積み立てることができ、60歳を過ぎれば老齢給付金として受け取れます。より豊かな老後を実現するための資産形成手段として、多くの方に利用されています。
加入年齢の上限は、2022年5月の法改正で60歳から65歳に引き上げられました。原則として、国民年金の被保険者なら65歳になるまで加入できます。
企業型確定拠出年金(会社が従業員のために運営する年金制度)に加入している場合でも、年金規約によってはiDeCoとの併用が可能です。
NISA
NISAとは、投資を行う際に一定の金額までなら税金がかからないお得な制度です。通常、金融商品に投資すると売却益や配当に対して約20%の税金が発生しますが、NISAを利用すると一定枠内での利益がすべて非課税になります。
利益をそのまま再投資に回せるため、複利効果によって資産を効率よく運用できる仕組みです。特に2024年からスタートした新NISA制度は、以下の特徴があります。
- 年間360万円まで投資が可能
- 生涯で最大1,800万円まで非課税
- 成長投資枠(上限年間240万円)とつみたて投資枠(上限年間120万円)を併用できる
- 投資期間に制限なし
- 18歳以上であれば誰でも利用可能
このように、新NISAは投資初心者でも始めやすい制度なので、まだ利用していない方はぜひ始めてみてください。
不動産投資(任意組合出資)
不動産投資は、物件を購入し、運用することで家賃収入や売却益を得る投資方法です。特に家賃収入は株価のように大きな変動がないため、安定した収入源として注目されています。
しかし「不動産投資は初期投資が高いためなかなか手が出せない」と思っている方も多いのではないでしょうか。そのような方におすすめなのが「Vシェア」という新しい不動産投資方法です。Vシェアには、以下の2つの特徴があります。
- オフィスビルなどの不動産を小口化して複数人で購入できるため、少額からの投資が可能
- 資金評価額を引き下げることで相続税や贈与税の負担を軽減
不動産小口化商品にご興味ある方・詳しいお話を伺いたい方は、こちら。
(リンク先は、株式会社ボルテックスが運営しています。)


おわりに
日本では、諸外国と比べてまだまだ投資や資産運用の文化が根付いておらず、ギャンブル要素が強いと思われがちです。しかし、この認識は必ずしも正しくありません。近年「人生100年時代」や「老後2,000万円問題」が注目を集めるなか、多くの方が資産運用の重要性に気づき始めています。このコラムで紹介したような資産運用方法を上手く活用し、安心できる老後生活を実現しましょう。
急な出費に安心!セゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD」がおすすめ
セゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD(マネーカードゴールド)」は、資金の利用目的が自由であることに加え、年会費・入会費が0円で、保有コストがかかりません。融資額も最大300万円です。全国のコンビニ・ATMで利用でき、ATM手数料も何度利用しても無料です。
急な出費への対応ができるMONEY CARD GOLD(マネーカードゴールド)をご検討ください。


マネーカードゴールドについて詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。