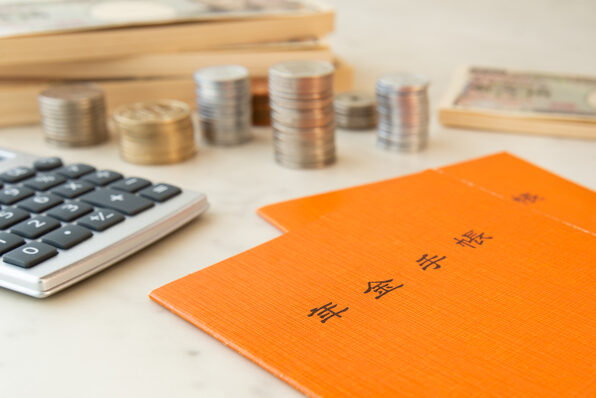家計を支えていた方が亡くなった場合、残された家族は経済的にも不安になることもあります。そんな方々の生活を支えてくれるのが、国から提供される遺族年金です。遺族年金は、亡くなった方の納付状況や働き方などによって、受給できる金額や期間、条件などが異なります。
インターネットで年金を受け取れる期間や条件について調べられるものの、制度が複雑なため「遺族年金はいつまでもらえるのか?」「どうすれば遺族年金を受け取れるのか?」などの疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、遺族年金を受け取れる期間や条件について詳しく解説します。
- 遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
- 2つの遺族年金は、受け取る要件と受け取れる期間が異なります。
- 遺族年金を受け取るには、手続きが必要です。
遺族年金とは?

遺族年金とは、国民年金や厚生年金の保険料を納めていた方が死亡した場合に、その遺族に支給される公的年金制度です。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金という2つの種類があり、それぞれ年金の納付状況や年齢に関する受給条件が設定されています。ここでは、各遺族年金の概要について解説します。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金制度です。国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する年金制度で、自営業者や会社員、公務員など、雇用形態に関わらず加入しなければなりません。自営業者などが該当する第1号被保険者が亡くなった場合は、遺族基礎年金のみが支給されます。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者である会社員や公務員が亡くなったときに、その遺族に支給される年金です。遺族厚生年金で受け取れる金額は、亡くなった方の加入実績や平均標準報酬月額などに応じて変わります。
また、厚生年金に加入していた方が亡くなり、遺族基礎年金の受給条件も満たしている場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。
遺族年金はいつまで受け取れる?

遺族基礎年金と遺族厚生年金では、受け取れる期間が異なります。ここでは、各遺族年金を受け取れる期間について詳しく解説します。
遺族基礎年金|子どもが18歳になる年度末まで
遺族基礎年金を受け取れる期間は、亡くなった方の子どもが18歳の誕生日を迎える年度末(3月31日)までです。ただし、障害等級1級または2級の障害がある子どもの場合は20歳未満までが対象となります。
また、子どものいる配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子どもは遺族基礎年金を受給できません。
その他、遺族基礎年金の受給資格を失う事由は、以下のいずれかに該当する場合です。詳しくは、以下の表をご確認ください。
| 受給権者 | 遺族基礎年金が受給できなくなる事由 |
|---|---|
| 妻または夫 | 1.亡くなったとき 2.結婚したとき(内縁関係を含む) 3.直系血族または直系姻族(配偶者の親族)以外の方の養子となったとき |
| 受給権を有しているすべての子が次のいずれかに該当したとき 1.亡くなったとき 2.結婚したとき(内縁関係を含む) 3.受給権者以外の方の養子となったとき 4.亡くなった方と離縁したとき 5.受給権者と同じ生計でなくなったとき 6.18歳になった年度の3月31日に到達したとき(障害等級1級・2級に該当する障害状態であれば、20歳に到達したとき) 7.18歳になった年度の3月31日以降、20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき | |
| 子ども | 1.亡くなったとき 2.結婚したとき(内縁関係を含む) 3.直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき 4.亡くなった方と離縁したとき 5.18歳になった年度の3月31日に到達したとき(障害等級1級・2級に該当する障害状態であれば、20歳に到達したとき) 6.18歳になった年度の3月31日以降、20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき |
引用:日本年金機構「遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき」
遺族厚生年金|受給要件を満たす限り無期限
遺族厚生年金を受け取れる期間は、亡くなった方との関係性によって異なります。それぞれの受け取れる期間は、以下のとおりです。
| 受け取る方 | 受け取れる期間 |
|---|---|
| 妻 | 夫が亡くなってから一生涯(ただし、30歳未満で子どもがいない妻は5年間のみ) |
| 55歳以上の夫 | 60歳から一生涯 (遺族基礎年金を受給できる場合は、55歳から60歳の間も受給可能) |
| 子ども、孫 | 18歳になった年度の3月31日まで (障害等級1級・2級に該当する場合は、20歳になるまで) |
| 55歳以上の父母、祖父母 | 60歳から一生涯 |
遺族厚生年金は、子どもがいない配偶者も受給可能で、一生涯受け取れます。ただし、30歳未満で子どもがいない妻は、5年間のみの受給となります。
また、受け取れる対象者が遺族基礎年金よりも幅広く、父母、孫、祖父母まで受け取れるのも特徴です。
遺族厚生年金を受け取っている方が特定の事由に該当した場合は、受給が停止されます。
遺族厚生年金の受給資格を失う事由は、以下のとおりです。
| 受給権者 | 遺族厚生年金が受給できなくなる理由 |
|---|---|
| 妻 | 1.亡くなったとき 2.結婚したとき(内縁関係を含む) 3.直系血族または直系姻族(配偶者の親族)以外の方の養子となったとき 4.夫が亡くなった当時30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を経過したとき 5.遺族基礎年金もしくは遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき ※4及び5は、平成19年4月1日以降に夫が亡くなり、遺族厚生年金を受け取ることとなった場合に限る |
| 夫 | 1.亡くなったとき 2.結婚したとき(内縁関係を含む) 3.直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき |
| 子ども | 1.亡くなったとき 2.結婚したとき(内縁関係を含む) 3.直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき 4.亡くなった方と離縁したとき 5.18歳になった年度の3月31日に到達したとき(障害等級1級・2級に該当する障害状態であれば、20歳に到達したとき)6.18歳になった年度の3月31日以降、20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき |
| 父母 | 1.亡くなったとき2.結婚したとき(内縁関係を含む)3.直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき4.亡くなった方と離縁したとき5.亡くなった方の死亡当時胎児であった子が生まれたとき |
| 孫 | 1.亡くなったとき2.結婚したとき(内縁関係を含む)3.直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき4.離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき5.18歳になった年度の3月31日に到達したとき(障害等級1級・2級に該当する障害状態であれば、20歳に到達したとき) 6.18歳になった年度の3月31日以降、20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき7.亡くなった方の死亡当時胎児であった子が生まれたとき |
| 祖父母 | 1.亡くなったとき 2.結婚したとき(内縁関係を含む) 3.直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき 4.離縁によって亡くなった方との親族関係が終了したとき 5.亡くなった方の死亡当時胎児であった子が生まれたとき |
引用:日本年金機構「遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき」
遺族基礎年金の受給要件と受け取れる金額は?

遺族基礎年金を受け取るためには、亡くなった方と受け取る方の両者が要件を満たしている必要があります。それぞれの要件について詳しく確認していきましょう。
亡くなった方の要件
遺族基礎年金を受け取るためには、亡くなった方が以下の要件のいずれかを満たしている必要があります。
- 国民年金の被保険者である
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所がある
- 老齢基礎年金の受給権者であった
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた
上記要件の1と2に記載されている「国民年金の被保険者」の条件は、生涯で国民年金に加入していた期間のうち、保険料を納めていた期間(免除期間も含む)が3分の2以上あることです。
ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たせる特例があります。
また、上記要件の3と4の「老齢基礎年金の受給資格」を満たすためには、免除期間も含めて25年以上、国民年金に加入している必要があります。
遺族基礎年金を受け取る方の要件
遺族基礎年金は、亡くなった方の条件だけでなく、受け取る方の条件も満たす必要があります。遺族基礎年金を受け取る方の要件は以下のとおりです。
- 死亡した方により生計を維持されていた
- 子どものいる配偶者もしくは子ども
「死亡した方により生計を維持されていた方」とは、同居していた方で年収850万円未満の方(もしくは別居していて仕送りを受けたり、被扶養者になっていたりする方)が該当します。そのため、配偶者の年収が850万円以上だった場合、亡くなった方に生計を維持されていたとみなされず、遺族基礎年金の対象となりません。
ただし、亡くなった時点で年収が850万円以上だったとしても、死亡後5年以内に年収が下がると認められる事由があれば、遺族基礎年金を受け取れる可能性もあります。
また、遺族基礎年金の受給要件に記載される「子ども」とは、18歳になった年度の3月31日までの方、もしくは障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の方を指します。
なお、子どもが遺族基礎年金を受けられないケースは以下のとおりです。
- 子どものいる配偶者が遺族基礎年金を受け取っている
- 子どもと生計を同じくする父または母がいる
遺族基礎年金の受給額
遺族基礎年金で支給される金額は、以下の計算式をもとに算出されます。
- 計算式:816,000円 + 子どもの加算額
- 1人目・2人目の子どもの加算額:234,800円(ひとり当たり)
- 3人目以降の加算額:78,300円(ひとり当たり)
遺族基礎年金の金額は、毎年見直されます。上記の計算式は、令和6年4月分以降の金額で計算しています。最新の金額を知りたい方は、日本年金機構のWEBサイトをご確認ください。
例えば、子どもが2人の家庭で妻が遺族基礎年金を受け取る場合、以下が年間の支給金額です。
年間の受給額:816,000円 + 234,800円 (子ども1人目)+ 234,800円(子ども2人目) = 1,285,600円
参照元:日本年金機構|遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
遺族厚生年金の受給要件と受け取れる金額は?

遺族厚生年金の受給要件は、遺族基礎年金と同様に、死亡した方と受け取る方の要件が決められています。ここでは、遺族厚生年金の受給要件と受け取れる金額について詳しく解説します。
亡くなった方の要件
亡くなった方の要件は、以下のとおりです。
- 厚生年金の被保険者である
- 厚生年金の被保険者期間に初診日のある病気やケガにより、初診日から5年以内に死亡した
- 1級・2級の障害厚生年金(障害共済年金)を受け取っている
- 老齢厚生年金の受給権者であった
- 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていた
遺族厚生年金を受け取るには、亡くなった方が、国民年金加入期間のうち保険料を納めていた期間(免除期間も含む)が3分の2以上でなければいけません。
ただし、65歳未満の方が令和8年3月末までに亡くなった場合、亡くなる直前の1年間に保険料の未納がなければ要件を満たせる特例があります。
また、上記要件の4と5に記載される「老齢厚生年金の受給資格」の条件を満たすためには、免除期間も含めて加入期間が25年(300ヵ月)以上あることが必要です。
上記の要件のうち、1〜3を短期要件、4と5を長期要件といいます。加入期間が25年(300ヵ月)あるかどうかで、受給金額の計算方法が異なります。
遺族厚生年金を受け取る方の要件
遺族厚生年金の受け取りができる対象は、亡くなった方により生計が維持されていた遺族です。また、本人との関係性によって、受け取る優先順位も決められています。受け取る方の優先順位と要件は、以下のとおりです。
- 妻:要件なし(ただし、30歳未満であれば5年間のみ)
- 夫:死亡時55歳以上(受給開始は60歳から。ただし、遺族基礎年金を受給できる場合は55歳から60歳の間も受給可能)
- 子ども:18歳の誕生日がある年度の年度末まで、または20歳未満で障害年金の等級1級、2級の障害者
- 父母:死亡時55歳以上(受給開始は60歳から)
- 孫:18歳の誕生日がある年度の年度末まで、または20歳未満で障害年金の等級1級、2級の障害者
- 祖父母:死亡時55歳以上(受給開始は60歳から)
遺族厚生年金を受給する優先順位は、配偶者と子どもが第1位で、続いて父母、孫、祖父母の順になっています。
また、子のある妻、または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受給している間は、子どもに遺族厚生年金は支給されません。
妻が30歳未満だった場合、遺族厚生年金が受給できるのは5年間のみで、それ以降は支給停止されます。また、夫や父母、祖父母は、死亡時に55歳以上でないと遺族厚生年金を受け取れず、受給開始は60歳からです。
中高齢寡婦加算の要件
中高齢寡婦加算とは、以下の要件に該当する妻が受け取れるものです。
- 夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子どもがいない。
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けている子どものいる妻が、子どもが18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等の理由で、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
要件1の「生計を同じくしている子ども」とは、18歳到達年度の3月31日を経過していない子どもや、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害がある子どもを指しています。
上記1.2の要件のいずれかに該当する方は、40歳〜65歳の期間に受け取る遺族厚生年金に、年額61万2,000円が加算されます。
遺族厚生年金の受給額
遺族厚生年金の受給額は、厚生年金加入時の報酬により異なります。受給額の計算方法については、以下の表をご確認ください。
| 被保険者期間 | 計算式 |
|---|---|
| 300ヵ月以上 | 老齢厚生年金の報酬比例部分 × 3/4 |
| 300ヵ月未満 | 加入実績に応じた老齢厚生年金額 × (300ヵ月 ÷ 加入月数) × 3/4 |
厚生年金加入者かつ遺族基礎年金の受給条件を満たしていれば、2つの年金を同時に受け取れます。また、遺族基礎年金を受給できない40歳以上の妻は、中高齢寡婦加算として遺族基礎年金の4分3にあたる612,000円が受け取れます。
ただし、老齢厚生年金の計算は複雑です。算出するときには、ねんきん定期便に記載のある「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」を活用して計算しましょう。
実際の支給額についてより具体的に知りたい方は、年金事務所の窓口で直接確認することをおすすめします。
参照元:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
遺族年金を受け取る手続きについて

遺族年金を受け取るためには、受付窓口へ行って手続きをする必要があります。また、遺族基礎年金と、遺族厚生年金では、窓口の場所が違うため注意しましょう。ここでは、遺族年金を受け取る手続きの流れについて確認します。
必要書類を準備する
遺族年金の手続きには、以下の書類が必要です。
| 対象者 | 必要書類 |
|---|---|
| すべての方 | ・基礎年金番号通知書(または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにできる書類) ・戸籍謄本(記載事項証明書)(*) ・世帯全員分の住民票の写し(*) ・死亡者の住民票の除票 ・請求者の収入が確認できる書類(*) ・子どもの収入が確認できる書類(*) ・死亡診断書(死体検案書など)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 ・受け取り先金融機関の通帳など(本人名義のもの) (*)の書類は、マイナンバーの記入で省略可能 |
| 死亡の原因が第三者行為の場合 | ・第三者行為事故状況届 ・交通事故証明もしくは事故が確認できる書類 ・確認書 ・扶養していたことがわかる書類 ・損害賠償金の算定書 |
| その他状況に応じて必要 | ・年金証書(他の公的年金を受給している場合) ・合算対象期間が確認できる書類 |
遺族基礎年金と遺族厚生年金の手続きでは、基本的に同様の書類が必要です。ただし、個人の状況に応じて追加で書類の提出を求められる場合もあります。受付窓口で相談しつつ、状況に応じて必要書類を揃えられるように準備しておくとよいでしょう。
対象の受付窓口へ行く
遺族基礎年金だけを申請する方と遺族厚生年金を申請する方では、受付窓口が違います。各遺族年金の受付窓口は以下のとおりです。
- 遺族基礎年金のみを申請する場合:死亡した方の住所地の市区町村役場
- 遺族厚生年金も申請する場合:最寄りの年金事務所もしくは年金相談センター
亡くなった方が加入していた年金の種類によって受付窓口が変わるため、申請前に確認しておきましょう。
受給の手続きをする
遺族年金を受給するまでに必要な手続きは、以下のとおりです。
- 必要書類を用意する
- 遺族年金の申し込み窓口で年金請求書を記入
- 必要書類とともに年金請求書を提出
- 書類提出後、2ヵ月以内に自宅に年金証書が届く
- 年金証書を受け取ってから1~2ヵ月後に年金の振り込みがスタート
遺族年金を受け取るためには、亡くなった日の翌日から5年以内に手続きを行う必要があります。期間内に請求しなければ、時効により受給権が消滅する可能性があるため、早めに手続きをしましょう。手続きに必要な書類は、前述した「5-1.必要書類を準備する」をご確認ください。
年金請求書の内容に不備があると、年金証書を受け取るまでに時間がかかってしまいます。提出書類の不備を減らすため、受付窓口の職員に相談しながら記入するとよいでしょう。
また、遺族年金を受け取る銀行口座にも注意が必要です。遺族年金の受け取り口座は、受給権を持つ方の名義でなければいけません。
亡くなった方の口座で申請すると受理してもらえないため、年金請求書を提出する前に記載されている口座の名義を確認しておきましょう。
自営業者が受け取れる可能性のあるもの

自営業の方が亡くなった場合、遺族厚生年金が受け取れないため、遺族の保障が不十分だと感じる方も多いでしょう。しかし、遺族基礎年金以外にも、遺族を守るための制度はあります。
ここでは、自営業の方が亡くなった場合に遺族基礎年金以外に受け取れるものについて解説します。
寡婦年金
寡婦年金は、死亡した夫がもらうはずだった老齢基礎年金の一部を妻が受け取れる公的年金です。国民年金の第1号被保険者として保険料を収めた期間(免除期間も含む)だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額が受給できます。ただし、寡婦年金を受給するためには、夫の条件と妻の条件を満たす必要があります。
寡婦年金を受け取る要件
| 対象者 | |
| 死亡した夫 | ・死亡日の前日において、死亡日の前月までの国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせてが10年以上ある ・老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ったことがない |
| 受け取る妻 | ・夫の死亡時に65歳未満 ・生計を同一にしており、妻の収入または所得が850万円未満 ・夫と10年以上継続して婚姻関係がある(内縁・事実婚でも可) ・自身が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受け取っていない |
参照元:日本年金機構「寡婦年金」
死亡一時金
死亡一時金とは、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていない自営業者が亡くなった場合に支給される一時金です。
死亡一時金を受給する要件
- 死亡日の前日において、死亡日の前月までの保険料納付済期間が36ヵ月以上あること
- 亡くなった方の要件を満たしていた場合、生計を同一にしていた遺族が受け取れる(優先順位あり)
死亡一時金を受け取れる遺族の優先順位は、以下のとおりです。
- 配偶者
- 子ども
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
死亡一時金で受け取れる額
保険料納付済期間ごとの金額は、以下のとおりです。
- 36ヵ月以上180ヵ月未満:120,000円
- 180ヵ月以上240ヵ月未満:145,000円
- 240ヵ月以上300ヵ月未満:170,000円
- 300ヵ月以上360ヵ月未満:220,000円
- 360ヵ月以上420ヵ月未満:270,000円
- 420ヵ月以上:320,000円
寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たしている場合、受け取れるのはどちらか一方のみです。どちらを受け取るべきか、状況に応じて検討しましょう。
参照元:日本年金機構「死亡一時金」
おわりに
遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、それぞれ受給要件や受給できる金額が異なります。特に、各遺族年金の受給期間について把握しておくことは大切です。
遺族基礎年金は、子どもが18歳を迎える年度末を過ぎると受け取れなくなります。一方、遺族厚生年金は、子どもの有無に関わらず、受給条件を満たしていれば受け取れます。各遺族年金をいつまで受け取れるか把握して、将来のライフプランを立てておくことも大切です。
ただし、受け取れる年金額の計算は複雑で、家族構成など個人の状況に応じて変わります。具体的な金額が気になる方は、市町村役場や年金事務所などで直接確認してみるとよいでしょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。