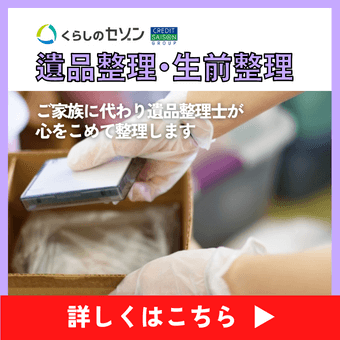現代社会では、パソコンやスマートフォンの普及により、写真や動画、SNSアカウント、ネット銀行など、多くの重要な情報がデジタル環境に保存されています。これらのデジタル遺品が適切に管理されないと、遺された家族に大きな負担をかける可能性があります。
そこで注目されているのが「デジタル終活」です。デジタル終活とは、万が一の際に備えて、デジタル機器やオンラインサービスの情報を生前に整理することを指します。この記事では、デジタル終活の基本知識から具体的な進め方、注意点まで分かりやすく解説します。
- デジタル終活とは、パソコンやスマートフォンに保存されたデータやオンラインアカウントを生前に整理すること
- デジタル遺品にはオンライン(SNS、ネット銀行)とオフライン(写真、動画)の2種類がある
- デジタル終活は洗い出し、仕分け、エンディングノートへの記録という3つのステップで進める
- パスワード管理と情報セキュリティの確保、家族への情報共有、定期的な見直しが重要
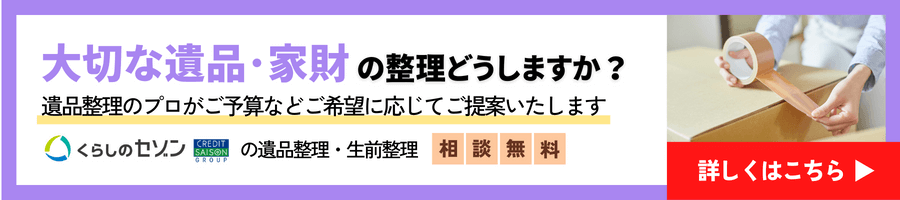
デジタル終活とは?基本と重要性

現代社会では、パソコンやスマートフォンの普及により、私たちの生活にデジタル技術が深く浸透しています。これに伴い、従来の終活に加えて「デジタル終活」という新しい考え方が重要になってきました。
デジタル終活とは、万が一の際に備えて、デジタル機器やインターネット上に保存されたデータを生前に整理することを指します。
以下では、デジタル終活の基本的な内容と、なぜ今注目されているのか、そして実践することで得られるメリットについて解説します。
デジタル終活とデジタル遺品の関係
デジタル終活を理解するためには、まず「デジタル遺品」について知っておく必要があります。デジタル遺品とは、故人が所有していたパソコンやスマートフォンなどのデジタル機器に保存されているデータや、インターネットサービスやSNSなどのログイン情報を指します。
具体的には、写真や動画のファイル、連絡先やメール本文のデータ、各種アプリやインターネットサービスのログイン情報、SNSのアカウント情報などが含まれます。これらのデジタル遺品は、従来の物理的な遺品とは異なり、目に見えない形で存在するため、遺族がその存在や内容を把握することが困難な場合があります。
デジタル終活は、こうしたデジタル遺品を遺さないよう、元気なうちにデジタルデータやアカウントなどの整理整頓を行うことです。デジタル遺品の増加が想定される現代において、適切なデジタル終活を行うことの重要性はますます高まっています。
なぜ今デジタル終活が注目されているのか
デジタル終活が注目される背景には、高齢者のデジタル機器の利用拡大があります。総務省の「令和6年版情報通信白書」によると、60歳以上のスマートフォン利用率や、インターネットやSNSの利用率が増加傾向にあり、多くの高齢者が日常的にデジタル機器を利用していることがわかります。
また、ネット銀行やネット証券といったオンライン金融サービスの口座数も各社の公表資料を見ると増加傾向にあることが明らかになっており、デジタル資産を保有する人々が着実に増えています。さらに政府は、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を掲げ、誰もがデジタル技術を活用して、自分に合ったサービスを選べる社会の実現を目指しています。年齢や住んでいる場所、ITスキルの有無に関わらず、すべての人が取り残されることなく安心して暮らせるデジタル社会の構築が進められています。
このようなデジタル社会の進展により、亡くなった後にデジタル遺品を遺す人も今後ますます増えていくと考えられます。それに伴い、自分の死後に備えてデジタル資産を整理・管理する「デジタル終活」の重要性もさらに高まっていくでしょう。
デジタル終活で得られるメリット
デジタル終活を実践することで、3つの重要なメリットを得ることができます。
1.遺産の相続漏れを防げる
ネット銀行やネット証券の口座がデジタル遺品として適切に整理されていない場合、遺産がその存在に気づかず、相続財産として申告されない恐れがあります。これにより、相続税申告後に税務署から申告漏れの指摘や税務調査が入り、延滞税や無申告加算税といったペナルティを受ける可能性があります。
2.経済的な損失を回避できる
株やFXなど価値が変動する金融資産は、放置している間に価値が下落し損失が発生することがあります。また、故人が契約していたサブスクリプションサービスを解約しなければ、利用料金の請求が続くため、無駄な出費を防ぐためにも事前の整理が有効です。
3.個人情報の悪用を防げる
インターネット上の個人情報を放置すると、詐欺集団などに悪用されるおそれがあります。例えば、SNSアカウントの乗っ取りにより、詐欺行為に利用されるケースがあり、家族や友人など身近な人が被害に遭う可能性もあります。
デジタル遺品の種類と整理方法

デジタル終活を効果的に進めるためには、まずデジタル遺品の種類を正しく理解することが重要です。デジタル遺品は大きく「オンライン」と「オフライン」の2つに分類でき、それぞれ異なる特徴と処理方法があります。また、適切な整理を行うためには、明確な基準を設けて「残すもの」と「処分するもの」を仕分けする必要があります。
ここでは、各種類の詳細な内容と、効率的な整理方法について解説します。
オンラインのデジタル遺品とは
オンラインのデジタル遺品とは、インターネット上に存在するサービスやアカウントを指します。
これらはWEBサービスの運営会社が関わるため、相続人だけでは処理ができない特徴があります。
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| SNSアカウント | X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、LINE |
| 金融関連サービス | ネット銀行(楽天銀行など)、ネット証券口座、FX口座、仮想通貨・暗号資産 |
| 有料サブスクリプション | 動画配信サービス、音楽配信サービス、定額課金アプリ |
| クラウドストレージ | iCloud、Googleドライブ、Dropbox |
| WEBサービス | ブログ、ホームページ、有料情報サイト |
| 電子決済サービス | QRコード決済、電子マネー |
| メールアカウント | Gmail、その他のメールサービス |
各サービスの利用停止やアカウント削除、データの取得などを行うには、サービスを提供する運営会社の利用規約に従った手続きが必要になります。これらの手続きを進めるには、故人との関係を証明する書類や法的な手続きが求められるケースも少なくありません。
オフラインのデジタル遺品とは
オフラインのデジタル遺品とは、パソコンやスマートフォンなど物理的な端末に保存されているデータを指します。基本的には、相続人が直接処理できるという特徴がありますが、パスワードやロック解除といったアクセス権の問題が生じるケースがあります。
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| デジタル機器 | パソコン、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ |
| 保存データ | 写真、動画、文書データ、日記 |
| 個人情報 | アドレス帳、連絡先情報 |
| 各種アプリ内データ | スマホ・PCアプリに保存されている情報 |
| 記録媒体 | USBメモリ、外付けハードディスク |
オフラインのデジタル遺品は第三者の関与を前提としていないため、相続人が直接管理・処理できますが、端末のロック解除やパスワードがわからない場合は、データへのアクセスが困難になり、大きな課題となることもあります。
デジタル遺品の整理基準
デジタル遺品を効率的に整理するためには、明確な基準を設けて「残すもの」と「処分するもの」に分類することが大切です。分類の際は、以下の4つの観点を基準に判断すると仕分けがしやすくなります。
1.見られたくないか/見てほしいか(プライバシーの観点)
・対象例:写真・動画・日記・メッセージ履歴などの保存データ
・判断基準:家族や親族に「見てほしい思い出」か、「死後も見られたくない個人的な記録」かで分類。
・対処:見てほしくないものは生前に削除、または保存場所と処理希望を明記しておく。
2.重要性・影響度の高さ(相続・経済的損失の観点)
・対象例:ネット銀行口座、証券口座、仮想通貨ウォレット、有料サブスク契約
・判断基準:相続財産に該当するか、死後も費用が発生する契約があるか。
・ 対処:ログイン情報や契約内容をリスト化し、信頼できる家族に伝えておく。
3. 使用頻度・価値の有無(実用性の観点)
・対象例:アプリデータ、クラウドストレージ、連絡先、文書ファイル
・判断基準:日常的に使用していたか、他者にも有益か(例:仕事関係データ、住所録)。
・対処:必要性があるものは保管・共有し、不要なデータは削除・解約。
4. アクセス可能性(技術的制約の観点)
・対象例:パスワード付き端末、暗号化された記録媒体、クラウドサービス
・判断基準:相続人がアクセスできるか(パスワードや認証情報があるか)。
・対処:パスワード管理表の作成や、デジタル遺言書などへの明記が有効。
こうした基準を参考にしながら、定期的にデータを見直しておくことで、いざというときに家族の負担を減らすことができます。
デジタル終活の具体的な進め方

デジタル終活は適切な手順を踏むことで、遺された家族の負担を軽減し、重要な情報の漏れや手続き上の混乱を防ぐことができます。そのためには、「洗い出し」「仕分け」「記録」の3つの3つのステップに分けて実施するのが効率的です。
以下では、それぞれのステップの具体的な方法と注意点について解説します。
ステップ1:保有するデジタル遺品を洗い出す
まず、自分がどのようなデジタル遺品を保有しているのか、全体を把握することから始めましょう。
・写真や動画ファイル
パソコン・スマートフォン・タブレット・クラウドストレージ・USBメモリなどを確認します。
・電話番号やメールアドレスなどの連絡先
スマートフォン・パソコンの電話帳アプリなどを確認します。
・メールデータ
スマートフォン・パソコン・タブレットに標準搭載されているメールの受信フォルダや、Gmailなどのクラウド型のメールサービスの受信フォルダを確認します。
・アカウント情報
ブックマークやインターネットの閲覧履歴、銀行口座の引き落とし履歴などを調べることで漏れなく利用しているサービスを特定できます。
各項目をチェックしながらメモしていくと、整理がしやすくなります。
ステップ2:残すものと処分するものを仕分ける
洗い出したデジタル遺品を「残すもの」と「処分するもの」に仕分けていきます。残すものが多い場合は、「必ず残すもの」「必ず隠すもの」「できるだけ残したいもの」「できるだけ隠したいもの」など、重要度やプライバシーの観点に応じて細かく分類すると整理しやすくなります。
残したいデータを無理に処分する必要はありませんが、今後の管理や家族の負担を考えたうえで、適度にデータを減らしておくことも大切です。他人に見られたくないものを残す場合は、専用の保管場所を用意し、パスワードを設定しておくと安心でしょう。仕分けをしながら削除や解約の作業を同時に行うと混乱する可能性があるため、仕分けが終わった後に削除・解約を行うようにしましょう。
ステップ3:エンディングノートに情報をまとめる
デジタル遺品の整理が完了したら、重要な情報をエンディングノートにまとめます。これにより、遺された家族がスムーズに手続きを進めることができます。
記載すべき情報は、以下のような内容です。
- スマートフォンやパソコンのパスコード
- 利用しているサービスの名称やログイン情報
- SNSのアカウント情報
- ネット銀行やネット証券の金融口座情報
英数字・記号が混在したパスワードを設定している場合は、大文字、小文字の違いや記号の種類が一目でわかるよう丁寧に記載しましょう。
エンディングノートは手書きで作成しても問題ありませんが、パソコンを使ってインターネット上の無料テンプレートなどを活用することで、整然として読みやすい仕上がりになります。
デジタル終活で気をつけること

デジタル終活は、適切な情報管理を行わなければ、かえって家族に負担をかけたり、セキュリティリスクを高めたりする可能性もあります。また、デジタル技術の進歩やサービスの変化に対応するため、継続的な管理も欠かせません。
以下では、デジタル終活を安全かつ効果的に行うために注意すべきポイントについて説明します。
パスワード管理と情報セキュリティを確保する
ネット銀行のログイン情報など、デジタル終活で整理した重要な情報は、保管方法に十分注意する必要があります。自宅に金庫を用意するなど、財産に関する重要な情報は人目につかない場所に保管し、情報漏えいを防ぐための工夫を行いましょう。
身近な人に預けるのも、情報漏えいのリスクがあるためおすすめできません。重要な情報が第三者の手に渡ると、不正利用や悪用につながる危険性があります。金庫や貸金庫など、セキュリティが確保された場所で保管することが重要です。適切な保管場所を選択することで、情報の安全性を保ちながら、必要な時に家族がアクセスできる環境を整えることができます。
エンディングノートの所在を家族に伝える
デジタル終活でエンディングノートを作成したとしても、家族がエンディングノートの存在に気付かなければ、適切な対応を取ることができません。重要な情報が記載してあるからといって、誰にも所在を知らせずに隠してしまうと、死後に発見されないおそれがあります。
デジタル終活を行ったことや、具体的なデジタル終活の内容、エンディングノートの保管場所を可能な範囲で家族に伝えておくと良いでしょう。完全に秘匿するのではなく、信頼できる家族や親族に最低限の情報を共有しておくことで、万が一の際にスムーズな対応が可能になります。情報の機密性を保ちながらも、必要な時に発見してもらえるバランスを取ることが大切です。
定期的な見直しと更新を習慣にする
デジタル終活は、一度行えば終わりというものではありません。デジタルデータの内容は時間の経過とともに変化するため、定期的な見直しと更新が必要です。見直しのたびに、必要な情報の整理や不要データの削除・処分を行い、常に最新の状態を保ちましょう。
定期的な見直しの際は、次のようなポイントを確認しましょう。「残したいデータや処分してほしいデータが増えていないか」「新たに利用を始めたサービスがないか」「ログインIDやパスワードを変更した項目がないか」といった点です。こうした変更があった場合は、エンディングノートの内容も忘れずに更新しておくことが大切です。
定期的なメンテナンスを習慣化することで、常に最新の状態でデジタル終活を維持することができ、家族への負担を最小限に抑えることが可能になります。
デジタル遺品の放置によるリスクと対策

デジタル遺品を適切に処理せずに放置してしまうと、さまざまなトラブルや損失を招く可能性があります。特に、ネット銀行やネット証券の存在を見落とした場合の相続税の申告漏れ、サブスクリプションサービスの継続課金、SNSアカウントの不正利用などは、深刻な問題に発展するケースが実際に報告されています。
以下では、具体的なリスクと効果的な対策について解説します。
相続税の申告漏れ
ネット銀行やネット証券の口座が相続税の申告から漏れてしまった場合、税務調査の対象となり、延滞税、無申告加算税といった深刻なペナルティが発生する可能性があります。
実際の事例として、父親が亡くなった後に税務調査が入った遺族のケースがあります。
亡くなった父親はデジタル機器が苦手で、安否確認のためにスマートフォンを持っていたものの、実はネット銀行とネット証券を利用していたことが後に判明しました。相続税の申告を終えた後、税務署から税務調査の連絡が入り、インターネット上の金融資産の存在が明らかになったことで、申告漏れが発覚。結果として、遺族は加算税などのペナルティを課されることになりました。
このような相続税の申告漏れを防ぐためにも、デジタル終活の段階ですべての金融機関の口座情報を整理し、家族に正確に伝えておくことが重要です。
解約忘れによる継続課金の問題
サブスクリプションサービスは、自動的に解約されないため、相続人が解約手続きを行わない限り支払いが続くという問題があります。
例として、60代の男性が亡くなった兄の遺品整理を進めていた際に、クレジットカードの解約手続きをしようとしたところ、カード会社から「何らかのサービスの引き落としが続いているため解約できない」と言われました。調査を進めた結果、動画配信サービスや英会話アプリの月額サービスの支払いが続いていることが判明し、それらの退会手続きを行った後、ようやくクレジットカードを解約が完了しました。
このような問題を防ぐためには、生前に利用しているサブスクリプションサービスをリスト化し、定期的に見直して不要なサービスは解約しておくことが大切です。
SNSアカウントの乗っ取りとなりすまし被害
SNSアカウントが乗っ取られた場合、プライバシーの侵害や詐欺被害につながる深刻なリスクがあります。実際の事例として、男子高校生が、ある事件により死亡した人のX(旧Twitter)のアカウントを乗っ取り、なりすましを行った事件があります。
まるで生存しているような投稿や、ハッカー集団であることをほのめかす投稿をしていたことが判明し、不正アクセス禁止法違反で逮捕されました。このような被害を防ぐためには、SNSアカウントの適切な処理が必要です。X、Instagram、Facebook、LINEなど各サービスには故人のアカウント削除や追悼アカウント設定の手続きが用意されているため、生前に家族にその方法を伝えておくことが重要です。
くらしのセゾンで安心のデジタル遺品整理サポート
くらしのセゾンでは、デジタル遺品を含む総合的な「遺品整理・生前整理」サービスを提供しています。相続トラブルを防ぐための事前整理や、故人が遺したデジタル機器の対応まで丁寧にサポートします。
特にデジタル遺品については、以下のようなお困りごとに対応可能です。
- ロック解除・パスワードの調査
- 起動しないパソコンからのデータ復旧
- プライバシーに配慮したデータの完全消去
デジタル終活のサポートは、デジタル機器に精通した専門スタッフによる対応のため、安心してお任せいただけます。
また、生前整理・空家整理・リフォームなど、人生のさまざまな転機に寄り添う幅広いサービスを展開しています。親世代・ご自身のために、デジタル遺品を含めた「終活」を少しずつ始めてみませんか。
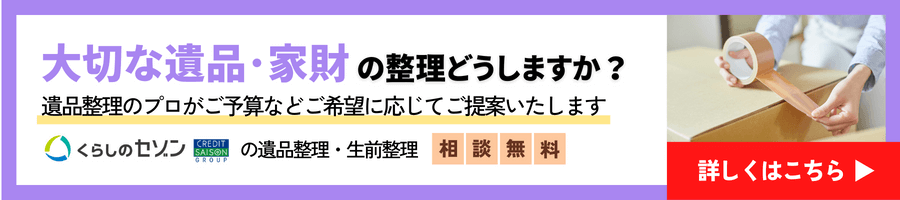
おわりに
デジタル時代において、デジタル終活は誰もが取り組むべき重要な課題です。高齢者のデジタル機器利用率が急速に増加し、ネット銀行や各種オンラインサービスが普及する現代において、適切なデジタル遺品の管理なしには、遺族が深刻なトラブルに直面するリスクが高まっています。デジタル終活に取り組むことで、相続税申告漏れや継続課金などの経済的損失を防ぎ、個人情報の悪用リスクを軽減できます。計画的にデジタル終活を進めることで、大切な家族に負担をかけることなく、安心して人生の最期を迎えることができるでしょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。