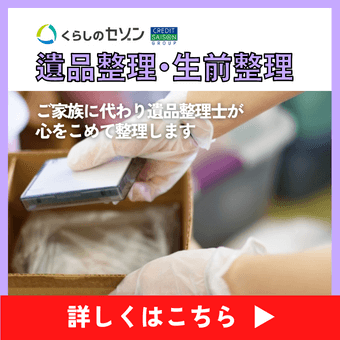人生の終わりについて考えることは、誰にとっても避けては通れないテーマです。「もしものとき、家族に迷惑をかけたくない」「何から準備すればよいのか分からない」と不安になる方も多いでしょう。
この記事では、死ぬ前に準備すべきことを具体的にリストで整理。財産やデジタル情報の整理から、医療・介護・葬儀の希望、家族への想いの伝え方まで、今からできる準備を分かりやすく解説します。
- 死ぬ前に準備すべき4つの主要カテゴリーと各項目の具体的な内容
- デジタル遺品の放置リスクと、IDパスワードを安全に家族と共有する方法
- 生前整理を効率的に進めるための5つのステップと、体力があるうちに大きなものから片付けを始めることの重要性
- 自分だけで生前整理が困難な場合に利用できる専門業者のサービス内容と、業者選びの際の確認ポイント
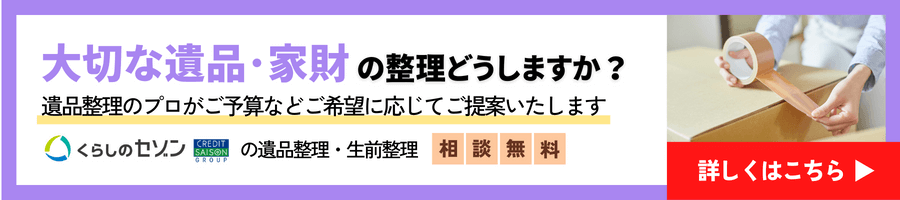
残りの人生をより良く生きるための準備とは

病気や身近な人の死を経験すると、自分の「死」について真剣に考え始めます。不安や恐怖を感じるのは自然なことですが、この機会を前向きにとらえることが大切です。
事前の準備は、残される家族の負担を軽くするだけではありません。銀行口座の解約手続きや遺品整理など、家族が行わなければならない手続きは想像以上に多く、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。しかし、きちんと準備をしておけば、家族は悲しみに向き合う時間を十分に持てるようになるでしょう。
さらに重要なのは、準備を通じてご自身のこれからの人生を見つめ直せることです。終活は決して後ろ向きな活動ではありません。これまでの人生を振り返り、本当に大切なものは何か、残された時間をどう過ごしたいかを考える貴重な機会となります。多くの方が終活を通じて新たな目標を見つけ、より充実した日々を送るようになっています。
死ぬ前にやっておきたいことリスト

これから紹介する「死ぬ前にすること」を分かりやすく一覧にまとめました。大きく4つのカテゴリーに分けて、それぞれで必要な準備項目を示しています。
| カテゴリー | 具体的にやること |
|---|---|
| 財産・持ち物 | ・財産の整理:預貯金や不動産、借入金などをまとめた「財産目録」を作成する。 ・身辺整理:不要な家財や使っていない家電などを処分する。 ・貴重品の整理:保険証書や印鑑、預金通帳などをまとめて保管する。 |
| デジタル情報・契約 | ・デジタルデータの整理:PCやスマホ内のデータやSNSアカウントを整理する。家族に伝えたいデータは分かりやすく保管し、見られたくないデータはロックをかけるか削除する。 ・不要なサービスの解約:利用していないサブスクリプションサービスなどを解約する。 |
| 医療・介護・葬儀 | ・医療・介護の意思表示:延命治療の希望の有無などをエンディングノートや書類に記す。 ・身元保証人の決定:頼れる人がいない場合は、身元保証会社などを検討する。 ・葬儀・埋葬の準備:葬儀の希望や参列してほしい人の連絡先などをリストアップする。 |
| 想いを伝える準備 | ・エンディングノートの作成:ご自身の情報や家族へのメッセージなどを書き記す。 ・遺言書の作成:法的な効力を持たせて財産の分配や相続に関することを記す。 |
それぞれの項目について、以下で詳しく解説していきます。
財産・持ち物に関する整理
まず取り組むべきは、ご自身の財産をすべて把握することです。預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借入金といったマイナスの財産も含めて「財産目録」を作成しましょう。
財産目録があれば、相続手続きがスムーズに進みます。特に重要なのは、複数の金融機関に分散している口座情報を一覧にすることです。使用していない銀行口座やクレジットカードは、この機会に解約しておくとよいでしょう。毎月引き落とされているサブスクリプションサービスも見直し、不要なものは解約することで、死後の手続きの煩雑さを大幅に減らせます。
思い出の品の整理も大切な作業です。写真アルバムや手紙、長年愛用してきた趣味の道具など、思い入れのある品々については「残す」「家族や友人に譲る」「処分する」の3つに分類していきます。処分する際も、お寺での供養という選択肢があることを知っておくとよいでしょう。整理を進める中で、家族と思い出話に花を咲かせるのも素敵な時間となります。
デジタル情報・契約に関する整理
現代社会では、スマートフォンやパソコンに保存されたデータも重要な遺品となっています。これらは「デジタル遺品」と呼ばれ、写真や動画、SNSのアカウント、ネット銀行の口座情報などが含まれます。
放置すると、SNSアカウントの乗っ取りやネット銀行の不正利用といったリスクがあります。家族がアクセスできないまま、有料サービスの料金が引き落とされ続けるケースも少なくありません。
IDやパスワードは、信頼できる家族と共有する必要がありますが、同時にセキュリティも重要です。パスワードを暗号化して保管し、解読方法を別途伝えるといった工夫が必要でしょう。見られたくないプライベートな情報は、あらかじめ削除するか、自動削除ソフトを活用する方法もあります。
生命保険や損害保険の契約内容も整理が必要です。保険証券の保管場所を家族と共有し、契約内容を一覧表にまとめておきましょう。受取人の変更が必要な場合は、早めに手続きを済ませることが大切です。
医療・介護・葬儀に関する意思表示
突然の病気や事故で意思表示ができなくなる可能性は誰にでもあります。延命治療を希望するかどうか、どこで最期を迎えたいかなど、医療・介護に関する希望は明確にしておきましょう。
リビング・ウィルと呼ばれる書面に希望を記載し、家族や主治医と共有しておくことで、ご自身の意思が尊重されやすくなります。「人工呼吸器は使用しないでほしい」「できるだけ自宅で過ごしたい」など、具体的に記載することが重要です。
葬儀についても、家族の負担を減らすために希望をまとめておきましょう。一般葬にするか家族葬にするか、呼んでほしい人は誰か、宗教的な儀式は必要かなど、詳細に記録しておくと家族が迷わずに済みます。
お墓についても選択肢が増えています。従来の墓石だけでなく、樹木葬や散骨、永代供養など、さまざまな方法があります。費用面でも大きな違いがあるため、家族と相談しながら決めていくとよいでしょう。生前にお墓を準備する「生前墓」も選択肢の一つです。
家族・友人への想いを伝える準備
遺言書とエンディングノートは、それぞれ異なる役割を持っています。以下の表で、両者の違いを確認してみましょう。
| 比較項目 | 遺言書 | エンディングノート |
|---|---|---|
| 法的効力 | あり 法律で定められた様式で作成する必要があり、相続において最優先される。 | なし 法的な強制力はないため、家族への希望を伝えるメッセージとしての役割が主となる。 |
| 記載内容 | 死後の相続に関する希望や思いを記す。 ・財産の分け方など、相続に関する内容に限定される。 ・生前のことについては書けない。 | 生前のことから死後のことまで自由に記せる。 ・自身の人生の振り返りや家族へのメッセージ。 ・介護や医療、葬儀に関する希望。 ・友人や知人の連絡先、ペットのことなど。 |
| 作成方法 | 法的に定められた形式で作成する必要がある。 ・自筆証書遺言:本人が自筆で作成する。 ・公正証書遺言:公証人が作成し、公証役場で保管される。 ・秘密証書遺言:作成した遺言書を公証役場で保証してもらう。 | 決まった形式はなく、自由に作成できる。 市販のノートや便箋、デジタルデータなど、ご自身がやりやすい方法で作成可能。 |
| 主な目的 | 相続トラブルを防ぎ、ご自身の望む相続を実現する。 | 家族が困らないように情報を引き継ぎ、想いを伝える。また、ご自身の人生を振り返るきっかけにもなる。 |
エンディングノートには、家族への感謝の気持ちや、これまでの人生の思い出を自由に綴ることができます。残された家族にとって、故人の想いが詰まったノートは何物にも代えがたい宝物となるでしょう。
訃報を伝えてほしい友人・知人のリストも重要です。年賀状のやり取りがある方、趣味の仲間、昔の同僚など、連絡先を整理しておきましょう。家族が知らない交友関係もあるはずですから、詳しく記載しておくことが大切です。
家族への負担を減らす「生前整理」という考え方
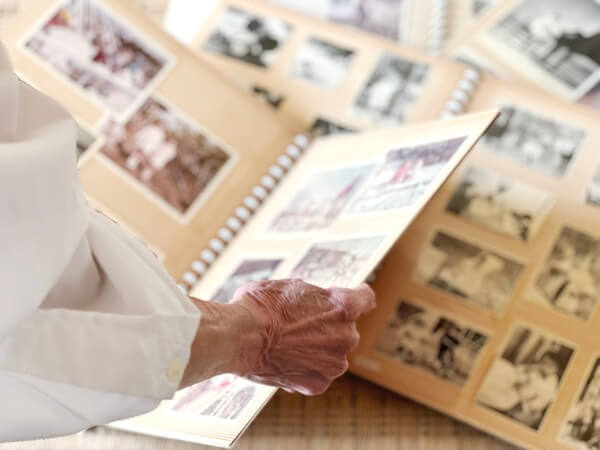
故人が亡くなった後、残された家族は悲しみの中で膨大な遺品整理に直面します。思い出の詰まった品々を仕分けし、処分することは、精神的にも肉体的にも想像以上の負担となります。家族は故人を偲ぶ時間も十分に取れないまま、片付けに追われることになってしまいます。
生前整理は、こうした家族の負担を大幅に軽減できるだけでなく、ご自身にとってもメリットがあります。物が少なく整理された空間で暮らすことで、転倒などの事故リスクが減り、掃除も楽になります。必要なものがすぐに見つかる環境は、日々のストレスを軽減してくれるでしょう。
生前整理を始めるタイミングとして最適なのは、定年退職した時、子どもが独立した時、引っ越しを考えている時などです。体力と判断力が十分にあるうちに始めることで、後悔のない選択ができます。
なぜ家の中の片付けが重要なのか
実際に遺品整理を経験した方の多くが「もっと早く片付けておけばよかった」と後悔しています。
物が多い家では、重要な書類を探すだけでも一苦労です。通帳や保険証券が見つからず、相続手続きが滞ることも珍しくありません。体力的にも、重い家具を動かしたり、大量の不用品を処分したりする作業は、高齢の家族には大きな負担となります。
一方で、物が少なく整理された空間は、ご自身の生活の質を向上させます。必要なものだけに囲まれた生活は、心にゆとりをもたらし、本当に大切なことに時間を使えるようになります。体力や判断力があるうちに始めることで、一つ一つの品物と向き合い、納得のいく選択ができるでしょう。
生前整理をスムーズに進めるための手順
生前整理を効率的に進めるには、正しい手順を踏むことが大切です。まず、家の中にあるものを「残すもの」「不要なもの」「保留するもの」の3つに分類します。迷ったものは一旦「保留」にして、時間をおいて再度判断するとよいでしょう。
効率的な片付けの手順は以下の通りです。
- ステップ1:大きなものから始める
家具や家電など、部屋の中で場所を取っているものから整理を始めます。これらを片付けると、部屋が広くなったと実感でき、モチベーションが上がります。 - ステップ2:必要/不要/保留の3分類で仕分け
1年以上使っていないものは、基本的に不要と判断してよいでしょう。ただし、季節の行事や冠婚葬祭など特別な場面で使うものは例外として考えます。 - ステップ3:不要品を処分
リサイクルショップへの売却、自治体の粗大ごみ回収、不用品回収業者の利用など、処分方法を検討します。思い出の品は写真に撮ってから処分する方法もあります。 - ステップ4:細かいものを整理し、保管場所を明確化
書類、写真、小物類など、細かいものの整理を行います。重要書類は一箇所にまとめ、家族にも保管場所を伝えておきます。 - ステップ5:デジタルデータを整理・バックアップ
パソコンやスマートフォン内のデータも整理します。不要なファイルは削除し、大切なデータはバックアップを取っておきます。
生前整理は一人で抱え込まず、家族に相談しながら進めることが大切です。思い出話をしながら作業を進めれば、家族の絆も深まるでしょう。また、一度決めたことも状況に応じて見直す柔軟性を持つことで、より良い選択ができます。
自分で行うのが難しい場合は専門家の力を借りる選択も

長年住み慣れた家には、想像以上に多くの物が蓄積されています。重い家具の移動や大量の不用品の処分は、高齢の方や体力に自信のない方にとって大きな負担となります。
専門業者に依頼することで、短時間で効率的に片付けを進められます。プロの手を借りれば、通常なら数か月かかる作業も数日で完了することが可能です。体力的な負担が軽減されるだけでなく、適切な処分方法のアドバイスも受けられます。
業者選びでは、見積もりの内容が明確であること、遺品整理士などの資格を持つスタッフがいることを確認しましょう。信頼できる業者は、依頼者の気持ちに寄り添いながら、丁寧に作業を進めてくれます。
【くらしのセゾン】の遺品整理・生前整理でできること
くらしのセゾンの「遺品整理・生前整理」サービスでは、遺品整理士の資格を持つ専門スタッフが、一つ一つ丁寧に仕分けと搬出をサポートします。
サービスは無料の現地調査とお見積りからスタートします。予算や状況に応じて、最適なプランを提案してくれるため、初めて利用する方でも安心です。作業内容には、必要品と不用品の仕分け、梱包、搬出、簡易清掃まで含まれており、依頼者の負担を最小限に抑えます。
「実家が遠方で片付けに行けない」「重いものを自分で運び出せない」「何から手をつけていいか分からない」といったお悩みを抱える方々が数多く利用しています。たとえば、70代の女性が施設入居に伴い2DKのアパートの家財整理を依頼されたケースでは、4名のスタッフが6時間で作業を完了し、「一人では到底できなかった。本当に助かりました」と感謝の声が寄せられています。
また、デジタル終活にも対応しており、パソコンやスマートフォン内のデータ整理についてもサポートがあります。個々の状況に合わせて、柔軟に対応してくれるサービスとして評価されています。
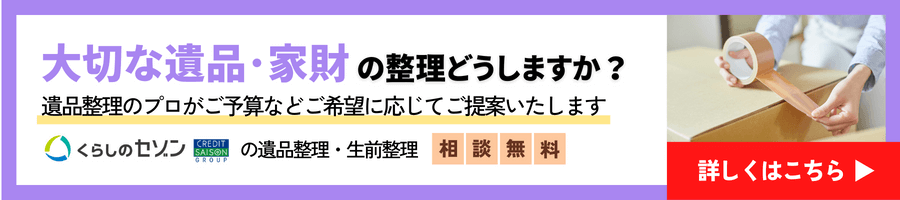
おわりに
死ぬ前にやることは、未来を悲観するためではなく、今日を安心して生きるための準備です。
財産や持ち物、そして大切な人への想いを整理することで、あなた自身も、家族も、心穏やかに過ごせる時間が増えます。できることからひとつずつ。前向きに過ごすための第一歩を、今日から踏み出してみませんか。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。