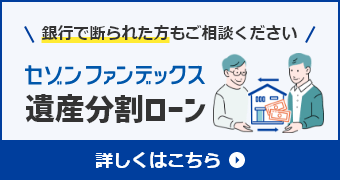相続人が複数いて相続財産の多くが不動産で預金などの現金が少ない場合、財産をどのように分けるかが問題になることがあります。そのような場合の解決方法として「代償分割」が選ばれることが多いです。
代償分割とは、不動産などの分割しにくい財産を相続した相続人が他の相続人に現金を支払い公平に相続財産を分ける方法です。代償分割を選択することが決まった際、手元に現金がなかったらどうすれば良いでしょうか。
相続財産の内容によっては、支払う金額が高額になる可能性があります。また、一般的な不動産売買と違い、親族間でのやり取りは適切に手続きを行わないと贈与とみなされ、余計な税金が発生するおそれもあります。
本記事では、代償分割で現金がないときの6つの対処法と注意点を解説します。あわせて、代償分割時の相続税の計算方法も説明しているので、ぜひ参考にしてください。あらかじめ対処法を知っておけば、相続時のトラブルリスクを最低限に抑えられます。
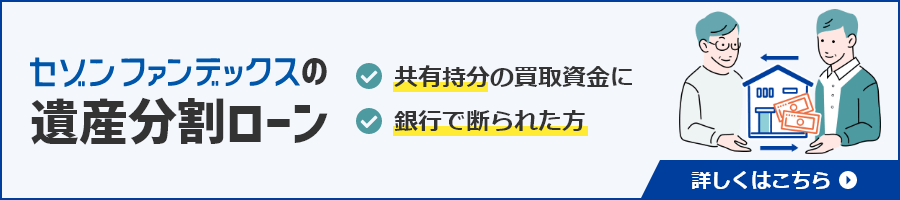
代償分割で支払う現金がないときの6つの対処法

代償分割で現金が用意できないときの対処法は、以下の6つです。
- 分割支払いにする
- ほかの資産を現金の代わりにする
- 不動産担保ローンを利用する
- 現物分割や換価分割を検討する
- 土地を分筆する
- 生命保険を活用して生前対策する
代償分割を行うケースは、不動産を相続人のひとりが引き継ぎ、その代わりにほかの相続人に対して持ち分に応じた現金を支払うという場合が多いです。しかし、不動産の評価額が高額であったり、相続人の数が多かったりすると、相応の現金を用意できないケースもあります。そうした場合に備えて、以下の対処法をあらかじめ知っておき、トラブルに備えておきましょう。
分割支払いにする
代償分割における代償金は一括払いが原則ですが、相続人全員の合意があれば分割で支払うこともできます。ただし合意をとる際は、後々のトラブルを防ぐためにも「分割で支払う旨」「支払い方法」や「期限」などの内容を遺産分割協議書に明確に記載しましょう。
ほかの資産を現金の代わりにする
現金を用意できない場合には、不動産や株式など、現金以外の財産で代償金を支払う方法もあります。たとえば、相続財産とは別に保有している不動産や株式を代わりに提供するケースです。
ただし、代わりに提供する財産の価値は、現金と同等である必要があり、他の相続人の合意が必要です。また、財産の評価額は客観的かつ正確に算出する必要がありますので、相続に詳しい司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
不動産担保ローンを利用する
代償金の支払い資金として、不動産担保ローンを利用する方法もあります。相続した不動産を担保として提供することで、無担保ローンと比べて高額な融資を受けることが可能です。
融資を受けた本人は、その資金でほかの相続人に代償金を支払い、以降はローンの返済を続けていく形になります。ただし、不動産担保ローンは通常の住宅ローンに比べて金利が高く(3〜15%程度)、利息負担が大きくなる点には注意が必要です。利用する前に必ず返済計画を立てて、無理なく返済できるか確認しておきましょう。
どの不動産担保ローンを使うべきか迷っているなら、セゾンファンデックスの「フリーローン(不動産担保)」がおすすめです。資金使途が自由で、代償金の支払いに利用可能。さらに、最短3営業日で審査が完了するスピード感も魅力です。ただし、担保とする不動産に居住している場合には、原則ご利用いただけません。ご利用条件などを事前にご確認ください。
現物分割や換価分割を検討する
現金を用意できない場合には、次のような遺産分割方法も検討しましょう。
- 現物分割:財産をそのままの形で分割する方法。たとえば、土地を分筆して相続人ごとに分けます。売却の手間がかからないというメリットがありますが、土地の価値に差があると不公平になりやすい点に注意が必要です。
- 換価分割:財産を売却して現金化し、その代金を相続人に分配する方法。たとえば、600万円で売却した土地を3人で分ければ、それぞれ200万円ずつ受け取ることができます。公平性の高い方法ですが、売却には手間や費用がかかり、思い入れのある財産を手放すことになるデメリットもあります。
いずれの方法も、相続人全員の合意が必要です。不公平感が生じないよう、慎重に検討しましょう。
土地を分筆する
現物分割の方法として、土地を分筆して相続する方法について、もう少し詳しく説明しましょう。ひとつの土地を複数の独立した土地として分割し、それぞれを登記すること分筆といいます。これは、代償金の支払いなしに公平な分割を実現できる方法です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 土地の形状や立地によっては均等に分割できず、不公平感が生じる可能性がある
- 測量・境界確定・移転登記などの費用が発生し、50〜100万円以上かかるケースもある
- 自治体によっては最低敷地面積の規制があり、分筆後に建物が建てられない可能性もある
- 不合理分割とみなされると、かえって土地の評価が上がり、相続税負担が増えるおそれがある
こうしたリスクを避けるためにも、土地の分筆については相続や不動産に詳しい専門家へ相談するのが安心です。
生命保険を活用して生前対策する
生命保険を活用することで、相続時の不公平感を和らげる「代償分割」の準備が可能です。
例えば、長男に自宅を相続させたい場合、生前のうちに他の相続人を受取人とした生命保険に加入しておくことで、長男が現金を用意せずに済みます。保険金を受け取った他の相続人は、その分を代償金として受け取ることになり、遺産分割における不公平感を減らせます。
また、生命保険金は受取人固有の財産として扱われ、他の相続人の合意を得ることなく受け取れる点も魅力です。保険金は現金で支払われるため、代償金に充てやすいといえます。
さらに、契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が法定相続人である場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。現金のまま相続するよりも節税効果が期待でき、生前対策として有効です。
ただし、生命保険の活用はあくまでも生前対策のひとつですので、相続が発生してからでは利用できません。早めに検討・準備をしておくことが重要です。
現金がない時に行う代償分割の注意点

代償分割で支払う現金が不足している場合、次の5つの点には注意しましょう。
- 分割払いは滞納されるリスクがある
- 現金以外で代償するときは譲渡所得課税が発生する可能性がある
- 建物の取得費から減価償却費を控除する
- 遺産分割協議書に分割内容を明記する
- 共有分割はできるだけ避ける
どのような方法をとっても、相続人同士の合意や税務面など、しっかり確認する必要があります。
分割払いは滞納されるリスクがある
代償金の支払いを分割払いにすると、途中で支払いが滞るリスクがあります。遅れても最終的に支払ってもらえれば良いのですが、資金が不足した場合や支払う気持ちがなくなったなどの理由であれば支払ってもらえないかもしれません。
滞納が発生した場合、最終的には弁護士や裁判所を介して強制執行という手段も視野に入ります。特に、遺産分割協議書を公正証書にしておけば、強制執行がしやすくなりますが、それでも全額を回収できるとはかぎりません。最悪の場合、未払分を一切回収できないケースもあります。
分割払いを認めるのであれば、支払者の返済能力を十分に確認したうえで、滞納リスクに備える必要があります。
また、不動産の共有持分を代償分割する場合は、必ず代償金を受け取ってから移転登記を行ってください。先に登記してしまうと、代償金の支払いを先送りされるおそれがあります。一方で、登記が済んでいなければ不動産の利用に制限がかかるため、支払者にとっても代償金を早期に支払う動機になります。
現金以外で代償するときは譲渡所得課税が発生する可能性がある
代償金を現金以外の資産(不動産や株式など)で支払った場合、その資産は「譲渡」とみなされ、譲渡所得に対する税金(内訳は所得税と住民税で、以降は「譲渡所得税」と記載)が課税される可能性があります。
譲渡所得金額は、
「代償分割時の時価 – (取得費用 + 譲渡費用)」
で求められ、譲渡所得(利益)が発生した場合は課税対象となります。例えば、長男が1,500万円で土地を手に入れていて、その時価が3,000万円になっていたとしましょう。その後、その土地を次男への代償金に充てて、譲渡費用が300万円かかった場合、1,200万円が譲渡所得となります。その分の譲渡所得税が長男にかかってしまいます。
また、譲渡所得はほかの所得と合算しない分離課税が適用されます。他の所得と相殺して税額を抑えることはできません。
さらに、土地などの不動産で代償分割を行う場合、譲渡する側だけでなく、土地を受け取った側に所有権移転登記や不動産取得税などの費用が発生するため、現金に比べて双方の金銭的な負担が大きくなる傾向があります。
建物の取得費から減価償却費を控除する
現物分割や現金の代わりに不動産を受け取る場合、その取得費から建物部分の減価償却費を控除する必要があります。
減価償却費は「建物の取得費 × 0.9 × 償却率 × 経過年数」で算出することが可能です。
償却率は建物の構造によって異なり、主な例は以下の通りです。
| 建物の構造 | 償却率 |
|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造 | 0.015 |
| れんが造または石造またはブロック造 | 0.018 |
| 骨格材の肉厚4mm超の金属造 | 0.020 |
| 骨格材の肉厚3mm超4mm以下の金属造 | 0.025 |
| 骨格材の肉厚3mm以下の金属造 | 0.036 |
| 木造または合成樹脂造 | 0.031 |
| 木骨モルタル造 | 0.034 |
詳細は国税庁のWEBサイトにて確認してください。
例えば、鉄筋コンクリート造の建物の取得費が3,000万円で、経過年数が8年であれば、減価償却費は324万円です。
なお、取得費が不明な場合は、譲渡費用の5%を取得費とすることができます。
遺産分割協議書に分割内容を明記する
代償分割を行う際は、遺産分割協議書にその内容を明記しておく必要があります。記載が不十分だと、代償金の支払いが「贈与」とみなされ、贈与税が課される可能性があります。
ここで注意すべきなのは、相続税と贈与税では税率が大きく異なり、たとえば贈与税は3,000万円超で最高税率55%が適用されます。これは相続税の6億円超と同じ最高税率であるため、記載漏れによって不要な税負担が発生するリスクは無視できません。
このような事態を避けるために遺産分割協議書には代償分割を行う旨をきちんと明記しておきましょう。
共有分割はできるだけ避ける
代償金の用意が難しい場合に共有分割(不動産を複数人の共有名義にする方法)を選ぶケースがありますが、できるだけ避けた方がよい手法です。
現金の支払いを発生させず、一見すると公平に見えますが、以下のようなデメリットが多数あります。
- 将来的に所有者が増えていってしまう可能性がある
- 不動産すべてを売却するには所有者全員の同意が必要となる
- 共有持分のみ売却することは難しい
- 不動産の活用も所有者の過半数の同意が求められる
共有相手との合意が取れなければ、不動産の売却や取り壊し、賃貸に出すなども一切できなくなってしまいます。その意思決定にあたって、将来的に共有相手と揉めてしまう可能性があるため、安易に共有分割をするのは危険です。
遺産分割せず不動産を共有相続した場合の対処法
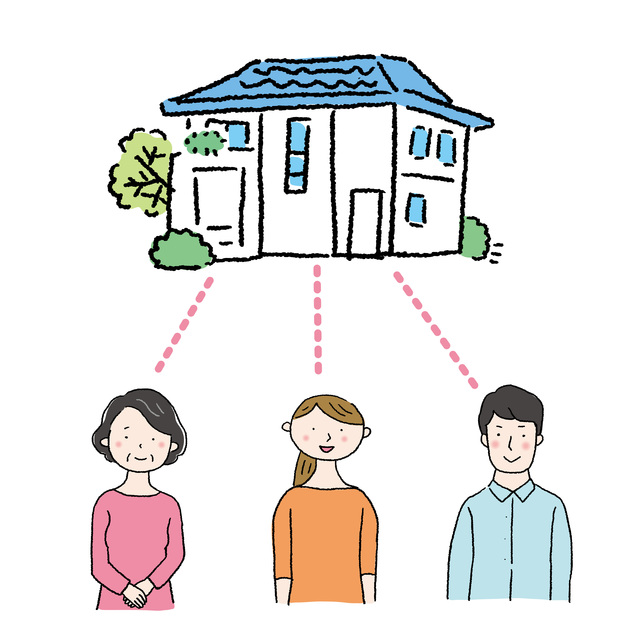
不動産を共有相続してしまった場合は、他の相続人の共有持分を買い取ることで、共有状態を解消できます。共有状態を解消すれば、不動産を自由に売却したり、単独で活用したりすることが可能になります。
ただし、共有持分の買い取りにはまとまった資金が必要となるため、経済的な負担が大きく、すぐに実行できないという方も少なくありません。
そのような場合には、セゾンファンデックスの「遺産分割ローン」の利用を検討してみてください。このローンは、共有名義の不動産について他の相続人の持分を買い取る際に利用でき、たとえば、複数人で相続した自宅に1人で住み続けたいケースなどに有効です。
親族間売買においては、税務署に贈与と疑われる可能性があったり、貸付金を他の使途に流用されるリスクがあったりするため、銀行からの融資が受けにくい傾向があります。しかし、セゾンファンデックスの「遺産分割ローン」は、不動産の担保価値を最大限に評価する柔軟な審査が特徴で、こうした親族間売買にもご利用いただけます。
相続による不動産の共有に悩んでいる方は、ぜひ「遺産分割ローン」の活用をご検討ください。
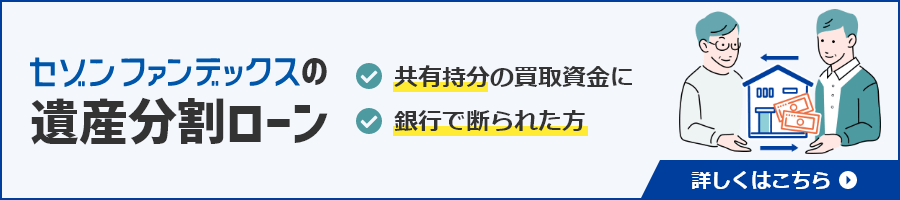
代償分割時の相続税計算方法
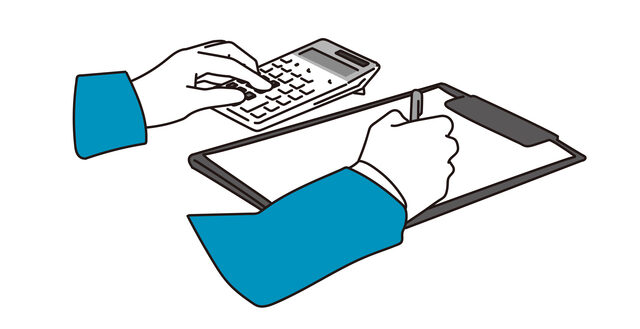
代償分割を行った際の相続税の計算方法は、代償金を支払った方と代償金を受け取った方で異なります。
(1)代償金を支払った方の課税価格
相続によって取得した財産の価額 – 交付した代償金額
(2)代償金を受け取った方の課税価格
相続によって取得した財産の価額 + 交付をうけた代償金額
そして、この課税価格に基づいた相続税率を乗じて求めた額が最終的な相続税額です。
(相続税の計算例)
相続人が子どもAとBの2人で相続財産が不動産のみの場合、Aが不動産を相続しBに対して代償金を支払うケースを想定します。
不動産の相続税評価額:3,000万円(代償分割時の時価:4,000万円)
AがBに対して支払う代償金額:1,500万円
Aの相続税評価額
3,000万円 – 1,500万円 = 1,500万円
Bの相続税評価額
1,500万円
相続税評価額を基にする計算ではなく、代償分割時の時価を基に代償金の金額を決めるケースもあります。その場合、AとBの相続税評価額は以下のようになります。
Aの相続税評価額
3,000万円 – {1,500万円 × (3,000万円 ÷ 4,000万円)} = 1,875万円
Bの相続税評価額
1,500万円 × (3,000万円 ÷ 4,000万円) = 1,125万円
代償分割で現金がなくても乗り切る方法はある

代償分割を行う際に手元に十分な現金がなくても、分割支払いにしたり不動産担保ローンを利用したりと、さまざまな対処法があります。あらかじめ生命保険で備えておくのもひとつの手です。
大切なのは、相続人全員が納得できる方法を選ぶこと。そのためにも、相続に詳しい専門家のサポートを受けながら、しっかりと話し合いを進めましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。