親から受け継いだ実家。愛着もあって、その処分は単なる金銭的価値の問題に留まらない、感情が絡む難しい決断となることが少なくありません。
しかしその一方で、維持や管理にかかる経済的負担、空き家化によるリスクなど、現実的な課題も山積しています。
「住み続ける」「賃貸に出す」「売却する」──実家の相続には、主にこの3つの選択肢が考えられますが、それぞれにメリットとデメリットが存在します。
本記事では、多くの人が直面する実家相続の悩みに焦点を当て、各選択肢の具体的な側面を不動産相続に精通する山村暢彦弁護士が解説していきます。
まず確認すべきは「誰が住む予定か」
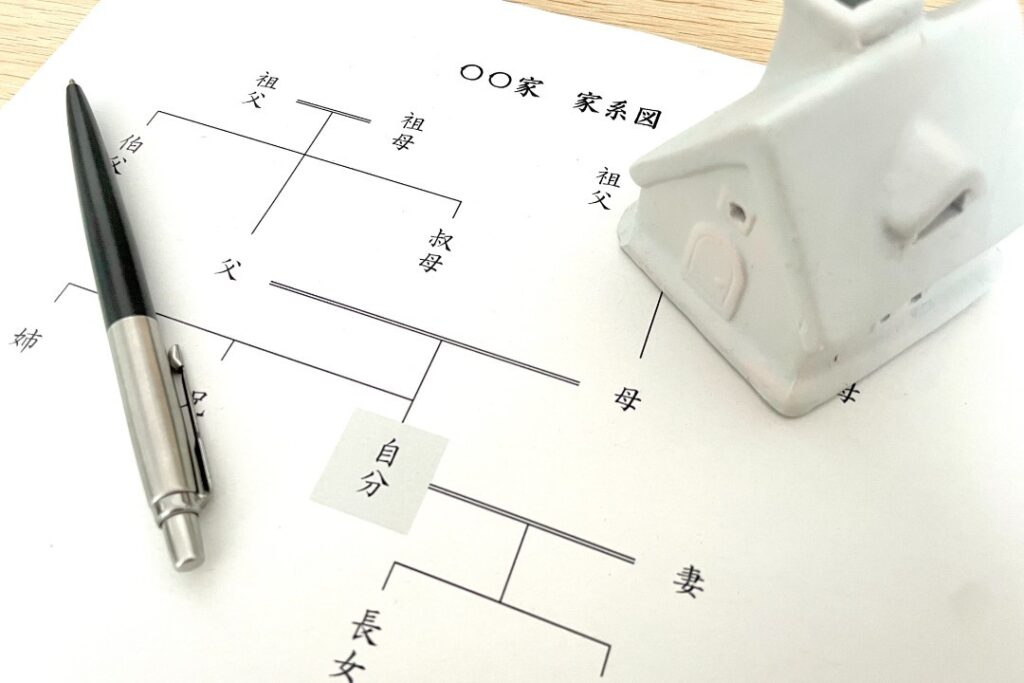
実家の活用を考えるにあたって、最初に確認すべきなのは「相続人の中にその家に住む意向のある人がいるかどうか」です。
たとえば、親と同居していた子がそのまま住み続けたいと考えている場合や、近隣に住んでいて実家を生活圏として活用したいと希望する人がいる場合には、「相続して住む」という選択肢が有力となります。
この場合の最大のメリットは、売却や賃貸と比べて手続きが比較的少なく、実家の維持や管理が容易になる点です。
一方で、他の相続人とのあいだで「一人だけ得をしているのではないか」といった不公平感が生じやすく、金銭的なバランス調整(代償金の支払いなど)が必要になることがあります。
弁護士としての実務経験上も、この「不公平感の調整」がトラブル防止のカギとなります。
問題ゼロというわけではありませんが、実家を生活拠点として利用してくれる親族がいる場合には、代償金等の相続問題を解決するだけでよいので、一番シンプルに解決できる状態でしょう。
貸せば楽に賃貸収入が得られる?

次に検討されるのが、「とりあえず貸して収益化する」という方法です。思い出のある家をすぐに手放したくない、いずれ子どもが戻ってくるかもしれない、といった理由でこの選択をする人も多いでしょう。
確かに、賃貸に出すことで固定資産税や維持費の一部を家賃でカバーすることが可能です。また、売却せずに不動産を保有し続けることができるため、将来的に使いたくなった場合の選択肢も残されます。
ただし、注意すべき点も少なくありません。築年数の経った建物の場合、水回りのトラブルや屋根・外壁の老朽化による修繕費が高額になることがあります。
維持費を家賃収入で賄えるはずが、数年分の収益を突発的な修繕費用で失ってしまうという事態も珍しくありません。
また、いったん入居者が決まると、その後に「売却したい」「建て替えたい」と思っても、賃貸契約が障害となることも。立ち退き交渉が必要になったり、法的なトラブルに発展したりする可能性もあるため、長期的な見通しを持ったうえで賃貸化を判断する必要があります。
さらに、最近は「サブリース」と呼ばれる家賃保証付きの契約形態もみられますが、こちらも万能ではありません。原状回復費の負担が重くなるケースや、借主との契約解除が難航しやすい点も注意が必要です。また、リフォーム費用を差し引かれることや、保証される家賃が相場より低いことがあります。さらに契約期間中は自由に売却ができないなどの制約もあるため、契約内容は慎重に精査すべきです。
総じて、比較的築浅のマンション等であれば賃貸は問題が生じづらいのですが、老朽化している物件は賃貸に出すと問題が生じやすいです。戸建てはトラブルが生じるたびに賃借人と法的トラブルを抱えるような状態になりかねませんし、
老朽化区分マンションでひとたび水漏れなどのトラブルが生じると、その解決は大変です。「貸せば楽に賃貸収入が得られる」というのは、老朽化物件においては大間違いだということを知っておきましょう。
「売却」という選択は後ろ向きではない

「実家を売るのは冷たいように感じる……」という声もよく聞きます。思い出が詰まった家を手放すことには感情的な抵抗もあるでしょう。しかし、実際には「売却が最も合理的な選択」であるケースも少なくありません。
たとえば、相続人全員が遠方に住んでいて、誰も実家に住む予定がないという場合、空き家のまま放置するとリスクは非常に高くなります。
固定資産税を支払い続ける必要があるだけでなく、建物の劣化により修繕費用が膨らみ、周囲に迷惑をかけることも。
特に、老朽化した家屋は台風や地震などの災害時に倒壊し、他人に被害を与えてしまう危険性もあります。
民法717条に定められた「工作物責任」により、所有者が損害賠償責任を問われるケースもあるのです。
また、売却にあたっては、土地の境界があいまいな場合に近隣住民との立会いが必要となるなど、事前準備に手間がかかることもあります。
特に長期間空き家だった場合、隣人との関係が希薄で連絡が取りづらいほか、境界トラブルや越境物(樹木・建物)などを巡って近隣住民から反対されるケースもあります。
こうした問題も発生しがちです。
これらのことを踏まえると、実家を売却して現金化し、相続人間で公平に分配するという方法は、決して「感情を切り捨てる行為」ではなく、家族や自分自身の将来にとって現実的かつ合理的な選択だといえるでしょう。
実家相続の判断軸は「感情」と「経済」のバランス

弁護士として、これまで多くの相続案件に関わってきたなかで強く感じるのは、実家にまつわる問題は単なる不動産処分ではなく、「家族の歴史や感情」と「経済的な現実」とのバランスをどう取るかに尽きるということです。
実家には、家族との思い出や先祖代々の歴史が詰まっているため、簡単には手放せないという気持ちはよくわかります。筆者自身、実家の処分を検討するとなれば、迷うことは間違いありません。
しかし、感情だけで維持を続けるには限界があります。経済的な負担、管理責任、将来的なトラブルのリスクを考えると、「どうすれば家族全体にとって最も幸せな形になるか」という視点で、冷静に判断することが大切です。
実家の相続や処分に迷ったら、早めに専門家へ相談を
「住む」「貸す」「売る」それぞれにメリット・デメリットがあるからこそ、最終的な判断に迷うことは当然です。そんなときは、弁護士や不動産会社、税理士などの専門家に早めに相談することをお勧めします。
相続登記の手続きや名義変更、遺産分割協議、空き家管理、売却の法的手続きなど、関係する作業は多岐にわたります。どの順番でなにを進めればいいかわからないという人でも、専門家と一緒に整理すれば、無駄なトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
賃貸が馴染むエリア、建物なのか、売却時の障害はないのか、その際の見込み売却金額はいくらかなど、各種専門家に話を聞いて初めて判断材料がそろってくることも多いです。
また、最近では空き家対策のために補助金を出してくれる自治体もあり、相続不動産を売却する際に税務面での控除などが使える制度もあります。
こうした制度は地域や物件ごとに要件が異なるため、専門家に相談しながら活用することで、費用負担を大きく抑えることが可能です。
おわりに…実家の未来は、家族と地域の未来
実家の相続は、単なる資産処分ではなく、「家族の将来をどう設計するか」という視点が問われる決断です。
住む、貸す、売る、どの選択が正解かは、家族構成や経済状況、地域の不動産市況などによって異なります。
「特に経済的に困っていないし、いったん放っておこう」と延々と放置し、地方の空き家物件が増えているという背景もあります。
ただし共通していえるのは、「悩んでいるうちに事態が悪化する」というリスクがあることです。
感情面も大切にしながら、現実的な負担やリスクにも目を向け、家族全員で率直に話し合うことが欠かせません。家族全体が納得できる判断を早めに下すことが、後悔しない相続の第一歩となります。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、最新情報はホームページ等でご確認ください。

























