いざという時のために、事前になにを準備しておけばよいのか。相続が発生したあと、どのような手続きが必要になるのか。
不動産相続は、誰しも直面する可能性があるものの、多くの人が「よくわからない」とためらうテーマです。
本記事では、不動産相続に精通する山村暢彦弁護士が、事前準備と相続発生後の手続きを時系列で整理したチェックリストを用意しました。さらに、「親が借金を残していたら?」「相続放棄はどうする?」といったよくある疑問にもわかりやすく解説していきます。
生前にできる準備が「争続」を防ぐ
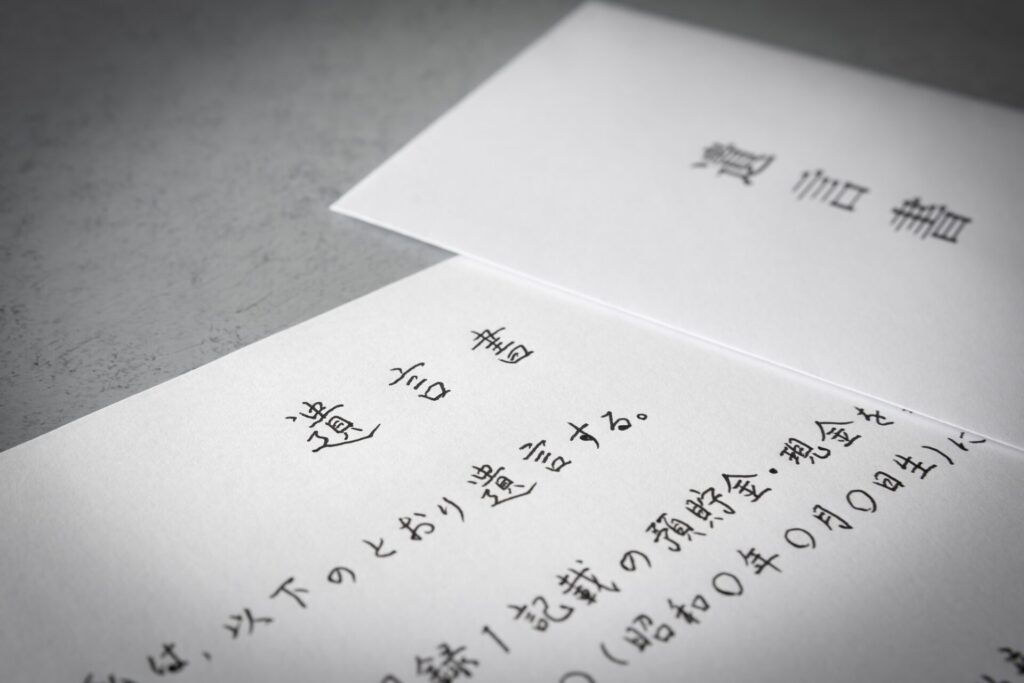
不動産相続で揉める最大の原因は、「家族のあいだで財産について話し合っていなかったこと」に尽きます。生前のうちから家族で不動産の処分方針を共有し、方針を確認しておくだけでも、相続後のトラブルを大きく減らすことができます。
相続対策というと、親等の上の世代に「死んだあとのことを考えてほしい」というのに等しい事柄です。
心情的にもなかなか話しづらいことがあるでしょう。ただ、実際に相続対策がなされておらず、どこにどんな財産があるのかわからない、といった事態になると、残された側も大変な負担で相続手続きを行う必要が生じてしまいます。
また、体調が悪くなったあとに、このような心的ストレスのかかる話をするのは一層容易ではありません。そのため、心情的に難しさ、辛さがあるかもしれませんが、ある程度の年齢になってきたら、「相続のこと」は少しずつ話していくとよいと思います。
《事前準備》チェックリスト
□家族会議の実施
- 不動産の処分方針(誰が引き継ぐのか、売却して分けるのかなど)を家族で話し合い、共有する。
□遺言書の作成
- 可能であれば、公正証書による遺言書を作成する。
□不動産名義の確認
- 登記簿謄本を確認し、不動産の名義が被相続人(親など)になっているかを確認する。
- 祖父母や先代の名義のままになっている場合は、早めに名義変更を検討する。
□財産リストの作成
- 預貯金、株式、不動産、借入金など、すべての財産(プラス/マイナスを問わず)をリストアップする。
- 作成した財産リストの所在を家族にわかる形で残しておく。
- 特に負債や連帯保証などの「マイナスの財産」も必ずリストアップし、家族と共有しておきましょう。気付かず相続してしまうリスクを未然に防げます。
相続開始後の必要手続き…特に「財産の全体像を把握する作業」が重要なワケ

被相続人が亡くなったあとの手続きは、期限が設けられているものも多いため、時系列で把握し、計画的に進めることが大切です。
《相続発生後》チェックリスト
① 相続開始直後(~死亡から7日以内)
□死亡届の提出
- 医師が作成した死亡診断書を添えて、7日以内に役所に提出する。
- 火葬許可証の発行を受ける(通常、葬儀社がサポート)。
② 相続人の確定
□住民票の除票/戸籍謄本の取得
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人全員を確定する(転籍や婚姻歴がある場合は複数自治体への請求が必要)。
- 煩雑な場合は、士業(弁護士など)に依頼し、職権での一括請求も検討。
③ 財産調査の開始
□【超重要】財産の全体像の把握
- 「なにが遺産として残っているのか」を正確に調査する。
★ポイント……プラスの財産(預貯金、不動産、有価証券など)だけでなく、マイナスの財産(借金、保証債務など)のすべてを正確に調査する。
◎預貯金:通帳やキャッシュカード、郵便物などから取引銀行を特定し、残高を確認(銀行は死亡を知ると口座を凍結するため注意)。
ネット銀行や証券会社、オンラインサービスに関する情報も見落としやすいため、IDやパスワード管理状況を必ず確認しましょう。
◎不動産:
- 法務局で登記簿謄本を取得し、所有者や抵当権の有無を確認。
- 市区町村で固定資産評価証明書を取得し、相続税評価額の目安を把握。
- 所有不動産が不明な場合は、役所から「名寄帳」を取得し、参考にする。
- 共有名義の土地や私道、未登記地など「見えにくい資産」の見落としに注意。
◎借金/保証債務:
- 収益不動産の抵当権設定、銀行取引履歴、信用情報機関への照会などを検討。
- 被相続人が法人経営者の場合、会社の債務保証に注意。判断が難しい場合は早期に弁護士に相談。
④ 相続放棄の検討と手続き(~相続開始を知った日から3ヵ月以内)
□相続放棄の検討
- 調査の結果、明らかにマイナスの財産のほうが大きいと判明した場合に検討する。
- 家庭裁判所への申立ては「相続開始を知った日から3ヵ月以内」。
- 期限に余裕がない場合や迷う場合は、できるだけ早めに弁護士・司法書士など専門家へ相談してください。期限切れによる相続トラブルが多発しています。
□家庭裁判所への申立て
- 相続開始を知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所に申立てを行う(「知った日」から3ヵ月とあるものの、「いつ知ったか」の認定が曖昧になる可能性もあるため、実務的には「死亡日」から3ヵ月以内が目安)。
- 期間内の調査が困難な場合は、放棄申述期間の延長申請も可能。
□相続放棄後の管理責任に注意
- 単純に「放棄すれば終わり」ではない。放棄後も、被相続人が所有していた社用車や事務所のリース機器などの管理責任が発生することがあり、手続きを誤ると「相続した」とみなされるリスクも。法的リスクを十分に確認する。
⑤ 遺産分割協議と相続登記
□遺産分割協議の実施
- すべての財産調査と相続人確定後、相続人全員で「財産をどう分けるか」を話し合う。
- 相続人全員の合意がないと成立しない。
- 不動産(特に実家)の引き継ぎを巡って意見が割れる場合は、家庭裁判所の調停も検討。
- 遺産分割協議書を作成する。
- 合意内容を書面にまとめる(不動産の登記や預金の払い戻しに必要不可欠)。
□不動産の相続登記
- 遺産分割協議がまとまり次第、不動産の相続登記を行う。
- 2024年から相続登記が義務化。相続を知った日から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があるため、迅速に進める。
よくあるQ&Aで疑問を解消

相続に関する疑問として特によくある疑問を解消していきましょう。
相続放棄によって回避可能です。ただし、相続開始を知った日から3ヵ月以内という期限があるため、注意が必要です。期限を過ぎると放棄できなくなるため、早めの確認と対応が求められます。
また、保証債務(連帯保証人となっている借金など)も相続対象になるため、必ず調査しておきましょう。
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるなどの手段を講じることで対応可能です。ただし、これらの手続きには時間を要するため、早期の対応を心掛けましょう。
実家を売却するには、まず遺産分割協議を終え、相続登記を完了させておく必要があります。これらの手続きが済んでいなければ売却はできませんので、上述の段取りを誤らないことが重要です。
専門家相談の勧め
相続に関する疑問や不安が残る場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。手続きの進め方や注意点を個別にアドバイスしてもらえます。
おわりに…相続に「備えること」が、家族を守る

不動産相続は、誰にとっても初めての経験であることが多く、複雑な手続きと感情のはざまで悩まされる局面が多くあります。しかし、あらかじめ必要な知識と準備を備えておくことで、大切な家族のあいだに不要な争いを生まずに済むことも事実です。
生前のうちから家族での話し合いを重ね、財産の所在を明らかにし、必要に応じて遺言書を準備する。そのうえで、相続発生後は冷静に調査と手続きを進め、必要な場面では専門家の力を借りる、これこそが、相続の不安を乗り越える最も確実な道筋です。
「うちはまだ先の話だから」と思う前に、ぜひ今日から一歩踏み出してみてください。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、最新情報はホームページ等でご確認ください。

























