65歳以上の働き方を考える際に避けて通れない年金制度が、在職老齢年金です。「高齢になってからも働きたいけれど、年金が減るのは避けたい」「どのくらい稼ぐと年金が減額されるのだろう」といった不安を解消するためには、在職老齢年金について正しく理解することが大切です。
本記事では、在職老齢年金の基本的な仕組みや、65歳以降でも満額の年金を受け取りながら働くためのコツについて解説します。年金と収入のバランスを保ちながら働けるようになるため、ぜひご参考ください。


65歳以上の方は働きながら「在職老齢年金」を受給できる

65歳以上の方は在職老齢年金により、働きながら年金を受け取れます。社会とのつながりを持ちながら収入を増やせることから、高齢者にとっては大きなメリットといえます。
一方で、在職老齢年金の仕組みによって年金額が調整される場合があるため、注意が必要です。
在職老齢年金とは?
在職老齢年金とは、60歳以降に厚生年金に加入している方が、働きながら年金を受給できる制度です。年金制度が設立された当初、老齢年金は退職しなければ受け取れない仕組みになっていました。しかし、高齢になってから働く場合は賃金が低く、退職後の生活が成り立たないケースも多かったことから、1965年に在職老齢年金制度が設けられました。
その後、働いても年金が不利にならないようにすべきという観点から、制度の見直しが行われてきました。現在では「一定以上の収入がある場合に年金額を調整する制度」として、広く知られています。
在職老齢年金の支給対象となるのは、以下に該当する方です。
- 60歳以上70歳未満で厚生年金保険に加入している方
- 70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤めている方
本来受け取る年金より少なくなる場合もある
在職老齢年金では、勤務先からの月給や賞与の金額によって、受け取る年金が減額または支給停止されることがあります。具体的には「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が50万円を超えた場合に年金が調整される仕組みです。
詳しい計算式は後述しますが、年金額が調整されるために、頑張って働いたとしても思うように収入が伸びないケースもあります。
なお、在職老齢年金制度で減額や支給停止の対象となるのは老齢厚生年金のみで、退職後も減額された分は受け取れるわけではありません。老齢基礎年金や障害厚生年金は減額されないため、老後の資金計画を立てる際に混同しないように気をつけましょう。
65歳以降に満額の年金をもらいながら働く方法

65歳以上で働いている場合、年金を満額受け取るためには給与との合計額の調整が必要な場合があります。そのため、在職老齢年金制度の仕組みや支給停止基準額の計算方法を正確に理解しておきましょう。
ここでは、年金を減らさずに働くための具体的な方法について解説します。
- 年金と給与の合計を50万円以下に抑える
- 個人事業主やパートとして働く
ひとつずつ見ていきましょう。
年金と給与の合計を月50万円以下に抑える
在職老齢年金では、基本月額(老齢厚生年金の月額)と総報酬月額相当額の合計が50万円以下の場合、年金は全額支給されます。総報酬月額相当額は、被保険者が受け取る税引前の給与を一定の幅の区分で表した「標準報酬月額」と、「その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除した額」を合算した額を指します。
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
| 老齢厚生年金額 | 年額120万円 |
| 標準報酬月額 | 24万円 |
| 標準賞与額 | 年額180万円 |
この場合、基本月額は10万円(=120万円÷12)、総報酬月額相当額は39万円(=24万円+(180万円÷12))で、合計は49万円(=10万円+39万円)です。
50万円を超えないため、年金は全額支給されます。
一方、基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超えてしまうと、次の計算式で求めた金額が支給停止となります。
「(総報酬月額相当額+基本月額-50万円 )÷1/2」
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
| 老齢厚生年金額 | 年額120万円 |
| 標準報酬月額 | 36万円 |
| 標準賞与額 | 年額240万円 |
この場合、基本月額は10万円(=120万円÷12)、総報酬月額相当額は56万円(=36万円+240万円÷12)で、合計は66万円(=10万円+56万円)と、合計額が50万円を超えます。
減額される年金は月額8万円(=66万円−50万円 ✕1/2)で支給されるのは毎月2万円(=10万-2万)です。。
厚生労働省の「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、老齢厚生年金(報酬比例部分)の平均的な受給額は月額約8.8万円です。先述の計算式から逆算すると、年金を満額受給したい場合、給与収入は40万円程度に抑える必要があります。
出典:厚生労働省「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
個人事業主やパートとして働く
厚生年金に加入しない働き方を選べば、在職老齢年金による年金の減額や支給停止を避けられます。
会社員時代に培ったスキルや知識を活かし、業務委託契約などで個人事業主として働くのもひとつの方法です。個人事業主は雇用関係がないため、厚生年金の被保険者には該当しません。そのため、収入が増えても在職老齢年金の減額対象にはならず、年金を満額受給しながら働けます。
ただし、個人事業主として働く場合、所得税や国民健康保険料などを自分で納付する必要があります。そのため、手続きや金額面での負担が増える点は考慮しなければなりません。また、事業が上手くいかなかった場合は収入が不安定になりかねない点も理解しておきましょう。
また、厚生年金の加入条件に該当しない範囲で、パートやアルバイトとして働くのも良いでしょう。
以下いずれかの条件を満たした場合、厚生年金の被保険者には該当しないため、在職老齢年金により年金が減額されることはありません。
- 週の所定労働時間が20時間未満
- 所定内賃金が月額8.8万円未満
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがない
- 働いている企業が従業員数50人以下
パートやアルバイトとして働く場合は、労働時間や収入に上限が出るため、大きな収入増は見込めないかもしれません。
65歳以上の方が厚生年金に加入しながら年金をもらうメリット

厚生年金に加入し続けながら働くことには、以下のようなメリットがあります。
- 毎月の収入が増える
- 在職定時改定によって年金が増える
- 勤務先の健康保険に継続加入できる
メリットを理解することで、65歳以上でも働くべきか判断できるようになるでしょう。
毎月の収入が増える
65歳以上の方が厚生年金に加入しながら働くと、給与収入に加えて在職老齢年金を受け取れるため、毎月の収入が増えます。年金と給与のバランスをうまく調整することで、働きながら収入を最大化しやすくなります。
例えば老齢厚生年金を毎月10万円受け取っており、標準報酬月額が38万円の仕事を続けている65歳以上の方がいるとします。年金と給与の合計は48万円(=10万円+38万円)と、減額の基準額である50万円を下回っているため年金は全額支給されます。
一方で、給与が47万円に増えた場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計額は57万円(=10万円+47万円)です。この場合、在職老齢年金の仕組みにより、年金の一部(月額3.5万円)が減額されてしまいます。それでも、働いた分の給与はそのまま手元に入るため、働き続けることで結果的に収入を増やせる可能性があります。
在職定時改定によって年金が増える
2022年4月に在職定時改定が導入されたことにより、厚生年金の加入期間に応じて、働きながらでも年金額が少しずつ増額するようになりました。在職定時改定とは、厚生年金に加入中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年再計算される仕組みです。
基準日(9月1日)時点で厚生年金に加入中の場合、前年9月から当年8月までの厚生年金保険の加入期間が反映され、10月分(12月受取分)から年金額が改定されます。
ちなみに2022年3月以前は、退職時や70歳到達時など被保険者資格を喪失したタイミングでのみ改定されていました。
在職定時改定によって増える年金額の目安は、以下のとおりです。
| 働く期間 | 標準報酬月額20万円 | 標準報酬月額30万円 | 標準報酬月額41万円 | 標準報酬月額50万円 |
|---|---|---|---|---|
| 66歳まで | 1.3万円 | 2.0万円 | 2.7万円 | 3.3万円 |
| 67歳まで | 2.6万円 | 3.9万円 | 5.4万円 | 6.6万円 |
| 68歳まで | 3.9万円 | 5.9万円 | 8.1万円 | 9.9万円 |
| 69歳まで | 5.3万円 | 7.9万円 | 10.8万円 | 13.2万円 |
| 70歳まで | 6.6万円 | 9.9万円 | 13.5万円 | 16.4万円 |
※標準報酬月額×5.481÷1,000×老齢厚生年金額に反映される厚生年金保険加入期間の月数で計算。100円以下は四捨五入
例えば、65歳まで給与月額20万円で厚生年金保険に加入していた方が、70歳まで引き続き給与月額20万円で加入した場合は、1年間の在職で1年ごとに年額1.3万円も年金が増えます。
出典:日本年金機構|年金Q&A(老齢厚生年金全般)
ただし、厚生年金に加入できるのは原則70歳までで、それ以降も継続して働く場合は在職定時改定は適用されないため、注意しましょう。
勤務先の健康保険に継続加入できる
65歳以上の方が厚生年金に加入しながら働くと、健康保険の給付を引き続き利用できることも大きなメリットです。厚生年金に加入する場合、原則として健康保険(被用者保険)もセットで加入する必要があるためです。
健康保険に継続加入できると、病気やケガで4日以上仕事を休んだ場合に支給対象となる「傷病手当金」などの保障が受けられます。
さらに、一定の要件を満たせば配偶者をはじめ、同居している家族を健康保険の被扶養者として追加できます。被扶養者とするための条件は、主に以下の2つです。
- 年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
- 被保険者の年間収入の2分の1未満であること
この条件を満たせば、家族の健康保険料が免除されつつも被保険者と同様の保障を受けられるため、家計の負担を抑えられます。
ただし、年金について65歳以上の厚生年金被保険者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、被保険者本人が65歳になったタイミングで第1号被保険者(国民年金)への切り替え手続きが必要となる点に注意が必要です。
65歳以上の人が厚生年金に加入しながら年金をもらうデメリット

厚生年金に加入しながら働くことには多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットも押さえておきましょう。
- 収入によっては受け取れる年金が減る
- 繰り下げ受給の増額が期待できない場合がある
デメリットも考慮したうえで、老後の働き方を決めることが大切です。
収入によっては受け取れる年金が減る
一定額を超える収入がある場合、在職老齢年金の仕組みにより受け取れる年金が減額される可能性があります。減額される基準については上述していますが、頑張って働いても年金が減らされる場合があるため、収入が多い方は注意が必要です。
退職すれば年金の減額や支給停止は解除されるものの、減額された年金が退職後に返還されることはありません。
また、加給年金も受給できなくなる場合があることも押さえておきましょう。加給年金とは、65歳以上の厚生年金被保険者に扶養している配偶者や子どもがいる場合に、追加で支給される年金です。在職老齢年金が全額支給停止となった場合は、加給年金も支給停止になるため、収入が想定よりも大きく減る可能性があります。
さらに、65歳以上でも厚生年金に加入して働いている場合、70歳まで保険料の支払いが続く点にも注意が必要です。厚生年金保険料は給与に応じて引かれるため、手取り収入が思ったほど増えないケースもあります。
自分の収入と年金額を事前にシミュレートし、バランスを取りながら働き方を考えることが大切です。
繰り下げ受給の増額が期待できない場合がある
繰下げ受給を選択した場合、年金の受給開始を遅らせることで、年金額が増額されます。ただし、65歳以降に在職老齢年金を受給していた場合、増額の対象となる年金額が減る可能性があります。
年金の繰下げ受給とは、年金を受け取るタイミングを65歳以降に遅らせることで、1ヵ月あたり0.7%ずつ年金が増額される制度です。繰り下げは最大で75歳まで可能で、65歳時点の年金額に対して最大84%(=10年×12ヵ月×0.7%)増額されます。
ここで注意したいのが、在職老齢年金との関係性です。繰下げ受給で増額の対象となるのは、実際に支給された年金に限られます。つまり、在職老齢年金によって減額または支給停止となった部分は、繰り下げ受給の増額対象から除外されるのです。
例えば、65歳時点での老齢厚生年金額が20万円の方が、在職老齢年金によって実際に支給される年金が10万円に減額されたとします。
この場合に70歳まで繰り下げをすると、4.2万円(=10万円×0.7%×60ヵ月)の増額となります。8.4万円(=20万円×0.7%×60ヵ月)ではないため、間違えないように気をつけてください。
在職老齢年金の受給者は確定申告をすべき?そうでないケースとともに解説
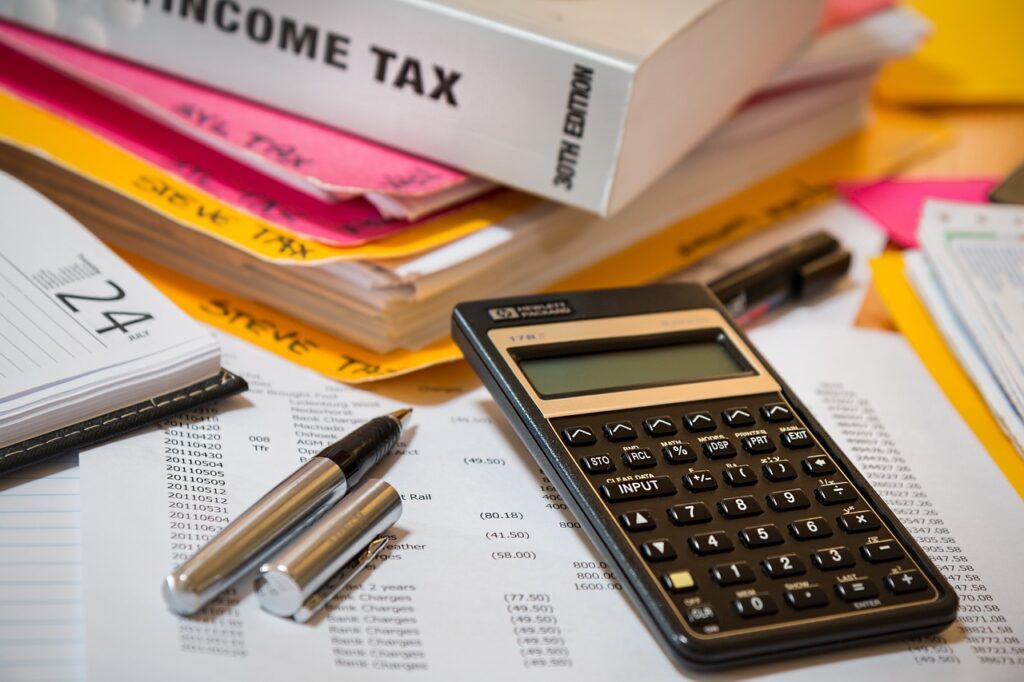
年金の受取額によっては、確定申告が必要になることがあります。そのため、年金を受け取りながら働くとなると、確定申告が必要なのか悩む方もいるでしょう。
確定申告が必要か否かは、年金や収入の額によって異なります。申告漏れがあった場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティを受ける可能性があります。
確定申告が必要なケースについて、事前に理解しておきましょう。
必要なケース
在職老齢年金に該当する方のうち、確定申告が必要なのは以下のいずれかに該当するケースです。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超えている
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超えている
- 所得税の還付を受けるために申告する場合
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額には、以下の所得が含まれます。
- 給与所得
- 公的年金以外の雑所得(個人年金など)
- 配当所得(株式の配当金など)
- 一時所得(生命保険の満期保険金など)
例えば、収入源が勤務先からの給与と年金に限られている場合、給与収入が年収75万円超(給与所得控除55万円を差し引いた後の所得が20万円超となるため)の場合は確定申告が必要です。
また、医療費控除(1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる控除)や雑損控除(災害や盗難などで損害を受けた場合に適用される控除)の対象者で、所得税の還付がある場合は確定申告が必要です。
なお、確定申告を行った場合は税務署がデータを地方公共団体に送信するため、住民税の申告書を改めて提出する必要はありません。そのため、確定申告を一度済ませれば、所得税と住民税の手続きが同時に完了します。
不要なケース
在職老齢年金に該当する方でも、以下両方の条件を満たした場合は確定申告が不要です。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
例えば、年金収入が年間180万円程度で、毎月の給与収入が5万円程度(年間60万円)の場合、給与所得控除55万円を差し引くと給与所得は5万円(=60万-55万)です。「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」を満たすため、確定申告は不要です。
ただし、確定申告が不要な場合でも、以下に該当する場合は住民税の申告が必要になるケースがあります。
- 公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合
- 公的年金などに係る雑所得のみがある場合で、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除(生命保険料控除、医療費控除など)の適用を受ける場合
在職老齢年金の仕組みを理解して65歳以降も安定した収入を得よう

在職老齢年金は、勤務先から受け取る給与や賞与の額に応じて年金額が調整される制度です。この制度を正しく理解することで、収入を最大化できる働き方を計画しやすくなるでしょう。
制度を上手に活用し、自分に合った働き方を選ぶことで、経済的な不安を軽減できるようになるかもしれません。
また、年金を受け取りながら働く以外で老後の資金を確保する手段として、リースバックを活用することも選択肢のひとつです。リースバックとは、自宅を売却してまとまった資金を得ながらも、引き続きその家に住み続けられる仕組みです。
リースバックは「働く時間を減らしたい」「家は手放したくないが資金が必要」といった方にとって、生活の安定を保ちながら老後資金を確保する手段として注目されています。
「セゾンのリースバック」では、最短即日・無料で見積もりが可能です。対象エリアは全国(一部地域を除く)で、戸建てやマンションなどの住宅だけではなく、オフィスビル・事務所・店舗などもリースバックの対象としています。
働き方と資金確保を両立させる方法として、在職老齢年金とリースバックを上手に活用し、自分に合った老後の生活設計を進めていきましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。




























