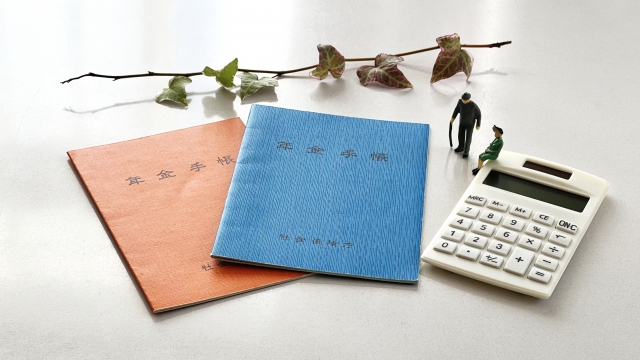「年金だけで生活していけるのだろうか」と不安を抱き、60歳を過ぎても働き続けたいと考える人は少なくありません。しかし、働くと年金が減額されるという「在職老齢年金」の仕組みに疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
「給料が高いと年金がどのくらい減るのか?」「働くことで本当に損をするのか?」と悩む声もよく耳にします。
本記事では、在職老齢年金の基本的な仕組みをわかりやすく解説するとともに、具体的な計算方法やメリット・デメリットについて詳しく紹介します。


在職老齢年金とは?

在職老齢年金が適用されると、賃金や働き方によって年金が減額される可能性があります。老後の資金計画を適切に立てるためにも、制度の概要や導入の背景を正しく理解しておきましょう。
制度の概要
在職老齢年金は、年金の受給資格を持つ60歳以上の方が、働きながら年金を受け取れる仕組みです。ただし、1ヵ月あたりの給与(ボーナスを含む)と年金の合計額(支給停止基準額)が50万円を超えると、その超えた金額の半分が年金から減額されます。
なお、2024年11月に厚生労働省が公表した資料によると、支給停止の対象となっているのは、年金受給権者全体の約16%です。
出典:厚生労働省「在職老齢年金制度について」
在職老齢年金は、60歳代前半を対象者にした「低所得者在職老齢年金(低在老)」と、65歳以上を対象とした「高年齢者在職老齢年金(高在老)」の2種類に分けられます。
なお、在職老齢年金の対象になるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金や障害厚生年金は減額されません。
制度が設けられた背景
もともと厚生年金は、「退職」を条件に支給されるものでした。しかし、高齢者の中には賃金だけでは生活が成り立たない方も多く、特例として働きながらでも年金を受け取れる制度として「在職老齢年金」が導入されました。
「働いても年金が不利にならないようにすべき」「現役世代とのバランスから、一定の賃金を有する高齢者については給付を制限すべき」という2つの考え方をベースに、今日までに見直しや調整が進められました。結果として、給与と年金の合計額が一定額を超えた場合に減額される現行の制度で運用されています。
なお、在職老齢年金制度は日本独自の仕組みです。アメリカやイギリス、ドイツ、フランスなどの諸外国では、年金の満額支給開始年齢以降であれば、働いていても年金が減額されることはありません。
在職老齢年金が適用される人の条件

在職老齢年金の対象者は、以下の条件に該当する方です。
- 60歳以上70歳未満の厚生年金の加入者
- 70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している方
ひとつずつ詳しく解説します。
60歳以上70歳未満の厚生年金の加入者
在職老齢年金が適用されるのは、60歳以上70歳未満の厚生年金の加入者です。アルバイトやパートタイマーでも、以下の条件をすべて満たせば厚生年金の加入対象(被保険者)となり、在職老齢年金の対象者となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 従業員数が51人以上の企業で働いている
出典:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」
ただし、個人事業主など厚生年金に加入していない方は、在職老齢年金の対象外です。
70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している人
70歳以上で厚生年金保険の適用事業所で勤務している場合も、在職老齢年金の対象です。
70歳以上の方は厚生年金の加入者(被保険者)ではなくなるため、厚生年金保険料の負担は発生しません。しかし、給与と年金の合計額が50万円を超えると、在職老齢年金により老齢厚生年金が減額または支給停止されます。
【早見表あり】在職老齢年金の計算方法

在職老齢年金では、基本月額と総報酬月額相当額の合計(支給停止調整額)が50万円を境に、年金の支給額が決まります。
- 基本月額:老齢厚生年金(年額)を12で割った額
- 総報酬月額相当額:被保険者が受け取る税引き前の給与を一定の幅の区分で表した「標準報酬月額」と「その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除した額」を合算した額
支給停止調整額が50万円以下の場合、年金は全額支給されます。一方、50万円を超える場合は「(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2」で算出した金額が減額されます。
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
| 老齢厚生年金額(年額) | 240万円(→基本月額:20万円) |
| 標準報酬月額 | 20万円 |
| 標準賞与額 | 60万円(年間ボーナス) |
基本月額は20万円(=240万円÷12)、総報酬月額相当額は25万円(=20万円+(60万円÷12))で、合計は45万円(=20万円+25万円)です。
支給停止調整額は50万円を下回るため、この場合は年金は全額支給されます。
基本月額と総報酬月額相当額に基づき、実際に支給される年金額(在職老齢年金)を計算したのが以下の表です。
在職老齢年金の早見表
| 基本月額(厚生年金月額) | |||||||
| 5万円 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 30万円 | ||
| 総報酬月額相当額 | 5万円 | 5万円 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 30万円 |
| 10万円 | 5万円 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 30万円 | |
| 15万円 | 5万円 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 30万円 | |
| 20万円 | 5万円 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 30万円 | |
| 25万円 | 5万円 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 | 27.5万円 | |
| 30万円 | 5万円 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 22.5万円 | 25万円 | |
| 35万円 | 5万円 | 10万円 | 15万円 | 17.5万円 | 20万円 | 22.5万円 | |
| 40万円 | 5万円 | 10万円 | 12.5万円 | 15万円 | 17.5万円 | 20万円 | |
| 45万円 | 5万円 | 7.5万円 | 10万円 | 12.5万円 | 15万円 | 17.5万円 | |
| 50万円 | 2.5万円 | 5万円 | 7.5万円 | 10万円 | 12.5万円 | 15万円 | |
赤色になっている部分は在職老齢年金が適用され、本来もらえる老齢厚生年金から減額されます。
支給停止調整額は毎年4月に見直され、令和6年度に48万円から50万円に変更されました。
なお、以前は支給停止調整額が年齢によって異なっており、60歳以上65歳未満は28万円、65歳以降では48万円でした。しかし、令和4年4月の年金制度改正により、60歳以上65歳未満も65歳以上と同じ支給停止調整額に改正されています。
【参考】在職老齢年金の支給停止の仕組み
在職老齢年金のメリット

在職老齢年金のメリットは、以下のとおりです。
- 在職定時改定がある
- 被用者保険に加入できる
在職老齢年金を受け取りながら働き続けることで、安定した老後生活を送れる可能性があります。
在職定時改定がある
在職老齢年金の大きなメリットは、働きながら将来受け取る年金を増やせる「在職定時改定」の仕組みがある点です。
在職定時改定とは、在職中における年金受給者の年金額を定期的に再計算する仕組みです。対象者は、基準日(9月1日)に厚生年金保険に加入中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給権者となります。前年9月から当年8月までの厚生年金保険加入期間を反映し、毎年10月分(12月受取分)から年金額が改定されます。
在職定時改定によって増える年金額の目安は、以下のとおりです。
| 働く期間/標準報酬月額 | 20万円 | 30万円 | 41万円 | 50万円 |
|---|---|---|---|---|
| 66歳まで | 1.3万円 | 2.0万円 | 2.7万円 | 3.3万円 |
| 67歳まで | 2.6万円 | 3.9万円 | 5.4万円 | 6.6万円 |
| 68歳まで | 3.9万円 | 5.9万円 | 8.1万円 | 9.9万円 |
| 69歳まで | 5.3万円 | 7.9万円 | 10.8万円 | 13.2万円 |
| 70歳まで | 6.6万円 | 9.9万円 | 13.5万円 | 16.4万円 |
※標準報酬月額×5.481÷1,000×老齢厚生年金額に反映される厚生年金保険加入期間の月数で計算。100円以下は四捨五入
例えば、65歳まで標準報酬月額30万円で厚生年金保険に加入していた方が、65歳以降も引き続き標準報酬月額30万円で厚生年金保険に加入した場合は、1年で約2万円ずつ年金が増えていきます。
働いた分の実績が年金額に上乗せされていくため、将来の経済的な安心につながるでしょう。
被用者保険に加入できる
在職老齢年金を受給しながら働く場合、被用者保険(勤務先の健康保険)に継続して加入できることも、メリットのひとつです。
厚生年金と被用者保険は原則としてセットで加入します。被用者保険に加入していれば、一般的な年金生活者が加入する国民健康保険よりも手厚い保障を受けられます。
例えば、病気やケガで4日以上働けなくなったときには「傷病手当金」として、給与のおよそ3分の2に当たる金額を最大1年6ヵ月にわたり受給することが可能です。
また、配偶者などの家族が一定の条件を満たしていれば、被扶養者として被用者保険に加入できます。被扶養者として加入するための条件は、主に以下の2つです。
- 年収が130万円以下
- 被保険者の年間収入の2分の1未満であること
被扶養者の条件を満たせば、家族も被保険者と同様の保障を受けられるうえ、健康保険料がかからないため、家計全体の負担を抑えられます。
在職老齢年金のデメリット・注意点

在職老齢年金には以下のようなデメリットや注意点もあるため、押さえておきましょう。
- 減額された年金は退職後に取り戻せない
- 減額された金額分は繰下げ受給の対象外
- 加給年金を受給できなくなるリスクがある
- 高年齢雇用継続給付を受けていると支給停止額が大きくなる
これらのポイントを理解したうえで、在職老齢年金の活用方法を検討することが大切です。
減額された年金は退職後に取り戻せない
在職老齢年金では、収入によって年金が減額されたり、支給停止になったりすることがあります。しかし、在職中に減額および支給停止された年金が、退職後に一括支給されることはありません。
一方で、働いている間は在職定時改定によって、定期的に年金額が見直される可能性があります。また、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給している70歳未満の方が退職した場合、1ヵ月経過後にそれまでの厚生年金加入期間を反映して年金額が再計算される「退職改定」と呼ばれる仕組みもあります。
在職中に減額された分は直接取り戻せないものの、在職定時改定や退職改定によって年金額が増加するため、完全に働き損にはなりにくいでしょう。
減額された金額分は繰下げ受給の対象外
在職老齢年金によって減額された年金は、年金の繰下げ受給の対象にはなりません。年金の繰下げ受給とは、年金を受け取るタイミングを遅らせることで、1ヵ月あたり0.7%ずつ年金が増額される制度です。繰り下げは最大で75歳まで可能で、65歳時点の年金額に対して最大84%(=10年×12ヵ月×0.7%)が増額されます。
「在職老齢年金」の制度によって繰下げ受給の対象となるのは、支給停止部分を除いた、実際に受け取る年金額になります。
例えば、65歳時点での老齢厚生年金額が30万円の方が、在職老齢年金によって実際に支給される年金が20万円に減額されたとしましょう。
75歳まで年金受給を繰り下げた場合、増額される年金は8.4万円(=20万円×0.7%×60ヵ月)です。減額前の金額をベースに算出した12.6万円(=30万円×0.7%×60ヵ月)ではありません。
加給年金を受給できなくなるリスクがある
在職老齢年金の対象となってしまうと、加給年金を受給できなくなるケースもある点にも注意が必要です。加給年金とは、65歳以上の厚生年金被保険者に扶養している配偶者や子どもがいる場合に追加で支給される年金のことです。家族手当のようなものと考えるとわかりやすいでしょう。
加給年金が支給停止されるケースは、主に以下の3つです。
- 老齢厚生年金が全額支給⇒加給年金は全額支給
- 老齢厚生年金が一部支給停止⇒加給年金は全額支給
- 老齢厚生年金が全額支給停止⇒加給年金は全額支給停止
老齢厚生年金が全額支給停止となると、加給年金も同時に停止されるため、想定していた収入が大きく減る可能性があります。自身の収入や働き方によって加給年金がどう影響を受けるかを確認しておきましょう。
加給年金について詳しくは、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
高年齢雇用継続給付を受けていると支給停止額が大きくなることも
高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金が60歳到達時の75%未満に低下した場合に、低下分を補填するために給付を受けられる制度です。給付金は賃金額の低下率に応じて計算され、2025年3月31日までは賃金額の15%、同年4月1日以降は10%に相当する額を限度として支払われます。
一方で、年金を受けながら高年齢雇用継続給付を受ける場合、在職老齢年金に基づく年金支給停止に加え、さらに年金の一部が追加で支給停止される可能性があります。年金の支給停止額(月額)は、最高で標準報酬月額の6%相当額です。
例えば、年金月額10万円の方の賃金額が、60歳以降に35万円から20万円になった場合(賃金割合が75%未満に低下)、高年齢雇用継続給付は3万円(=20万円×15%)支給されます。このとき、受給できる年金額は8.8万円{=10万円-(20万円×6%)}です。したがって、受け取れる合計額は31.8万円(=20万円+3万円+8.8万円)となります。
出典:日本年金機構「雇用保険の給付を受けると年金が止まります!」
なお、高年齢雇用継続給付による年金の支給停止額や支給率は、実際の年金額や賃金額などにより異なります。そのため、実際の支給額については、最寄りの年金事務所に問い合わせてみましょう。
在職老齢年金を受給するまでの流れ
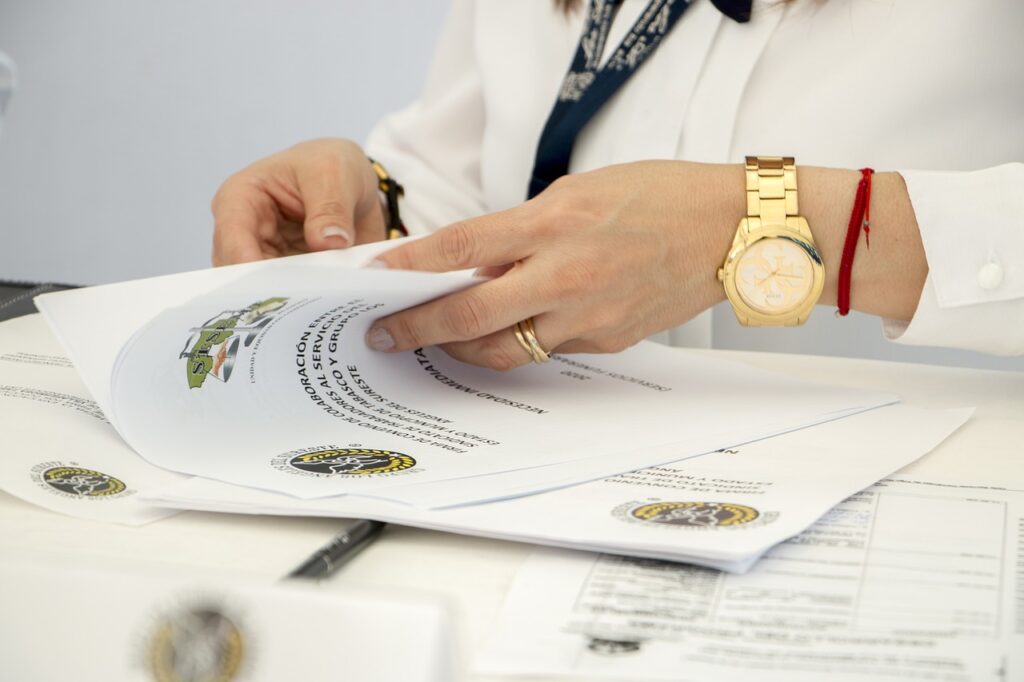
在職老齢年金を受給する手続きは、一般的な年金手続きとほとんど変わりません。
まずは、受給権が発生する年齢(通常は65歳)の誕生日の前日以降に、年金請求書と必要書類を年金事務所や街角の年金相談センターに提出します。申請する際に必要な書類は、以下のとおりです。
- 生年月日の確認書類(戸籍抄本、戸籍謄本、住民票など)
- 受取先金融機関の通帳やキャッシュカード
- 老齢年金の受取方法確認書(繰下げ受給に関する確認)
ただし、マイナンバーが日本年金機構に登録済みの場合や、すでに年金請求書に記載済みの場合には、一部の書類(戸籍や住民票、所得証明書など)の提出を省略できる場合があります。
年金請求書を提出すると、日本年金機構が受給権を確認し、通常1~2ヵ月後に「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。さらに1~2ヵ月後に「年金振込通知書」などが届き、実際の年金の受け取りが始まります。
受給手続きをスムーズに進めるためには、勤務先の人事部門と密に連絡を取り、年金受給に関する情報を正確に届け出ることが重要です。
在職老齢年金に関するFAQ

在職老齢年金の仕組みや今後の制度変更について気になっている方もいるでしょう。ここでは、在職老齢年金に関してよくある質問をQ&A形式でまとめました。
2030年までの廃止が検討されているものの、具体的な時期はまだ決まっていません。2024年12月時点では、支給停止基準額を現行の50万円から62万円に引き上げる方向で議論が進められています。この基準額の引き上げにより、より多くの人が減額や支給停止の対象外となる見込みです。
一方で、制度を撤廃することで働く年金受給者の給付額が増えるものの、年金財政への影響が懸念され、将来世代の受給水準が低下する可能性が指摘されています。
特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年金は別の制度です。
特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢の引き上げをスムーズに進めるための経過措置として設けられた制度です。簡単にいえば、65歳より前に年金を受け取れます。
特別支給の老齢厚生年金の支給対象者は、以下のとおりです。
- 昭和36年4月1日以前生まれの男性
- 昭和41年4月1日以前生まれの女性
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたことがある
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分の2つから成り立っています。このうち、報酬比例部分は在職老齢年金による支給額調整の対象です。
在職老齢年金のポイントを押さえて老後の収入計画を立てよう

在職老齢年金では、給与と年金の合計額が一定基準(50万円)を超えると、年金が減額または支給停止される仕組みになっています。働きながら老齢厚生年金を受給する場合、老後資金の計画が難しくなることもあるでしょう。
もちろん、在職定時改定や退職改定などで将来の年金額を増やす方法はあります。しかし、減額分がそのまま戻ってくるわけではないため、収入と年金のバランスを考えながら、老後の働き方を考える必要があるでしょう。
また、老後資金が不足した場合に備えて、収入源を増やしておくのもひとつの方法です。例えば「リースバック」は老後資金を確保する手段として、注目を集めています。
リースバックとは、自宅や所有する不動産を売却して資金を得た後も、賃貸契約を結ぶことでそのまま住み続けられる仕組みです。在職老齢年金の収入調整による減額分を補う資金を確保できたり、自宅を売却しても住み慣れた環境で暮らせたりするなどのメリットがあります。
「セゾンのリースバック」では、最短即日・無料で見積もりが可能です。対象エリアは全国(一部地域を除く)で、最短2週間で契約できます。事務手数料や調査費用、礼金、賃貸借契約の更新手数料などもかからないため、安心して老後生活を送りたい方は活用を検討してみてはいかがでしょうか。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。