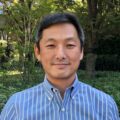定年後の生活を考えるとき、「どのくらいお金がかかるのか」「公的制度でどこまで備えられるのか」といった疑問を感じる方は少なくありません。老後には収入が限られる一方で、生活費や医療費、介護費などの支出は続きます。
本記事では、老後にかかる3つの代表的な支出「生活費」「医療費」「介護費」について、総務省や厚生労働省など公的データをもとに解説します。
老後の生活費は夫婦で月約27万円が平均

総務省「家計調査報告(2024年)」によると、65歳以上の夫婦高齢者無職世帯が1カ月に使う生活費の平均は約26万5,000円です。
なかでも食費は約7万円と最も大きく、ついで交通・通信費、教養娯楽費などが続きます。住居費が平均で1万5,000円程度に収まっているのは、持ち家に住んでいる世帯が多いほか、住宅ローンの返済が終わる人が増える世代であるためと考えられます。
![[図表]総務省「家計調査報告 2024年(令和6年)平均結果の概要」より「65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の家計収支」から作成](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/2e741597563f9d90ea143026eb9c0a85-650x1024.png)
さらに年代を区切ってみると、60代後半では消費支出が約31万円であるのに対し、70代前半では約27万円、75歳以上では約24万円と減少傾向にあることがわかります。
![[図表]総務省「家計調査報告 2024年(令和6年)平均結果の概要」より「65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の家計収支」から作成](https://life.saisoncard.co.jp/wp-content/uploads/2025/08/a0910c4e7855e8f7bf85b4e77cb6dc8a-810x1024.png)
老齢年金を含む社会保障給付を含めても、毎月3万円前後の不足があることもわかります。
これは貯蓄を取り崩すことで、年金プラスアルファの生活を送っていることを示しています。より豊かな生活を送るためには、貯蓄や退職金、資産運用を活用していくことが有効です。
一方で、住んでいる地域によって家賃や物価は異なります。年金の受給額についても、これまでの納付額や保険料納付期間によって違いがあります。
支出の内訳や住居環境次第では、年金の範囲で充分暮らしていける方も少なくないため、「平均額」にとらわれすぎず、自分の生活スタイルをもとに考えることが重要です。
退職に伴って外出頻度が下がると、食費や交際費が減っていく傾向にあります。年齢を重ねて行動範囲が狭まることも、交通費や旅行費などの出費の減少につながっているでしょう。
過度に不安になって無理に生活費を切り詰める必要はありません。暮らしに合わせて、緩やかに支出が減っていくと考えていいでしょう。
細かく老後資金を試算するより、まずはざっくり今の支出を把握するところから始めましょう。
今から3カ月ほど家計簿をつけてみて、その7割程度が老後の生活費になると想定しておけばOKです。
医療費は75歳以上で年間約94万円

厚生労働省「令和4(2022)年度 国民医療費の概況」をみると、65歳以降のひとり当たりの医療費は保険で賄われる部分を含め約78万円となっています。
そのうち70歳以上では約84万円、75歳以上では約94万円と、年齢が上がるほどに医療費も高くなる傾向がうかがえます。
なお、この調査における医療費に含まれる項目は、保険診療の対象となるものに限られます。診察や手術、入院、薬、通院にかかる交通費などが対象です。先進医療費や差額ベッド代、健康診断の費用は含まれません。
保険診療の場合、実際に私たちが支払う金額(自己負担額)は、3割に抑えられています。70歳〜74歳では原則2割、75歳以上で原則1割と、年齢が上がるほど負担の割合は減っていきます。
さらに、高額療養費制度を活用すれば、ひと月に一定額以上の医療費を支払った場合、超えた分は払い戻されます。
例えば、70歳で年収370〜770万円(3割負担)の場合、「80,100円+(総医療費−26,700円)×1%」が自己負担額の上限です。
(例)70歳で年収370〜770万円で、1カ月の医療費が100万円の場合
自己負担限度額:80,100円+(100万円−26,700円)×1%=87,430円
この制度は、申請をすれば払い戻しが受けられますが、多くの健康保険組合では自動適用されるケースもあります。詳細は加入している保険者(協会けんぽ・国保など)に確認してみてください。
なお、年間10万円を超える医療費がある場合は、確定申告で「医療費控除」を受けられる可能性もあります。
また、医療費控除との選択制にはなりますが、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できるOTC医薬品の購入額が年間12,000円を超えた場合、セルフメディケーション税制によって超えた金額が所得控除となります(上限88,000円)。
いずれにせよ、病院や薬局、ドラッグストアで受け取った領収書は保管しておきましょう。
高齢になると骨折や手術の機会も増えます。手術そのものよりも、術後のリハビリ入院で時間と費用がかかるケースもあるでしょう。しかし、公的医療保険によりカバーされる部分も多いため、心配しすぎる必要はありません。
介護にかかるお金は月額平均9万円

生命保険文化センターの調査によると、介護に要した費用は平均で月約9万円(2024年度調査)となっていますが、在宅介護の場合は53,000円、施設介護の場合で138,000円と差があります。
介護にかかるお金は、月額のサービス利用料など毎月定期的にかかる費用だけではありません。
例えば、自宅で介護をする場合、住宅改修や介護用品の購入といった一時的な費用も発生します。同調査によると、手すりの設置や段差解消などの住宅改修、介護ベッドの購入といった一時的な出費の合計は472,000円になるとの結果が出ています。
ただ、この出費は公的介護保険サービスの補助も含めた金額です。要介護認定を受けると、介護サービスの自己負担割合は原則1割(一定所得者は2〜3割)で、訪問介護、通所サービス、福祉用具レンタルなど、生活を支えるさまざまな支援が受けられます。
先ほどの出費の自己負担額は1割なら47,200円になります。
また、かかる費用は必要な介護の程度によって異なり、杖などの補助器具があれば自分で生活できる人は、それほど多額の費用はかかりません。高齢になり、外出が困難になったり、寝たきりの状態になったりする場合には費用がかかる傾向にあります。
施設介護になると、どの程度のサポートを必要とするか、サービスや娯楽はどこまで充実しているかなどによって費用が大きく変わります。早いうちから高齢者施設を見学するなど情報収集をしておくと、自分にあった老後を過ごせるでしょう。
介護についての悩みや疑問は、各自治体の「地域包括支援センター」で相談できます。介護サービスの紹介だけでなく、ケアマネジャーとの面談や支援計画の作成など、包括的なサポートが受けられます。
公的介護保険制度はかなり手厚く、要介護度に応じた支援がきちんと用意されています。まとまったお金をあらかじめ準備しておくと考えるよりも、制度を上手に使うことを意識しましょう。
おわりに
老後の生活がイメージできていないと、漠然とした不安を感じやすいといえます。どのくらいお金が必要かを把握できれば、将来に向けてやるべきことがクリアになり、前向きに備えていく意識へとつながります。
ただし、平均額はあくまで目安でしかありません。住んでいる地域や日ごろの支出によっても費用感は変わるため、自分の場合に置き換えてイメージしておくことが大切です。ざっくりでいいので、今の家計や支出を見直しながら、先の未来を見据えてみてください。
お金を貯めるだけでなく、使える制度や相談先など情報収集を進めておくことも、安心して老後を過ごすための糧になるでしょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。