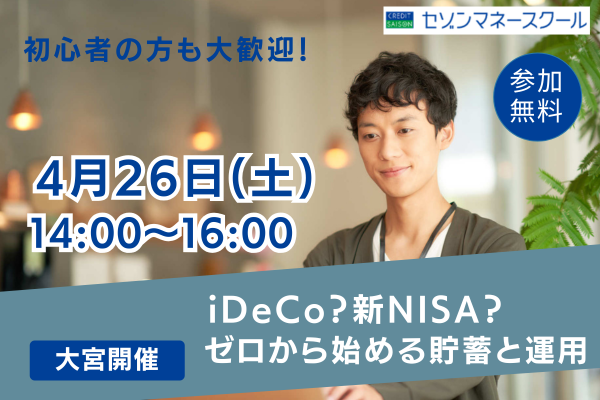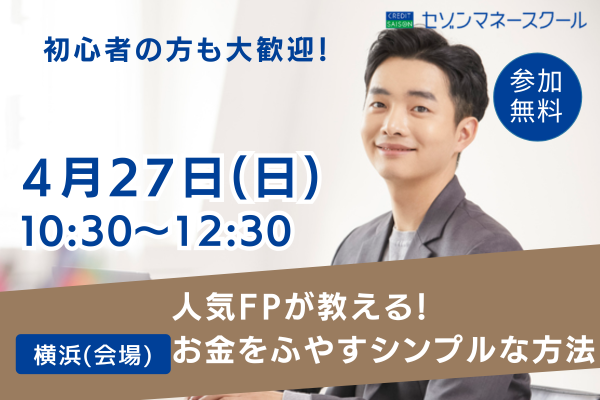親の介護と仕事の両立に悩み、退職を考えている方は少なくないでしょう。総務省の調査によると、年間約10万人もの方が介護を理由に離職しているのが現状です。
「仕事を辞めれば介護に専念できる」と思われるかもしれませんが、実は離職後に精神面・経済面で負担が増したと感じる人が全体の6割を超えています。しかし、介護休業制度や介護保険サービスを上手に活用すれば、仕事を続けながら親の介護と向き合うことは可能です。
この記事では、介護離職のリスクと、仕事との両立に役立つ制度やサービスについて解説します。仕事を辞める前に、まずは選択肢を知っておきましょう。
- 親の介護を理由とした離職は年間約10万人にのぼり、40~50代の働き盛りに多く発生している深刻な社会問題
- 介護離職を経験した6割以上が、精神面や経済面で負担が増加したと感じており、安易な退職は避けるべき
- 介護休業制度や介護保険サービスなどの支援制度を活用することで、仕事を続けながら親の介護と向き合うことが可能
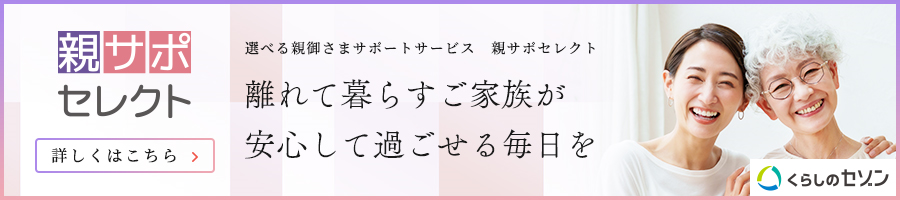

介護離職とは?親の介護で退職を決めた理由

親の介護のために仕事を辞める、いわゆる「介護離職」は、多くの家庭で現実的な課題となっています。特に40代から50代の働き盛りの世代に多く、企業にとって中核となる人材の流出という深刻な問題となっています。
厚生労働省のデータによると、年間約10万人が介護を理由に仕事を辞めており、その半数以上が中高年層です。親の介護と仕事の両立は非常に困難な問題ですが、退職が必ずしも最善の選択ではないことを知ることが重要です。
介護離職の理由としては、主に以下のようなものが挙げられます。
一つ目は職場環境の問題です。「介護と仕事を両立するための制度が整っていない」または「利用しづらい雰囲気がある」といった理由で、必要な休暇や制度を活用できないことが原因となる場合があります。また、親の介護に関する制度やサービスについての情報不足も、退職を検討する大きな要因となっています。
二つ目は、親の介護に専念したいという本人の希望です。親の介護が必要になると、どうしても仕事と介護のどちらを優先すべきか葛藤することが増えます。結果として「介護に専念すれば家族のためになる」と考え退職を選ぶ人もいます。
さらに、自身の健康状態の悪化も理由の一つです。介護は肉体的にも精神的にも負担が大きく、長期化することで介護者自身の健康が損なわれるケースも少なくありません。特に50代では、体力やストレス耐性が若い頃ほど高くないため、介護による負担が直接的に退職につながることがあります。
以上のように、親の介護で退職する理由はさまざまですが、介護離職は多くの場合、退職後に予想外の困難を引き起こします。例えば、収入が減少することで家計が圧迫されるだけでなく、キャリアや社会的なつながりを失うリスクも高まります。
介護離職のメリット

介護離職により新たな問題が発生する可能性はあるものの、状況によってはメリットもあります。
ここでは介護離職による主なメリットについて解説します。
心身の負担が軽くなる
仕事をしながら介護を行うことは、心身ともに大きな負担となります。仕事中に病院から電話が入ったり、介護サービスの手配や調整に追われたりと、常に気が休まらない状況が続きます。介護離職により介護に専念することで、このような精神的なストレスから解放されます。
また、介護に十分な時間を確保できることで、要介護者と密なコミュニケーションを取ることができ、お互いの心理的な安心感も高まります。特に遠方に住む親の場合、泊まり込みケアも可能になり、より手厚い介護ができるようになります。
介護費用の負担が減る
仕事と介護を両立するために利用していた介護サービスの費用を削減できることも、大きなメリットの一つです。訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの介護サービスは、介護保険を利用しても一定の自己負担が発生します。
家族が直接介護を担うことで、これらのサービス利用を必要最低限に抑えることができ、介護にかかわる費用負担を軽減できます。
家族が直接介護を担うことで、これらのサービス利用を必要最小限に抑えることができ、介護にかかる費用負担を軽減できます。また、日中の時間に余裕ができることで、有料の時間外サービスや緊急対応サービスの利用も減らすことができるでしょう。
介護離職のデメリット

親の介護のために退職を決断することは、精神的な葛藤を伴う大きな選択です。一見すると介護に専念することで問題が解決するように思えるかもしれませんが、介護離職には経済的な問題や将来への影響など、さまざまなリスクが伴います。
以降では、介護離職がもたらす主なデメリットについて詳しく解説します。
介護者の収入が減る
介護離職の最も大きなデメリットの一つは、収入が減少することです。離職することで安定した収入を失うだけでなく、長期的には退職金や年金の受給額にも影響を及ぼします。例えば、勤続年数が短くなると退職金が大幅に減少し、さらに将来的な公的年金の額も減るため、老後の生活費が不足するリスクが高まります。
また介護の期間は見通しが立ちにくく、長期化すれば貯蓄を切り崩すことになり、将来の生活設計に大きな影響を及ぼす可能性があります。このように、介護離職は一時的な解決策であっても、長期的な経済的負担を増大させる可能性があるのです。
自分の時間が保てなくなる
介護離職をすることで、訪問介護やデイサービスなどの利用を控えざるを得ないケースもあります。その結果、介護者が一人で多くの時間を介護に費やすことになり、プライベートな時間を確保できなくなる可能性があります。心身の負担が増大し、精神的に追い詰められることも少なくありません。
実際に介護離職を経験した人の中には、介護に専念したものの自由な時間がなくなり、ストレスや孤独感に悩まされるケースが多いことが報告されています。介護離職後に心身の健康を損なう人が少なくないことは見逃せない問題といえるでしょう。
再就職が難しい
介護が終わった後に再就職を試みたとしても、離職前のような職場や条件で働けるとは限りません。特に50代以降の再就職は難易度が高く、仮に職を得られたとしても、以前の収入より大幅に減少することが一般的です。
介護離職後に非正規雇用や時給制の仕事に就くケースが増えており、社会保障の面でも不利な立場に置かれる人が多いといわれています。また、介護離職によってキャリアが途絶えることで、自分の能力やスキルを活かしにくくなることも再就職の壁となります。
介護離職は一時的な解決策である一方、経済的・精神的・将来的なリスクを伴う選択です。退職を検討する際は、これらのデメリットをよく理解し、慎重に判断することが求められます。
介護離職しないための4つの方法

介護離職は一度決断すると、生活費の確保や再就職の困難さなど、さまざまな問題に直面することになります。また、退職理由を職場にどう伝えるかという悩みも生じます。
じつは、介護と仕事の両立を支援するための制度やサービスは数多く存在しており、これらを上手に活用することで介護離職を回避できる可能性があります。
【1】職場に理解を求める
まずは職場に介護の状況を正直に伝え、理解を求めることが重要です。今の自分にできることとできないことを整理し、上司や人事担当者に明確に伝えましょう。
「介護を理由に昇給・昇格できないのでは」という不安から、介護の事実を隠してしまう人もいますが、育児・介護休業法では、介護を理由とした解雇や降格、減給などの不利益な扱いは禁止されています。また、職場での嫌がらせ防止措置も事業主に義務付けられているため、安心して相談することができます。
【2】職場の両立支援制度を活用する
多くの企業では、介護休業や介護休暇など、仕事と介護の両立を支援する制度を整備しています。介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得が可能です。
また、介護休暇は年5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで取得でき、通院の付き添いなど短時間の用事に活用できます。さらに、所定労働時間の短縮や時間外労働の制限なども利用可能です。これらの制度を積極的に活用することで、仕事を続けながら介護との両立を図ることができます。
【3】間接介護を利用する
直接介護が難しい場合は、介護施設への入居やデイサービスなどの外部サービスの利用を検討しましょう。介護保険制度を利用すれば、所得に応じて1~3割の自己負担で各種サービスを利用することができます。
特に遠方に住む親の場合や、フルタイムで働いている場合は、介護施設の利用が両立の有効な選択肢となります。
【4】介護についての相談先を確保する
介護に関する制度やサービスは複雑で、独力で最適な選択をするのは困難です。市区町村の地域包括支援センターでは、介護保険制度の利用方法や介護サービスの選び方など、無料で相談することができます。
また、ケアマネジャーは介護プランの作成だけでなく、介護全般に関する相談にも応じてくれる心強い味方です。さらに、介護の専門家による民間のサポートサービスも増えています。一人で抱え込まず、複数の相談先を確保しておくことで、より良い介護と仕事の両立が実現できるでしょう。
親の介護で頼れる支援サービス例

介護離職を防ぐためには、介護サービスを上手に活用することが重要です。公的な介護保険制度から民間のサービスまで、状況に応じて選択できるサービスは数多くあります。ここでは、仕事と介護の両立に役立つ具体的なサービスを紹介します。
介護保険制度|要介護度に応じたサービスを利用する
介護保険制度は、要支援・要介護認定を受けた方が利用できる公的サービスです。自己負担は所得に応じて1~3割で、比較的安価にサービスを利用することができます。
訪問介護(ホームヘルプ)では食事や入浴の介助、デイサービスでは日中の介護や機能訓練を受けられます。また、ショートステイを利用すれば、一時的に施設での宿泊介護も可能です。
要介護認定の申請は市区町村で行い、認定結果に応じて利用できるサービスが決まります。ケアマネジャーに相談しながら、適切なケアプランを作成することで、効果的なサービス利用が可能となります。
民間サービス|介護保険対象外のサービス利用を検討する
介護保険対象外でも、介護の負担を軽減できる民間サービスがあります。家事代行サービスでは掃除や洗濯、食事の準備などを代行してもらえます。また、配食サービスを利用すれば、栄養バランスの取れた食事を定期的に届けてもらうことができます。
さらに、見守りサービスでは緊急時の通報システムや安否確認が可能です。通院や買い物の付き添い代行サービスもあり、仕事で付き添えない時間帯のサポートを受けられます。これらのサービスは全額自己負担となりますが、介護保険サービスと組み合わせることで、より充実した介護体制を整えることができます。
親の介護に関するサポートなら「親サポセレクト」がおすすめ

介護と仕事の両立に悩む方をサポートする「親サポセレクト」(選べる親御さまサポートサービス)は、セゾンカードでおなじみのクレディセゾンのグループ会社「くらしのセゾン」が提供する会員制サービスです。
親御さまのライフステージに合わせて必要なサービスを選べる柔軟な設計で、離れて暮らすお子さまの不安を軽減してくれます。
以降では、「親サポセレクト」の特徴的なサービスについてご紹介します。
見守り・毎日の生活サポート
離れて暮らす親の安否が気になる方に安心のサービスです。センサーを使った見守りシステムで異常を検知した際は、ご家族へ通知が届きます。緊急時には専任のスタッフがご自宅に駆けつけるため、突然の事態にも対応できます。
さらに、通院や買い物の付き添い代行、掃除・洗濯といった家事代行まで、日常生活全般をカバー。平日9時から19時の基本料金は1時間5,500円(税込)からと、必要な時に必要なだけ利用できる料金体系です。
入退院・施設入退居のサポート
親が急に入院することになり、仕事を休めない場合でも、入院セットの準備から手続きのサポートまで依頼することが可能です。また、介護施設のご紹介や見学時の付き添い、入居時の荷造り、引っ越しのお手伝いなど、施設入居に関する支援も充実しています。
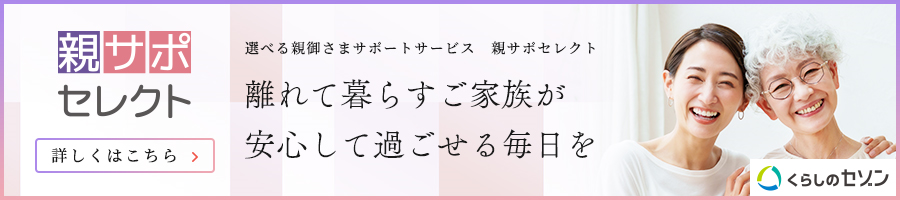

おわりに
親の介護と仕事の両立は、決して簡単な道のりではありません。しかし、介護休業制度や介護保険サービスなど、両立をサポートする制度やサービスは着実に整備されています。介護離職は一度すると再就職が困難で、経済的にも大きな影響を及ぼすため、安易な決断は避けるべきでしょう。
職場への状況の共有や両立支援制度の活用、さらに介護の相談窓口を確保することで、仕事を続けながら親の介護と向き合うことができます。介護の不安を一人で抱え込まず、支援制度やサービスを上手に活用することが、親の介護と仕事の両立への近道となります。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。