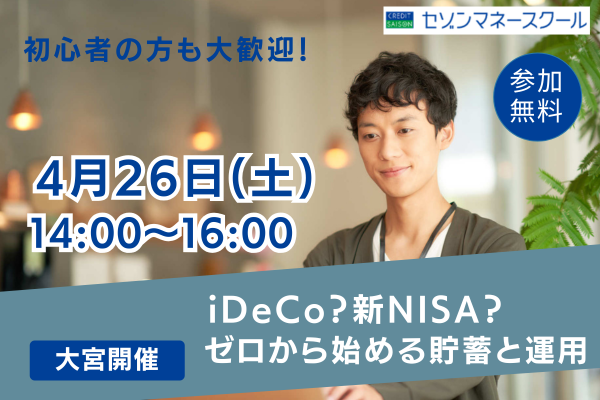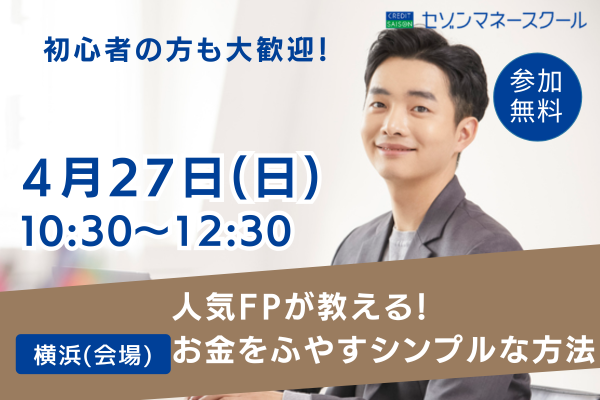親の介護が始まると、思った以上に心身に負担がかかるものです。精神的なストレス、体力的な疲労、経済的な負担など、介護に伴う課題は多岐にわたります。また、介護が長期化することでリスクが高まり、仕事や家庭との両立が難しくなるケースも少なくありません。「しんどい」と感じながらも、誰にも相談できず、一人で抱え込んでしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、親の介護における負担や辛さを軽減する方法を具体的に解説します。介護保険サービスや行政のサポートの活用法、家族間での役割分担の進め方、高齢者施設の選択肢など、多角的な視点で解決策をご紹介。また、介護が長期化することで起こり得るリスクについても解説し、事前に備える重要性をお伝えします。介護で悩んでいる方、負担を少しでも軽くしたい方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
- 親の介護による負担には、精神的・体力的・経済的の3つがあり、介護の長期化に伴いこれらの負担は増大する
- 介護保険サービスや行政サービスなど、利用可能な支援制度を活用することで、介護の負担を大きく軽減可能
- ケアマネジャーや地域包括支援センターなどの専門家に相談することで、適切なアドバイスや支援を受けらる。
- 家族での役割分担や施設入居の検討など、状況に応じた選択をすることで、持続可能な介護生活を実現可能
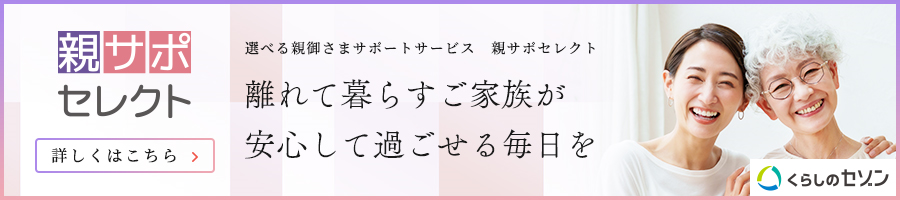

親の介護がしんどいと感じるのはどんなとき?3つの負担

親の介護は身体的な疲労だけでなく、精神的・経済的にも大きな負担がかかります。介護の長期化により、これらの負担は徐々に重くなっていき、介護者自身の生活にも大きな影響を及ぼすことになります。
ここでは、介護者が感じる3つの主な負担について詳しく見ていきましょう。
精神的な負担
介護は深夜・早朝にトラブルが起きやすく、週末や年末年始などの大型連休でも家族だけで対応せざるを得ないことが多くあります。介護サービスをフル活用していても、完全に介護疲れを回避することは難しいのが現状です。
特に在宅介護の場合、常に「介護者」としての役割を意識し続けなければならず、本来ならくつろげるはずの自宅が、常に責任と緊張を背負いながら過ごす場所となってしまいます。
また、介護者が一人の場合、誰にも相談できず孤立感を深めてしまうことも。「親の介護は自分がしなければ」というプレッシャーから、ストレスが日々蓄積していきます。
体力的な負担
在宅介護では、起床介助や移動介助、入浴介助など、一日に何度も要介護者を持ち上げたり支えたりする必要があります。
特に夜間のおむつ交換や排せつ介助が必要な場合は、十分な睡眠時間を確保することができず、疲労が慢性的に蓄積していきます。中には腰やひざを痛めてしまうケースもあり、介護者自身の体調を崩すリスクも高まります。
介護保険サービスを利用していても、体力的な負担を完全になくすことは難しく、このような生活が毎日続くことで、介護者の心身は徐々に疲弊していってしまいます。
経済的な負担
介護が始まると、普段の生活費に加えて介護サービス費の自己負担分が新たに必要となります。介護保険の対象となるサービスでも、1~3割の自己負担が発生します。さらに、紙おむつやデイサービス・デイケアでの食事代など、日常生活にかかる費用は全額自己負担となります。
住宅をバリアフリー化する場合は、数百万円の支出が必要になることもあります。特に兄弟姉妹がいない場合は、介護費用を一人で負担しなければならず、経済的な重圧は増すばかり。この経済的な不安は、さらなる精神的なストレスへとつながっていきます。
親の介護がしんどいと感じる辛さを軽減する7つの方法

介護の負担を一人で抱え込まずに、できるだけ早い段階から適切なサポートを受けることが大切です。
以下では、介護の辛さを和らげるための具体的な方法をご紹介します。
専門的な相談先を見つける
介護の悩みは誰に相談すればよいのか分からなかったり、相談しにくかったりするものです。しかし、誰かに相談することで気持ちが楽になり、有益な情報を得られることも多くあります。下記は具体的な相談先の例です。
【ケアマネジャー】
要介護者の生活状況を把握し、最適な介護プランを立てる専門家です。要介護認定を受けた後、ケアマネジャーを通じてサービスを調整できます。
【地域包括支援センター】
市区町村が運営する窓口で、高齢者の生活全般に関する相談を受け付けています。介護だけでなく、医療や福祉に関する支援も得られます。
【介護家族の会】
同じ悩みを持つ人々と情報共有が可能な場です。孤独を感じやすい介護者にとって、心の負担を軽減する重要なサポートとなります。
【専門医】
信頼できるかかりつけ医がいると、要介護者の健康管理がしやすくなり、安心感が生まれます。医療と介護の連携は、家族の負担軽減にもつながります。
介護保険サービスを利用する
介護の負担を軽減するには、介護保険サービスの活用が効果的です。
【訪問介護】
ホームヘルパーが自宅を訪問して排せつ・入浴・食事介助などの身体介護や生活支援を行います。要介護者が住み慣れた自宅で介護を受けられ、施設入居と比べて費用も抑えられるメリットがあります。
【デイサービス】
要介護者が施設に通って食事や入浴などの生活支援、機能訓練を受けられる日帰りのサービスです。送迎付きで、要介護者の社会参加や気分転換にもなります。
これら以外にも、重要なのが「レスパイトケア」と呼ばれる、介護者の休息のためのサービスがあります。例えばショートステイでは、要介護者が介護施設に短期間宿泊し、介護サービスや生活支援を受けられます。介護者が休息を取ったり、冠婚葬祭や旅行で外出したりする際に利用でき、介護の小休止として活用できます。
市区町村による行政サービスを活用する
各市区町村には、独自の介護支援制度があります。例えば、紙おむつの助成制度は多くの自治体で実施されており、毎月数万円かかる紙おむつ代の負担を軽減できます。また、介護サービス費や医療費が高額になった際の負担を軽減する制度もあります。
具体的には、高額介護サービス費、高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費制度などがあります。これらの制度を利用することで、介護にかかる経済的な負担を抑えることができます。
利用できるサービスは自治体によって異なるため、お住まいの地域の役所窓口や地域包括支援センターに問い合わせて、どのような支援が受けられるか確認してみましょう。経済的な負担が軽減されることで、精神的な余裕も生まれやすくなります。
介護保険外サービスを受ける
介護保険適用のサービスだけでは十分なサポートが得られない場合があります。そんなとき役立つのが介護保険外のサービスです。
主なサービスとしては次のようなものがあります。
【配食サービス】
栄養バランスの取れた食事を定期的に自宅へ届けてもらえます。糖尿病や腎臓病などの持病がある場合は、塩分やカロリーに配慮した食事も選択可能です。
【家事支援サービス】
料理、掃除、洗濯、買い物などの基本的な生活支援に加え、介護保険では対応できない庭の手入れやペットの世話なども依頼できます。同居家族がいる場合でも利用可能で、介護者の負担軽減に大きく貢献します。
これらのサービスは費用が全額自己負担となりますが、介護の状況に応じて柔軟なサービス利用が可能です。ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しながら、自分の状況に合ったサービスを選んでいくとよいでしょう。
介護に関する知識やスキルを身につける
介護のスキルがないことは大きなストレス要因となります。特に移動介助や排せつ介助などは、ある程度のスキルを身につけることで、要介護者も安心して介助を受けられるようになります。その結果、介護者と要介護者の間に信頼関係が生まれ、在宅介護全般がスムーズになっていきます。
多くの市区町村では「家族介護教室」などを開催しており、基本的な介護技術を学ぶことができます。また、認知症の家族を介護している場合は、認知症に関する正しい知識を得ることで、より適切な対応が可能に。介護の知識やスキルを身につけることは、介護者自身の心身の負担軽減につながる重要な取り組みといえます。
家族で役割分担する
介護の負担を一人で抱えるのではなく、家族間で役割分担を行うことで、大きな負担軽減が期待できます。例えば、遠方に住む家族には資金援助をお願いしたり、近くに住む家族が週末介護を担当したりすることで、一人ひとりの負担が軽減されます。
また役割を分担することで、介護者自身が休息を取る時間を確保できるようになり、長期間にわたる介護を支えるうえでの大きな助けとなります。家族間の協力を得るには、介護の現状や課題を率直に話し合い、それぞれができる範囲でサポートする仕組みを作りましょう。
重要なのは、介護の負担が特定の人に集中しないこと、そして介護者を孤立させないことです。
高齢者施設への入所を検討する
介護サービスを利用しても在宅介護が難しいと感じた場合は、施設入所を検討しましょう。施設入所は介護者の負担軽減だけでなく、要介護者にとっても専門スタッフから適切なケアを受けられるというメリットがあります。
特に認知症の方の場合、グループホームでは専門的な認知症ケアを受けることができ、症状の進行を緩和する効果も期待できます。また、他の入居者との交流により生活が活性化されたり、24時間体制の見守りで安全な生活が送れたりするメリットもあります。
施設入所を検討する際は、要介護者の状態や希望に合わせて、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、さまざまな選択肢から最適な施設を選びましょう。
親の介護が長期化するリスクとは?

親の介護は長期化することが多く、医療技術の進歩による長寿化に伴い、介護期間も長くなる傾向にあります。介護が長引くにつれて介護者の負担は増大し、以下のようなリスクが高まっていきます。早めに対策を講じ、深刻な事態を防ぐことが大切です。
介護離職
親の介護をするために仕事を辞める「介護離職」は、多くの介護者が直面する問題です。介護と仕事の両立が難しくなり、近所に頼れる親戚もいない場合、介護に専念するために退職を選択せざるを得なくなります。
しかし、介護離職により収入源がなくなることで、経済的負担が一気に増大。介護保険サービスの利用も難しくなり、生活費を賄うことさえ困難になってしまいます。また、社会との接点が失われることで精神的な孤立感も深まり、心の余裕を失っていきます。
介護うつ
介護うつは、慢性的な睡眠不足や疲労、ストレスなどの「介護疲れ」が蓄積することで発症します。
「楽しみや喜びを感じない」「食欲がない」「よく眠れず、途中で何度も目が覚める」などの症状が現れ、放置すると重症化する恐れがあります。介護うつになると介護者と要介護者の生活が成り立たなくなり、共倒れのリスクが高まります。早めに専門家に相談し、適切な対策を取ることが重要です。
介護放棄や虐待
介護者が疲れ果て、追い込まれてしまうと、冷静な判断ができなくなり、要介護者への虐待や介護放棄につながることがあります。厚生労働省の調査によると、2021年度の養護者による高齢者への虐待の相談・通報件数は36,378件にも上ります。
介護者の介護疲れやストレスが主な原因とされており、身体的虐待や暴言などの心理的虐待、食事やおむつ交換などの基本的なケアの放棄といった形で表れます。このような事態を防ぐためにも、介護負担の軽減と介護者自身のケアが不可欠です。
親の介護がしんどいと感じているなら「親サポセレクト」がおすすめ

離れて暮らす親のケアを一人で担うのは大変な負担となります。セゾンカードでおなじみのクレディセゾンのグループ会社「くらしのセゾン」が提供する「親サポセレクト」(選べる親御さまサポートサービス)は、親のライフステージに合わせて必要なサービスを選択できる会員プランです。
経験豊富な専任スタッフが、親の暮らしをサポートしてくれます。
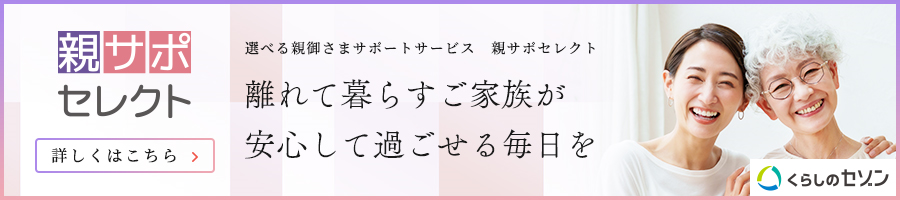

親の日常生活に関する「いつも」のサポート
親の足腰が弱くなってくると、日常生活での負担が増えていきます。「親サポセレクト」の見守りサポートでは、安否確認センサーの設置による緊急時の駆けつけサービスを提供。さらに、病院・買い物への付き添い(1時間あたり税込み5,500円から)や、掃除・洗濯などの家事代行、庭木の手入れまで、暮らしに関するさまざまなサポートを必要に応じて依頼することができます。
親の入院や施設入居時など「もしも」のサポート
突然の入院や施設入居もしっかりとバックアップします。施設への入居を検討し始めたら、介護施設選びの相談ができます。施設紹介から見学の付き添い、入居が決まった際の荷造り・引っ越し(税込み33,000円から)まで、スムーズな移行をサポートします。
また、親が施設に入居したあとに空き家となった実家の家財整理や空き家管理、相続対策など実家にまつわる困り事も相談できます。
親の介護に関する不安や負担を軽減するため、まずは無料の資料請求で最適なプランを確認してみてはいかがでしょうか。
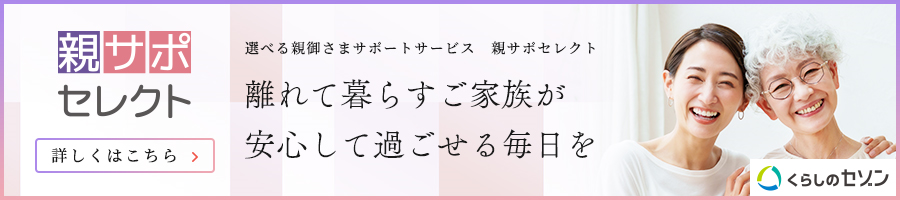

おわりに
親の介護は誰もが直面する可能性のある課題であり、身体的・精神的・経済的な負担は避けられません。しかし、一人で抱え込まず、介護保険サービスや行政サービス、介護保険外サービスなど、利用可能な支援を積極的に活用することで、その負担は大きく軽減できます。
また、家族での役割分担や施設入居の検討など、状況に応じた選択をすることで、介護者と要介護者の双方が安心して生活を送ることができます。介護の長期化に伴うリスクを理解し、早めに対策を講じることが、持続可能な介護生活への第一歩となります。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。