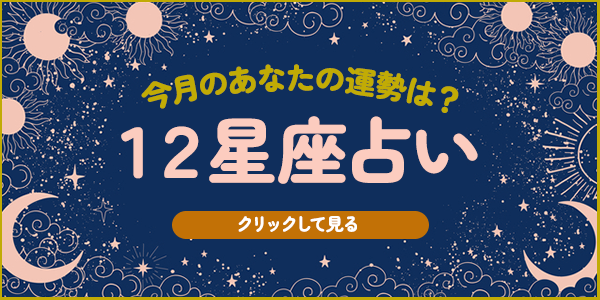相続税対策として「毎年110万円までの生前贈与であれば非課税」というのが広く知られている生前贈与。しかし、注意しなければ“贈与を受けた側”に多額の追徴課税が発生するケースがあると、多賀谷会計事務所の税理士・CFPの宮路幸人氏はいいます。事例をもとに、生前贈与を行う際の「落とし穴」と注意すべきポイントについてみていきましょう。
我が子を思って生前贈与も…子に「追徴税額1,000万円」の悪夢

生前贈与には大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの方法があります。このうち暦年課税の場合、1年間に贈与額が110万円以下は贈与税がかからないため、贈与税の申告も不要です。しかし、場合によっては贈与を受けた側が追徴税額を払わなければいけないこともあります。それはいったいどのような場合なのでしょうか。
知人のアドバイスをきっかけに、110万円ずつを20年間生前贈与したAさん
資産家のA家。都内に自宅と親から相続した賃貸物件を所有していたAさんは、相続税が心配になったため、すでに親の相続を経験している知人に相談しました。
すると知人は、「Aはこのままだと相続税がかかるよ」といいます。「じゃあ、どうすれば防げるんだ」とAさんが尋ねたところ、「今のうちから子どもとか孫に生前贈与しておくと良い。毎年110万円までだったら贈与税の申告も納付も必要ないし、相続税対策になる」と教えてくれました。
早速Aさんは息子名義の口座を作り、そこに毎年110万円を20年間にわたり振り込みました。
その後、Aさんは逝去。46歳の息子は相続税の申告をする段になりましたが、前述の贈与についてはすでに終わったものと考え、相続税の申告に含めずに提出しました。
すると2年後、税務署から連絡がありました。聞けば、「相続税の調査に伺いたい」といいます。そして調査の結果「生前贈与については、贈与の実態がなく認められないため、相続税の申告に含めて計算してください」と言われてしまいました。
相続税の税率は40%だったため、追徴税額として800万円を支払うことに。さらに延滞税と加算税が課され※、合わせて約1,000万円もの大きな金額を支払うはめになったのです。
※本税に加え、延滞税(原則7.3%~14.6%)が課されます。また過少申告加算税(10%~15%)か、悪質だと判断された場合は過少申告加算税に代え重加算税(35%)が課されます。
Aさんの生前贈与が認められなかったワケ

なぜ、110万円に収めたにもかかわらず、Aさんから息子への贈与は否認されたのでしょうか?それは、息子さんが生前贈与の事実を知った“タイミング”にあります。
息子が生前贈与の事実を知ったのは、Aさんが亡くなる直前でした。「実は、20年前から贈与税がかからない範囲で、お前名義の通帳を作り贈与を行っていたんだ」と聞かされ、またその分については相続税の対象とならないと聞かされた息子は、父親からの贈与をありがたく思い、相続税の申告には含めませんでした。
これはつまり、Aさんが贈与を行った時点では息子はその事実を把握していなかったということです。息子名義の通帳と印鑑は、父親であるAさんが管理していました。したがって、「贈与契約」が結ばれていないとみなされ、この贈与は税務調査により否認されることとなりました。
「贈与契約」とは、贈与者が「財産をあげます」、受贈者が「財産をもらいます」というお互いの意思表示のこと。今回の事例ではこれがなかったため、「Aさんが行った行為はAさんに対する贈与ではなく、あくまでも名義預金であり、相続財産に加算して相続税を納める必要がある」ということになりました。
贈与税は、贈与を行った側が生きている間はあまり問題となることはないのですが、いざ相続が起こったとき、子や孫がトラブルに巻き込まれる可能性が高いため注意が必要です。
相続税の税務調査の際、税務署はおおむね被相続人が亡くなる過去10年ほどの、通帳の資金の流れを把握してから調査に伺います。この際、100万円単位などの大きな資金移動がある場合は、「子や孫たちに対する贈与ではないか?」「名義預金ではないか?」と疑われるため注意が必要です。今回のように名義預金と判断された場合、重加算税がかけられる可能性が高いです。
生前贈与が認められるための「3つ」のポイント

では、生前贈与をする際はどのような点に注意して行えばよいのでしょうか?
贈与契約書を作成しておく
生前贈与が成立するためには、「この財産をあげます」と「この財産をもらいます」という贈与者・受贈者両方の合意(=贈与契約)が必要となります。
この贈与契約は口頭でも成立しますが、税務調査が行われるときは贈与者が亡くなっているため、証拠を残すために贈与者と受贈者が署名押印した「贈与契約書」を作成しておきましょう。できれば公証役場で確定日付をとっておくと、より証拠力が高まります。
生前贈与は現金手渡しでなく「銀行振込」で行う
現金で受贈者に渡してしまうと客観的な証拠が残らないため、銀行振込で行いましょう。この場合、通帳に印字されるなどして証拠が残ります。
通帳は受贈者本人が管理する
通帳は子や孫に管理させましょう。贈与者が通帳・印鑑を管理していると、あとで贈与とみなされない可能性が高まります。
“子に内緒で”はNG…追徴課税を受けないために

上記の理由のほか、Aさんのケースでは
- 子に内緒でこっそりと本人名義の通帳を作った
- 毎年110万円ずつ贈与を行った(=定期贈与とみなされた)
ことから生前贈与が認められず、子が追徴課税を受けることとなりました。
「働かずとも親からお金がもらえると思わせるのは教育上よくないだろう」「預金を子どもに管理させたら、無駄遣いするかもしれない」といった心配や親心から、Aさんのように子どもに知らせず贈与を行うケースは実際多いのですが、これでは後々子どもが困ることとなりますから、贈与を行う段階で子の合意を受けるようにしましょう。
また、定期贈与(連年贈与)にも注意が必要です。
毎年110万円の贈与を10年間行った場合であっても、父と子が贈与を行う時点で「1,100万円を110万円ずつに分けて贈与しますよ」と約束した場合「定期贈与」とみなされ、1,100万円に対し贈与税が課される場合があります。
「定期贈与とならないよう、あえて数年に1度110万円を超える贈与を行い、贈与税の申告と納税を済ましているから大丈夫」と思っている人がいるかもしれません。
しかし、こうした場合であっても、子が贈与を受けた認識がなく、その贈与税の申告書と納税を贈与者が行っているような場合には、やはり贈与の実態がないとされ否認されることとなるため注意が必要です。
まとめ
毎年110万円以下の贈与であれば、生前贈与として相続税の負担が少なくなるということは広く知られています。しかし、贈与の実態がない場合は税務調査の際に否認され、子や孫といった受贈者が追徴税額を徴収されることとなりますので注意しましょう。
また、税制改正により、2024年以降の生前贈与加算は3年から7年に徐々に延びることとなります。つまり、今回のような生前贈与による相続税対策に歯止めがかけられる形です。
したがって、生前贈与を行う際は専門家等によく相談されることをおすすめします。