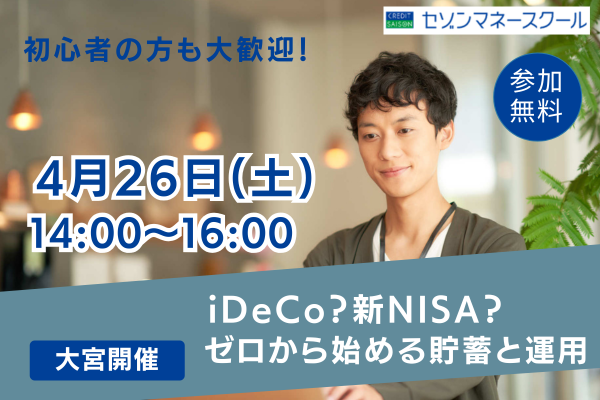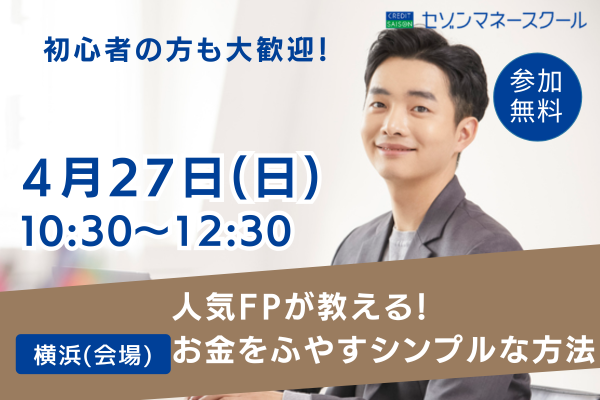親の高齢化に伴い、介護の問題に直面する人が増えています。しかし、介護の負担に不安を感じたり、親との関係性から介護を避けたいと考えたりする人も少なくありません。この記事では、親の介護に関する法的な知識から、介護の現実的な課題、そして介護保険サービスや施設の利用など、さまざまな支援制度を活用した介護の負担軽減方法などについて詳しく解説します。
- 親の介護には法的な義務があり、実子は親の介護を基本的に放棄できない。
- 親の介護を放棄した場合、保護責任者遺棄罪などの法的責任を問われる可能性がある。
- 親の介護は、親子関係や経済的負担、仕事との両立、認知症介護など、さまざまな要因でトラブルになりやすい。
- 介護の負担を軽減するには、親の意向確認、家族での分担、生活保護の活用など、複数の選択肢がある。
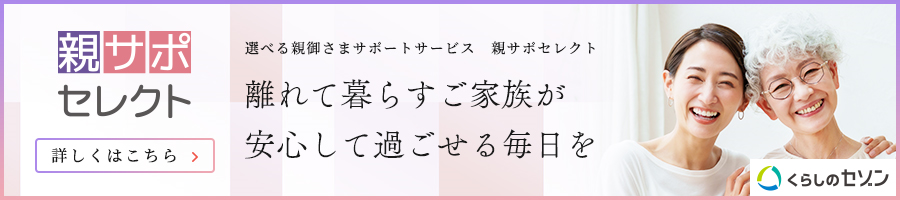

「親の介護」は子どもの義務って本当?

親の高齢化に伴い、介護の問題を避けて通れない時代となりました。「親の介護は子どもの義務である」という認識は広く浸透していますが、具体的にどのような義務があり、どこまで負担しなければならないのでしょうか。
以降では、法律的な観点から介護義務の実態について解説します。
実子には介護義務がある
民法第877条第1項では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。つまり、法律上、子どもには親を扶養する義務があり、これには介護も含まれます。
この介護義務は、以下の範囲の親族に適用されます。
- 実子(息子・娘)
- 孫
- ひ孫などの直系卑属
- 両親
- 祖父母などの直系尊属
- 兄弟姉妹
一方で、義理の親族(配偶者の親など)や、子どもの配偶者(嫁・婿)には法的な介護義務はありません。ただし、家族として協力して介護にあたることが望ましいとされています。
介護義務の内容とは
介護義務の本質は扶養義務であり、具体的には以下の2つの支援が含まれます。
【経済的支援】
- 介護に必要な費用の負担
- 施設入所費用の負担
- 医療費の負担
【身体的支援】
- 日常生活の介助
- 通院の付き添い
- 食事の準備
- 住居の提供
ただし、これらの支援は、介護する側の生活に支障が出ない範囲で行うことが前提です。自身や家族の生活が成り立たなくなるほどの負担を強いられることは想定されていません。
経済的に余裕がない場合は強制ではない
介護義務は法律で定められていますが、一律に強制されるものではありません。以下のような場合、家庭裁判所に申し立てることで、介護の義務を免れる可能性があります。
- 経済的に余裕がない場合
- 自身の生活が成り立たなくなる場合
- 介護者自身が病気や障害を抱えている場合
- 仕事と介護の両立が困難な場合
このような状況下では、介護保険サービスや福祉サービスを活用し、社会的な支援を受けることが推奨されます。介護は家族だけで抱え込むものではなく、社会全体で支えていく時代となっているのです。
親の介護をしないとどうなる?

親の介護を放棄することは、単なる民事上の義務違反にとどまらず、刑事罰の対象となる可能性があります。介護の必要な親を見捨てたり、適切な保護や介護を怠ったりすることは、以下の罪に問われる可能性があるため、慎重な判断が必要です。
| 保護責任者遺棄罪 | ・介助がないと生活できない親を、長時間自宅に置き去りにした ・安全ではない場所(山中など)に放置した ・食事や必要な治療を与えなかった | 3か月以上5年以下の懲役 |
| 保護責任者遺棄致死罪 | ・介助がないと生活できない親を、長時間自宅に置き去りにし、死亡させた ・安全ではない場所(山中など)に放置し、重度の障害を負った | 3年以上20年以下の懲役 |
| 保護責任者遺棄致傷罪 | ・親の介護を放棄してしまい、親に病気や怪我をさせた | 3ヵ月以上15年以下の懲役 |
ただし、これは介護の必要な親を完全に放置するなど、明らかな介護放棄があった場合に適用されるものです。仕事との両立が難しい、経済的な余裕がないなどの理由で、十分な介護ができない場合は、介護保険サービスや施設入所など、代替となる支援策を検討することが大切です。
また、介護に関する悩みは一人で抱え込まず、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な介護の方法を見つけることができるでしょう。
親の介護がトラブルにつながる理由

親の介護は、家族にさまざまな負担やストレスをもたらします。特に長期化する介護では、経済面、時間面、精神面での負担が重なり、家族関係の悪化や介護者の健康問題にまで発展することがあります。
ここでは、親の介護がトラブルにつながりやすい主な理由を解説します。
親子関係が悪く介護を放棄してしまう
親との関係性が良好でない場合、介護を行うことに強い抵抗を感じることがあります。過去の不仲や確執が原因で、介護を拒否したいという気持ちが芽生えてしまうのです。
しかし、介護を完全に放棄することは法的な問題に発展する可能性があります。このような場合は、専門家に相談し、介護施設の利用など、直接的な介護以外の方法を検討することが望ましいでしょう。
親の介護には費用がかかる
介護には予想以上の費用がかかります。施設入所の場合、月に10万円以上の費用が必要になることも珍しくありません。親の預金や年金だけでは賄えない場合、子どもが負担しなければならなくなります。
特に所得の少ない家庭では、自分たちの生活で手一杯のため、親の介護費用まで負担することは困難です。経済的な逼迫は、介護者の精神的なストレスをさらに高めることにもなります。
仕事と介護の両立が難しい
介護のために仕事の時間を削らざるを得なくなったり、最悪の場合、離職を余儀なくされたりすることがあります。厚生労働省の調査によると、介護を理由に離職する人は年間約10万人にのぼります。
収入の減少は家計を圧迫し、介護費用の捻出がさらに困難になるという悪循環を生みます。また、一度離職すると再就職が難しく、将来の生活設計にも大きな影響を及ぼします。
認知症の人を介護するのは心身ともに負担が大きい
認知症の親の介護は、特に大きな負担となります。徘徊や被害妄想、トイレの失敗、食事の記憶の混乱など、症状は多岐にわたります。時には警察のお世話になることもあり、介護者は24時間体制での見守りを強いられることも。
また、認知症の症状による言動の変化は、介護者に強い精神的ストレスを与えます。「自分の親が別人のようになってしまった」という喪失感や、適切なケアができているか不安を抱え続けることで、介護者自身が体調を崩してしまうケースも少なくありません。
介護の負担を軽減するためのポイント

親の介護は長期にわたることが多く、介護者の負担は想像以上に大きくなります。介護離職や介護うつなど、深刻な問題に発展することを防ぐためにも、早い段階から負担を軽減する方法を考えておく必要があります。介護負担を軽減するための具体的なポイントを以下でご紹介します。
親はどんな介護を望んでいるか元気なうちに確認しておく
判断能力が低下する前に、親の介護に対する希望を確認しておくことが重要です。
特に以下の点については、具体的に話し合っておきましょう。
- 介護が必要になったときの生活場所(自宅・施設など)
- 人生の最期を迎えたい場所(自宅・病院・老人ホームなど)
- 延命治療に対する考え
- 預貯金や資産の使い方
早めに話し合うことで、親の意思を尊重した介護計画を立てることができ、後々の判断に迷うことを減らせます。
一人で抱え込まず誰かを頼る
介護を一人で抱え込むことは、身体的にも精神的にも大きな負担となります。できるだけ多くの協力者を得て、負担を分散することが長期的な介護を続けるコツです。
兄弟や親戚で分担する
兄弟姉妹や親戚と話し合い、それぞれができる範囲で介護を分担しましょう。
以下のように分担を検討すると良いでしょう。
- 身体介護(食事・入浴・排せつの介助など)
- 通院の付き添い
- 買い物や家事
- 金銭管理
- 書類の手続き
それぞれの生活状況や時間的制約を考慮し、無理のない範囲で分担を決めることが大切です。
配偶者や子どもにも協力してもらう
配偶者には法的な介護義務はありませんが、家族として可能な範囲での協力を求めましょう。直接的な介護が難しい場合でも、以下のような形での支援が考えられます。
- 家事の分担
- 子育ての協力
- 介護者の精神的サポート
- 休日の介護交代
介護ができない場合、親が生活保護を受ける
介護の負担が大きすぎる場合、生活保護の利用も検討する価値があります。以下の条件を満たす場合、生活保護を受けられる可能性があります。
- 資産を持っていない
- 働くことができない
- 他の公的制度が利用できない
- 親族からの支援が受けられない
生活保護を受給することで、施設入所の費用を賄うことも可能です。ただし、事前に福祉事務所に相談し、詳しい条件を確認する必要があります。
親の介護をしたくない・できない場合の解決策

親の介護は大きな責任を伴いますが、仕事や家庭の事情で十分な介護ができない場合もあります。また、親との関係性や経済的な理由から、介護を担うことが難しいケースもあるでしょう。
まずは、どのようなサービスを利用できるか情報収集をしましょう。現在はさまざまな介護サポートがあり、状況に応じて適切なサービスを選択することで、介護の負担を軽減できます。
介護施設に入居する
介護施設への入居は、介護の負担を大幅に軽減できる選択肢の一つです。施設には専門のスタッフが常駐し、24時間体制で介護を提供してくれます。
主な施設タイプには以下があります。
- 特別養護老人ホーム(介護保険適用)
- 介護付き有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- グループホーム(認知症の方向け)
各自治体の「地域包括支援センター」に相談する
地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として各市町村に設置されています。介護の専門家が常駐しており、介護保険サービスの利用方法から施設の情報提供、介護予防に関するアドバイス、認知症の相談まで、幅広い支援を受けることができます。
介護に関する悩みを一人で抱え込まず、まずは相談してみることをおすすめします。
介護保険サービスを利用する
介護保険サービスは、65歳以上の高齢者と、40歳から64歳までの医療保険加入者で特定疾患の患者が利用できます。訪問介護による日常生活の支援や、デイサービスでの通所介護、短期入所による一時的な施設利用など、ニーズに合わせたサービスを選択できます。
利用者の自己負担は収入に応じて1割から3割となっており、比較的手頃な費用で必要なサービスを受けることができます。
民間の介護サービスを利用する
介護保険適用外のサービスとして、民間企業によるさまざまなサポートも充実しています。栄養バランスの取れた食事を定期的に届ける配食サービスや、掃除・洗濯・買い物などを代行する家事支援サービス、通院や外出をサポートする移送サービスなど、必要に応じて柔軟に利用することができます。
これらのサービスについても、地域包括支援センターで情報提供している場合がありますので、相談してみるとよいでしょう。
親の介護の相談はくらしのセゾンの「親サポセレクト」へ

介護の課題に直面する多くの方にとって、自身の生活との両立が大きな課題です。セゾンカードでおなじみのクレディセゾンのグループ会社、くらしのセゾンが運営する選べる親御さまサポートサービス「親サポセレクト」は、離れて暮らす親の介護を介護者とともに支えるさまざまなサービスを提供しています
このサービスの特徴は、親のライフステージに合わせて必要なときに必要なサービスを柔軟に選択できる点にあります。健康な時期からの見守りサービスはもちろん、生活支援が必要になった際の本格的なケアまで、状況の変化に応じて必要なサポートを組み合わせることができます。サービスの選択に迷った際は、ご要望を丁寧にヒアリングし、専門スタッフが最適な組み合わせを提案する体制が整っています。
安全面での対策も万全です。自宅に見守りシステムの専用機器を設置し、親の在宅時の様子を見守ります。また、体調不良などの緊急時にはかんたんな操作で通報でき、専任スタッフが駆けつけるため、離れて暮らす子どもの不安を大きく軽減します。
日常生活のサポートも充実しています。病院への通院や買い物などの外出時の付き添い代行、掃除・洗濯といった家事代行など、きめ細やかなサービスを提供します。親の自立した生活をバックアップし、帰省回数を減らして自分の生活との両立をスムーズにする体制が整っています。
親の介護は多くの方が避けて通れない人生の重要なステージです。介護の義務や負担に不安を感じる方も多いかもしれませんが、適切なサポートを活用することで、より良い介護環境を築くことができます。まずは「親サポセレクト」の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
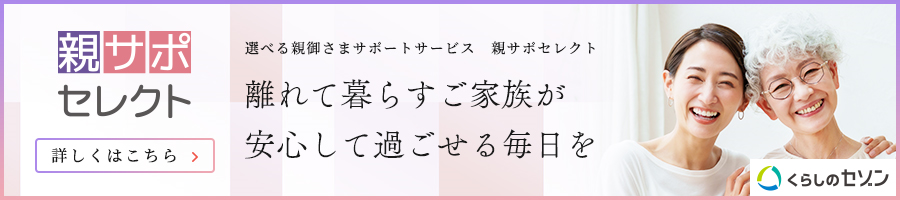

おわりに
親の介護は、法律上の義務があるものの、一人で抱え込む必要はありません。早い段階から親の希望を確認し、家族で介護の分担を話し合うことで、将来の負担を軽減することができます。また、介護保険サービスや施設の利用、地域包括支援センターへの相談など、さまざまな支援制度を活用することで、より良い介護環境を整えることが可能です。介護は長期戦となりますが、適切なサポートを受けながら進めることで、介護者自身の生活も大切にしながら親の介護を行うことができるでしょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。