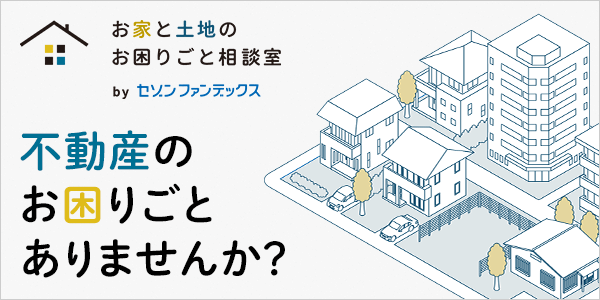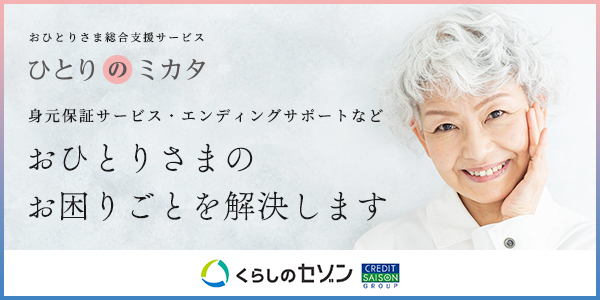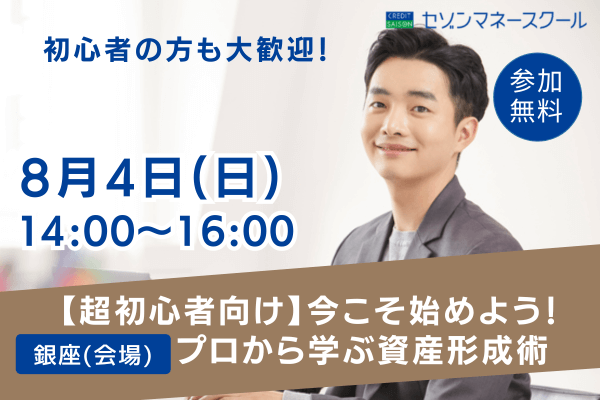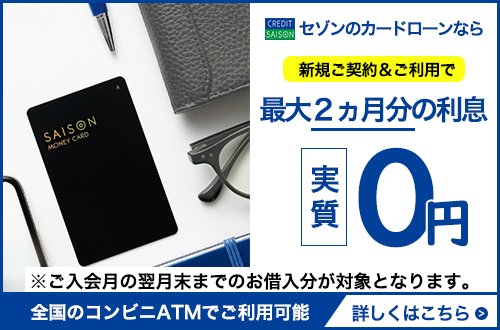意外とお金のかかる納骨について、できれば費用負担を抑えたいという方も多いでしょう。このコラムでは、比較的お金をかけずに納骨する方法や、納骨費用が足りないときの対処方法などをわかりやすく解説しています。
近年増加しているとされる墓じまいの費用を抑える方法についても触れているので、納骨だけではなく墓じまいにかかるお金を減らしたい方もぜひチェックしてみてください。


納骨に期限はある?

納骨は、火葬が終わったあとに遺骨をお墓や納骨堂に納めることです。納骨自体必ず行う必要があるものではありませんし、納骨する期限についても特に法的、宗教的な決まりはありません。
一般的な納骨のタイミングは、大きく分けて3種類あります。まず仏教で故人の魂が完全に死後の世界に向かうとされる「四十九日」です。四十九日には親戚などが集まる法要が執り行われるので、法要後に納骨を行う流れになります。
次に泣いてばかりいる日々から卒業するタイミングとされる「百か日」です。百か日であれば、死後にお墓を購入したとしても墓石などの準備が間に合うでしょう。3つ目のタイミングは喪が明ける「一周忌」です。このタイミングでも法要が行われるため、法要後に納骨を行います。
なお、遺骨をそのまま捨てると法律違反となり懲役刑や罰金を課せられる可能性があるため、ご自身で勝手に埋葬することは避けましょう。
お金をかけずに納骨する方法

一般的にお墓を立てる際の費用相場は100〜350万円といわれていますが、まとまったお金を捻出するのは難しいという場合も少なくないでしょう。とはいえ「お金はないけれど、きちんと供養をしてあげたい」という気持ちを持っている方も多いと思います。
そこでここからは、できるだけお金をかけずに納骨を行う方法をご紹介していきます。
参照元:お墓を買うお金がない場合の対処法!お金をかけずに供養をする方法とは | ライフドット
合葬墓
合葬墓は共同墓、合祀墓とも呼ばれるもので、他の方の遺骨とともに大きなお墓に納骨を行う方法です。費用は一体あたり30,000円〜150,000円程度となっています。納骨を行うと他の方と骨が混ざり、1度納骨してしまうと取り出せなくなるため、注意しましょう。
永代供養墓
合葬墓がすぐに他の方と一緒に納骨されるのに対し、永代供養墓は一定の期間個別に管理を行ってもらえる場合もある納骨方法です。個別の管理が行われることで合葬墓よりも手厚く供養を行ってもらえるため合葬墓よりも高いケースが多く、種類にもよりますが400,000円程度が相場とされます。
参照元:永代供養の一般的な料金・相場はどのくらい? 墓石、墓地
納骨堂
近年利用が増えているとされる納骨堂は、経営の主体によって種類が分かれます。
公営(市営)納骨堂
特に人気が高いとされるのが公営納骨堂です。30年利用しても2体で210,000円程度、1年で1体7,000円程度の費用で済む納骨堂があるなど、費用の安いことが人気の理由といえるでしょう。さらに自治体の管理であるために運営が安定しており、経営破綻などのリスクがないこともメリットです。
一方で全体の6%程度と数が少なく、人気であるために倍率が高いといったデメリットもあります。また最長でも5年など収骨期間が短い一時収蔵納骨堂も存在するため、使用できる期間は必ず事前に確認しましょう。
民間・寺院が運営する納骨堂
全体の7割以上を占めるのが、民間や寺院が運営する納骨堂です。公営のものよりも費用負担は大きくなりますが、手厚く供養を行ってくれる場合が多いとされます。寺院の場合には、年に数回行われる法要に家族が参加することなども可能です。
参照元:全国の公営納骨堂を紹介|メリットや費用、申込みの流れまで解説! | ライフドット
樹木葬
墓石ではなく樹木を墓標とする樹木葬には、個別に納骨するものと合葬するものがあります。個別に納骨する場合は500,000円程度、合葬するものでは50,000円〜400,000円程度が費用相場です。墓石を使わないため、個別であっても大きく費用相場を抑えられることが大きな特徴といえるでしょう。
ガーデニング風のものや日本庭園風のもの、自然に還るようなイメージの里山風のものなど、一口に樹木葬といってもさまざまな形があります。故人の好みを踏まえて選んであげるのも良いでしょう。また樹木葬は、基本的に永代供養とされます。
公営墓地
市などが運営する公営墓地は、土地使用料とされる永代使用料が民間のものよりも安いのが特徴です。年間管理料は1,000円~5,000円程度が相場で、使用料は都立であれば安いところで1平米当たり850,000円、高いところでは1平米275万円と大きく開きがあり、郊外に行くほど使用料は安くなる傾向があります。
申込のタイミングが限定されていたり、その自治体に居住する方だけが申し込めるなどの制限を設けたりしている場合もあるため、公営墓地の利用を考えているのであれば事前に確認しておきましょう。
参照元:公営墓地とは?費用や申し込み方法を解説!民営霊園や寺院墓地との違い
お墓を持たなくてもできる供養とは?

お墓を持たずとも故人の供養を行うことは可能であり、お墓を購入するよりも安価で済むケースが多くなっています。具体的にどういった供養方法があるのか見ていきましょう。
手元(自宅)供養
火葬場で骨壺に納めた遺骨をそのまま自宅に置いておくため、費用がかからないのが手元供養です。
骨壺そのままではなく、オブジェのような見た目をしたミニ骨壺やアクセサリーとして身に着けられるペンダントタイプのものなどで手元供養を行う方も増えてきています。種類にもよりますが、相場は30,000円〜100,000円程度です。
手元供養の場合、ご自身が管理できなくなったときにどうするのかを決めておくことが重要です。先に述べたように遺骨は勝手に埋葬するなどの方法が取れないため、周囲の方に遺骨をどうしたいのかあらかじめ伝えておきましょう。
散骨
散骨は粉状にした遺骨をまく供養方法で、散骨方法によって費用は異なります。海に遺骨をまく海洋散骨や山などに遺骨をまく山散骨は、50,000円程度から行うことが可能です。
宇宙に向けてバルーンを飛ばしたりロケットに遺骨を乗せて成層圏に散骨したりする宇宙葬は240,000円程度から行えるとされます。
もしご自身で散骨を行いたいという場合には散骨自体の費用はかかりませんが、遺骨を粉状にする費用はかかるので注意しましょう。
参照元:散骨にはどんな種類があるの?種類ごとの料金と注意点とは?
送骨・迎骨
遺骨を寺院などに送付して永代供養墓などに入れてもらうサービスが送骨で、スタッフが自宅まで遺骨を受け取りに来て合祀墓に埋葬してもらうサービスが迎骨です。送骨は安いもので10,000円から行えますが相場としては30,000円〜50,000円程度で、迎骨は30,000円と別途10,000円以上の手数料がかかるとされます。
遺骨を郵送で送る場合にはゆうパックを使用する形になりますが、遺骨を郵送することに抵抗がある場合には迎骨を選ぶなどすると良いでしょう。
参照元:迎骨とは?遺骨を供養したいけどお金がない人必見です! | お墓さがし
本山納骨
信仰する仏教の宗派があれば、宗派の本山に納骨する方法も選べます。納骨の際にはお布施が必要となり、お布施の相場は30,000円〜50,000円以上です。お布施といわれてもいくら支払えば良いか分からずに悩む場合もあると思いますが、ほとんどの寺院では目安の金額が提示されています。
寺院の中には宗派を問わずに納骨可能なお寺もあるため、本山納骨に興味があれば調べてみましょう。
骨仏
遺骨で大仏を作る骨仏という供養方法もあり、費用の負担は30,000円〜100万円と幅広くなっています。永代供養を手厚く行う場合などは費用負担が大きくなるようです。骨仏の作り方はさまざまあり、空洞の大仏の中に遺骨を入れるものや、粘土に骨を混ぜて焼き上げ骨仏を作るものなどがあります。
骨仏がある寺院にお墓参りすることはできますが、多くの方が入った大きな骨仏の場合には順番待ちが発生し、かなり時間がかかってしまう場合もあるとのこと。どのような形の骨仏なのか事前に確認しておくと安心でしょう。
納骨費用が足りないときは?
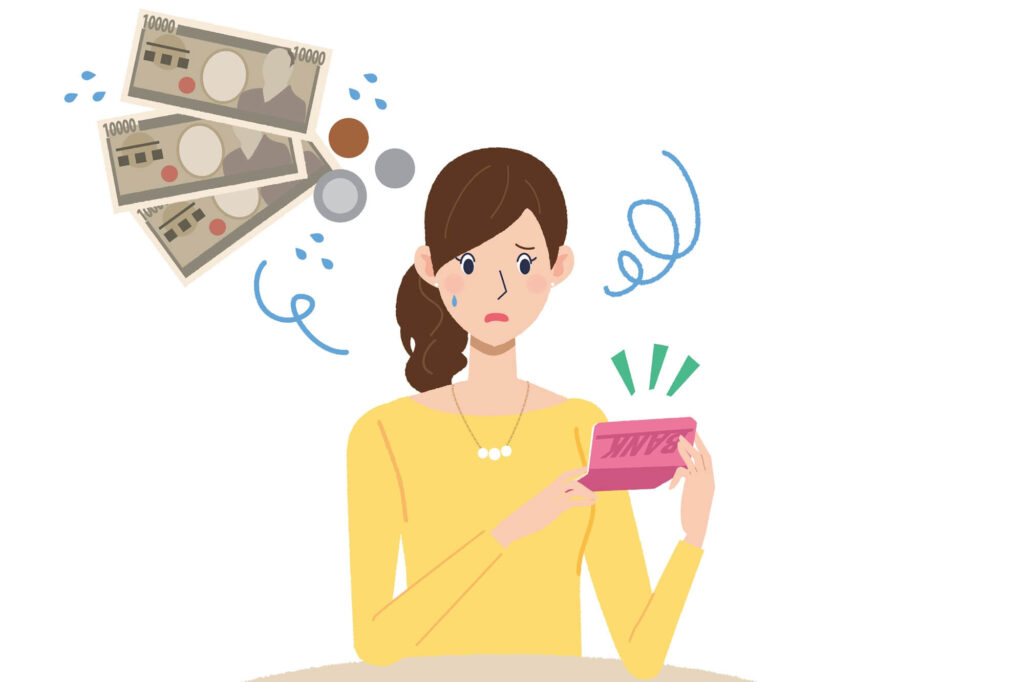
さまざまな納骨方法を見てきましたが、「お金に余裕はないけれど、やっぱりきちんとお墓を立てて供養してあげたい」と考える方もいるでしょう。ここからは、納骨費用が足りないときにどうすれば良いのかまとめていきます。
補助制度の利用
亡くなった方が共済組合や組合健保、協会けんぽなどの社会保険組合に加入していた場合、遺骨の埋葬を行う方に補助金の出る制度があります。必要な書類を添付すれば申請可能なので、加入の有無を調べて申請してみましょう。
ただしこの補助金は亡くなった日の翌日から2年以内が申請期限となっているため、申請を忘れないよう注意が必要です。
参照元:全国健康保険協会 ご本人・ご家族が 亡くなったときの給付金
メモリアルローン
一部の金融機関などが提供しており、お墓や葬儀、仏具などに使う目的でローンを組むことができるのがメモリアルローンです。金利は6%〜10%程度が相場とされます。
メモリアルとついているとおり、資金を使用できるシーンが限られているのが特徴で、どのような目的でも使用できるローンに比べて金利は安い傾向にあります。金融機関ごとに使用できる範囲は異なるため、墓石の購入に使えるかなどをチェックしてから契約するようにしましょう。
なお、ローンなどを組む場合には借入金額が100,000円以上と定められている場合があります。先に挙げたようなお金がかからない納骨方法の場合には金額によってローンが組めないことも考えられるので、注意が必要です。
参照元:お墓にローンは使える?樹木葬や納骨堂の場合は? | お墓さがし
墓石ローン
石材店が独自に用意しているローンを墓石ローンと呼びます。金利相場は0〜4%と金融機関のものよりも低い傾向です。ただし墓石に関わらない費用、例えばお墓の場所代にあたる永代使用料などはローンの対象とならない場合があります。
また全国の優良石材店が加盟する「全優石」に加盟している石材店では、墓石ローンではなくメモリアルローンが実施されている場合もあるとされます。ローンの内容がどういったものなのか、きちんと確認しておくことが大切でしょう。
フリー(多目的)ローン
フリーローンは目的を問わずに使えるローンなので、ほとんどの金融機関で取り扱いのあるのが特徴です。金利の平均は1.5%〜15%と開きがありますが、同一金額を借りる場合にはメモリアルローンに比べて金利が高いとされます。
クレディセゾンが提供する「MONEY CARD(マネーカード)」は、最短即日でお金を受け取れる利用目的が自由のローンです。


マネーカードについて詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
近年増加する「墓じまい」の費用を抑えるコツ
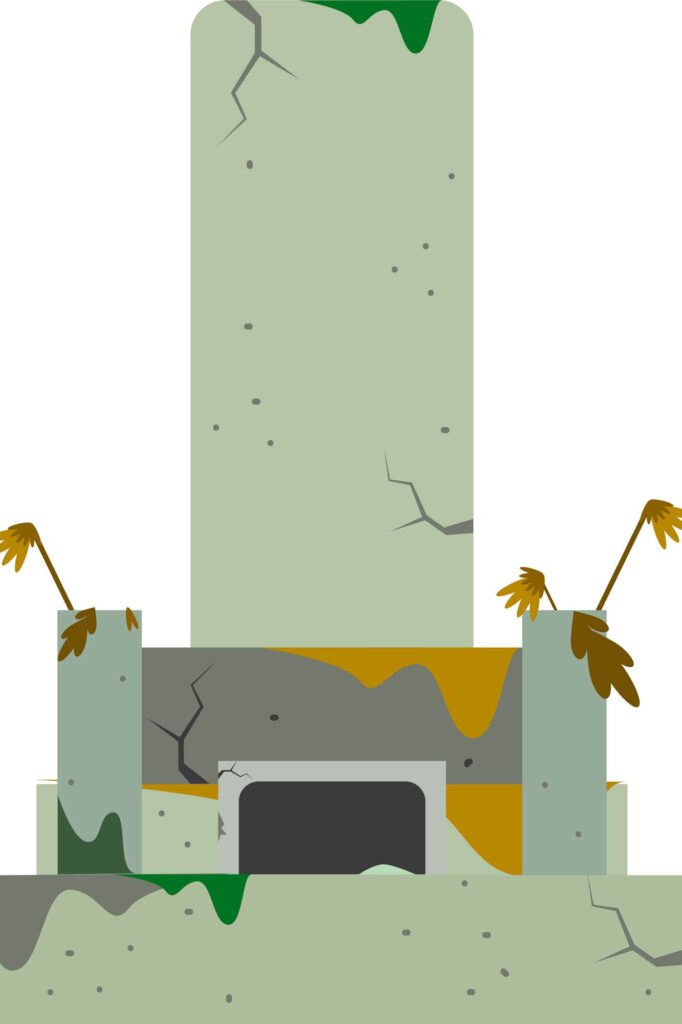
跡を継ぐ方がいないお墓を解体して処分する墓じまいは、「お墓が遠すぎてお参りに行けない」「家族に負担を掛けたくない」などの理由から、近年増加の傾向にあります。
費用は区画の面積や石がどれほど使われているかで変わってきますが、200,000円〜300,000円が相場です。他にもお墓から遺骨を取り出すときに魂を抜く閉眼供養を行う場合には、お布施として30,000円〜100,000円ほどかかるとされます。
ここでは、墓じまいにあまりお金をかけたくない場合に押さえておきたいポイントをご紹介していきましょう。
参照元:墓じまいに補助金はある?費用を安く抑える方法も解説 | お墓さがし
補助金や優遇措置を利用する
お墓を管理する方がいなくなる無縁仏を増やさないため、自治体によっては墓じまいに対する補助金や墓じまいを行いやすいような制度を設けている場合があります。
補助金や制度はなくてもお墓を使用し始めてからの期間が短い場合や墓石を建立していない場合などは、使用料を返金してくれることもあるでしょう。
現状では補助金が出る自治体の数は多くありませんが、公営墓地の中には先に挙げたように条件次第で使用料の一部が返還されることもあります。墓じまいをするとなったら、まずお墓がある場所の自治体に何か利用できる制度がないか相談してみると良いでしょう。
複数の事業者から見積もりをとる
いくつかの石材店から相見積もりをとることで、費用負担を減らせる可能性があります。相見積もりをとると適正な価格かどうかの判断がつきやすくなるうえ、価格の交渉も行いやすいでしょう。目安として6社以上から相見積もりをとると、最も安い値段に近い金額になるとされています。
公営墓地や共同墓地では指定石材店がいないケースが多いものの、民間の霊園や一部の寺院の墓地では指定の石材店がある場合も。指定石材店がある場合には原則として相見積もりは取れないため、注意してください。
なお解体専門会社にお墓の撤去工事を依頼することもできますが、安い解体専門会社を選んだ結果他のお墓に傷を付けてしまい、トラブルになったケースもあります。お墓のプロである石材店を利用した方が安心して工事を頼めるでしょう。
参照元:相見積もりとは?意味やメリット、マナーなど交渉のポイントを解説 | Leaner Magazine
新たな供養先の費用を抑える
墓じまいをしたとしても、手元供養をしない限りは新たな供養先を用意しなければなりません。新たな供養先を設ける場合には、これまで挙げてきたような費用負担の少ない納骨方法や供養方法を選ぶと、墓じまいにかかる費用を抑えることができます。
寺院とのトラブルを避ける
寺院が管理する墓地の場合、これまでお世話になった感謝の気持ちを込めたお布施である「離檀料」を寺院に納めることがあります。まれではありますが、突然墓じまいをするなどと寺院に話したために、数百万円など高額な離檀料を請求されたという事例があります。
寺院とのトラブルを避けるためにも急に墓じまいについて話すのではなく、お墓の管理が難しくて困っているなどの現状を事前に伝えておくことが大切です。万が一、支払えないほど高額の離檀料を請求されてしまった場合には、撤去を依頼する石材店や法律の専門家などに相談してみましょう。
おわりに
お金がないという理由から、納骨をあきらめてしまっている方もいるかもしれません。しかし補助金やローンの利用、費用負担を抑えられる納骨方法を選ぶことで、お金をかけずに納骨を行うこともできるのです。
故人の意向や遺志を尊重した納骨方法を選んで、故人をきちんと供養してあげましょう。