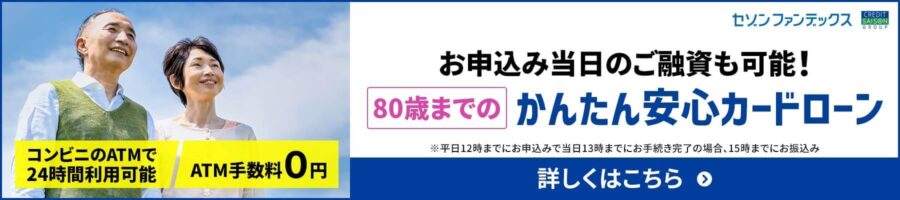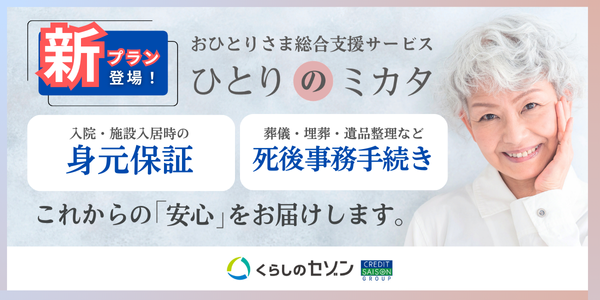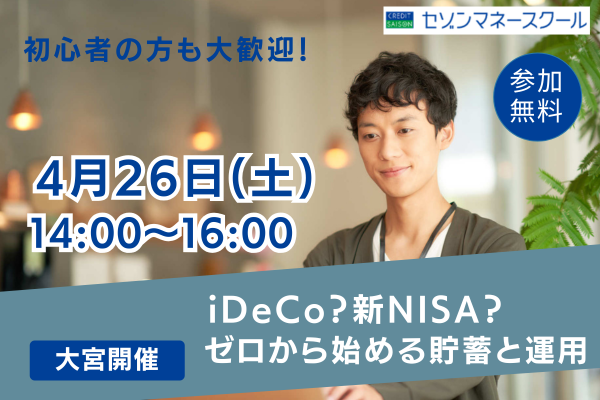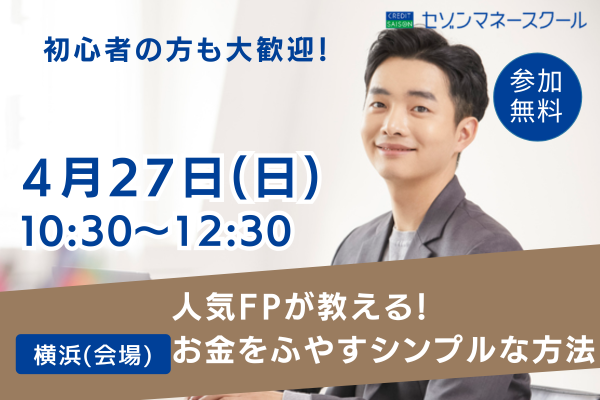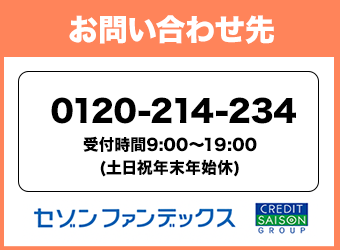贈与税は財産を贈与された場合に課せられる税金ですが、さまざまな理由から納付が難しい方も少なくありません。今回は贈与税が払えないときの対処法を詳しく解説します。また計算方法や滞納時のペナルティなども紹介するので、贈与税を総合的に理解したい方はぜひご一読ください。
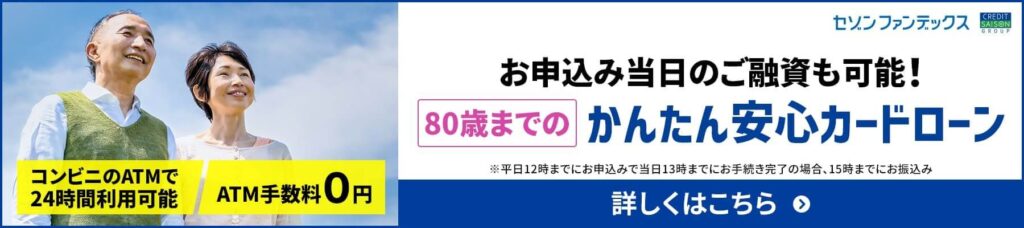
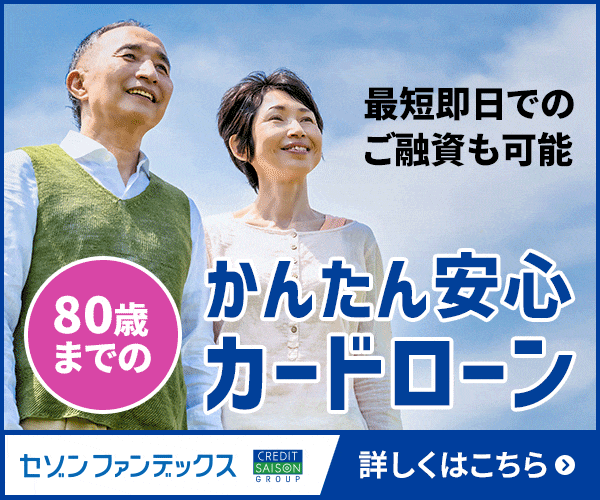
贈与税とは?課税の対象は

贈与税とはどういったものなのか、その計算方法や課税対象などを詳しく解説します。
贈与税とは
贈与税とは、個人が生前に贈与を受けた財産に課せられる税金です。生前贈与とは、財産を所有する方が生前に自分の意思で他の方に財産を譲ることをいいます。ただし法人から財産を受け取った場合は、贈与税ではなく所得税が課せられます。
また財産の受け取りには遺産相続もありますが、これは被相続人の死後に行われるため贈与税ではなく、相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。それぞれの概要は以下のとおりです。
| 課税方法 | 概要 |
|---|---|
| 暦年課税 | 1月1日から12月31日までの間に受けた贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた後、残りの金額に適用される税率をかけて算出する課税方法。 |
| 相続時精算課税 | 上記の基礎控除額110万円に加え、特別控除額2,500万円(前年以前に控除を行っている場合は残額)までは贈与税が課せられない代わりに、贈与者の死亡時に相続税を納める課税方法。 |
課税方法は、1人の贈与者につき一方を選択します。例えば贈与者が2人いる場合は、1人には暦年課税、もう1人には相続時精算課税を適用することも可能です。
なお、相続時精算課税を選択する際は、贈与者と受贈者について以下の条件を満たす必要があります。
- 贈与者:贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母
- 受贈者:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人(相続権の優先順位が最も高い者)または孫
相続税の具体的な算出方法は次の章で見ていきましょう。
参照元:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」「No.4103 相続時精算課税の選択」
贈与税の計算方法
贈与税は1月1日から12月31日までの間に受けた贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた後、残りの金額に適用される税率をかけて算出します。ただし1年間に複数の贈与を受け、かつ暦年課税と相続時精算課税の両方を適用する場合は、220万円が贈与額の合計から控除されます。
なお贈与財産は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2種類に分けられており、それぞれ異なる税率が適用される点が特徴です。特例贈与財産とは、18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の方が直系尊属(父母や祖父母など)から受けた贈与のことで、一般贈与財産はそれ以外を指します。
暦年課税を選択する場合、それぞれの計算には下記の速算表が用いられます。
【一般贈与財産の場合】
| 基礎控除後(110万円または220万円超)の財産の価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【特例贈与財産の場合】
| 基礎控除後(110万円または220万円超)の財産の価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
なお一般贈与財産と特例贈与財産の両方を計算するケースもあり、例えば18歳以上の方が自分の両親と配偶者から贈与を受けたときは、以下の方法で計算します。
- すべての財産を一般税率で計算した税額に占める一般贈与財産の割合に応じた税額を計算する。
- すべての財産を特例税率で計算した税額に占める特例贈与財産の割合に応じた税額を計算する。
- 1と2の計算額を合計する。
例:一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合
- すべての贈与を一般贈与財産として計算する
すべての贈与を一般贈与財産として計算し、基礎控除後の課税価格に対する税額を求めます。- (100万円+400万円−110万円(基礎控除))×20%−25万円=53万円
- 一般贈与財産に対応する税額を計算
一般贈与財産の全体に占める割合を求め、税額を計算します。- 53万円×(100万円/500万円)=10.6万円
- すべての贈与を特例贈与財産として計算
すべての贈与を特例贈与財産として計算し、基礎控除後の課税価格に対する税額を求めます。- (100万円+400万円−110万円(基礎控除))×15%−10万円=48.5万円
- 特例贈与財産に対応する税額を計算
特例贈与財産の全体に占める割合を求め、税額を計算します。- 48.5万円×(400万円/500万円)=38.8万円
- 2と4を合計する
両者の税額を合算します。- 10.6万円+38.8万円=49.4万円
暦年課税だと、納付する贈与税額は、一般贈与財産と特例贈与財産の合計です。
一方、相続時精算課税の場合は以下の式で贈与税額を計算します。
贈与税額 = (相続財産の合計額 – 基礎控除額(110万円または220万円) – 特別控除額(2,500万円 – 前年以前に受けた控除額)) × 税率(20%)
暦年課税の場合とは異なり、税率が一律20%である点を押さえておきましょう。
参照元:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率」「No.4103 相続時精算課税の選択」
贈与税が課せられるもの
次に贈与税が課せられるものを紹介します。
- 生活費や教育費以外の現金や預金
- 株式などの有価証券
- 土地・建物などの不動産
また以下のケースは「みなし贈与」と呼ばれ、贈与税の対象になる場合があります。
- 掛金を負担せずに生命保険や損害保険などの保険金を受け取った
- 対価を支払わず不動産や株券の名義を自分に変更した
- 無利子あるいは低利子で金銭を借りた
- 借金を肩代わりした
- 相場よりも極端に低い価格で財産を譲り受けた
参照元:国税庁「No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」
贈与税が課せられないもの
ここでは贈与税が課せられないものを紹介します。教育費・学費、結婚式の費用などは上限額や条件がありますので注意が必要です。
- 日常の生活費
- 学校や塾などに支払う教育費・学資金
- 結婚式の費用
- 出産費用
- お祝い金
- お香典・見舞金・贈答品
- 基礎控除額(110万円)以内の贈与(ただし、被相続人が亡くなる前7年以内の贈与は相続税の対象となります)
- 法人からもらった財産(※ただし所得税がかかります)
- 宗教や慈善、学術などの公益を目的とする事業を行う者が取得した財産
- 心身障害者共済制度に基づいて支給された給付金
- 公職選挙法の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産
- 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
贈与税がかからないケースを頭に入れておきましょう。
参照元:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」「No.4402 贈与税がかかる場合」「財産をもらったとき」
贈与税を払わないとどうなる?
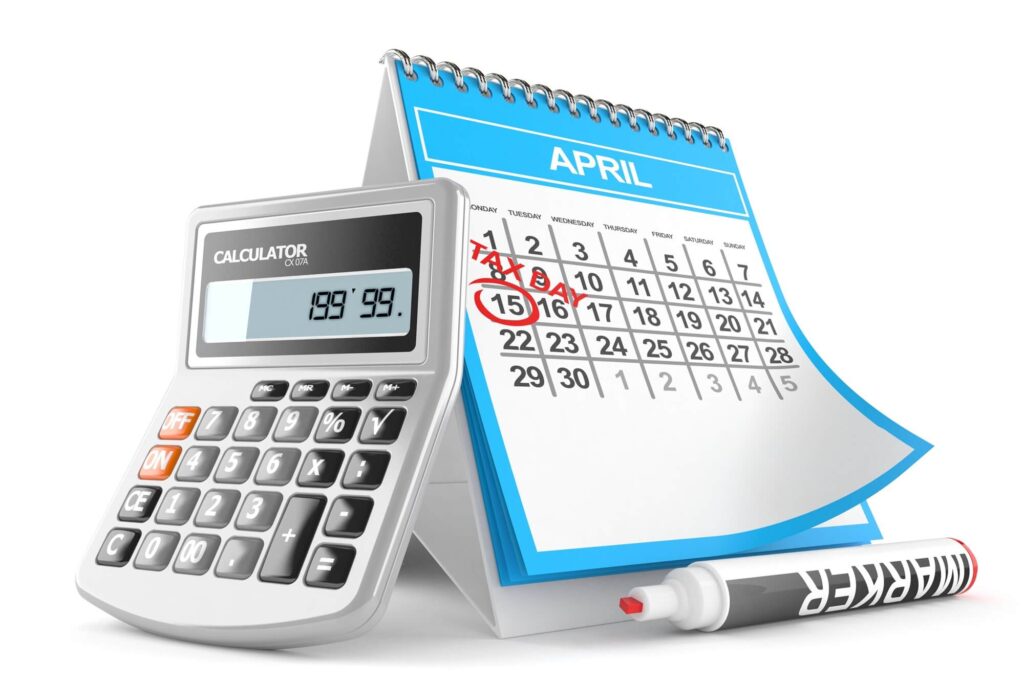
贈与税を納めなかった場合と、納付が遅れたときに起こるリスクを解説します。
申告せずに放置していた場合
贈与税を申告せずに放置していた場合、課税処分を受ける可能性があります。なお贈与税の時効は原則6年で成立しますが「偽りその他不正の行為」の場合は、除斥期間が7年に延びます。
贈与税の申告を怠ったときに課せられる加算税は、以下のとおりです。
| 加算税の名称 | 課税要件 | 税率 |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 期限内申告について、修正申告や更正処分があった場合 | 10%~15% |
| 無申告加算税 | 期限後申告や決定処分があった場合 期限後申告や決定処分について、修正申告や更正処分がなされた場合 | 15%~30% |
| 重加算税 | 仮装隠蔽があった場合 | 35%~40% |
なお7年経過した場合でもあとから相続税として課税される可能性があります。
参照元:財務省
納付が遅れた場合
贈与税を納期限以降に納めた場合は延滞税が課せられます。税率は納税までの期間に応じて以下のとおりに定められています。
納期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで
| 令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間 | 年2.4% |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間 | 年2.5% |
納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降
| 令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間 | 年8.7% |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間 | 年8.8% |
ペナルティが科される事態にならないよう、期限内の納付を心がけましょう。
参照元:国税庁 延滞税について
贈与税の延納制度

贈与税の一括納付が困難な場合は、延納制度を利用できるケースがあります。
ここでは延納制度の適用条件や手続き方法を詳しく紹介します。
延納制度とは
延納制度を利用すると、条件を満たすことで最長5年間に分けて分割納付が可能です。
なお延納制度を利用するときは、利子税を納める必要があります。税率は延滞税よりも低いですが、分割納付する時期により異なるため、利用する際は確認を忘れないようにしましょう。
延納制度の適用条件
延納制度を利用するには、以下3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 贈与税額が10万円を超える
- 納期限までに金銭納付が可能な金額よりも贈与税額が多い
- 延納期間が3年を超えるときや納税額が100万円を超える場合には税務署に担保提供をする
これらの要件を満たすと延納制度の手続きを行うことができます。
参照元:国税庁 相続税贈与税の延納の手引
延納制度の手続き方法は
延納制度を利用するには、事前に所轄税務署長の承認が必要です。納付期限までに「贈与税の延納申請書」と「担保提供関係書類」を提出してください。ただし担保が必要ない場合は「担保提供関係書類」は不要です。
なお延納制度は許可制のため、税務署が認めた場合のみ分割納付が可能です。提出する書類に不備があると申請が却下される可能性もあります。その場合は、速やかに贈与税を一括納付する必要があり、遅れると延滞税も併せて納めることになります。
確実に延納制度を利用したい場合は、税理士事務所に相談して手続きを依頼しましょう。
延納制度で適用される税率
延納制度を利用すると、延納によってかかる利子税が発生します。この利子税は、以下の計算方法で求められます。
- 利子税額 = 延納税額 ×(延納利子税割合 × 延納特例基準割合 ÷ 7.3%)
延納利子税割合は、延納金額にかかる利子税の割合を示し、贈与税を延納する場合は6.6%と定められています。
延納特例基準割合は銀行の新規短期貸出約定平均金利の年平均に0.5%を加えた割合で、令和6年度は0.9%です。
延納特例基準割合が7.3%未満の場合、令和6年度の贈与税にかかる利子税率は以下のように計算されます。
- 利子税率 = 6.6%(延納利子税割合)× 0.9%(延納特例基準割合)÷ 7.3%=0.8%(小数点第二位以下切り捨て)
税率は今後も変更される可能性があるため、最新の情報は国税庁のWEBサイトで確認してください。
延納制度を利用できない場合の贈与税対策

延納制度が利用できない場合の対策を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
相続時精算課税制度を利用して納税額を減少させる
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫への生前贈与の際、2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。ただし贈与した方が亡くなったときは、過去にこの制度を利用して贈与した財産にも相続税が課されます。最終的には納付しなければいけないため、税金の先送りができる制度になります。
この制度の注意点は、利用すると110万円の暦年非課税枠が使えなくなる点ですが、2024年度の改正により相続時精算課税制度に毎年110万円の控除枠が設けられました。
相続時精算課税制度を利用する際は「贈与税の申告書」と「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出します。1回目の提出の際は、受贈者の戸籍謄本か戸籍抄本も添付する必要がありますが、2回目以降は必要ありません。
贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書は、税務署で受け取るか国税庁のホームページでダウンロードしてください。戸籍謄本と戸籍抄本は、本籍地のある市区町村役場で取得できます。
参照元:国税庁 相続税の計算
国税庁 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
国税庁 [手続名]贈与税の申告手続
身内・銀行に借りる
身内や銀行に納税資金を借りて贈与税を納める方法もあります。延納制度は担保の提供が必要なため、手間を考慮すると身内や銀行に借りて一括納付する方が負担を減らせます。
ただし身内から借りる場合でも、契約書や返済計画などを作成して、返済の意思を示しましょう。借金と判断されずに贈与とみなされると、贈与税が課せられる可能性もあるため注意が必要です。
ローンを利用する
フリーローンを利用して贈与税を納める方法もあります。
セゾンファンデックスの「かんたん安心ローン」は、最短申し込み当日に借り入れが可能で手数料も無料です。また全国のコンビニや金融機関のATMで24時間利用できるため、土日祝日でも急な資金調達に対応できます。さらに電話サポートも用意されているため、初めての方でも安心して利用できるでしょう。
「贈与税の納付でお金が必要だけど、手元資金が足りない」という方は、セゾンファンデックスの「かんたん安心ローン」を検討してみてください。
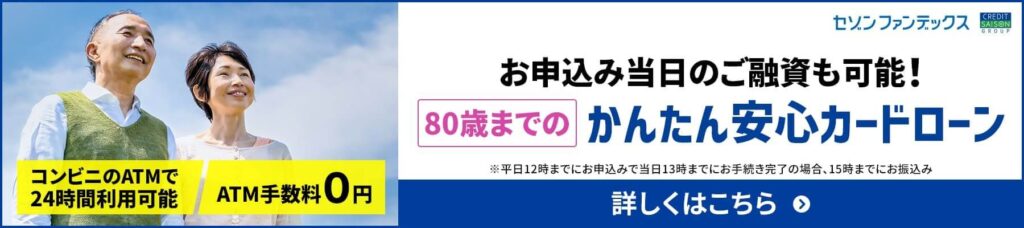
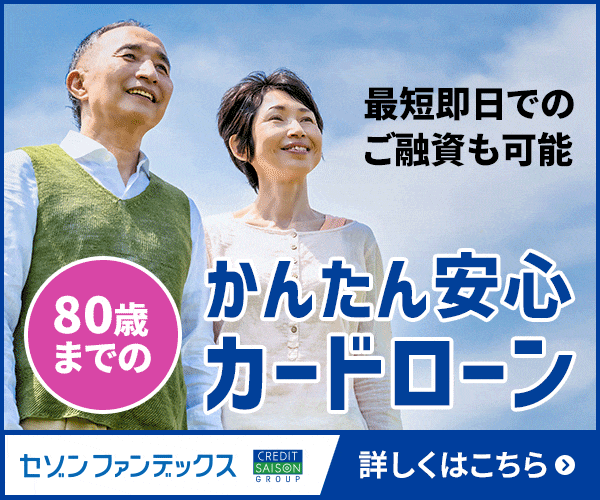
おわりに
贈与税は財産を譲り受けた場合に課せられる税金で、申告して納税する義務があります。ただし納付が難しい場合や負担を軽減したいときに、利用できる制度や方法はいくつかあります。仕組みを理解して申告漏れや延滞が発生しないよう、早めに税金対策を進めましょう。
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。