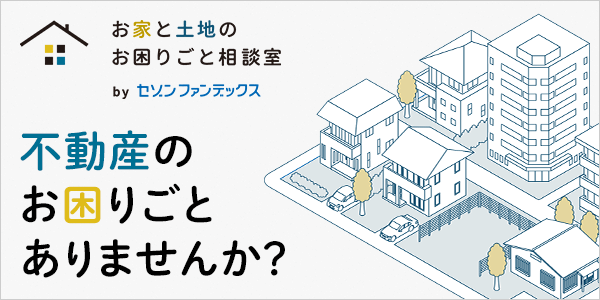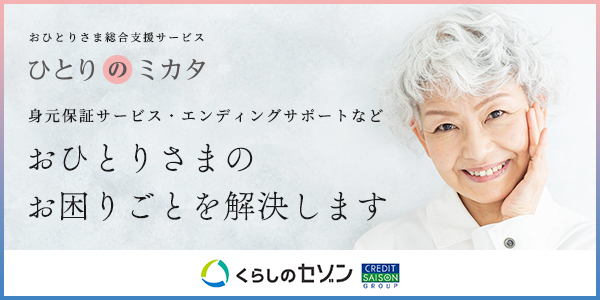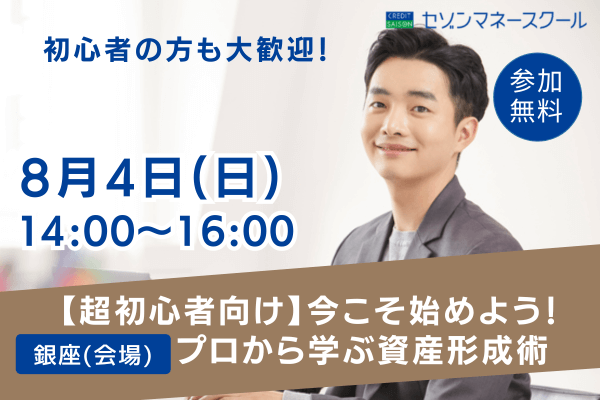「なぜ金利が変わると債券の価格も一緒に動くのだろうか」「株式のように債券にもリスクはあるのだろうか」といった疑問をお持ちではないでしょうか。金利と債券価格に関係があることはなんとなく聞き覚えがあるけれど、理由までは知らないという方は多いかもしれません。
債券の特徴は、金利が上昇すると債券価格が下がり、金利が低下すると債券価格が上がるということです。債券を途中売買して利益を得ようと考えている方は、金利の動きを確認しないと損をする可能性があります。このコラムでは、金利が債券価格に与える影響や債券投資のリスクについて分かりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
1.債券とは
債券とは、国や民間企業が資金を調達したいときに発行する有価証券で、定期的な利息の支払いと額面金額での償還を出資者に約束するものです。国や企業といった発行元の借金として扱われます。債券の購入は証券口座を持っている方なら債券を購入できます。
債券には、株式ほどの大きなリターンは期待できません。しかし、債券は一般的に銀行へ預貯金しておくよりも利息が高く、金利が固定化されています。そのためFXや株と異なり、低リスクで購入しやすい点がポイントです。
例えば、みずほ銀行では普通預金の金利が0.001%で設定されています。10,000,000円を貯金しても、1年で利息が100円しか得られません。しかし、現在国が募集している個人向け国債5年固定金利では、最低金利0.05%が保証されています。10,000,000円分の国債を購入すると半年ごとに利子を受け取れるため、少なくとも年間5,000円が得られるのです。(2022年9月現在)
債券が株やFXと異なるところは、発行元が倒産や財政難に陥らない限り、額面金額と利息を低リスクで得られるということです。投資を考えている初心者の方でも、比較的挑戦しやすい金融商品といえるでしょう。
参照:個人向け国債窓口トップページ : 財務省|預金金利・利率 | みずほ銀行
2.金利が債券価格に与える影響
金利とは借りたお金を返金する際に支払う利子の割合であり、債券価格は債券が市場で売買される際の価格を指します。債券を返還期限まで所持する場合は、額面金額と決まった利子を得られますので、市場での債券価格は関係ありません。しかし、市場での売買による利益を狙う投資家などにとっては、債券価格に影響を与える金利の変動は見過ごせないものです。
債券の多くは、発行時から返還期日まで利子が変わらない「固定金利」が適用されています。なお、債券の金利は市場金利の影響も受けるため、発行時期によって異なる場合があります。
2-1.金利が上がって債券価格が下がる場合
債券を購入する立場だと、金利が高い債券を買って運用した方が、得られる利子が多くなります。
例えば、債券価格が1,000,000円で金利4%の債券を買って、その後金利が5%に上昇したときを考えます。固定金利の場合、金利が4%のときに買った債券は、後から発行された債券と同じように金利が5%に上がるわけではありません。金利は購入時点の4%で固定されるためです。債券を買って1年後に得られる利子を見てみると、以下のとおりです。
- 金利が4%の債券の場合:1,000,000円×4%×年2回=80,000円
- 金利が5%の債券の場合:1,000,000円×5%×年2回=100,000円
つまり、金利5%の債券が流通している場合、金利4%の債券は買う価値が低いといえます。ですので、現段階の市場価格より金利が低い場合は、債券価格も100万の価値よりかは低くなります。
2-2.金利が下がって債券価格が上がる場合
市場での債券購入検討者の立場だと、新規に発行された金利が低い債券を買うよりも、既に発行された金利が高い債券を買って運用する方が、獲得できるリターンが大きくなると考えます。
例えば、債券価格が1,000,000円、金利4%の債券を買って、その後金利が3%に減少したときを考えます。固定金利の場合、金利が4%のときに買った債券は、後から発行された債券と同じように金利が3%に下がるわけではありません。1年後に得られる利子を計算してみると、以下のとおりです。
- 金利が4%の債券の場合:1,000,000円×4%×年2回=80,000円
- 金利が3%の債券の場合:1,000,000円×3%×年2回=60,000円
債券購入検討者からすれば、金利の低い債券を買うよりも、既に発行されている金利の高い債券の方が心惹かれるでしょう。つまり、金利3%の債券が流通している場合、金利4%の債券は買う価値が高いといえます。ですので、現段階の市場価格より金利が高い場合は、債券価格も100万の価値よりかは高くなります。
3.金利以外で債券価格に影響を与える3つの要因
債券価格に影響を与える要因は、金利以外にも存在します。金利だけを気にしていると、思わぬところで債券価格が変動して損することもあるので注意しましょう。
3-1.為替相場の変動
ドルやユーロなど、外貨で利子や額面金額が支払われる外貨建て債券では、受け取り時点での為替水準で円の受取金額が決まります。債券価格は為替相場の変動で上下し、価値は一定とはなりません。為替が円安になると受取金額が増え、円高になると受取金額が減る傾向にあります。
例えば、債券購入時の為替が「1米ドル=100円」だった場合、10,000米ドル分の債券を買うと、購入時に払う価格は「10,000米ドル×100円」で1,000,000円です。債券満期時の為替が「1米ドル=105円」になって円安になった場合の額面金額は、「10,000米ドル×105円」で1,050,000円となり、50,000円分の利益が出ます。円高の場合は、円安の逆になり受け取れる額面金額が減ってしまうのです。
海外の債券は、設定されている金利が日本よりも高く、高金利で運用できるメリットがあります。一方で、為替相場の変動によっては、購入時の額面金額を下回る可能性があるため、外貨建て債券などを買う場合は為替にも気を配りましょう。
3-2.格付けの変動
格付けとは、第三者の外部機関が債券の発行元の信用度や、利子と額面金額を予定どおりに支払える能力があるかどうかを「AAA」などの記号で表したランクのことです。一般的に、格付けが高い債券ほど金利は低く、格付けの低い債券ほど金利は高くなる傾向にあります。
格付けが低い債券は信用度が低いため、格付けが高い債券よりも金利を高く設定する傾向にあります。格付けは、購入を検討したり、気になる債券の安全性や金利の妥当性を判断したりする材料の1つと利用できます。また、格付けは定期的に見直しされます。
国内の格付け会社で代表的な先は、日本格付研究所(JCR)、格付投資情報センター(R&I)です。海外の代表的な格付け会社は、S&P(スタンダード・アンド・プアーズ)、Moody’s Corporation(ムーディーズ)、Fitch Ratings Ltd.(フィッチ)です。
3-3.景気の変動
一般的に、金利は景気と密接な関係にあります。景気回復につれ、金利は上昇します。景気後退時には、金利を低下させ、景気回復の下支えとして、循環を繰り返します。景気の良し悪しに合わせ、市場全体の金利調整を各国の中央銀行でコントロールしています。
4.債券投資に潜む2つのリスク
債券には、FXや株より比較的安全に運用ができるという魅力があります。定期的に利子を受け取りつつ、期日には債券の購入金額が返還されるため、安定して収益を得られるでしょう。しかし、債券にはリターンだけではなくリスクも存在しています。
4-1.売却価格が購入価格を下回る可能性がある
債券を途中で売却するとき、条件次第では損失が発生する可能性があります。債券価格は金利の影響を受けて変動するためです。購入時よりも金利が下がっていた場合、保有している債券が「現時点よりも高金利な債券」として価値が上昇し、売却益を得られます。
しかし、購入時よりも金利が上昇した場合、保有している債券が「現時点よりも低金利な債券」として価値が下落し、売却損につながってしまう可能性があります。債券を満期時まで持ち続けるなら、当初の額面金額と利子が予定通り返還されるため、金利による価値変動のリスクはありません。
ただし、外貨建て債券の場合は、為替相場によって、満期時に額面金額を下回る可能性がありますので、為替の動きに注意しましょう。
4-2.発行元が破綻して支払不能になる可能性がある
債券は、発行元が倒産か財政難に陥ると支払が不能となります。決められた利子や額面金額の返還を受けられなくなってしまうのです。国債の場合は、債券の発行元が国であるため、戦争などの有事がない限り破綻することはないかもしれません。
しかし、民間企業は、倒産する可能性がゼロではありません。債券を買う前に格付けを確認して、信用度が良好な企業を選択するほうが良いでしょう。
債券は発行元の経営状況によっては無価値なものになってしまうため、購入に際しては注意が必要です。「信用度が高く金利の低い債券を選ぶ」か「信用度が低く金利の高い債券を選ぶ」かを充分に検討しましょう。
おわりに
債券は、金利が上がった場合に債券価格が下がり、金利が下がった場合に債券価格が上がるものです。株式やFXとは異なり、定期的に利子を受け取ることができ、満期になると発行元から購入元本を返還してもらえるため、比較的安全に運用できるメリットがあります。
しかし「債券の発行元が経営破綻する」「為替相場の変動で償還時に購入元本価値が下がってしまう」などのリスクは完全にはなくせません。そのため、運用の際には景気や為替の状況などにも注目しましょう。