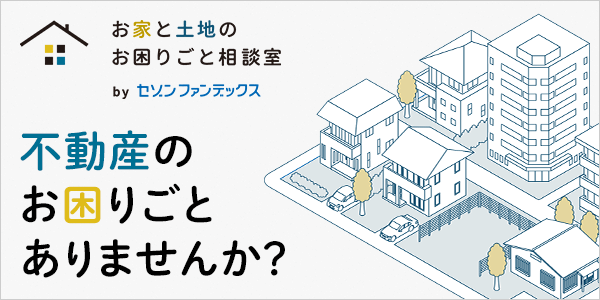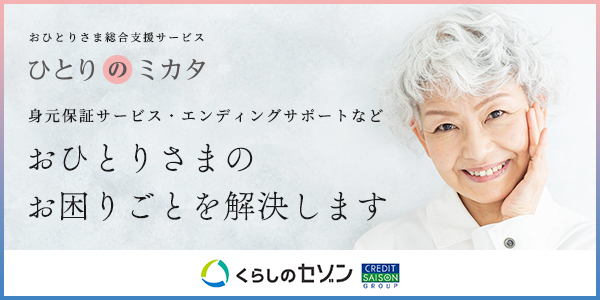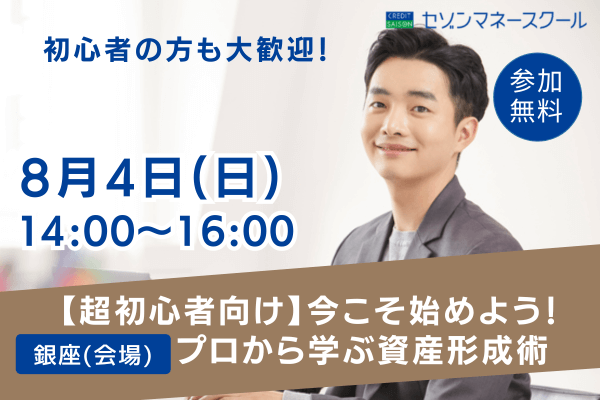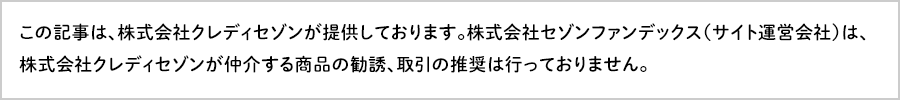
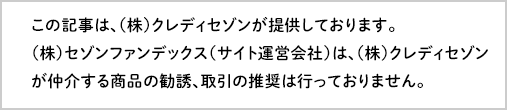
株式投資をする上で、配当金は株式の売買益や株主優待と並ぶ利益の一つ。ただし、配当落ち日に注意して株式を保有していなければ、損をすることもあるため注意が必要です。配当落ち日とは、配当を受け取る権利がなくなる日のこと。このコラムでは配当落ち日の基本知識や確認方法、配当落ち日を利用した投資について解説しています。株式投資をしている方や、これから始める予定の方は、ぜひ参考にして投資に役立ててください。
この記事を読んでわかること
株式投資における利益のひとつ、配当益。その配当を受け取るために注意しておきたいのが「配当落ち日」です。配当落ち日とは、配当を受け取る権利がなくなる日のこと。配当を受け取るには、基本的に決算日と同日に設定される権利確定日が基準となり、その時点で株主でなければ配当は受け取れません。また、権利確定日に株主名簿に登録されるには、権利付き最終日までに株式を購入する必要があります。権利付き最終日や配当落ち日がいつになるのかを正しく理解していないと、受け取れるはずだった配当を受け取れないこともあるため要注意です。反対に、配当落ち日の前後は株価に大きな変動が見られるため、売買に利用すると利益を得られる可能性があります。
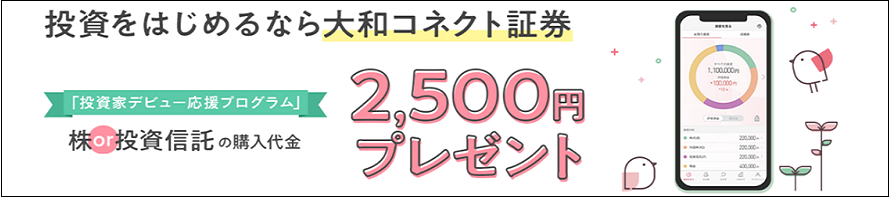
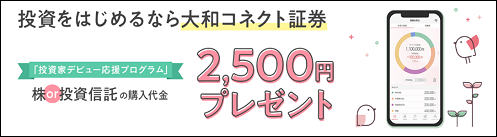
配当落ち日に関する基本情報

まず、配当や「配当落ち日(はいとうおちび)」の基本的な情報を押さえておきましょう。また、似たような言葉で「権利落ち日」もありますので、併せて解説します。
そもそも配当とは?
株式投資における配当とは、株主が保有する株数に応じて企業が株主に利益を分配することです。通常は決算時期にあわせて配当金が支払われますが、必ずしも支払われるとは限りません。企業の業績悪化等が理由で、配当が行われないこともあるのです。反対に、特別大きな利益が上がったときなどは、特別配当といって通常の配当に上乗せで支払われたり、別に支払われたりします。
配当落ち日とは?
配当落ち日とは、配当を受け取る権利がなくなる日のことです。配当を受け取る権利があるのは、通常決算日と同日に設定されている「権利確定日」の時点で株主名簿に登録がある株主。その決算期の株主に対して支払われる配当を受け取る権利が消滅することを、配当落ちと呼ぶのです。
株式購入から株主名簿の登録までは、タイムラグがあります。権利確定日に間に合うように売買できる最終日の翌日は、配当を受け取る権利がなくなる配当落ち日となります。権利付き最終日より後の権利確定日や配当落ち日に株式を購入しても、権利確定日に株主として登録されないため配当は受け取れません。
また、配当を受け取る権利が消滅した分、株価が下がったことを配当落ちと呼ぶこともあります。例えば、1株1,500円の株式を保有していて、1株あたり10円の配当があったとしましょう。その配当を受け取る権利がなくなると、理論上は株価がその配当分の10円下がったとみなされ(配当落ち)1株1,490円になります。
ただし、あくまでも理論上のことであり、株価はその他さまざまな要因で変動するので、理論どおりの株価になるとは限りません。
配当落ち日と権利落ち日の違い
株式投資に関する用語を見ると、配当落ち日と似たような言葉で、権利落ち日という言葉を目にして迷うことがあります。基本的には同じことを指し、2つの違いはほとんどありませんが、配当に対する権利が消滅することを配当落ち、分割や株主優待などの権利が消滅することが権利落ちです。
配当落ち日の確認の仕方
配当による利益を得るには、配当落ち日を意識して株式を保有する必要があります。配当落ち日は企業によって異なるため、配当を受け取るにはいつの時点で株主でなければならないのか確認しておきましょう。
決算日が基準になる
企業には決算日があり、3月や9月、12月など企業によって異なります。配当や株主優待を受けられる権利確定日は、決算日に設定されていることが一般的です。その決算日時点で株主名簿に登録されていないと、配当や株主優待を受ける権利はありません。
保有している株式を発行している企業の決算日を確認して、確実に配当や株主優待を受けられるようにしましょう。
権利付き最終日とは?

株式の配当や株主優待などを受ける権利を得るための最終売買日を「権利付き最終日」と呼びます。先述のとおり、配当などを受けるには権利確定日時点で株主名簿に登録されていることが条件ですが、株式を購入してすぐに株主名簿に登録されるわけではありません。
株式を購入後、約定日を含め3営業日目に受け渡しとなるため、権利確定日を含む3営業日前までには購入を済ませる必要があります。その権利確定日に間に合う最終売買日のことを、権利付き最終日と呼ぶのです。
例えば、2023年3月末決算の企業の場合、3月31日(金)が権利確定日となるため、その日を含む3営業日前の3月29日(水)が権利付き最終日です。この日までに株式を購入しておけば、その決算期の配当を受け取れます。
権利付き最終日の翌営業日、3月30日(木)は権利落ち日(配当落ち日)ですので、3月30日時点で株式を購入してもその決算期の配当などは受け取れません。反対に、権利落ち日に株式を売却しても、権利は獲得しているため配当や株主優待は受け取れるのです。
権利付き最終日は営業日ベースで決定するため、権利確定日との間に土日祝日を挟む場合は注意が必要です。例えば、2023年10月末決算の場合、権利確定日は10月31日(火)ですが、その日を含めて3営業日前の10月27日(金)が権利付き最終日となります。3日前ではないため、株式の売買の際には曜日も確認しておきましょう。
米国株の配当を受け取るには?
米国株の購入についても、約定日を含め3営業日目に受け渡しとなるため、考え方は国内株と同じです。ただし、権利確定の基準となるのは現地時間であり、日本時間の日付とは異なるため、売買のタイミングには注意しましょう。
投資信託の配当を受け取るには?
投資信託の配当は、決算日の前営業日までに約定すると受け取れます。ただし、銘柄によって約定日が注文日当日の場合と注文日の翌営業日の場合があるため、最終の注文ができるタイミングは異なることに注意しましょう。
また、注文には締め切り時間があり、ファンドによって異なるため注文時間によっては翌営業日の扱いになることもあります。必ず目論見書などで確認しておきましょう。投資信託の約定日も営業日ベースで決定するため、土日祝日を挟む場合は注意が必要です。
配当落ちを利用した投資手法
配当落ちを意識して株式を保有することは、配当益を確実に得るために大切です。さらに、権利付き最終日や配当落ち日には株価が大きく変動する傾向にあるため、投資に利用すると良いでしょう。
権利付き最終日までは上昇基調が多い
先述のとおり、権利付き最終日時点で株式を購入していると配当などが受け取れます。権利確定日まで1年間その株式を保有していても、1日だけ保有していても権利自体は同じです。そのため、権利付き最終日が近づくと権利を取得しようと購入する投資家が増え、株価が上がる傾向にあります。
権利落ち日は下降基調が多い
権利付き最終日までに株式を購入しておけば、配当などの受け取りが可能です。そのため、権利だけ獲得しておいて、権利付き最終日の翌日の権利落ち日に株式を売却する投資家が増える傾向にあります。売却が増えると株価は下がるため、その決算期の配当や株主優待を受け取れなくても良いのであれば、権利落ち日の購入を検討するのも良いでしょう。
配当落ち日前に空売りをする

信用取引を利用するのも、一つの方法です。実際に株式を購入するには買付資金を全額用意する必要がありますが、信用取引では保有している株式や現金を担保にして、証券会社から買付代金を借りられます。利用には委託保証金が必要ですが、自己資金の範囲を超えた売買ができることや、現物取引の株式売買と異なり売却から始められるのがメリットです。
実際に購入している株式を売却することを「現物の売り」と呼びますが、信用取引では証券会社から株を借りて売る「空売り」という手法が取られることがあります。空売りをするメリットは、株価の変動リスクを回避できること。
現物取引の場合、株価が下がったときに購入して株価が上がった時点で売却することで売却益が出ますが、保有していない株式の売却は不可能です。一方で信用取引では、株価が高いときに先に売却(空売り)して、株価が下がったら買い戻すことで利益を出せます。
この空売りを利用して、権利落ち日時点での株価下落のリスクヘッジができるのです。具体的な手法としては、まず権利付き最終日までに現物取引で株式を購入して権利を確定させます。同時に、同じ株式を株価が高い時点で空売りしておくのです。
権利落ち日に現物取引で売却すると、株価が下がっているため損失が出る可能性がありますが、空売りした株式を買い戻すと反対に利益が出ます。現物取引と信用取引の空売りで、損失と利益を相殺できるのです。
信用取引では、実際に株式の取引をしているわけではないため、配当や株主優待を受けることはできません。ただし、配当に関しては配当落調整金が支払われます。これは、配当金の支払いによる株価変動分を調整する目的で、実際の配当金とは異なるため税法上は配当所得にはなりません。譲渡損益となるため、配当所得控除の対象外となることに注意しましょう。
配当が多い企業を調べるには?配当以外に受け取れるもの
配当は企業の利益の分配のため、必ず受けられるものではありません。企業の業績悪化などにより、配当金の支払いがない企業やストップするケースもあります。また、利益を分配するという性質上、どれくらいの配当を出しているのかは企業によって大きな差があるのです。配当益を目的とした株式投資では、配当が多い企業の株式の選定が重要になります。
株式投資の目的にしている方も多い株主優待は、すべての企業で実施しているものではありません。株主優待の有無や優待の条件は企業によって異なるので、購入前に確認しておきましょう。
配当利回りで調べられる
配当利回りを調べることで、その企業がどれくらいの配当を出しているのかを調べることができます。配当利回りの計算方法は、以下のとおりです。
配当利回り(%)=1株当たりの配当金÷現在の株価
例えば、1株当たりの配当金が15円のA社とB社、2つの企業で比べると、どちらも配当金は同じですが、株価によって配当利回りは異なります。
1株当たりの株価がA社は500円、B社が1,500円だったとします。
A社の配当利回り
15円÷500円=3%
B社の配当利回り
15円÷1,500円=1%
このように、1株当たりの配当金が同額の場合、株価が低い方が配当利回りは高くなるのです。つまり、1株あたりの配当金が同額であれば、同じ株数を保有するなら株価が低い企業の方が少ない投資額で済みますし、同じ額を投資するなら株価が低い企業のほうが株数が多くなり配当益は多くなります。
株主優待
株主優待制度は、企業が株主に対して自社製品やチケットなどのプレゼントを贈る制度です。全ての企業が実施しているわけではなく、配当と異なり権利確定日に株主であれば無条件で優待が受けられるとは限りません。
「権利確定日時点で100株以上保有」「権利確定日時点で200株を2年保有」など、企業によって条件が付いているケースもあります。また、もらえる商品も自社製品や自社のサービス、金券やチケットなどさまざま。金額に換算すると配当金よりも高利回りになることも多く、投資目的としても見逃せません。
ご自身がよく利用するサービスや食品等の株主優待があるなら、株式の購入を検討してはいかがでしょうか。
株式分割
株式分割とは、1株をいくつかに分割して株式数を増やすことです。背景としては、株価がかなり上昇した場合に、1株あたりの株価を下げる目的で株式分割を行うことがあります。
株式分割を行えば株価は一旦下がりますが、投資家にとって悪いことばかりではありません。例えば、100株保有していた株式が株式分割で200株に増えたとします。分割の際に1株あたりの配当が据え置かれたままだと、単純に配当金が2倍になり増配と同じ効果が期待できるのです。
株式取引におすすめの証券会社5選
ここからは、株式取引におすすめの証券会社をご紹介します。各証券会社の特徴やおすすめポイントをご紹介しているので、ご自身に合った証券会社選びの参考にしてください。
マネックス証券

オンライン証券会社のマネックス証券は、米国株への投資に興味がある方におすすめの証券会社です。5,000を超える米国株銘柄の取り扱いがあり、2023年4月現在、米国株の買い付けにかかる円から米ドルへの為替手数料は無料となっています。
マネックス証券では、米国株を円で取引できる「円貨決済サービス」が利用できます。米ドルに両替することなく取引可能で、両替に関するコストがかさみません。
もう1つの魅力は、株式の取引手数料の安さ。パソコンや携帯電話で手軽に取り引きでき、最低手数料55円(税込)と低水準です。
【主な特徴】
- 米国株買付の為替手数料無料
- 米国株を円で取引可能
- 5,000銘柄を超える米国株の取扱い
| 取扱商品 | 国内株・外国株・ETF・FX・暗号資産CFD・債券・金/プラチナ取引 |
| 株式の取引手数料(現物) | 55円~2,750円(税込)※単元未満株の買い付けは無料 |
| 公式WEBサイト | https://www.monex.co.jp/ |
松井証券
松井証券は、投資初心者でも気軽に始められる証券会社。どのような投資信託を選べば良いのか分からない方には、8つの質問に答えるだけでロボアドバイザーから最適なポートフォリオ(組み合わせ)を提案してもらえる「投信工房」がおすすめです。
株式投資においては、日本株は1日の約定金額500,000円以下は手数料が無料。米国株も手数料無料から利用できるため、手数料がかさんで実質利益が出ないという心配もありません。米国株専用のアプリで1株からの少額投資が可能で、アプリからの入金も手数料無料で簡単にできます。
【主な特徴】
- 手数料無料から利用できる株式投資
- 25歳以下の利用は手数料無料
- 他の証券会社からの乗り換え手数料無料
| 取扱商品 | 国内株・外国株・ETF・REIT・ETN・FX |
| 株式の取引手数料 | 0円~110,000円(税込)※25歳以下は無料 |
| 公式WEBサイト | https://www.matsui.co.jp/ |
楽天証券
楽天証券は2022年3月30日現在、主要ネット証券5社の中で新規口座開設数が4年連続第1位と多くの方に支持されている証券会社です。
国内株の取引手数料が低水準で、一定条件を満たす「超割コース大口優遇」では約定代金100,000円までの手数料が無料、少額で何度も取引する方におすすめの「いちにち低額コース」では1日の取引金額100万円までは手数料無料となっています。
楽天ユーザーなら、買物などで貯めた楽天ポイントを国内株や投資信託の購入に使えるのも見逃せない点です。投資を始めたばかりで不安な方は、楽天ポイントを利用したポイント投資から始めてみるのも良いでしょう。
【主な特徴】
- コースによっては取引手数料が無料
- 楽天ポイントを利用できるポイント投資
- 楽天銀行や楽天カードとの連携でお得に
| 取扱商品 | 国内株・外国株・FX・債券・投資信託・金/プラチナ取引 |
| 株式の取引手数料 | 0円~3,300円(税込) |
| 公式WEBサイト | https://www.rakuten-sec.co.jp/ |
セゾンポケット
セゾンポケットでは、セゾンカードやUCカードを利用した投資ができます。カード払いを利用した毎月一定額の積立や、貯まった永久不滅ポイントを投資に回すことも可能。もちろんカード払いを利用した積立分にもポイントが付与されるので、ポイントを貯めたい方にはおすすめの方法です。
また、上場企業の株式に少額から投資できる「株つみたて」も魅力的。国内株は通常100株単位での購入が必要で、まとまった資金を用意しなければなりません。しかし、セゾンポケットの株つみたてでは、ソフトバンクや三菱UFJフィナンシャルグループなど大手企業の株式に、カード払いで月々5,000円から投資ができます。
【主な特徴】
- カード払いで積立分にもポイント付与
- 少額から投資可能
- 積立金額は1,000円~50,000円まで1円単位で設定
| 取扱商品 | 国内株・ETF |
| 株式の取引手数料 | 55円(税込)~取引金額の0.55%(投資信託は無料) |
| 公式WEBサイト | 「セゾンポケット」について詳しくはこちら |
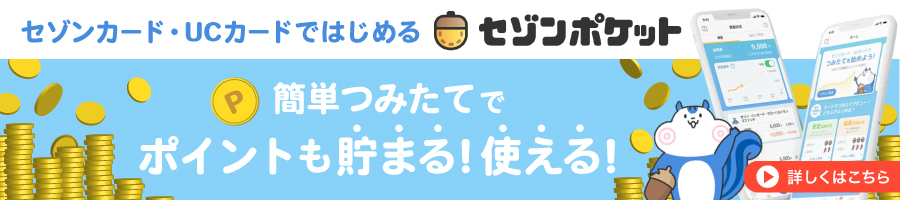
大和コネクト証券
大和証券グループのスマホ専業証券である大和コネクト証券。口座開設から取引までアプリで手軽にできるのは、手続きが面倒に感じる方にとって大きなメリットです。大和コネクト証券では、dポイントやPontaポイントが投資に使えます。1ポイントから投資に利用できるため、期限切れ間近で最低利用単位に満たないポイントも有効活用可能です。
国内有名企業の銘柄に1株単位で投資できる「ひな株」にもポイント投資ができるため、実質自己資金がゼロでも株式投資できるのは魅力的ではないでしょうか。ポイントを貯めるポイ活をしている方は、必見のサービスです。
【主な特徴】
- dポイントやPontaポイントが利用できるポイント投資
- クーポン利用で毎月10回まで手数料無料
- 大手証券会社の大和証券グループ
| 取扱商品 | 国内株・米国株・ETF・ETN・REIT |
| 株式の取引手数料 | 0円~660円(税込)※無料クーポンあり |
| 公式WEBサイト | 大和コネクト証券の詳細はこちら |
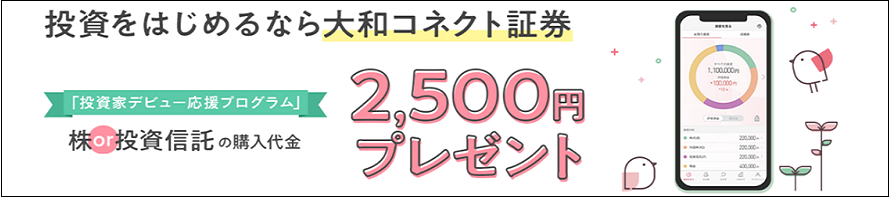
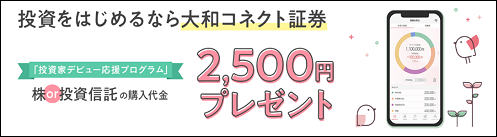
おわりに
このコラムでは、配当落ち日の解説を中心に、権利付き最終日や配当落ち日と権利確定日の関係、配当落ちを利用した投資についてご紹介しました。特に投資初心者の方にとっては難しい言葉かもしれませんが、配当落ちについて理解しておくことで投資の幅が広がるのではないでしょうか。配当落ち付近の株価変動を上手に利用して、投資に活かしてください。