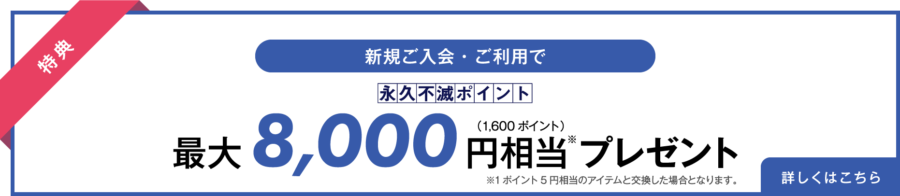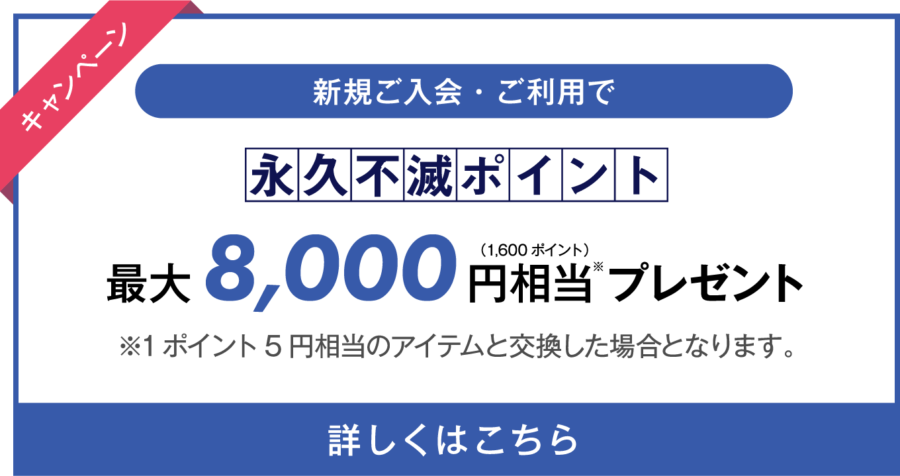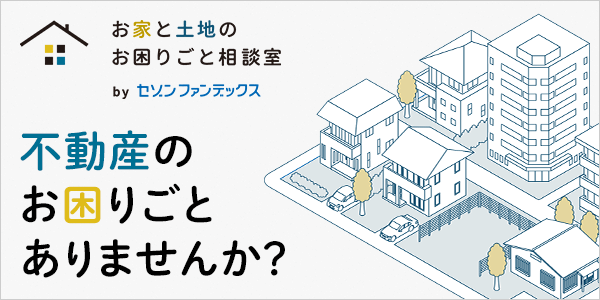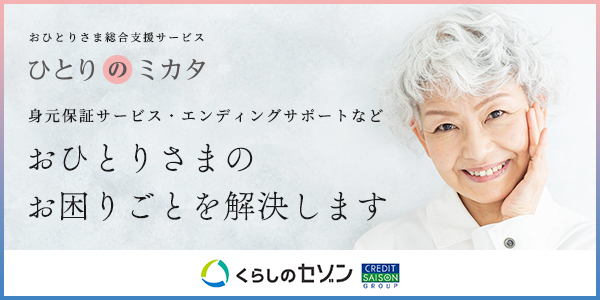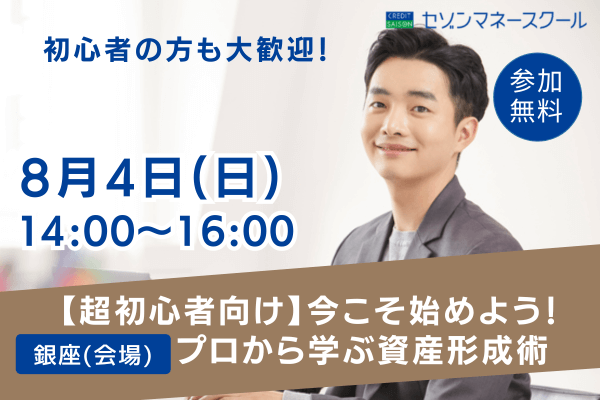「リモートワークで自分の時間が増えたので副業にチャレンジしたい」「将来のために給与以外の収入源も作っておきたい」とお考えではありませんか。実際に会社員でありながら、副業を始めたいとする希望者は年々増加傾向にあるようです。
そこで今回は「会社員をしながら個人事業主になれるのか」という点に着目し、メリットやデメリット、必要な手続きなどについてまとめました。このコラムを読めば、副業の実現に向けて一歩踏み出せますよ。
会社員をしながらでも個人事業主になれる
結論を述べると、会社員として働きながらでも個人事業主になれます。つまり、本業の会社員と、副業の個人事業主は両立可能なのです。
2020年に厚生労働省から発表された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、副業や兼業の普及を図る方向性が示されました。これにより、企業に対し従業員が副業や兼業が行えるよう整備が求められています。政府をあげて、副業や兼業をしやすい環境をバックアップしているといえるでしょう。
個人事業主になれば、ゆくゆくは独立や開業といった道も見込めます。「会社員の給料だけでは先行きが不安」という場合でも、個人事業主になっていれば将来の備えにつながるでしょう。
会社員と個人事業主は何が違う?

そもそも、会社員と個人事業主は具体的に何が違うのでしょうか。名前のとおり「会社員は会社で働く人」「個人事業主は個人で事業を起こしている人」といったイメージがあるかもしれません。
会社員をしながら個人事業主になる方法や、メリット・デメリットなどを説明する前に、ここで会社員と個人事業主の違いをおさらいしておきましょう。
会社に雇用されている「会社員」
会社員は会社に雇用され、組織の一員として働きます。会社から給与が支給されるため、収入がなくなるリスクが少ないです。確定申告の必要もありません。社会保険の負担が軽いことや福利厚生が手厚いのも会社員の特徴です。
一方、個人のやりたいことではなく会社の意向や方針に沿って仕事をします。また、経費として計上できるものが少ないため、節税が難しい面もあります。
独立して仕事を請け負う「個人事業主」
会社などに雇用されず、独立して利益をあげるのが個人事業主です。組織に入るわけではないため、働く時間や請け負う仕事を調整でき、マイペースに仕事ができるでしょう。確定申告は必要ですが、経費として計上できるものも多くなっています。
ただし、事業を起こしたからといって、収入が保証されるわけではありません。仕事のスキルやクライアントとのコミュニケーション能力などがなければ、安定した収入につながらない恐れもあります。
会社員をしながら個人事業主になるとどんなメリットやデメリットがある?
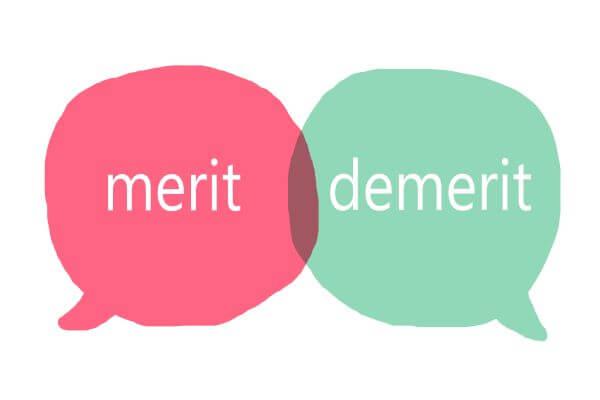
会社員を続けながら個人事業主になる場合に考えられるメリットとデメリットの双方を踏まえ、個人事業主になるかどうか検討を深めていきましょう。
メリット
会社員が個人事業主になる場合のメリットとして、以下の4つが挙げられます。
・副業の必要経費を計上でき節税対策になる
個人事業主になると、収入から必要経費として差し引けるものが多いため、課税所得額が少なくなり、所得税の納付額を抑えられます。
では、具体的にどのようなものが経費として計上できるのか、一例を見てみましょう。
【経費に計上できるもの】
- 仕事に必要なもの(パソコン、コピー機、ボールペンなど)
- 宣伝広告費(広告、チラシなど)
- 水道光熱費(水道代、電気代など)
- 通信費(電話代、インターネット代など)
- 交通費(ガソリン代、電車賃など)
ここで紹介しているものは、経費として計上できるものの一部です。自宅を事務所として使用している場合、「家事按分(かじあんぶん)」として副業に使っている分の家賃や光熱費なども計上できます。加えて、事業を家族に手伝ってもらい給与を支払っているっているのであれば、給与分も経費になります。
このように、個人事業主は経費に計上できるものが多く、その分節税が叶うのです。
・青色申告特別控除をプラスできる
個人事業主になると、青色申告特別控除が可能です。そもそも、確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。青色申告は白色申告より複雑で確定申告時に必要な帳簿も多いですが、その分特別控除が受けられるのです。
きちんと帳簿や必要書類を揃え、期限までに提出できれば、最高550,000円の特別控除が受けられます。さらに、e-Taxで申告(電子申告)すれば、最高650,000円の特別控除が可能です。会社員として得る給与の給与所得控除にプラスし、青色申告特別控除も受けられるのは大きなメリットでしょう。
ただし、青色申告ができるのは「事業所得」や「不動産所得」「山林所得」を得ている方が対象です。ここでのポイントは、副業の収入が「事業所得」であるかどうかになります。
というのも、国税庁が2022年8月に公示した所得税基本通達の改正案で、2022年分から「副業の300万円以下の収入は雑所得に該当する」という案が出されました。つまり、副業の収入が300万円を超えないと「事業所得」には該当せず、「雑所得」になってしまうのです。雑所得では青色申告ができず、特別控除を受けられません。
この改正案については、2022年8月31日まで意見を公募していました。どのような改正がなされるのか、行方を見守りましょう。
参照元:No.2070 青色申告制度|国税庁
e-GOV パブリック・コメント別 紙 所得税基本通達新旧対照表
e-GOV パブリック・コメント「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案) (雑所得の例示等)
・本業の所得と副業の所得を損益通算できる
個人事業主として収入があると、会社員の所得と副業の事業所得で損益通算できます。副業の事業所得が赤字となった場合、会社員の所得と相殺できるのです。例えば、会社員の収入が500万円、副業の収入が-100万円だった場合、損益通算し、トータル400万円の収入となります。
例で挙げたケースだと、400万円をベースに税金を計算するため、会社員の収入の500万円で計算するより税金の納付額が抑えられるのです。
注意したいのが、損益通算に関しても「事業所得」が対象となっていること。「雑所得」では損益通算ができません。なお、雑所得が赤字となった場合、所得金額は0円として扱われます。
参照元:副業収入がある人は「損益通算」で節税ができる? | ファイナンシャルフィールド
・独立や起業の練習ができる
本格的に事業を起こす前に、独立や起業の練習ができるのもメリットです。会社員としての収入がある中で、徐々に個人事業主としての経験を積んでいけます。
独立や起業をすると、資金繰りや収支の管理、確定申告などをご自身で行わなければなりません。事業が小さい副業のうちに各種手続きやお金のやりくりを練習しておくことで、本格的に個人事業主としてスタートしたときの足掛かりとなるでしょう。
デメリット
メリットがある一方、デメリットがあることも否めません。主なデメリットとして次の3つが挙げられます。
・確定申告の手間がかかる
個人事業主になったら、確定申告は必須です。会社員で得た収入は確定申告の必要はありませんが、副業分の収入については確定申告しなければなりません。
特に青色申告を考えている場合、より複雑な帳簿の付け方が求められます。比較的簡単に青色申告ができる会計ソフトもありますが、確定申告について勉強したり、ソフトに金額を打ち込んだりと時間や手間がかかってしまうでしょう。
・自由時間が少なくなる
副業を始めると、ご自身の自由時間が少なくなることが予想されます。副業の作業や売り上げを伸ばすための施策、帳簿付けなどの時間を捻出しなければならないためです。
「休みの日は映画鑑賞をしている」「会社帰りにジムに寄っている」といった自由時間から、副業のための時間を割くことになるでしょう。また、充分に休息がとれず、体調を崩して本業に影響が出るといった事態も考えられます。
・失業保険がもらえないリスクがある
会社員に加えて個人事業主をしていると、会社員を辞めたときに失業保険がもらえないリスクがあります。
そもそも、失業保険を受け取るには「失業状態」でなければなりません。個人事業主をしていると、会社員を辞めても無職とはいい難く、失業状態と認定されない可能性があるのです。これは、副業の収入が赤字であっても同様です。
会社を辞めたとき副業の収入がしっかりあれば問題ありませんが、あまり収入がない状態で失業保険がもらえないとなると困ってしまいます。失業時に副業の収入が思わしくないようであれば、個人事業主の廃業も検討した方が良いでしょう。
会社員が個人事業主になるには?必要な手続き

ここからは、会社員が個人事業主になるために必要な手続きを紹介します。個人事業主としてスムーズなスタートをきるには、以下の手続きを済ませてください。
開業届を提出する
個人事業主になるには、「開業届」の提出が必須です。事業をスタートした日から1ヵ月以内に税務署に開業届を提出しましょう。
開業届のフォーマットは、国税庁のWebサイトにてダウンロードできます。開業届に名前や屋号、開業日など必要事項を記入し、税務署の窓口に提出するか郵送して手続き完了です。なお、国税電子申告・納税システムのe-Taxを活用すれば、インターネット上で手続きが済みます。
開業届の提出以外、ほかに必須な手続きはなく、個人事業主になれます。ただ、スムーズなスタートをきるために、次から紹介する手続きについても進めていきましょう。
参照元:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
青色申告承認申請書を提出する
青色申告を検討している方は、開業届と同時に「青色申告承認申請書」も税務署に提出するのがおすすめです。青色申告承認申請書は、事業開始から2ヵ月以内に提出する必要があります。副業を始めたばかりで忙しくしていると、うっかり提出漏れしてしまうこともあるため、開業届と同時に提出しておけば、安心でしょう。
事業用の口座開設・クレジットカードの作成
事業用の口座の開設やクレジットカードの作成も検討してください。というのも、通帳や明細に事業と個人の収支が入り混じると、「どれが仕事の出費だったのか」とその都度悩むことになり、確定申告や帳簿の作成に手間がかかってしまいます。
屋号入りの口座を開設すれば、個人の収支と区別しやすく、確定申告の作業がしやすいです。クレジットカードも同様に、プライベート用と事業用を使い分けると便利でしょう。また、個人事業主であっても税務調査を受けることがあります。その際に事業用の口座やクレジットカードがあれば、税務署員にプライベートな収支を見られずに済みます。
事業用のクレジットカードを作成する場合、ビジネスサービスに特化したカードを選ぶと業務の効率化が望めます。ここでおすすめしたいのが、「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」。このカードは、開業前から申し込めます。会計ソフトと連携でき、毎月の経費処理も簡単です。CrowdWorksやYahoo!JAPANといった特定加盟店で利用すれば、永久不滅ポイントが4倍になる限定サービスなども展開しています。
【セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの主な特徴】
- 年会費が永年無料
- 引き落とし口座が法人と個人のいずれかを選べる
- 貯めたポイントを経費削減に充てられる
| 利用限度額 | ニーズに対応して限度額を設定 |
| 追加カード | 9枚まで無料で発行 |
| 優待 | エックスサーバー(レンタルサーバー)の初期設定費用が無料 「かんたんクラウド™」(クラウドサービス)の月額使用料が3ヵ月無料 |
| 公式HP | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの詳細はこちら |
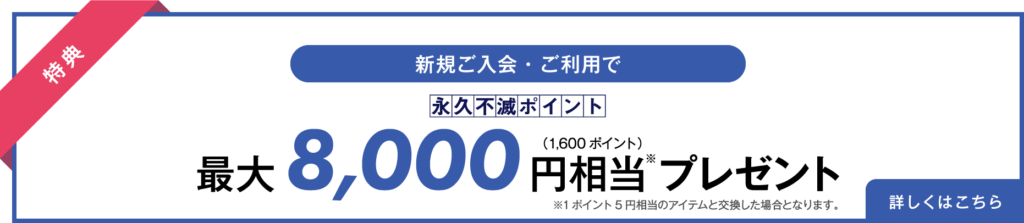
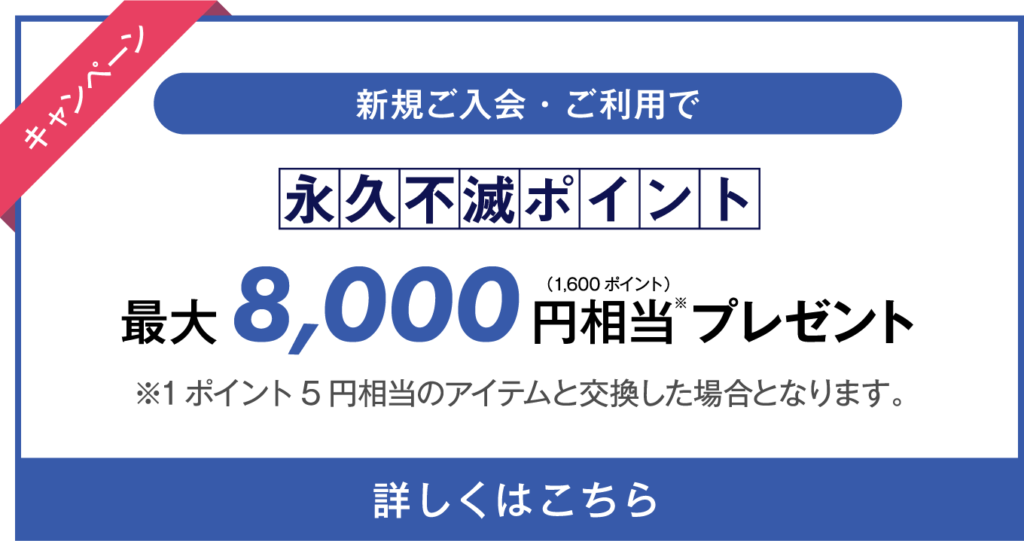
会計ソフトの利用申し込み
確定申告をできるだけ簡単に済ませられるよう、会計ソフトの利用も視野に入れましょう。会計ソフトがあれば収支の管理や帳簿付けが簡単になり、確定申告がしやすくなります。
また、「マネーフォワード クラウド」や「クラウド会計ソフト freee会計」といったクラウド型の会計ソフトは、口座の情報を会計ソフトへの取り込みが可能なため、さらに簡便化が目指せるでしょう。
確定申告や社会保険についての気になる疑問

ここまでで、会社員をしながら個人事業主になるメリットやデメリット、必要な手続きなどをご理解いただけたと思います。最後に、会社員と個人事業主を両立していく上で抱きがちな疑問点を解決しておきましょう。
確定申告はいくら利益があった場合に必要?
個人事業主になると確定申告が必要であるとお伝えしましたが、所得税の確定申告がいらないケースもあります。それは、本業の収入が2,000万円以下、副業の利益が20万円以下の場合です。
ポイントは、副業の「利益」ということ。売上から経費を差し引いた利益(儲け)が20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。もし会社員の収入が年末調整されていないようであれば、副業の利益に年末調整されなかった収入をプラスし、2,000万円を超えるかどうかで確定申告の有無を判断してください。所得税の還付が見込まれる場合は、20万円を超えていなくても確定申告をした方が良さそうです。
ただし、副業の利益が20万円を超えていなくても、住民税の確定申告は必要です。確定申告をしないと、脱税になってしまう恐れがあるのでご注意ください。
参照元:確定申告が必要な方|国税庁、副収入などがある方の確定申告|国税庁
社会保険はどうなる?
会社員が副業で個人事業主になる場合、基本的に今まで通り「会社の健康保険」や「厚生年金保険」に加入します。会社に籍がある限り、個人事業主になったとしても変更の手続きをする必要はありません。
税金の支払いは?
会社員と同様、個人事業主も所得税と住民税を納付します。税額は、本業の会社員の給与と副業の収入を合計し、損益通算した額で決まります。
会社に個人事業主になったことはバレる?
勤務先に個人事業主になったことが知られてしまう可能性は否定できません。会社に通知される住民税の金額が給与との比率より高かった場合、副業で収入を得ていることがバレる恐れがあります。
会社に知られたくないようであれば、確定申告書の際に「住民税徴収方法」の選択欄で「普通徴収」を選択しましょう。普通徴収を選択しておけば、個人事業分の住民税納税通知書が自宅に届き、会社には通知されません。
おわりに
会社員をしながらでも個人事業主になれることが分かりました。働き方の見直しや将来の備えのために、副業を選択するのも有効な方法でしょう。個人事業主になれば、副業の経費を計上できたり、控除額が多い青色申告ができたりと、メリットがあります。一方で、確定申告の手間や自由時間が削られるといったデメリットがあることも事実です。今回のコラムを参考に、個人事業主にチャレンジするかどうかじっくり検討してみてください。