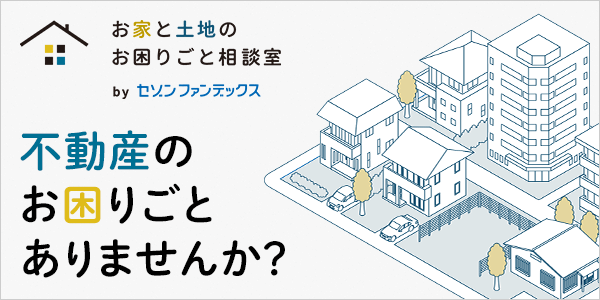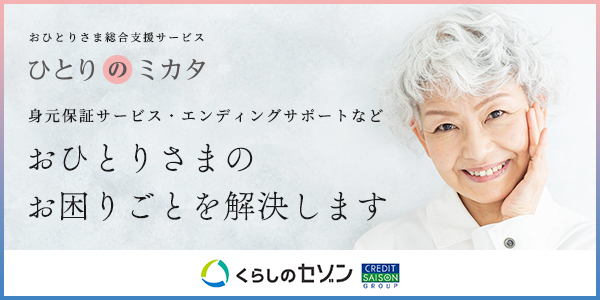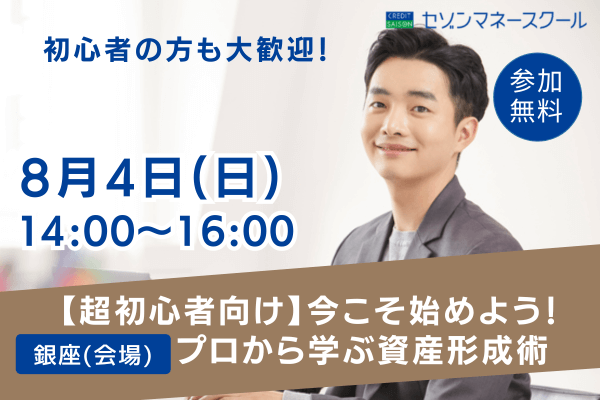出産費用に利用できる制度を活用して、足りない分を補うことができます。具体的にどのような制度を利用できるのか、それでも足りないときはどのように費用を用意できるのか見ていきましょう。実際に出産にはどの程度の金額がかかるのかについても解説します。

出産費用は平均50万円かかる
厚生労働省が公表した資料によれば、出産にかかった費用の平均額(令和元年度)は46万127円です。地域によって、あるいは医療機関が公立・私立かによっても差はありますが、40万〜50万円を見積もっておくことができるでしょう。
| 出産費用(平均額) | 中央値 | |
| 全体 | 460,127円 | 451,120円 |
| 公的病院 | 443,776円 | 440,530円 |
| 私的病院 | 481,766円 | 467,805円 |
| 診療所(助産所を含む) | 457,349円 | 449,300円 |
公的病院の出産費用が高額な都道府県を上位から5つ紹介します。
| 都道府県 | 出産費用(平均額) | 中央値 | |
| 1位 | 東京都 | 536,884円 | 536,196円 |
| 2位 | 茨城県 | 502,470円 | 492,615円 |
| 3位 | 神奈川県 | 486,464円 | 487,616円 |
| 4位 | 宮城県 | 473,158円 | 478,740円 |
| 5位 | 山形県 | 467,387円 | 471,625円 |
出産費用に活用できる制度
出産費用は、原則として医療保険が適用されません。ただし、帝王切開などの異常分娩と判断されるときには医療保険が適用されますが、正常分娩のときは原則として100%自己負担となります。しかし、公的な制度を利用することで、出産費用に充てることが可能です。利用できる制度を紹介します。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 自治体で実施している助成制度
それぞれどの程度の金額を受け取れるのか、目安についても見ていきましょう。
2-1.出産育児一時金
出産するときは、加入している健康保険から出産育児一時金を受け取ることが可能です。出産育児一時金とは、基本的に子ども1人あたり42万円が支払われる手当金で、多胎児であれば人数分(双子であれば84万円、三つ子であれば126万円)受け取れます。なお、健康保険の被扶養者も、出産育児一時金を受け取ることができます。健康保険に加入している配偶者に受給手続きをしてもらいましょう。
・出産育児一時金が支給される条件
出産育児一時金は以下の条件を満たす場合には、受給できます。
- 健康保険に加入している、あるいは健康保険に加入している方の被扶養者である
- 妊娠4ヵ月(85日)以上で出産
外国籍で国民健康保険に加入している場合には、在留資格が1年以上あることが条件に加えられます。ただし、自治体が滞在延長を許可するときには受給できることもあるため、気になるときは自治体の健康保険窓口に相談してみましょう。また、海外で出産した場合であっても、出産日と妊娠期間が分かる証明書があれば受給できることがあります。出産した医療機関で証明書を受け取り、帰国後、手続きをしましょう。
・出産育児一時金を受け取れるのはいつ?
出産育児一時金の受け取り申請方法により異なります。受け取りの申請方法は、直接支払制度、受取代理制度、事後申請の3つです。
直接支払制度と受取代理制度について、利用できるかどうか医療機関等に確認し、利用できる場合には手続き方法も確認してみましょう。直接支払制度と受取代理制度も直接、医療機関等に支払われ、出産費用が42万円を上回った場合、超過分を退院時に支払います。
事後申請を行う場合には、受給できるのは、手続き完了後から2週間〜2ヵ月後程度です。出産育児一時金の申請期限は、出産日の翌日から2年以内です。できるだけ早く申請をしましょう。
・直接支払制度を活用しよう
直接支払制度とは出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が本人に代わり、健康保険組合に対し出産費用を請求する制度をいいます。直接支払制度を利用した場合、健康保険組合は、被保険者に支給する出産育児一時金を医療機関等に直接支払うことになります。
直接支払制度を利用することにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を超過した金額のみとなり、出産後に健康保険組合に出産育児一時金の申請が必要なくなるのもメリットです。なお、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が支給されるため、申請が必要となります。
2-2.出産手当金
産前産後に休業し、給料を受け取れない場合には、加入している健康保険から出産手当金を受け取れます。出産前42日間と産後56日間の合計98日間の給料に関して、過去12ヵ月分の給料から1日あたりに換算して3分の2に相当する金額を日数分受け取ることが可能です。なお、多胎児を出産した場合は、出産前98日間と産後56日間の154日間に対して出産手当金が支払われます。
・出産手当金を受け取れるのはいつ?
受給できるのは、出産手当金の申請受理から約1〜2ヵ月後程度です。申請受理が完了後、送られてくる出産手当金支給決定通知書で支給日が確認できます。出産手当金の申請期限は、産休開始の翌日から2年以内です。できるだけ早く申請をしましょう。
2-3.自治体で実施している助成制度
自治体によっては、出産費用として活用できる助成制度を実施していることがあります。お住まいの自治体の健康保険や母子関係の窓口に問い合わせてみましょう。
出産費用が足りないときに利用できる方法
出産するときには、さまざまな費用がかかります。医療機関に支払う費用だけでなく、赤ちゃんの衣類や小物、マタニティ向けの下着や部屋着、外出着なども必要になるでしょう。また、仕事を休んでも一定期間は出産手当金を受給できますが、収入は下がってしまうため、その分、生活費にも影響が及ぶかもしれません。
出産関連の費用が不足するときは、次の方法を検討してみましょう。
- 親族などから借りる
- クレジットカードでキャッシングを利用する
- ローンを利用する
それぞれの方法を利用するメリットや注意点について解説します。
3-1.親族などから借りる
緊急入院などにより、予定よりも産前休業や産後休業を長く取ることになるケースもあるでしょう。収入が減るだけでなく、入院や手術などの医療費がかさみ、予定していたよりも出産費用が増えるかもしれません。
事情を親などの親族に話し、お金を借りるのもひとつの方法です。いつ頃に返済できそうか、どの程度必要なのか説明して理解を得たうえで、借用書を作成しておきましょう。借用書がないと贈与と考えられるため、年間110万円を超えると贈与税が課せられます。
3-2.クレジットカードでキャッシングを利用する
キャッシング枠のあるクレジットカードを所有している場合は、キャッシング機能を活用してお金を借りることもできます。審査なしに利用できるため、今すぐ必要なときにも適した方法といえるでしょう。お持ちのクレジットカードにキャッシング機能がついているかどうかわからないときは、クレジットカードの会員マイページなどで調べることができます。
クレジットカードを持っていない場合、あるいはクレジットカードはあるけれどもキャッシング機能がついていない場合には、審査なしにお金を借りることはできません。
キャッシング枠を付けて新規にクレジットカードに申し込むか、すでに所有しているクレジットカードの発行会社に連絡し、キャッシング枠を申し込む必要があります。いずれも審査があるため、すぐには利用できない点に注意しましょう。
もし、まだクレジットカードをお持ちでなければ、最短5分で発行できる「SAISON CARD Digital」(セゾンカードデジタル)がおすすめです。「SAISON CARD Digital」は国内初の完全ナンバーレスカードです。クレジットカード番号はスマホに直接届けられ、プラスチックのカードにはクレジットカード番号が記されていないセキュリティにも配慮されたカードです。 キャッシングも併せて申し込みできます。
3-3.ローンを利用する
ローンを利用することで、不足する費用を用意できることがあります。ローンにはさまざまな種類がありますが、出産費用のように必要な金額がある程度分かっているときは、フリーローンが適しているでしょう。フリーローンとは最初にまとまった資金を借りて、計画的に返済していくタイプのローンです。住宅ローンやリフォームローンとは異なり、使い道が指定されていないため、出産費用などにも活用できます。
セゾンファンデックスのかんたん安心フリーローンは、出産費用のように一時的な利用に適したローンです。医療機関での支払いが不足するときなどにも活用できるかもしれません。
出産費用の支払い計画を立ててみよう
出産にはさまざまな費用がかかります。入院する費用や分娩費だけでなく、赤ちゃんや妊産婦の衣類、哺乳瓶などのこまごまとしたものも必要になるでしょう。また、正常分娩は医療保険が適用されないため、医療機関によっても費用は変わる点にも注意が必要です。
いくつかの医療機関に問い合わせて、費用を比較できるかもしれません。入院が長引くことも想定されるため、家族が通いやすい医療機関を選ぶことも大切です。可能な限り早めに出産費用の支払い計画を立てておきましょう。
支払いが難しそうなときには、親族から借りる、クレジットカードのキャッシングやローンなどを活用するという方法があります。出産後は一時的に収入が減ることもあるため、無理のない範囲で返済額を設定しておきましょう。