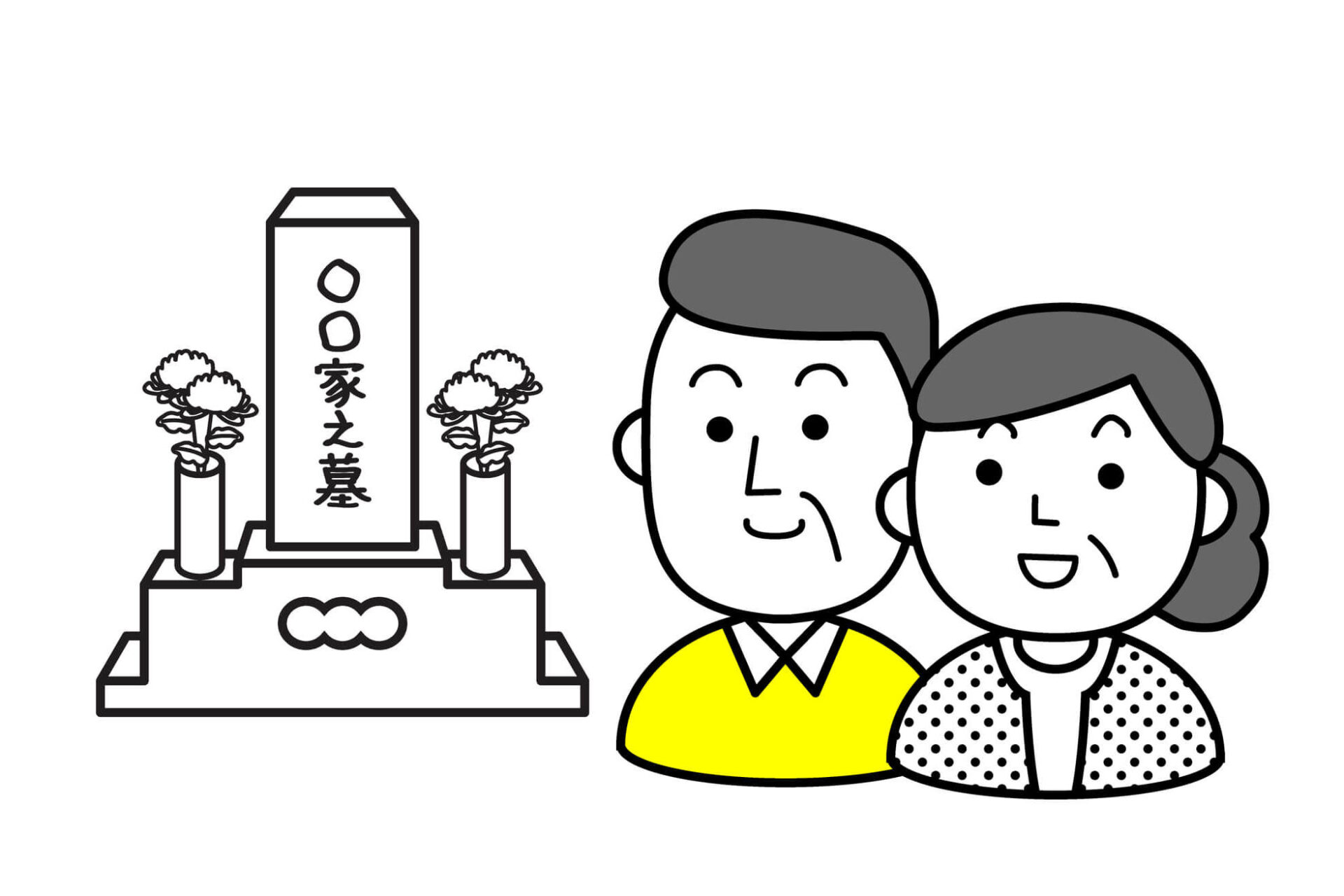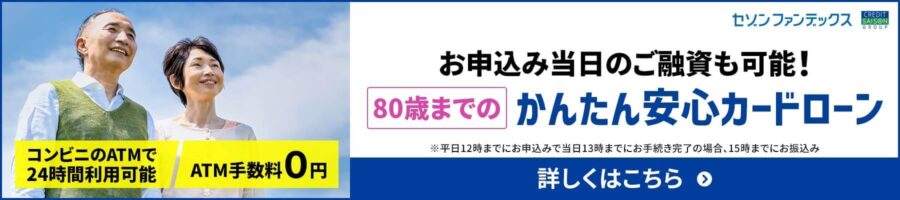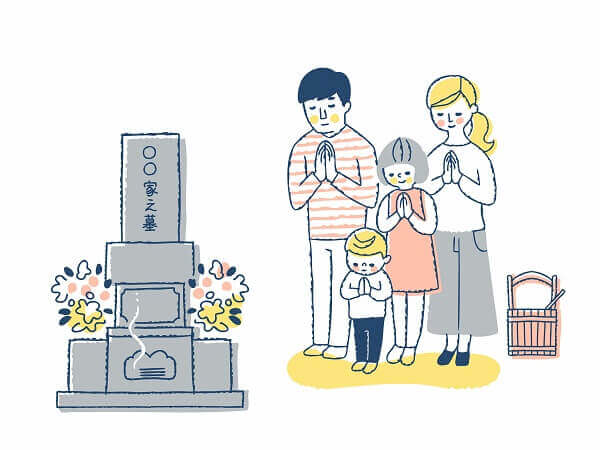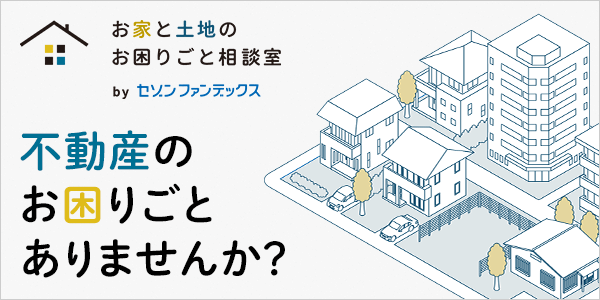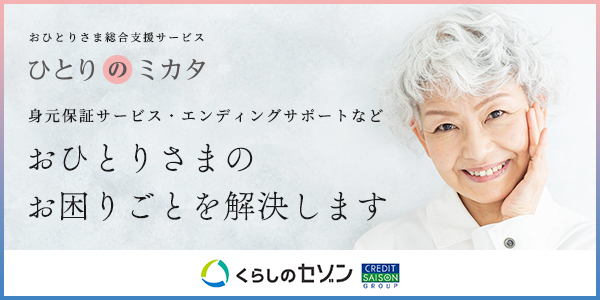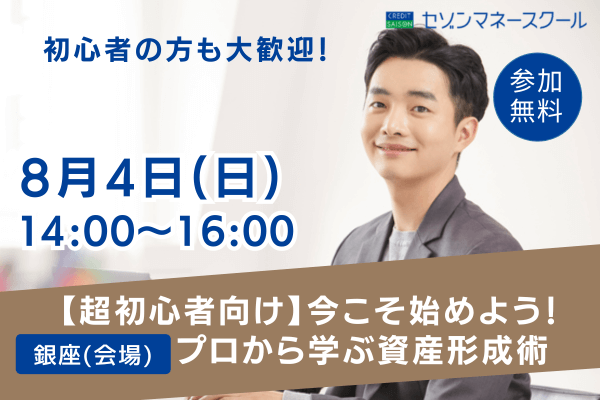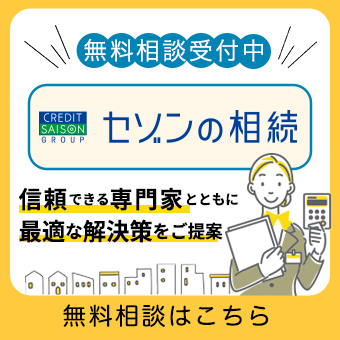「お墓までの距離が遠く管理できない」「墓じまいを考えているけど、どのくらい費用がかかるのだろう」と悩んでいるの方もいるのではないでしょうか。墓じまいには、お墓の閉眼供養などの費用がかかります。また墓じまいを実施する時には、その後の改葬についても考えなければいけません。
このコラムでは、墓じまいの方法と費用、そして「費用の工面が難しい場合の対処方法」について解説します。墓じまいに関する不安が解消できる内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。
お墓探し・お墓参りに関するお悩みなら
「最近はお墓の種類が多すぎて、どれを選べば良いかわからない…」「子どもがいないので、自分の死後、お墓を管理してくれる人がいない」そんな方におすすめなのがクレディセゾングループの「セゾンの相続 お墓探しサポート」です。人気のお墓の種類や、遺族に負担をかけない供養方法などのほか、お墓参りになかなか行けない方向けに「お墓参り・お墓掃除代行サービス」もご提案しています。
「セゾンの相続 お墓探しサポート」を見る
1.墓じまいについて解説
墓じまいにはお墓の解体や撤去、事務手続きなどの必要な作業がいくつかあります。その内容を解説していきます。
そもそも墓じまいとは何をすれば良いのか、どのような手順で行えば良いか分からない方は、ぜひ参考にしてみてください。
1-1.墓じまいとは
墓じまいとは、墓石を解体、撤去して墓所の使用権を管理者に返すことです。使用権を返さなければ、管理費を払い続けることになります。
注意していただきたいのは自身で勝手にお墓の解体、撤去を進めないことです。許可なく墓じまいをすることは、法律で禁止されてます。
墓じまいの前には、お墓の管理者へ相談し、円滑に墓じまいを行えるようにしましょう。
1-2.墓じまいに必要な事務手続き・手順
墓じまいには、6つの事務手続きとその手順があります。6つの手続きと手順は以下のとおりです。
- 新しい改葬先の決定
- 埋葬証明書の発行
- 改葬許可書の発行
- 墓の解体、撤去
- 遺骨の取り出し
- 改葬先への納骨
まずは新しい改葬先を決める必要があります。先に改葬先を見つけておかないと、遺骨の受入先がなくなってしまう可能性があるためです。
改葬先が見つかったら、お墓の管理者へ墓じまいすることを相談し、証明書関係を発行してもらいます。証明書関係が揃った時点で、お墓の解体や遺骨の取り出し、改葬先への納骨が可能となります。
墓じまいをする際は手順を守って、手続きを進めるようにしましょう。
2.墓じまいにかかる総額費用の目安
墓じまいにかかる費用の目安は、約10~30万円です。お墓を管理しているお寺によって、料金設定は異なります。
墓じまいは、3つの工程で構成されています。その工程は以下のとおりです。
- 閉眼供養
- お墓の解体、撤去
- 離檀
墓じまいでは、お世話になったお寺から離れる離檀も含まれます。それぞれの工程と費用について解説していきます。
2-1.閉眼供養
閉眼供養にかかる費用の目安は3~10万円です。
閉眼供養とは、お墓に宿っている故人の魂を抜き取ることです。宗派によっては性根抜きや魂抜き、遷仏法要、遷座法要ともいわれます。
閉眼供養をするのは、親族の心の負担を軽減することが目的の1つです。お墓に宿っている故人の魂を敬うことで、墓じまいを行う罪悪感をやわらげ安心感を得られます。
また閉眼供養をしなければ、お墓の解体や撤去をしてくれないケースが多いので、注意が必要です。
2-2.お墓の解体
墓石の立地状況や撤去方法によって変わりますが、お墓の解体費用の目安は1㎡当たり約10万円です。
お墓の解体とは、墓地から墓石を解体して撤去することです。お墓の解体、撤去の手続きを自身で行わなければなりません。
解体、撤去作業を依頼する先は石材店になります。お寺によっては石材店が決められているケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
2-3.離檀
離檀する際も離檀料という形で、費用が発生します。これまでのお寺との関係性や地域によって変わりますが、費用の目安は約3~15万円です。法要1回分のお布施として納める金額と同等になります。
離檀とは、お寺からお墓を撤去して檀家から抜けることです。檀家に入っていないと思っている方でも、加入していることがあるので確認しておきましょう。お寺にお墓を建てている場合、ほとんどのケースでその菩提寺の檀家です。
離檀の際は、なぜ離れるかの理由を真摯に話しましょう。離檀することを快く思わないお寺の管理者もいるからです。理由を説明し、離檀することを理解してもらいましょう。
3.墓じまいの費用が払えないときの対処法3選
墓じまいには多くの費用が必要です。事情があり費用を払えないという方もいるでしょう。
墓じまいの費用が払えないケースでも対処方法はあります。ここでは対処方法を3つ紹介します。すぐに墓じまいの費用が用意できないという方は、参考にしてみてください。
3-1.ローンを組む
1つ目の方法はローンを組むことです。ローンを組むことで墓じまいの急な出費に対応できます。墓じまいに利用できるローンには、セゾンファンデックスの「かんたん安心ローン」があります。
かんたん安心ローンを利用するメリットは下記の3点です。
- 定期収入がある80歳までの方が利用できる
- 60歳以上の場合、2ヵ月に1回の返済も選択可能
- 年会費・入会費が無料
かんたん安心ローンは特に、80歳までのシニアの方へおすすめできるカードローンです。墓じまいでローンを組もうと考えている方には、セゾンファンデックスのかんたん安心ローンがおすすめです。
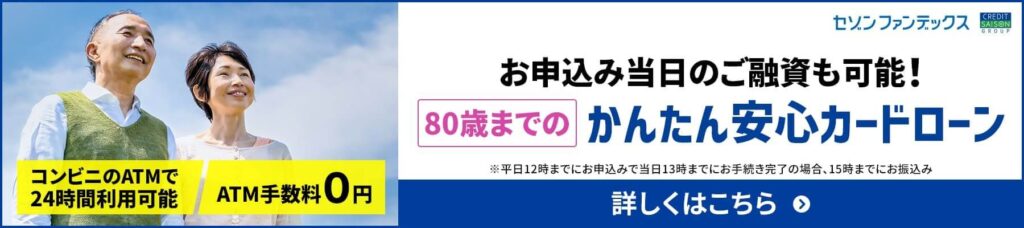
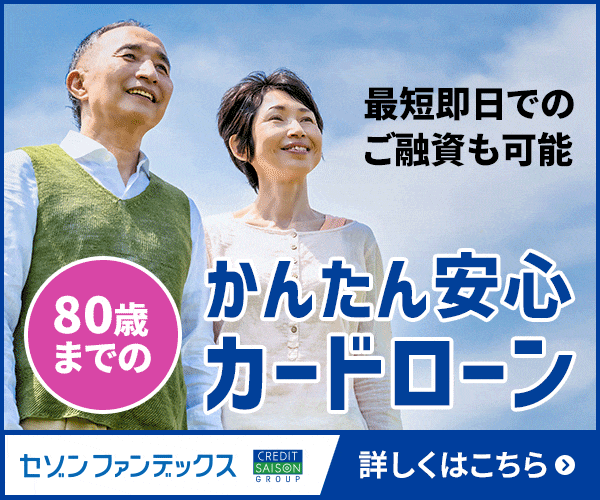
3-2.補助金を利用する
2つ目の方法は補助金を利用することです。自治体では墓じまいの費用を支援してくれる地域もあります。お墓が放置されることは、自治体としても避けたいためです。
例えば、千葉県市川市霊園一般墓地にお墓を建てている方は、条件付きで7.5~44万円の補助金が助成されます。 ご自身が住むところに補助金制度があるかは、自治体への問い合わせやWEBサイトで確認しましょう。
3-3.家族や親族に相談する
3つ目の方法は家族や親族に相談することです。お墓に関することは、あなただけでなく家族や親族全体の問題になります。
墓じまいを考えていることやその理由を充分に相談し、親族の同意を得ることが大切です。親族の同意を得た後、費用についても家族や親族間で負担できないか相談しましょう。
4.【改葬先別】墓じまい後の改葬費用の目安
墓じまいが終わったら、遺骨を改葬先へ移すことになります。遺骨の改葬先は大きく分けて6つあります。 6つの改葬先は、それぞれ埋葬方法や費用が違います。改葬先を選ぶ際の参考にしてみてください。
4-1.個別墓
改葬先の1つ目は個別墓です。建てるお墓の大きさにもよりますが、費用の目安は100~300万円です。
個別墓は、お寺や霊園などのお墓に遺骨を移して改葬します。個別墓のメリットとデメリットは、以下のようなものがあります。
【メリット】
- 他人の遺骨とは別で埋葬できる
- 同じ墓に埋葬する方を選べる
- 先祖代々で供養ができる
【デメリット】
- お墓の管理に手間や費用がかかる
- お墓の購入に費用が必要
- 無縁墓になる可能性がある
個別墓は先祖のみが入るお墓となるので、家族や親族で代々引き継いでいきたい方におすすめです。一方でお墓の購入や管理に費用がかかるため、他の埋葬方法に比べ高額となることが多いです。またお墓を引き継ぐ方がいなければ、無縁墓になるので注意しましょう。
4-2.永代供養墓【合祀墓】
改葬先の2つ目は合祀墓です。周辺の立地状況によりますが、費用の目安は約3~10万円となります。合祀墓とは、遺骨を複数の他人の遺骨と同じ場所へ埋葬する方法です。骨壺から取り出した遺骨のみを納骨します。合祀墓のメリットとデメリットは以下のとおりです。
【メリット】
- お墓の管理に手間がかからない
- お墓の管理費が少ない
- 無縁墓にならない
【デメリット】
- 他人の遺骨と一緒に納骨される
- 遺骨を取り出せない
合祀墓はお墓の管理者が、永代にわたって管理をしてくれるため、手間がかからず無縁墓になることがありません。さらに、管理費もかからないケースが多いです。一方で一度納骨すると、他人の遺骨と一緒になり取り出しができなくなるので注意が必要です。
4-3.永代供養墓【納骨堂】
改葬先の3つ目は納骨堂です。納骨堂の費用は、お墓の管理元により以下の3種類に分けられます。
| 種類 | 費用の目安 |
| 寺院納骨堂 | 10~100万円 |
| 公営納骨堂 | 20~60万円 |
| 民営納骨堂 | 50~100万円 |
納骨堂では、遺骨を骨壷に入れたまま室内に安置します。納骨堂のメリットとデメリットは以下のとおりです。
【メリット】
- お墓の管理に手間がかからない
- お墓の管理費が少ない
- 無縁墓にならない
- お墓参りが天候に左右されない
【デメリット】
- 一定期間で合祀墓に納骨される場合がある
- 預けられる遺骨に制限がある
納骨堂もお墓の管理者が、遺骨を永代にわたって管理してくれるため手間がかかりません。管理費もかからないケースが多いです。一方、一定期間で合祀墓に納骨されるケースや預けられる遺骨に制限があります。事前に確認しておきましょう。
4-4.永代供養墓【樹木葬】
樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を用いたり、草花を植えたりして埋葬する方法です。お墓の規模やお墓の種類にもよりますが、費用の目安は2人分の納骨で約70万円となります。 樹木葬のメリットとデメリットは以下のとおりです。
【メリット】
- お墓の管理に手間がかからない
- お墓の管理費がかからない
- 無縁墓にならない
- 草花があるので自然を感じられる
【デメリット】
- 人数によっては費用が上がる
- 粉骨必須のケースがある
- 遺骨を取り出せないケースがある
樹木葬は管理費がかかる可能性もあるため、事前に管理者に確認しておきましょう。また納骨できる人数は、お墓の規模によって変わります。規模が大きいお墓だと費用も高くなるので、注意しましょう。
4-5.手元供養
手元供養とは、自宅や身近なところに遺骨を保管して供養する方法です。保管方法によりますが、費用の目安は約0~20万円と考えておきましょう。 手元供養では遺骨をすべて自宅で保管したり、一部だけをお墓に埋葬したり散骨したりするなどの選択ができます。
自宅で保管する方法は大きく以下の3つです。
- 骨壺に入れる
- 骨壺に入れて仏檀に供える
- アクセサリーにする
遺骨を手元供養のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
【メリット】
- お墓の購入が必要ない
- 故人を身近に感じられる
【デメリット】
- 遺骨を継ぐ方を探す必要がある
- 親族の理解が必要
手元供養ではお墓の購入が必須ではないので、費用を抑えられます。一方お墓がないことで、遺骨を管理してくれる方を探す必要があります。
4-6.散骨
散骨とは、遺骨を粉末状にして、海や山などの自然に撒く埋葬方法です。費用の目安は散骨方法によりますが約3~30万円となります。 散骨のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
【メリット】
- お墓を購入する必要がない
- 管理費用がかからない
- 跡継ぎを選ぶ必要がない
【デメリット】
- 親族の理解が必要
- 遺骨が残らない
散骨は、遺骨が残らないので費用の負担が少ないです。しかし遺骨が残らないことで、親族の同意を得にくい可能性があります。親族と充分に話し合ってから、散骨を行う決断をしましょう。
また、散骨する場所には注意が必要です。法律によって散骨できる場所には、限りがあります。心配な方は、事前に散骨に対応できる専門会社に相談しましょう。
5.墓じまいをしないと無縁墓になってしまう
墓じまいをせずに、お参りや管理をしないまま放置されたお墓を「無縁墓」といいます。 費用が支払われないまま、お墓を継いだ方や親族との連絡が取れずに、管理者が決めた期間を過ぎるとお墓が強制的に撤去されてしまいます。
お墓が撤去された後は、遺骨が取り出され合祀墓へ移されることが多いです。そうなってしまうと故人の遺骨を特定できなくなり、二度と取り出せなくなるかもしれません。
故人や親族も、無縁墓になることは望んでいないと思います。無縁墓にしないためにも、管理が難しい場合は墓じまいを検討しましょう。
6.墓じまいの費用は誰が払うのか【墓の継承者】
墓じまいの費用は、お墓の継承者が支払わなければいけません。お墓の継承者とは、故人が指名した方を意味します。 故人が指名していなかった場合、日本の風習では長男や長女が支払うケースが多いです。しかしお墓の継承は拒否できます。
長男や長女が難色を示した場合は、家族や親族の話し合いで決定することになるでしょう。墓じまいにおいて家族や親族間でトラブルになるケースは多くあります。そのため充分に話し合いを行い、費用を分担するなどの結論を出せるようにしましょう。
おわりに
墓じまいは故人の供養のため、家族や親族の想いをつないでいくために必要な行事です。墓じまいをせず、故人を無縁墓に納骨してしまうことは避けなければいけません。
費用が払えないときは、補助金やローンを活用して、家族や親族同士で納得できる墓じまいをしましょう。
墓じまいで利用できるローンには、セゾンファンデックスの「かんたん安心ローン」があります。かんたん安心ローンは、80歳までのシニアの方におすすめできるカードローンです。入会費や年会費などの初期費用がかかりません。墓じまいでローンを組もうと考えている方には、セゾンファンデックスのかんたん安心ローンを検討してみてはいかがでしょうか。
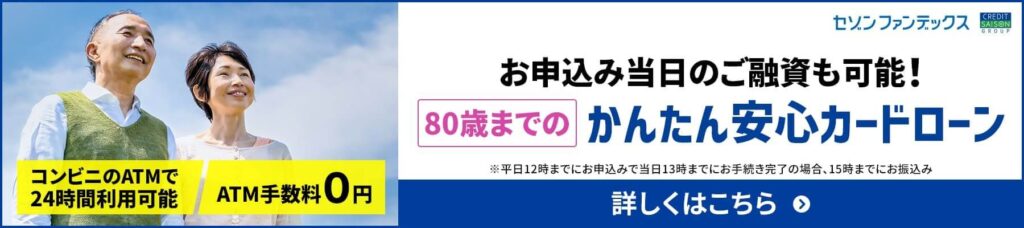
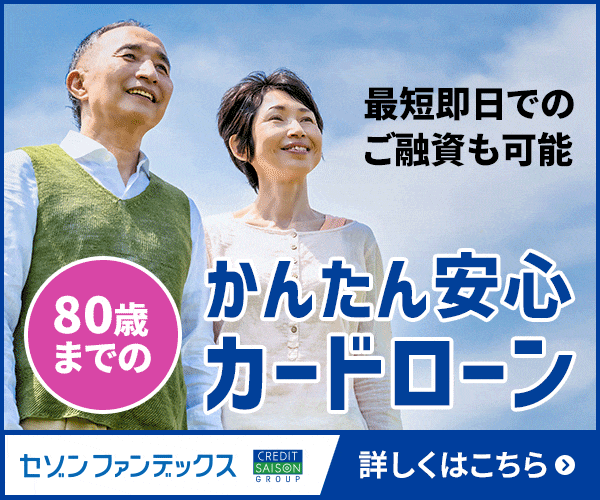
あなたにおすすめのコラム