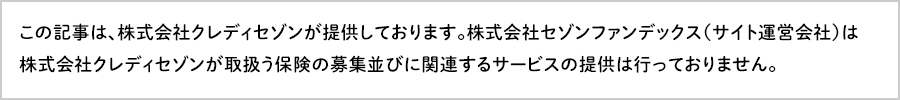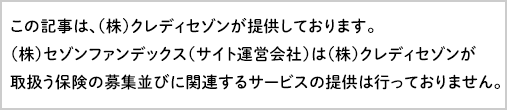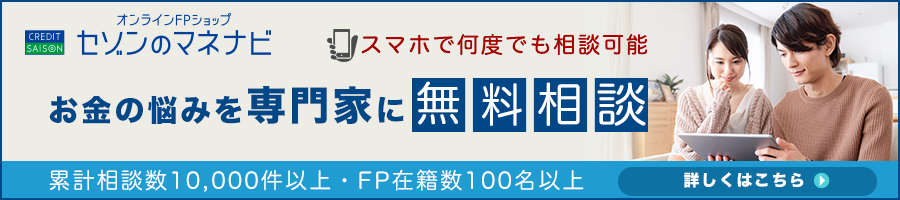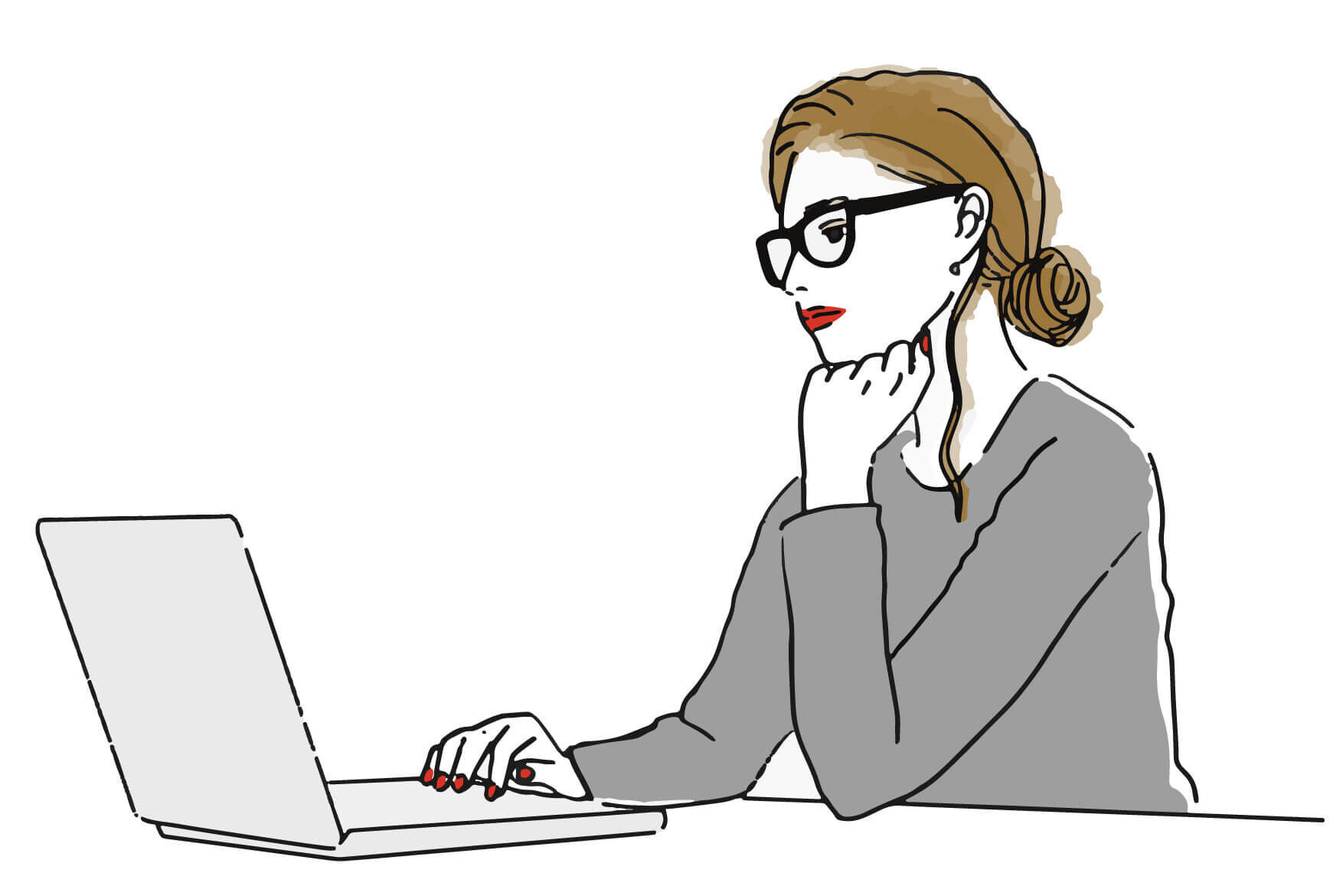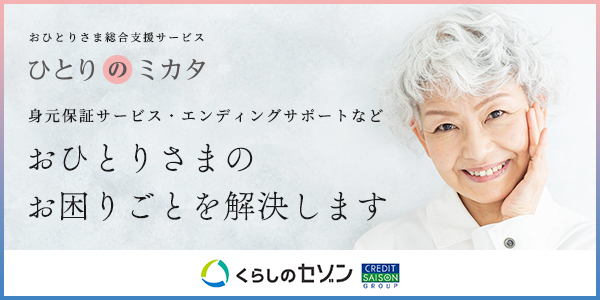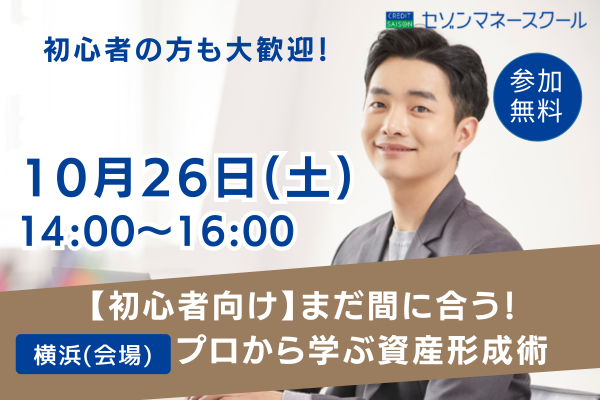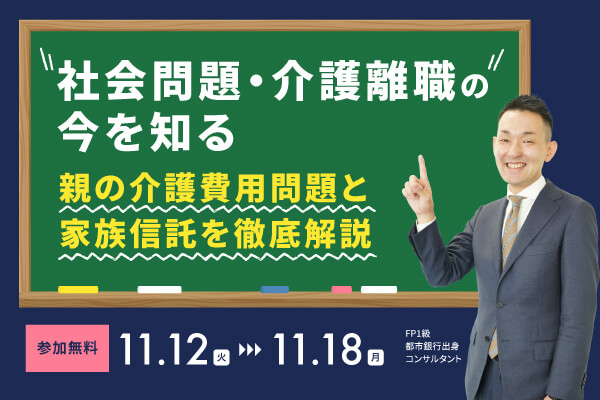入院などで医療費が高額になることが事前にわかっている場合は「限度額適用認定証」を申請するのがおすすめです。限度額適用認定証があれば、窓口での支払額を自己負担限度額まで抑えられます。
しかし、どのように申請手続きを行えば良いのかわからない方もいるでしょう。そこで、このコラムでは、限度額適用認定証の申請方法について「協会けんぽ」や「組合健保」と「国民健康保険」に分けて解説していきます。
限度額適用認定証の申請手続きに関するよくある疑問についても紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
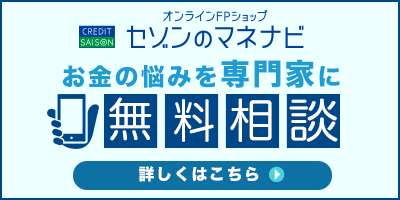
限度額適用認定証とは?
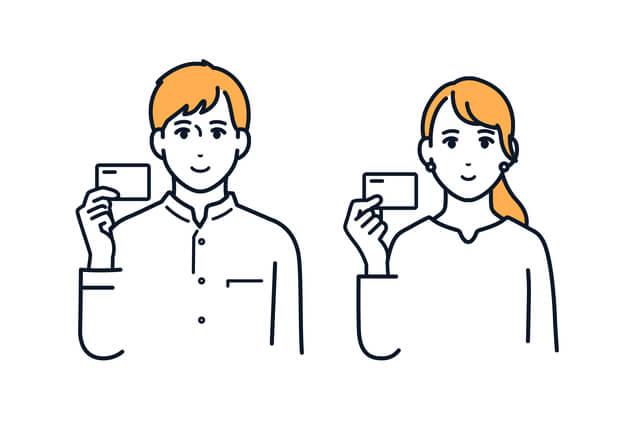
「限度額適用認定証」とは、入院などで高額な医療費がかかることが想定されるときに利用するものです。医療機関の窓口に限度額適用認定証を提示すれば、支払い金額が自己負担限度額までになります。
限度額適用認定証は、医療機関での支払い前に申請し交付してもらいましょう。大きな支払いが発生する前に準備しておけば、支払いに不安がある方も安心です。
限度額適用認定証の申請方法

限度額適用認定証の申請方法は、協会けんぽや組合健保などの被用者保険と、国民健康保険で異なります。ご自身が加入している保険の申請方法を確認してください。
協会けんぽ・組合健保・共済組合・国保組合の場合
協会けんぽ、組合健保、共済組合、国保組合などの被用者保険の場合は、保険証に記載されている保険の所属支部に申請します。勤務先を通して申請することもあるので、勤め先の総務部や人事部などに限度額適用認定証の手続きについて確認しておくと良いでしょう。
主な手続きの流れは、以下のとおりです。郵送手続きのため、交付まで1週間程度かかります。
- 申請書を保険の支部に提出する(申請書はホームページなどでダウンロード可)
- 限度額適用認定証が交付される
- 病院の窓口に保険証と合わせて限度額適用認定証を提示する
- 病院の窓口支払いが自己負担限度額までで済む
国民健康保険の場合
国民健康保険に加入している方は、区役所や市役所の国民健康保険係の窓口に申請します。自治体によっては、郵送で受け付けていることもあります。
申請には、国民健康保険証と本人確認書類が必要です。ただし、自治体により申請方法や手続き窓口が異なることがあるので、不明な点がある場合は問い合わせるのがおすすめです。
なお、保険料の滞納がある場合は申請できないことがあるので、ご注意ください。
限度額適用認定証の申請に必要な書類
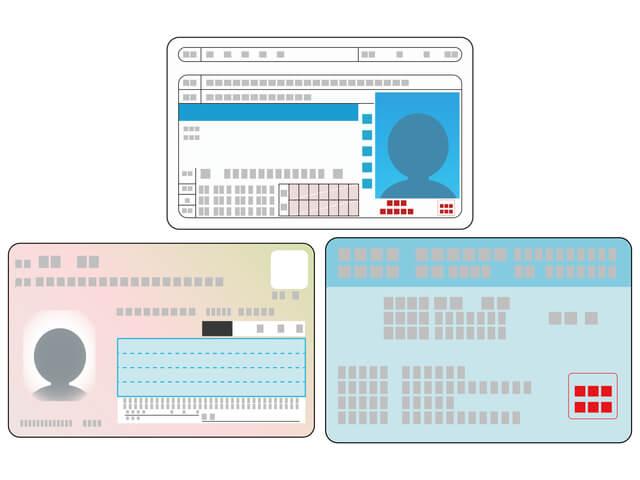
限度額適用認定証の申請に必要な書類は、加入している保険により異なります。例えば、国民健康保険に加入している方が、区役所の窓口で申請する場合に必要な書類は、以下のとおりです。
国民健康保険を利用している場合
- 被保険者の国民健康保険証
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーカード
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
マイナンバーカードがない場合は、個人番号の通知カードや、マイナンバーの記載がある住民票が必要です。書類が不足していた場合、もう一度申請しなければならず二度手間になってしまいます。事前に、提出先に必要書類について問い合わせておくと安心です。
限度額適用認定証を利用する際の注意点
限度額適用認定証を利用する際には、いくつか注意点があります。この注意点を知っておかないと、想定より自己負担額が増える可能性もあるので必ず確認しておきましょう。
月をさかのぼっての申請はできない
申請書受付月より前月の医療費に対して、限度額適用認定証を適用することはできません。
例えば、7月が申請書受付月となった場合、6月以前の医療費に対して、窓口での自己負担額を抑えることはできません。
限度額認定適用証の申請は日程に余裕を持って準備しましょう。
月をまたぐ場合は自己負担額が増える可能性がある
高額療養費制度で定められている自己負担限度額は、月額で決められており、月をまたぐと各月ごとに算定することになります。
実際に月をまたいだ場合とそうでない場合の自己負担限度額の差をシミュレーションしてみます。
例えば、窓口負担が3割である標準報酬月額40万円の40歳の方が、入院を20日間して、医療費が総額200万円であったケースで考えてみましょう。
- A:入院が月内におさまったケース(医療費200万円)
- B:入院が2ヵ月にまたがったケース(医療費は各月100万円で計200万円)
この方の場合、1ヵ月の自己負担限度額は「80,100円+(医療費−267,000円)×1%」で計算されます。
(A:入院が月内におさまるケースの自己負担限度額)
(B:入院が2ヵ月にまたがるケースの自己負担限度額)
87,430円=80,100円+(100万−26万7,000円)×1%
②2ヵ月目の自己負担限度額
87,430円=80,100円+(100万−26万7,000円)×1%
③自己負担限度額の合計
174,860円=①87,430円+②87,430円
上記のシミュレーションでは、自己負担限度額はAでは97,430円、Bのでは174,860円でした。つまり、月をまたいだ場合は自己負担限度額が77,430円(約1.8倍)も増えることになります。
このことから、高額療養費制度を有効利用するのであれば、1カ月の間に入院や治療が完了するスケジュールが望ましいといえます。そのため、入院や治療などのタイミングが遅れないよう限度額適用認定証は早めに発行手続きをしておくとよいでしょう。
利用を終えたら返却する必要がある
有効期限が切れたり、退職などで被保険者の資格がなくなったりしたときなどは、限度額適用認定証を指定の方法で返却する必要があります。
これは法律で定められているので、忘れずに対応しましょう。
限度額適用認定証の返却方法は、各自治体や保険組合のホームページで確認できます。
通常、各自治体や保険組合が指定する住所に、郵送で限度額適用認定証を送付して返却します。個人情報が書かれている書類なので、二つ折りにしたり、目隠しシートで隠したりしてから郵送するとよいです。
高額療養費制度の自己負担上限額をチェック
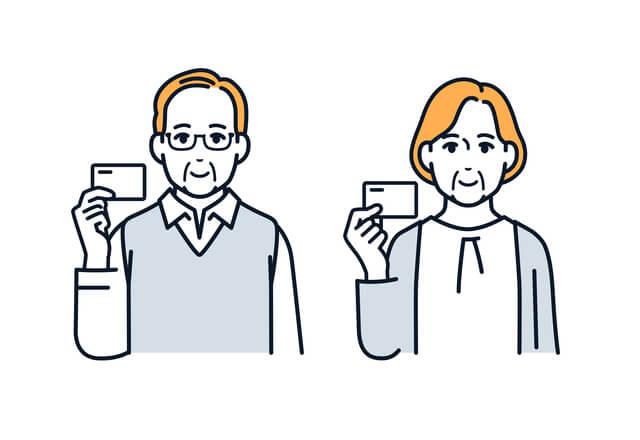
高額療養費制度は、1ヵ月の医療費が上限額を超えた場合は、その分を支給する制度です。限度額適用認定証を利用した場合との一番の違いは、医療機関の窓口での支払は請求額どおりに支払い、自己負担額を超過した分が後日支給される点です。また、世帯合算や複数医療機関の受診、高額な薬代がかかる場合には高額医療費制度の利用を検討しましょう。
高額医療費制度は、所得や年齢により、自己負担の上限額が設定されています。ここでは「69歳以下」「70歳以上75歳未満」「75歳以上」の3つに分けて、医療費負担の上限額について紹介します。
69歳以下の方

69歳以下の方が窓口で支払う自己負担額は、以下のとおりです。
| 適用区分 | 負担割合 | 月単位の上限額(円) | 多数回該当 |
|---|---|---|---|
| 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬83万円以上 国保:旧ただし書き所得 901 万円超 | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000 円)×1% | 140,100円 |
| 年収770~1,160 万円程度 健保:標準報酬月額 53~83 万円 国保:旧ただし書き所得 600~901 万円 | 3割 | 167,400円+(医療費-558,000 円)×1% | 93,000円 |
| 年収370~770 万円程度 健保:標準報酬月額 28~53 万円 国保:旧ただし書き所得 210~600 万円 | 3割 | 80,100円+(医療費-267,000 円)×1% | 44,400円 |
| 年収約 370 万円以下 健保:標準報酬月額 26 万円以下 国保:旧ただし書き所得 210 万円以下 | 3割 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税 | 3割 | 35,400円 | 24,600円 |
多数回該当とは、同じ世帯で過去12ヵ月間のうち自己負担限度額に達した月が4回目になると適用される金額のことです。
「旧ただし書き所得」は、すでに廃止されていますが、国民健康保険では旧ただし書き所得に所得割料率を掛け合わせて、保険料の所得割額を計算します。70歳未満は、医療費の自己負担が一律3割です。
70歳以上の方

70歳以上、75歳未満の方が窓口で支払う自己負担額は、以下のとおりです。
| 適用区分 | 負担割合 | 外来(個人ごと) | 月単位の上限額(円) | 多数回該当 | |
| 現役並み所得者 | 年収約1,160万円~ 標報83万円以上・課税所得690万円以上 | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | 140,100円 | |
| 年収770万円~1,160万円程度 標報53万円以上・課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | 93,000円 | |||
| 年収370万円~770万円程度 標報28万円以上・課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 | |||
| 一般 | 年収156万~370万円程度 標報26万円以下課税所得145万円未満等 | 2割 | 18,000円(年144,000円) | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税など | Ⅱ 住民税非課税世帯 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 | 適用なし |
| Ⅰ 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) | 15,000円 | 適用なし | |||
70歳以上75歳未満の場合は、窓口負担割合が2割~3割です。負担割合は、所得により異なります。
75歳以上の方
75歳以上の方は、後期高齢者に区分されます。後期高齢者の窓口負担について、厚生労働省が定める窓口負担割合と高額療養費の自己負担限度額を見ていきましょう。
| 適用区分 | 割合負担 | 外来(個人ごと) | 月単位の上限額(円) | 多数回該当 | |
| 現役並み所得 | 課税所得145万円以上 年収約383万円以上 | 3割 | 収入に応じて80,100~252,600円+(医療費-267,000~842,000円)×1% | 44,400円~140,100円 | |
| 一般 | 課税所得145万円未満 住民税が課税されている世帯(※)で年収383万円未満 | 1割 | 18,000円(年14.4万円) | 57,600円 | 44,400円 |
| 低所得Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税 年収約80万円超 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 | 適用なし |
| 低所得Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税 年収約80万円以下 | 1割 | 8,000円 | 15,000円 | 適用なし |
世帯の所得区分が「現役並み所得者」の場合、窓口で支払う自己負担は3割です。一方「一般」または「低所得者区分」の場合は、1割負担です。
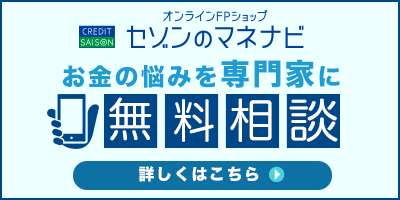
限度額適用認定証の申請方法についてよくある疑問

限度額適用認定証を申請する際によくある疑問を5つ紹介します。
限度額適用認定証の有効期限はいつまで?
限度額適用認定証の有効期限は、申請から最長で1年間です。定められている有効期限は、加入している保険により異なります。限度額適用認定証に有効期限が記載されています。また、期限が切れた後も引き続き限度額適用認定証が必要な方は、再度申請しなければなりません。
70歳以上は限度額適用認定証が必ず必要なのか?
70歳以上の方は、所得区分により限度額適用認定証が必要になる場合があります。所得区分が現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」が必要です。国民健康保険と協会けんぽの場合の現役並み所得者の区分は、以下のとおりです。
- 現役並みⅠ:健保標準報酬月額28万~50万円、または課税所得145万円以上
- 現役並みⅡ:標準報酬月額53万~79万円、または課税所得380万円以上
- 現役並みⅢ:標準報酬月額83万円以上、または課税所得690万円以上
上記の区分は、国民健康保険及び協会けんぽの場合です。健康保険組合や共済組合の場合は、組合へお問い合わせください。「現役並みⅢ」と「一般」の区分の方は、健康保険証と高齢受給者証を提示すれば、限度額適用認定証は不要です。
「限度額適用認定証」と「高額療養費制度」の違いがわからない
高額療養費制度とは、医療費が高額になった場合に自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられる制度です。限度額適用認定証との主な違いは、以下のとおりです。
限度額適用認定証
高額な医療費がかかりそうな場合、あらかじめ申請しておくと窓口支払いが自己負担額のみで済む
高額療養費制度
医療費の自己負担額が高額になり、限度額を超えた場合に後で金額が払い戻される
医療費が高額になった場合、一時的に窓口負担が大きくなりますが、後で払い戻しが受けられます。窓口での支払い時点で自己負担限度額に抑えたい場合は、限度額適用認定証を利用すると良いでしょう。
限度額適用認定証が退院までに間に合わない場合はどうすれば良い?
限度額適用認定証の申請が退院までに間に合わない場合は、いったん窓口で支払い、後に高額医療費の支給を待つことになります。高額療養費を申請する場合、支給までは3ヵ月程度かかります。医療費が高額になりそうだとわかっている場合は、早めに手続きを行うことをおすすめします。
限度額適用認定証はいつ提出すれば良い?
限度額適用認定証は、申請を行うと1週間程度で手元に届きます。限度額適用認定証が発行されたら、入院手続き時の際に提示しましょう。窓口支払いが自己負担上限額までに抑えられます。
入院日までに間に合わなくても、月末までに提示すれば良い場合もあります。いつまでに提示すれば間に合うかについては、病院で確認しましょう。
マインナンバーカードを健康保険証とする場合の限度額適用認定証は?
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では限度額適用認定証がなくても、限度額を超える一時支払いが不要になります。マイナンバーカードで受診し、顔認証付きのカードリーダーで情報提供に同意するだけなので、手続きも簡単です。
マイナンバーカードについての詳細は下記の記事で詳しく解説しています。
マイナンバーカードが健康保険証として対応しているかどうかは「マイナ受付」のポスターやステッカーでわかります。厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」でも確認できるので、ぜひご利用ください。
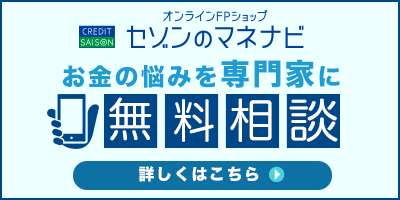
「限度額適用認定証」があると安心!申請方法を知っておこう

医療費が高額になりそうだとわかっている場合は、事前に限度額適用認定証を申請しておくと、窓口での一時的な高額支払いが不要になります。申請には日数がかかるので、入院などが決まっているなら、早めに手続きしましょう。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関の場合は、限度額適用認定証が無くても窓口負担が自己負担限度額になります。「手続きが難しい」と感じる場合は、病院や加入している健康保険の窓口に相談すると良いでしょう。
日頃から急な出費や不測の事態に備えて無料でプロに相談「セゾンのマネナビ」がおすすめ

今回のコラムでは、入院などで医療費が高額になると事前にわかっている場合には、窓口での支払額を自己負担限度額まで抑えるために、「限度額適用認定証」を申請することをおすすめしました。
医療費や入院費の支払いが難しい状態にある場合、公的制度を利用することで解決できる場合もあります。日頃からどんな制度があるのか、その制度を利用するためにはどのような手続きが必要なのか情報収集しておくようにしましょう。
また、急な出費や、不慮の事態に備えて家計の貯蓄を見直していくことも重要です。ライフプランを立てて支出の状況を可視化したり、固定費を削減したりして貯蓄を計画的に行い、急な出費や不慮の事態に困らないように、早いうちから準備しておきましょう。
これからのライフプランを見直したい方は、まずはオンラインFPショップ「セゾンのマネナビ」の活用がおすすめです。オンラインFPショップ「セゾンのマネナビ」は、将来のお金に関する悩みをオンラインでファイナンシャルプランナーに無料で相談できるサービスです。
例えば、退職金の運用方法、老後資金の不安などに悩まれている方もいるでしょう。漠然とした将来の不安を抱えている方もいるかもしれません。
セゾンのマネナビを活用すれば、何回でも無料でファイナンシャルプランナーに相談できるのでお金に関する不安や悩みを解決できます。担当のファイナンシャルプランナーをご自身で選ぶことも可能です。相談はオンラインで行えるため、気軽に相談できます。
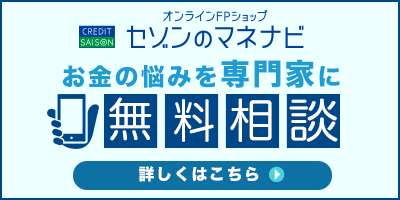
セゾンのマネナビを実際にご利用された方の声
ライフプラン表を作成してもらったことで今後備えていく必要があるのはどの部分なのか見える化できました。友人や知人にもできるだけ早くライフプラン表の作成をすすめたいです。(40代女性)
教育資金と老後資金の事を考えて、どのようにお金を貯めていけば良いか聞きたいと思い申し込みました。担当FPはいろいろ相談にのってくれ、とても話しやすくさまざまな知識を得ることができました。(30代女性)
おすすめポイント
- オンラインで相談できる
- 何回ご相談いただいても料金は無料
- ご自身で担当のFPを指名できる
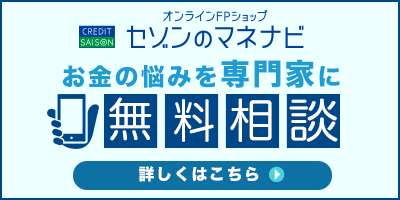
※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。